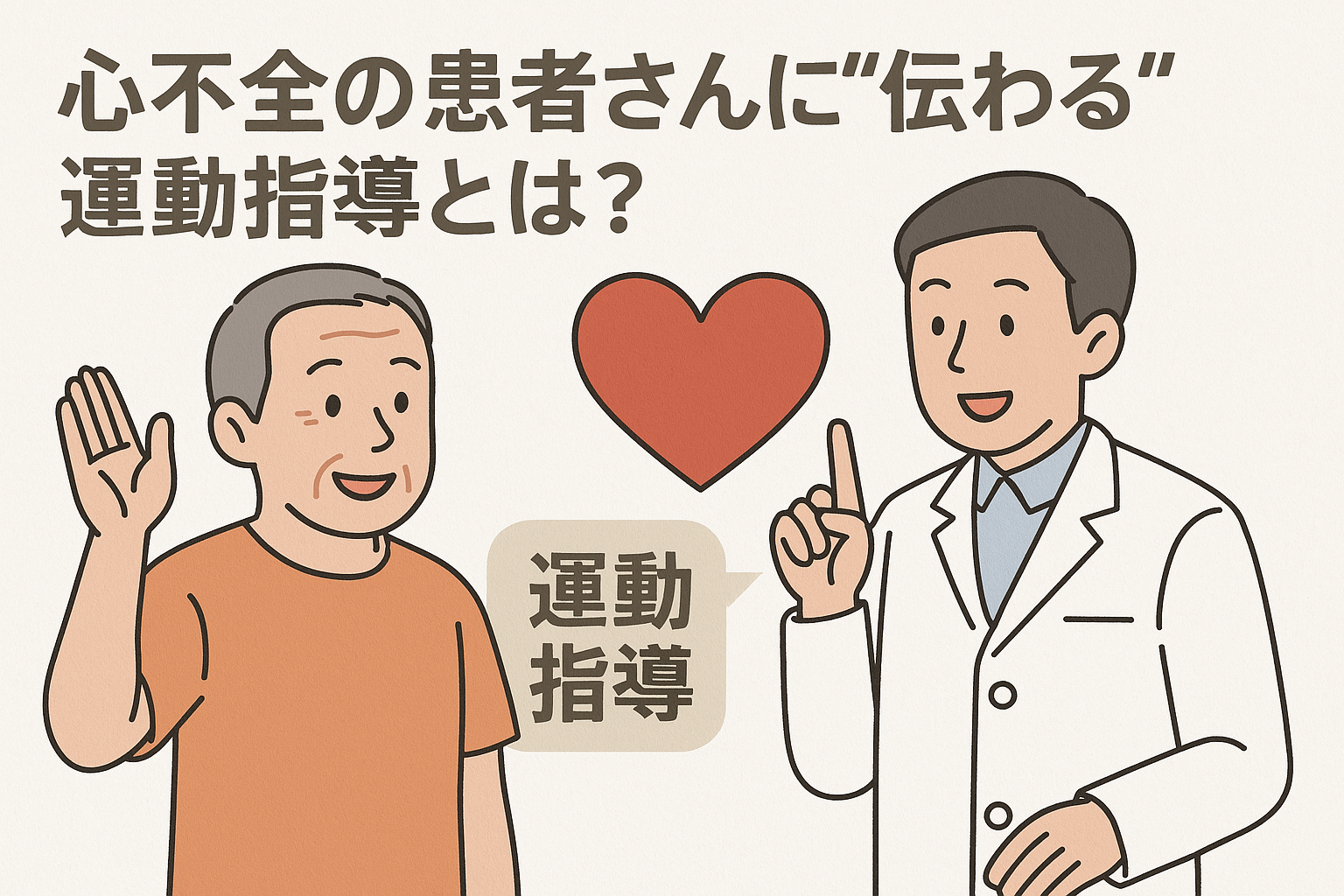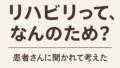はじめに|心不全リハビリは「伝える力」が勝負を分ける
心臓リハビリに限らずですが、患者さんに対するリハビリでは、何をするかより、どう伝えるかが重要です。
どれだけエビデンスに基づいたプログラムであっても、患者さん自身が理解・納得し、前向きに取り組まなければ効果は限定的になります。
もも特に心不全の患者さんは、運動に対して「怖い」「再発したらどうしよう」といった強い不安を抱えていることも多く、理学療法士の説明や指導が伝わりにくいことも珍しくありません。
この記事では、心不全患者さんに“伝わる”運動指導をするために、臨床現場で意識したい5つの視点をわかりやすく解説します。
⸻
【この記事はこんな人におすすめ】
• 心不全のリハビリに関わる理学療法士(PT)
• 患者さんへの説明・声かけに自信が持てない新人セラピスト
• 医療コミュニケーションを磨きたい人
• “動いてもらえない患者”に悩んでいるセラピスト
• 患者さんの不安に寄り添い治療を進めたい方
⸻
心不全患者の「心理」を理解しよう
心不全患者は身体的な問題だけでなく、精神的・社会的な不安を多く抱えていることを忘れてはいけません。
- 少し歩いただけで息切れし、「自分はもう普通に生活できないのでは」と感じる
- 「また再発して入院したらどうしよう」といった慢性的な不安
- 医師や家族から「無理をしないように」と繰り返し言われ、自信を失っている
- 以前の発作の記憶がフラッシュバックし、動くことに対する恐怖がある
このような心理状態では、「歩きましょう」と言われても、「怖くて歩けません」と拒否されるのも当然です。
理学療法士としてはまず、身体の訓練の前に、心のケアが必要な場合があることを認識すること。
“動かせない身体”ではなく“動くのが怖い心”に寄り添う姿勢が、リハビリの第一歩になります。
⸻
医学用語はNG!“患者の言葉”で伝える
理学療法士の専門性は重要ですが、それが「患者に伝わらなければ意味がない」のが臨床の現実です。
「有酸素運動が心機能に好影響を与える」といった説明は、患者さんには難解で理解しづらいもの。
小学生でもわかる言葉で伝える工夫が求められます。
例えば、
×「心拍出量が改善される」
→ ○「心臓が血を送る力が少しずつ元気になります」
×「筋ポンプ作用で静脈還流が促進される」
→ ○「ふくらはぎを動かすことで、血液が心臓に戻りやすくなりますよ」
また、「~です、~になります」といった一方的な説明口調ではなく、対話の形にすることで、より理解しやすくなります。
例:「この歩き方なら、息切れせずに続けられそうですか?」→「はい」と答えてもらえるような導入が、理解と安心につながります。
⸻
「理解」ではなく「納得」を引き出す指導を
患者さんに説明するとき、私たちはつい「理解してもらう」ことに注力してしまいがちです。
しかし、心不全のリハビリでは、“理解”よりも“納得”が優先されるべきです。
人は「自分にとって必要だ」と“納得”できたときにはじめて、行動に移すことができます。
そのためには、
• 体感してもらう:実際に運動してみて「意外とできた」と感じてもらう
• 比較してもらう:昨日よりも今日の方が歩けた、という“進歩”を自覚してもらう
• 実生活と結びつける:この運動が「自宅トイレまで歩く力」に繋がる、と伝える
これらの工夫を通じて、“自分ごと”として運動を捉えてもらうことが重要です。
⸻
成功体験を積ませる声かけの技術
心不全患者さんの多くは「自信を失っている」状態です。
だからこそ、少しの変化や進歩を“成功体験”として認識してもらう声かけが、運動継続のモチベーションに直結します。
声かけの例:
• 「今のペース、とても安定してますね。心臓にもやさしい動きです」
• 「昨日よりも休憩の回数が減りましたね!しっかり力がついてきてます」
• 「前は怖くて歩けなかったのに、今日は自分から動けましたね」
こうした声かけは、「自分にもできる」という自己効力感を高め、患者さん自身が前向きな変化を実感するきっかけになります。
患者さんの“努力”よりも“できたこと”を拾い上げて言葉にする――
その積み重ねが、最終的に「自立した生活」につながります。
⸻
よくあるNG指導と改善例
現場でありがちな「伝わらない指導」は、実はちょっとした言葉選びで改善できることが多いです。
NG例1:
×「がんばって歩きましょう」
→ 患者:「がんばりすぎて悪化したらどうしよう」
改善案:

息が上がらないくらいのペースで、途中で休憩を入れながら歩いてみましょう。歩くことで心臓も少しずつ元気になりますよ。
NG例2:
×「心臓にいい運動です」
→ 患者:「ピンとこない…」「本当に安全なの?」
改善案:

このくらいの運動なら、心臓に無理をかけずに、日常生活を楽にする力がついてきます。たとえば、家でトイレまで行くのが今よりラクになる可能性がありますよ
NG例3:
• ×「これを毎日続けましょう」
→ 患者:「毎日なんて無理…」
改善案:
「まずは週に2~3回でもOKです。できる日を一緒に考えてみましょう」
言葉を少し変えるだけで、患者の受け取り方も大きく変わります。
指導の技術=言葉の選び方といっても過言ではありません。
⸻
おわりに|“伝わる指導”が、患者の人生を変える
心不全のリハビリでは、「動ける身体」を取り戻す以上に、「動く意欲」「行動への納得感」が求められます。
理学療法士として、「伝わる説明」「寄り添う言葉」「共感を生む声かけ」を心がけることで、
患者さんは“自分の力で生活を取り戻す”一歩を踏み出すことができます。
私たちの何気ない一言が、その大きな一歩の後押しになる――
そんな気持ちで、今日も患者さんと向き合っていきましょう。