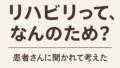■この記事はこんな方におすすめ!
• リハビリ職(PT・OT・ST)で、心不全患者に関わる機会がある方
• 新人〜中堅の医療職で、ガイドラインの改定ポイントを簡潔に把握したい方
• 多職種連携の中で「心不全に対する自分の役割」に悩んでいる方
• 訪問リハや地域包括ケアに携わる方で、再入院予防や脆弱期支援に関心がある方
• 医療学生や研修医で、国家試験・実習対策として基礎から学びたい方

ガイドラインって正直読むの大変…
そんなあなたのために、忙しい現場でも10分で理解できる要点重視型記事としてまとめました!
\より専門的な記事はこちら/

⸻
はじめに:なぜ今「心不全ガイドライン」なのか?
心不全は「人生の終わりに向かう病」とも言われ、急性増悪と安定期を繰り返しながら、徐々にADLやQOLが低下していく慢性進行性の疾患です。高齢化が進む日本では、患者数の急増とともに、心不全による入退院の増加、在宅介護への影響も深刻化しています。
この背景を受けて、2025年のガイドライン改定では、単なる「治療の指針」ではなく、予防・リハビリ・多職種連携・緩和ケアまでを含む“包括的な支援体制”を示す内容へと変化しました。
リハビリ職をはじめとする医療従事者が、患者の人生にどのように関わるかを考えるきっかけとなる改定と思っています。
⸻
主な改定ポイント6選
① ガイドラインの統合と名称変更
急性期〜終末期まで一貫した視点での診療
これまで分かれていた「急性心不全ガイドライン」と「慢性心不全ガイドライン」が統合され、「心不全診療ガイドライン」へ一本化されました。
これにより、急性期〜慢性期〜在宅〜終末期まで、一貫した視点での診療が求められるようになっています。
リハ職の視点では、「どの時期に、どんなアプローチがふさわしいか?」を見極める判断材料として重要です。
② ステージ分類の見直しと予防の強化
心不全の予防における早期介入の重要性
ステージA〜Dという分類が明確に定義され、それぞれの段階に応じた介入の必要性が示されました。注目すべきは、CKD(慢性腎臓病)が新たにステージAのリスク因子として追加されたことです。
この改定は、心不全の予防における早期介入の重要性を示しています。心不全になる前の段階から、多職種で生活習慣改善や身体機能維持への取り組みが求められます。
③ 薬物療法のアップデート
EFに基づく心不全の分類(HFrEF、HFmrEF、HFpEF、HFrecEF)ごとに、推奨される薬物療法がアップデートされました。
- SGLT2阻害薬
- ARNI
- フィネレノン
- GLP-1受容体作動薬
• SGLT2阻害薬:HFrEFだけでなくHFpEFにも適応拡大。心不全における“新たな第4の柱”として注目。
• ARNI(サクビトリル・バルサルタン):従来のACE阻害薬に代わり、予後改善効果がより強い。
• フィネレノン(選択的MRA):腎保護作用を持ち、CKD合併心不全に有効。
• GLP-1受容体作動薬:肥満や糖尿病を合併する心不全に対して新たな選択肢に。
薬物療法の理解は、リハ職にも重要です。「薬で何が改善されていて、リハでどこを補うべきか」を把握することで、アプローチの根拠が明確になります。
④ リハビリテーションの役割明確化
今回の改定では、心不全リハビリが“標準治療の一部”として明記されました。急性期のベッド上離床から、回復期・生活期の再発予防、さらには在宅支援まで、リハ職が果たす役割は非常に多様化しています。
• 早期離床による廃用予防
• ADL能力・運動耐容能の改善
• 栄養・フレイル・サルコペニアの包括的アセスメント
• 多職種との連携による支援体制の構築
特に理学療法士には、単なる運動療法だけでなく、全身状態・病態・心理社会的背景も含めたトータルケアが求められています。
⑤ 「脆弱期(フレイル期)」の明確化
退院後90日間を“脆弱期(脆弱な移行期)
今回の改定の中でも非常に重要なのが、退院後90日間を“脆弱期(脆弱な移行期)”と定義した点です。この期間は再入院のリスクが最も高く、医療と生活の橋渡しが必要なフェーズです。
• 多職種でのモニタリング
• リハ継続(訪問・通所)
• 栄養・服薬・運動・心理状態のフォロー
• 家族支援・介護負担の軽減
フレイルやサルコペニアを早期に捉え、再入院を防ぐ視点は、今後のリハにおけるスタンダードになります。
⑥ 緩和ケアの導入
心不全における緩和ケアは、がん領域に比べてまだ普及が遅れている分野でした。しかし今回の改定では、ステージC以降からの早期介入が推奨され、患者の身体的・心理的・社会的苦痛への包括的支援が明記されました。
リハビリとしてできる緩和ケア:
• 疼痛や呼吸苦への姿勢調整
• 最期まで自分らしく動けることの支援
• ご家族との関係性の中での心理的サポート
「元気にさせること」だけがリハの目的ではない。“生ききる”ことを支えるリハビリへの転換が求められています。
改定内容の臨床への活かし方(リハ職目線で)
2025年の心不全診療ガイドライン改定を、私たち理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が日々の臨床にどう活かすか?
単なる知識で終わらせず、「行動に変える」視点で具体例を交えながら整理していきます。
⸻
● ステージ分類に応じた関わりの明確化
改定では、心不全のステージ分類(A~D)がより現場で意識しやすい形に整理されました。
| ステージ | 状態 | リハ職の関わり例 |
| A | 発症リスクあり(CKD・DM・HTなど) | 予防的介入・身体活動維持・生活指導 |
| B | 構造的心疾患あり/症状なし | ADL維持・心拍数や血圧に配慮した有酸素運動 |
| C | 明らかな症状あり | 呼吸苦・浮腫に配慮しつつ、機能回復を図るリハ |
| D | 難治性/緩和ケア必要 | 疼痛緩和・活動維持・意思尊重のアプローチ |
特にステージA・Bの予防的介入は、高齢者やフレイル患者に多く見られる軽度な兆候(倦怠感・易疲労性など)を見逃さず、先手を打つことが重要です。
⸻
● 脆弱期(退院後90日間)を意識した介入
改定では、退院後の最初の90日間を“ハイリスク期間”と位置づけ、再入院予防の鍵となる時期として明記されました。
この期間において私たちが行うべきことは:
• 訪問リハ・通所リハとの連携強化
→ 退院前からサービス調整・カンファレンス参加が重要です。
• 早期再評価・生活状況のモニタリング
→ 歩行距離・体重・食事量・倦怠感・浮腫などをこまめにチェック。
• 家族・介護者支援の意識
→ 「家で心不全を悪化させない暮らし方」の理解共有が必須です。
このような関わりを通じて、単なる再発防止だけでなく、患者が“心不全とともに生きる”生活を支えることができます。
⸻
● 緩和ケアの視点をリハに取り入れる
従来の「改善を目指すリハ」から、「生活の質を保ち、穏やかに過ごすことを支えるリハ」へ。
ガイドラインでも、ステージC~Dでは早期の緩和ケア導入が求められており、リハビリ職がその一翼を担います。
たとえば…
• 「痛みがない姿勢」「息苦しさを和らげる座位」などの工夫
• できる限り“その人らしい”動作や習慣を守る支援
• 食事動作・トイレ動作・会話など、尊厳を保つ支援
これは、QOLを最期まで守る「生きる支援」としてのリハビリであり、医師や看護師、ケアマネとも情報を共有しながら進めることが大切です。
⸻
おわりに:これからの「心不全と生きる」を支える医療へ
今回の2025年改定で強く感じたことは、心不全という疾患が単なる“心臓の問題”にとどまらなくなっているということです。
薬物療法はもちろん、生活習慣、栄養、フレイル予防、心理社会的支援、そして緩和ケアに至るまで——
心不全はまさに、“人生全体”を支える医療・支援が求められる時代に入ったことを象徴しています。
リハビリテーション専門職としての私たちは、「動けるようにする」だけでなく、
• その人が“どう生きたいか”に寄り添い、
• 最期まで自分らしく過ごすことを支える立場でもあります。
このガイドライン改定をきっかけに、ぜひ現場でのリハビリのあり方やアプローチを、少し立ち止まって見直してみてください。