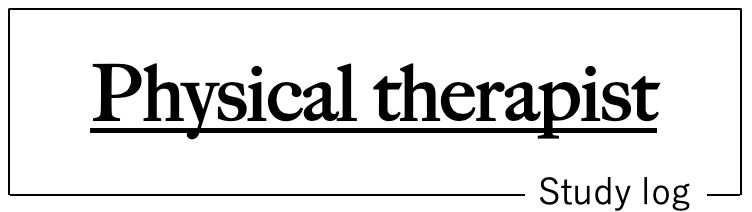はじめに

かず
こんにちは!
今回は心臓リハビリテーションにおける運動療法の適応と禁忌についての話をします。
手術療法や薬物療法に適応と禁忌があるように、運動療法にもあります。
運動療法は心臓リハビリテーションの中心的なプログラムです。
したがって、安全かつ効果的な運動療法を行うことが肝心であり、運動療法の適応と禁忌を理解することは不可欠です。
心リハにおける適応と禁忌
適応
- 医学的に安定している心筋梗塞後
- 安定狭心症
- 経皮的冠動脈形成術
- 冠動脈バイパス術
- 収縮機能障害または拡張機能障害のいずれかに起因する安定した心不全
- 心臓移植
- 弁膜症もしくは弁膜症術後
- 末梢動脈疾患
- 糖尿病、高脂血症、高血圧、肥満と判断され冠動脈疾患罹患のリスクがある
禁忌
- 不安定狭心症
- コントロールされていない高血圧(安静時収縮期血圧が180mmHgを超える、安静時拡張期血圧が110mmHgを超える。)
- 20mmHgを超える起立性低血圧で症状を伴うもの。
- 重度の大動脈弁狭窄症
- コントロールされていない心房または心室性不整脈
- コントロールされていない洞性頻脈(>120bpm)
- 非代償性心不全
- 3度房室ブロック(PMI未)
- 活動性心膜炎または心筋炎
- 亜急性期の塞栓症(肺または全身)
- 急性血管性肺静脈炎
- ・大動脈解離
- コントロールされていない糖尿病
- 運動を禁止されている重篤な整形外科的疾患
- 急性甲状腺炎、低カリウム血症、高カリウム血症または脱水のような他の代謝性病態(適切に治療されるまで)
- 重度精神障害
運動療法のリスク分類
SS心疾患患者の運動療法実際におけるリスク分類は、AHAのExercise Standard for Testing and Training(2013)が代表的に挙げられます。
特徴は、対象者の疾患重症度や臨床的特徴、運動耐容能、既往歴などを考慮して4段階にクラス分類されている点です。
監視型運動療法の監視の意味
運動療法における『監視』の意味は広義にわたる。
血圧や心電図、心拍数の監視以外にも下記のような事柄が挙げられます。
- 医療従事者による運動の直接の監視や指導
- 運動療法中の血圧や心拍数の監視
- 運動処方がしっかり守られているか
- 症状の変化や回復に基づいた運動処方の定期的な調整ができているか
最後に
運動療法は心臓リハビリテーションにおいて中心的なプログラムであり、安全かつ効果的に取り組むことが重要です。
運動によるプラスの影響を最大限に引き出すためには、個々の状況に応じて根拠に基づいた運動処方肝要です。
臨床の一助となりますように。