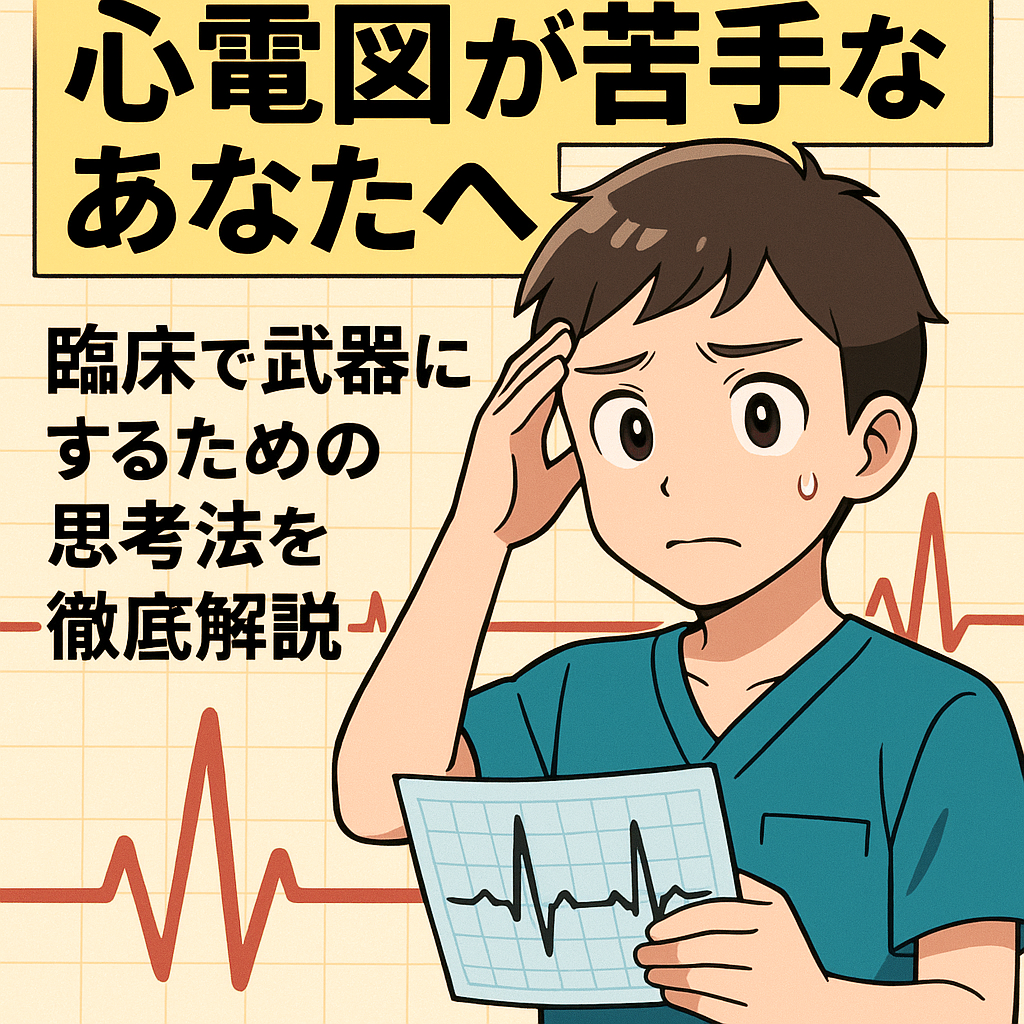はじめに
「心電図の波形を見ると、なんだか難しそうで苦手意識が…」
「循環器担当じゃないから、自分にはあまり関係ないかな?」
若手の理学療法士(PT)や学生の皆さんの中には、そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、高齢化が進み、多くの患者さんが何らかの心疾患リスクを抱える現代において、心電図はもはや循環器担当だけの知識ではありません。
整形外科でも、脳血管疾患でも、呼吸器でも、安全なリハビリテーションを提供する上で**理学療法士にとっての「必須スキル」**となりつつあります。
この記事では、難しい波形判読を一つひとつ覚えるのではなく、
- なぜ理学療法士に心電図の知識が必要なのか?
- 臨床でどう考え、どう活用すればいいのか?
という「思考法」に焦点を当てて、明日からの臨床に活かせるような知識を分かりやすく解説します。心電図への苦手意識を、「患者さんを守る武器」に変えていきましょう!
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。※有料記事が読み放題
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

理学療法士が知るべき2つの心電図【役割を理解しよう】
理学療法士が臨床で関わる心電図は、大きく分けて2種類あります。まずはそれぞれの「役割」をしっかり区別して理解することが、活用への第一歩です。
例えるなら、「健康診断」と「ドライブレコーダー」の違いです。
| 種類 | 役割 | タイミング | 例え |
| 標準12誘導心電図 | リスクの事前予測 | リハビリ介入前 | 心臓の健康診断 |
| モニター心電図 | リアルタイム監視 | リハビリ介入中 | 心臓のドライブレコーダー |
① 標準12誘導心電図:「心臓の健康診断」でリスクを予測する
標準12誘導心電図は、ベッドで安静にしている状態で12方向から心臓の電気活動を記録する精密検査です。これにより、リハビリを開始する前に、患者さんの心臓の「基本情報」や「隠れたリスク」を把握することができます。
カルテに貼られている検査結果の「所見」の欄が、私たちの見るべきポイントです。
- (例)所見に「右軸偏位」や「肺性P波」とあったら?
- 予測できること: もしかしたら肺の病気(COPDなど)が原因で、心臓の右側(右心系)に負担がかかっているかもしれない(=右心負荷)。
- リハビリでの注意点: こうした患者さんは運動中の息切れ(呼吸困難)や酸素飽和度の低下が起こりやすいかもしれない。リハビリ中は呼吸状態を特に注意深く観察しよう。
このように、細かい波形が読めなくても、「所見」から「リハビリ中のリスク」を予測し、備えることが理学療法士の重要な役割です。
② モニター心電図:「心臓のドライブレコーダー」で安全を守る
モニター心電図は、胸に数個の電極を貼り、リハビリ中など活動中の心臓の状態をリアルタイムで監視するものです。安静時ではわからない**「運動によって誘発される異常」**を見つけるのが最大の目的です。
理学療法士にとって、モニター心電図はリハビリの安全性を担保するための強力な「目」となります。
- 運動を「続けるか」「中止するか」の判断材料になる
- 患者さん一人ひとりに最適な「運動負荷量」を設定できる
- 安静時には見られない異常を発見し、医師や看護師に報告できる
理学療法士は、患者さんに運動という「負荷」をかける専門職です。だからこそ、負荷によって起こる心臓の変化を捉え、安全を確保する責任があります。


【実践】理学療法士は「多職種連携」で心電図を活かす
心電図の情報を最も活かせる場面の一つが、多職種との連携です。
安静にしている患者さんを看ている医師や看護師と違い、理学療法士は起き上がりや歩行練習といった負荷をかけている時の状態を直接観察できます。
- 「〇〇という運動をしたら、モニター心電図でこんな不整脈が出ました」
- 「介入前の12誘導で虚血の所見があったので、胸の痛みがないか確認しながら進めました」
こうした具体的な情報を共有することで、理学療法士は**チーム医療における「リスク管理のキーパーソン」**になることができます。薬剤(β遮断薬など)が心拍数に与える影響なども考慮しつつ、得られた情報を正確に報告することが、患者さんの治療全体に貢献するのです。
【要注意】理学療法士が特に注意すべき不整脈「心房細動」
数ある不整脈の中でも、理学療法士が臨床で出会う機会が多く、特に注意が必要なのが**「心房細動」**です。
心房細動は、心臓の中の「心房」が小刻みに震える不整脈です。これがなぜ危険かというと、心房内で血液がよどんで血の塊(血栓)ができやすくなり、その血栓が脳に飛ぶと脳梗塞を引き起こすからです。
【理学療法のリスク管理マニュアル】や【2021年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン】でも、心房細動患者のリハビリでは、心拍数の管理が重要であると指摘されています。
患者さんによって反応は異なりますが、急に心拍数が上がりすぎないよう、運動強度を慎重に設定することが求められます。また、交感神経が優位になると不整脈が出やすくなるため、患者さんがリラックスできる環境を整え、呼吸法などを取り入れることも有効なアプローチです。
まとめ:心電図は理学療法士の”味方”になる
今回は、理学療法士が臨床で心電図をどう活用すべきか、その思考法を中心に解説しました。
【今日のポイント】
- 心電図は全PTの必須スキル。患者さんを守るための武器になる。
- 介入前は「12誘導心電図(健康診断)」でリスクを予測する。
- 介入中は「モニター心電図(ドライブレコーダー)」で変化を監視する。
- 発見した情報は多職種に共有し、チーム医療に貢献する。
難しい波形判読を完璧にマスターする必要はありません。まずは、心電図から得られる情報を**「目の前の患者さんのリスク管理にどう活かすか?」**という視点で捉えることが大切です。
この記事を読んだあなたが、明日から担当患者さんのカルテを開き、心電図の所見に少しでも目を向けるきっかけになれば幸いです。
その小さな一歩が、患者さんの安全と、あなた自身の専門性を高める大きな一歩につながるはずです。