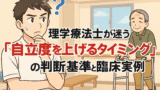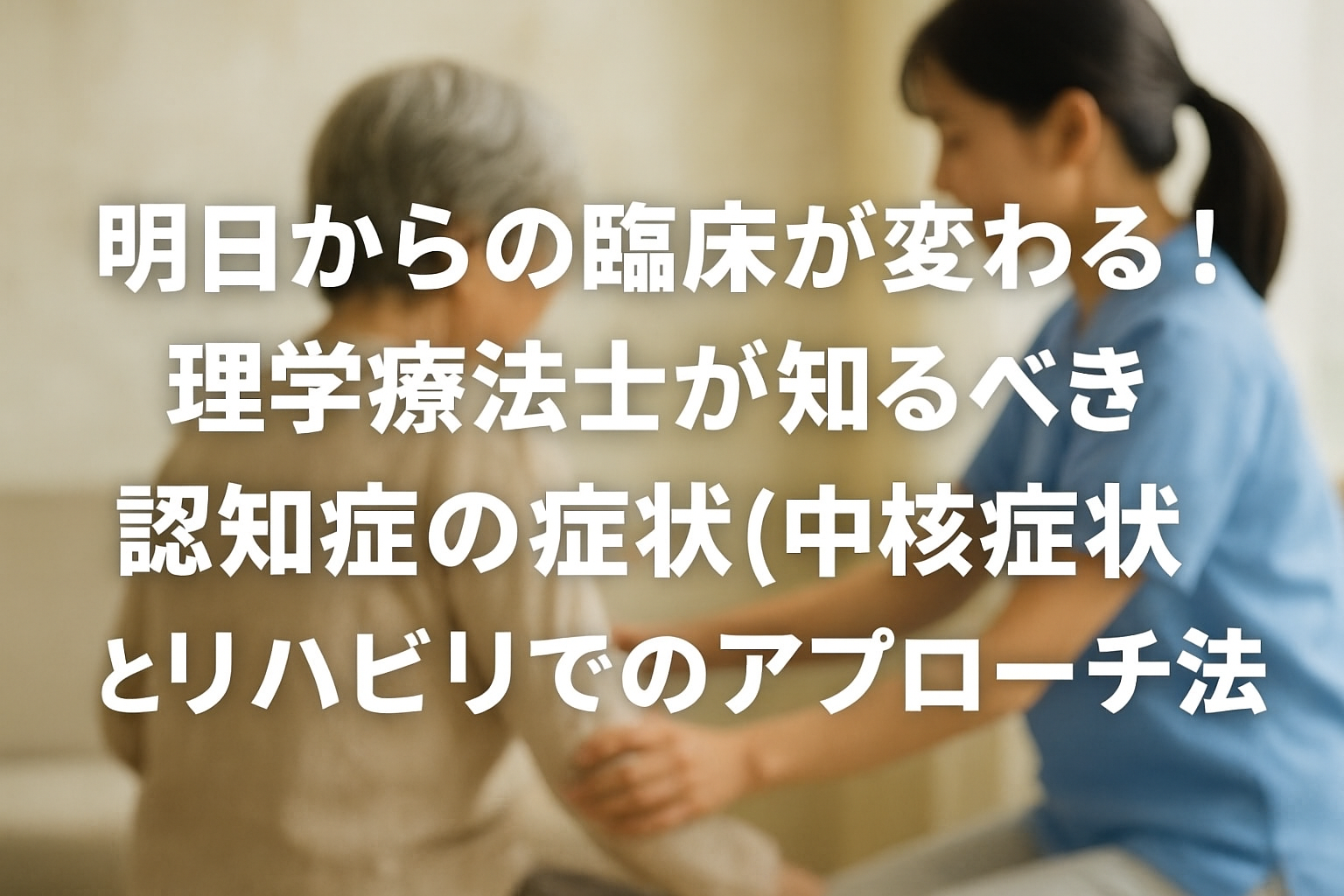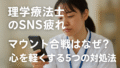こんなお悩み、ありませんか? ~認知症リハビリの壁~

昨日できた移乗動作が、今日は全くできなくなってしまった…

指示がなかなか伝わらず、何度も同じ説明を繰り返している…

急に『家に帰る!』とリハビリを拒否され、対応に困ってしまう…
理学療法士として認知症の患者さんを担当する中で、このような経験はありませんか?
これらの悩みは、患者さんの「やる気」や「性格」の問題ではなく、認知症の症状が原因かもしれません。認知症の症状を正しく理解することは、効果的なリハビリテーションを提供し、患者さんとの良好な関係を築くための第一歩です。
この記事では、理学療法士が知っておくべき認知症の「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」について、リハビリ場面の具体例を交えながらお話していきます。
この記事が、明日からのアプローチが変わり、リハビリの質が向上するヒントが見つかるきっかけとなれば幸いです。
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

なぜ私たち理学療法士が「認知症」を深く学ぶ必要があるのか?
高齢化が進む日本において、理学療法士が認知症の知識を持つことは、もはや必須と言えます。その意義は大きく分けて4つあります。
- リハビリ効果を最大化するため
認知機能は「運動学習」の土台です。記憶力や注意力が低下している方に、健常者と同じ指導をしても効果は限定的です。症状を理解し、その方に合った指示の出し方(短い言葉、ジェスチャーなど)や練習方法を工夫することで、運動学習を促し、リハビリ効果を最大限に引き出せます。 - 転倒などのリスク管理の質を高めるため
注意障害による見落としや、失行による道具の誤用は、転倒の直接的な原因になります。症状からリスクを予測できれば、「動線上の物を減らす」「歩行器の前に目印を置く」といった予防的な環境設定や介助が可能になり、患者さんの安全を守ることに繋がります。 - 患者・家族との信頼関係を築くため
リハビリ拒否や興奮といったBPSD(周辺症状)は、ご本人の不安や苦痛のサインです。その背景を理解しようと努める姿勢は、患者さんに安心感を与え、信頼関係を深めます。結果的に、リハビリへの意欲を引き出すことにも繋がります。 - チーム医療における専門性を発揮するため
理学療法士は、ADL(日常生活動作)を通じて「認知機能が身体機能にどう影響しているか」を最も評価しやすい職種の一つです。その専門的な視点からの情報を多職種(医師、看護師、OT、ケアマネジャー等)と共有することで、より質の高いケアプランの作成に貢献できます。
【脳の機能低下が原因】「中核症状」とリハビリでの着眼点
中核症状は、脳の神経細胞が壊れることによって直接引き起こされる症状です。
ここでは代表的な中核症状と、理学療法場面でどのように現れ、どう対応すればよいかを解説します。
| 中核症状 | 解説 | リハビリ場面での現れ方(例) | 対応のヒント(例) |
| 記憶障害 | 新しいことを覚えられない。特に直前の出来事を忘れやすい。 | ・前回の練習内容を覚えていない ・自主トレの方法や注意点を忘れる | ・毎回同じ手順で始める(手続き記憶※を活用) ・写真やイラスト付きの手順書を渡す ・「前回も上手にできましたよ」と成功体験を伝える |
| 見当識障害 | 時間、場所、人物などが分からなくなる。 | ・リハビリ室の場所が分からず迷う ・担当の理学療法士を認識できない ・「今は何時?」と何度も聞く | ・リハビリ開始時に「〇〇さん、こんにちは!理学療法士の〇〇です。ここはリハビリ室ですよ」と自己紹介と場所の確認を行う ・病室やリハビリ室にカレンダーや時計を置く |
| 理解・判断力の障害 | 物事を順序立てて考えたり、複数のことを同時に処理したりするのが難しい。 | ・「右手で手すりを持って、左足から…」のような複雑な指示が通らない ・急な予定変更に対応できない | ・指示は**「一つずつ」「短く」「具体的に」**(ワンステップ・コマンド) ・ジェスチャーや実演(モデリング)を多用する |
| 実行機能障害 | 計画を立てて、段取りよく行動することができない。 | ・着替えやトイレ動作の手順が分からなくなる ・歩行器を使って歩く、という一連の動作がスムーズに行えない | ・動作を「ズボンに足を通す」「立ち上がる」のように細かく分解して一つずつ誘導する ・声かけや軽いタッチで次の動作を促す |
※手続き記憶:自転車の乗り方のように、体で覚える記憶のこと。反復練習で習得しやすく、忘れにくいのが特徴です。
【心と環境が影響】BPSD(周辺症状)は患者さんからのSOSサイン
BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、中核症状に本人の性格、身体状態、環境、人間関係などが複雑に絡み合って生じる、行動面・心理面の症状です。
BPSDを「問題行動」と捉えるのではなく、「ご本人の困りごとや苦痛の表現(SOSサイン)」と捉える視点が、私たち専門職には不可欠となります。
ここでは、理学療法士がよく遭遇するBPSDのケースと対応のヒントをご紹介します。
- 背景にある感情・原因は?
- 身体的な苦痛(痛み、疲労、便秘、空腹など)
- リハビリへの不安(「また失敗するかも」「何をされるか分からない」)
- プライド(「できない姿を見せたくない」)
- 対応のヒント
- 否定しない、無理強いしない: 「やりたくないのですね」とまずは気持ちを受け止めます。
- 理由を探る: 「どこか痛いですか?」「少しお疲れですか?」と体調を確認します。
- ハードルを下げる: 「今日はベッドサイドで足の運動だけしませんか?」「少し廊下を散歩するだけでも違いますよ」など、本人に選択肢を提示し、受け入れやすい目標を設定します。
- 背景にある感情・原因は?
- 強い不安感・孤独感(「ここはどこ?」「自分の居場所がない」)
- 役割の喪失(「家に帰ってご飯の支度をしないと」)
- 身体的な不快感や、運動したいという欲求
- 対応のヒント
- 気持ちを受け止める: 「お家に帰りたいのですね。ご家族が心配ですよね」と共感的に関わります。
- 関心をそらす: 安全を確保しながら一緒に歩き、「お花が綺麗ですね」「お茶でも飲みませんか?」など、本人が興味を持ちそうな話題に切り替えます。
- 目的をリハビリに繋げる: 「お家に帰るためにも、しっかり歩く練習をしましょう!」と、本人の願望をリハビリの動機付けに変換します。
まとめ:認知症の理解は、理学療法士としての新たな武器になる
認知症のリハビリテーションは、一筋縄ではいかない難しさがあります。しかし、その言動の背景にある「中核症状」と「BPSD」を正しく理解することで、私たち理学療法士のアプローチは大きく変わります。
- 中核症状を理解すれば、効果的な運動学習の方法が見えてくる。
- BPSDを「SOSサイン」と捉えれば、患者さんの心に寄り添い、信頼関係を築ける。
目の前の患者さんの「できないこと」だけでなく、**「できること」や「感じていること」**に目を向けてみてください。認知症への深い理解は、あなたと患者さんとの関係をより豊かにし、理学療法士としての可能性を大きく広げる“新たな武器”になるはずです。
まずは明日からの臨床で、担当する患者さんの言動の背景を少しだけ考えてみることから始めてみませんか?