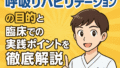はじめに:なぜ今、理学療法士がCOPDを深く知るべきなのか
新人・学生の皆さん、そして呼吸リハビリテーションの知識を再確認したい理学療法士の皆さん。臨床現場で「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」の患者さんを担当し、何から評価し、どうアプローチすれば良いか悩んだ経験はありませんか?
COPDは、日本の成人における死因の上位を占める疾患であり、その患者数は増加傾向にあります。そして、COPD患者の生命予後やQOL(生活の質)、再入院率を改善する上で、私たち理学療法士による「呼吸リハビリテーション」が極めて重要であることは、数多くのエビデンスで証明されています。
この記事では、COPDの理学療法に自信を持って臨めるよう、以下の内容を体系的に解説します。
- 介入の根拠となる「病態生理」
- 患者の状態を把握する「評価」
- エビデンスに基づいた「具体的な介入プログラム」
この記事から、明日からの臨床で「なぜこのアプローチが必要なのか」を自信を持って説明できるようになるヒントを知っていただけると幸いです。
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

【病態生理の再確認】COPDで肺に何が起きているのか?
理学療法介入の根拠を理解するため、まずはCOPDの病態生理を整理しましょう。COPDは主に2つの病態が混在しています。
1. 肺気腫(Emphysema):肺胞の破壊
長年の炎症により、酸素交換の場である「肺胞」の壁が破壊されます。これにより、肺は弾力を失い、古くなった風船のように伸び切ってしまいます。
その結果、息を吐き出す力(弾性収縮力)が弱まり、末梢気道が虚脱しやすくなります。これが「息を吐ききれない」状態、すなわち**閉塞性換気障害(FEV1/FVC < 70%)**の主因です。
2. 慢性気管支炎(Chronic Bronchitis):気道の炎症
空気の通り道である気道に慢性的な炎症が起こり、気道の壁が厚くなります(肥厚)。また、粘液を分泌する杯細胞が増加し、痰が多くなることで気道が狭くなります。
これらの病態が進行すると、以下の生理学的変化が生じます。
- ガス交換障害: 低酸素血症や高炭酸ガス血症を引き起こします。
- 肺の過膨張(Hyperinflation): 息を吐ききれないため、肺に空気が過剰に溜まった状態になります。これにより、主要な呼吸筋である横隔膜が押し下げられて扁平化し、筋収縮の効率が著しく低下します。
この横隔膜機能不全を代償するため、患者は頸部や肩甲帯の補助呼吸筋を過剰に使うようになり、これが肩こりや呼吸困難感の増悪に繋がるのです。
(ここに健康な肺とCOPDの肺の比較イラストを挿入)
[altタグ:COPDの病態生理 肺気腫と慢性気管支炎のイラスト]
【臨床での共通言語】GOLD分類と重症度評価
COPDの重症度を客観的に評価し、多職種と情報を共有するために「GOLD分類」を理解することは必須です。2023年に改訂された**「ABE評価ツール」**が現在の主流です。
| 評価項目 | 内容 |
| 気流閉塞 | 1秒率(FEV1)の予測値(%FEV1)に基づき重症度を分類(GOLD 1~4) |
| 症状評価 | mMRCスケール(息切れの程度)や CAT(包括的な症状評価)を使用 |
| 増悪歴 | 過去1年間の増悪(入院を含む)の回数 |
これらの3つの要素を組み合わせて、患者をグループA、B、Eに分類し、治療方針を決定します。私たち理学療法士も、担当患者がどのグループに属するかを把握しておくことが重要です。
【介入に繋げる評価】理学療法士が行うべきCOPDの評価
効果的なリハビリプログラムを立案するためには、多角的な評価が欠かせません。
- 問診・視診・聴診
- 視診: 樽状胸郭、口すぼめ呼吸、補助呼吸筋(胸鎖乳突筋など)の肥大、チアノーゼの有無を確認します。
- 聴診: 呼吸音の減弱(肺気腫)、Wheezes(笛音:気道狭窄)、Coarse crackles(水泡音:気道内分泌物)を聴き分けます。
- 呼吸機能検査(スパイロメトリー)の解釈
- FEV1/FVC < 70%: 閉塞性換気障害の確定。
- %FEV1: 気流閉塞の重症度を把握します。
- 呼吸困難の評価
- mMRCスケール: ADLにおける息切れの程度を把握します。
- 修正Borgスケール: 運動中の主観的な呼吸困難感や疲労度をリアルタイムで評価するために用います。
- 運動耐容能の評価
- 6分間歩行試験(6MWT): 全身持久力の指標となる最も代表的な評価です。歩行距離だけでなく、実施前後のSpO2、心拍数、Borgスケールの変化を記録することが極めて重要です。
- シャトルウォーキングテスト(ISWT): 段階的に速度が上がるため、最大運動耐容能を評価するのに適しています。
- 筋機能評価
- 呼吸筋力: 最大吸気圧(MIP)、最大呼気圧(MEP)で評価します。
- 四肢筋力: COPD患者は全身性炎症や低栄養、身体不活動により**「骨格筋機能障害」**を合併しやすいため、握力や大腿四頭筋筋力の評価は必須です。
【理学療法介入の実際】COPDリハビリテーションの3本柱
評価で抽出した問題点に基づき、具体的な介入を行います。COPDの呼吸リハビリテーションは、主に以下の3つの柱で構成されます。
COPD患者は「息が苦しいから動かない → 体力が落ちてさらに息苦しくなる」という呼吸困難-身体不活動の悪循環に陥っています。運動療法は、この悪循環を断ち切るための最も効果的な介入です。
- 目的: 運動耐容能の向上、呼吸困難感の軽減、QOLの改善
- 処方の原則(FITT):
- 頻度(Frequency): 週3~5回
- 強度(Intensity): **修正Borgスケール4~6(ややきつい)**程度、または6MWTの平均速度を参考に。SpO2が88~90%を下回らないようにモニタリング。
- 時間(Time): 1回20~30分。継続が難しい場合は、10分×3回などの分割も有効。
- 種類(Type): 歩行、自転車エルゴメーターなどの有酸素運動と、上下肢のレジスタンストレーニングを組み合わせます。
効率的な呼吸パターンを学習させ、排痰を促します。
- 呼吸法指導
- 口すぼめ呼吸: 息を吐くときに口をすぼめることで気道内圧を高め、末梢気道の虚脱を防ぎます。息苦しさを感じた際のセルフコントロール法として指導します。
- 腹式呼吸: 横隔膜の活動を促し、補助呼吸筋の過剰な使用を抑制します。ただし、過膨張が著しい患者では逆効果になることもあるため、安易な指導は禁物です。
- 気道クリアランス(排痰法)
- 痰の貯留が多い患者に対し、ハッフィングや体位ドレナージを指導・実施します。
日常生活での息切れを軽減し、自己管理能力を高める支援です。
- 省エネルギー動作指導(Energy Conservation):入浴や更衣などのADL場面で、動作と呼吸(特に呼気)のタイミングを合わせる「Pacing(ペーシング)」を指導します。
- 増悪時のアクションプラン教育: 痰の色や量、息切れの変化など、増悪のサインに自分で気づき、早期に受診行動がとれるよう教育することも理学療法士の重要な役割です。
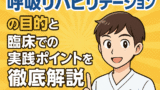
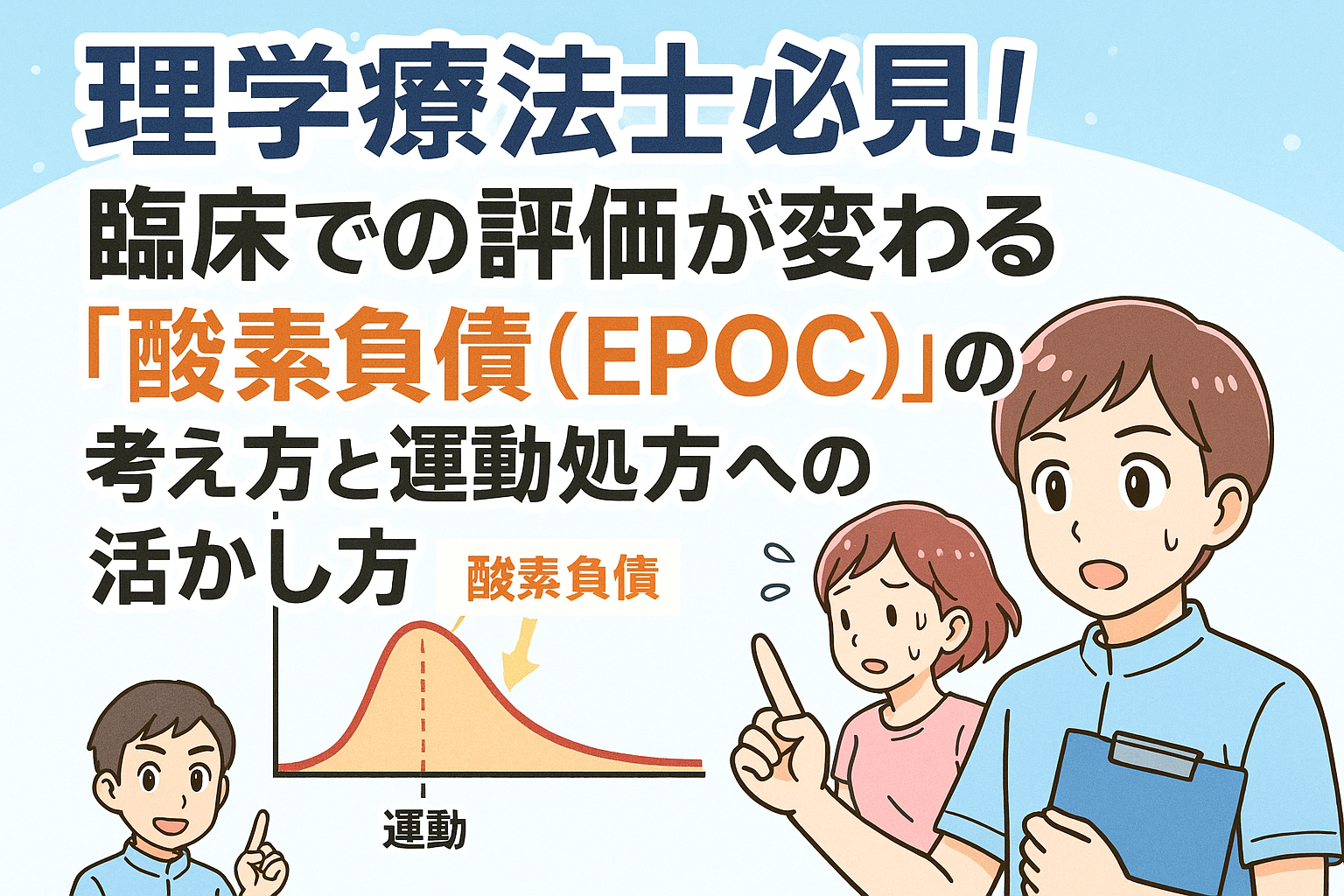
まとめ:COPD患者の人生に寄り添う理学療法士であるために
本記事では、理学療法士がCOPD患者を担当する上で必須となる病態生理、評価、介入の知識を解説しました。
- COPDは肺の過膨張と気道狭窄により、呼吸効率が低下する疾患である。
- 理学療法評価では、呼吸機能だけでなく運動耐容能や四肢筋力も評価する。
- 介入の核は運動療法であり、呼吸困難-身体不活動の悪循環を断ち切ることが目標となる。
COPDの理学療法は、単なる機能訓練ではありません。薬物療法や栄養療法と連携し、患者さんが自分らしく、より良い生活を送れるよう人生に寄り添う、非常にやりがいのある分野です。
この記事をきっかけに、ぜひさらに学びを深め、目の前の患者さんに最高のケアを提供できる理学療法士を目指してください。