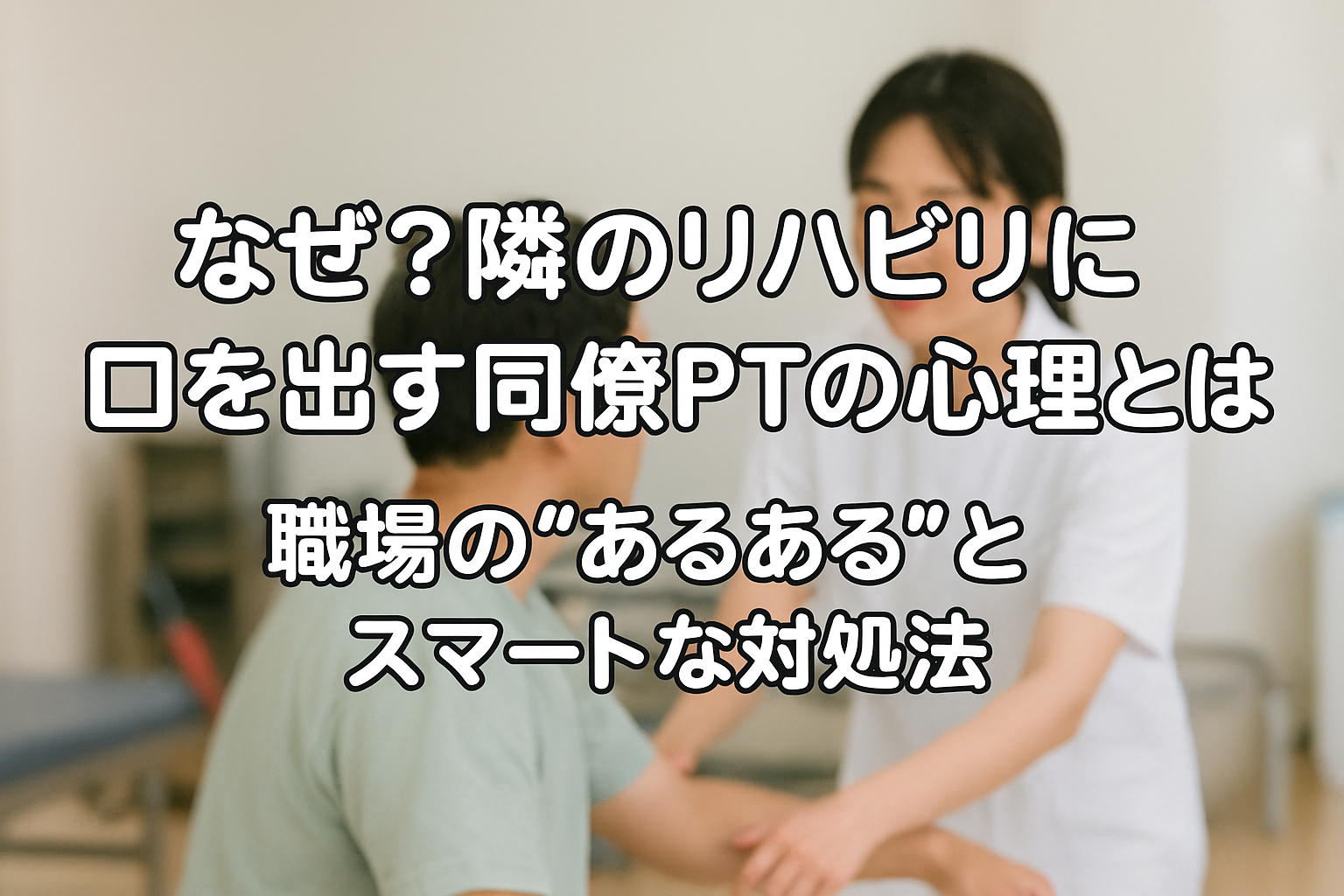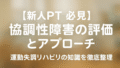その一言に、何度モヤっとしましたか?
患者さんと一緒に立てた目標に向かって、信頼関係を築きながらリハビリを進めている、その時。
ふと隣から現れた同僚(先輩)が、患者さんの前でこう言いました。
「あれ、なんでその運動やってるの?僕ならこうするけどな」
この瞬間、頭をよぎるのは様々な感情。
自分のアプローチを否定されたような気持ち。患者さんが不安そうな顔をしている焦り。計画の意図を一から説明する気力も失せる、あの何とも言えないモヤモヤ感…。
理学療法士(PT)なら、一度は経験したことがあるのではないでしょうか?
良かれと思って言ってくれているのは分かる。でも、タイミングも場所も、そして言い方も「それじゃない感」がすごい。
この現象、なぜ起きてしまうのでしょう。今回は、つい他人のリハビリに口を出してしまうPTの心理を深掘りし、私たちがプロとしてどう向き合っていけばいいのかを一緒に考えてみたいと思います。
なぜ彼らは口を出すのか?考えられる心理パターン5選
一方的に「やめてほしい」と思うだけでは、人間関係がこじれるだけかもしれません。まずは、相手の行動の裏にある心理を理解することから始めましょう。彼らの行動は、大きく5つのタイプに分けられるかもしれません。
善意100%の「お助けヒーロー」型
【心理】
「もっと良い方法があるのに!」「患者さんのためを思って!」という純粋な親切心と正義感からくるタイプ。悪気は一切なく、むしろ「良いことをしている」と信じています。
【特徴】
- 自分の知識や成功体験をシェアしたい気持ちが強い。
- 相手の治療プランの背景(患者さんの価値観、生活史、細かい評価結果など)を確認する前に、アドバイスが先行しがち。
- 「教えてあげる」というスタンスがにじみ出てしまうことも。
不安の裏返し「自己肯定感ウォンツ」型
【心理】
実は自分のアプローチに自信がなく、その不安を他者への指摘で補おうとしています。他人のやり方に意見し、それが受け入れられることで「自分の考えは間違っていない」と安心したい、という承認欲求が隠れています。
【特徴】
- 「〇〇ってどう思う?」と意見を求めるようで、実は自分の正しさを確認したいだけ。
- 「そうだね」と同意されると安心し、逆に反論されると不機嫌になることも。
- 実は自分自身も臨床で迷っていることが多いタイプです。
知識を披露したい「歩く教科書」型
【心理】
最近参加したセミナーや読んだ論文の知識を、誰かに話したくて仕方がないタイプ。「自分はこんなに勉強しているんだ」ということをアピールし、知的な優位性を示したいという欲求があります。
【特徴】
- 「〇〇の研究によると」「エビデンス的には…」といった言葉を多用する。
- 実践的な効果よりも、知識の正しさや新しさを重視する傾向が強い。
- 議論は好きですが、相手の臨床的な判断を尊重する視点が欠けていることも。
“俺のやり方”が絶対の「こだわり職人」型
【心理】
長年の経験で培った自分の治療スタイルや哲学が「唯一の正解」だと信じています。自分と異なるアプローチを許容できず、ある種の完璧主義や強いこだわりを持っています。
【特徴】
- 「普通はこうする」「基本はこうでしょ」といった、自分の価値観を基準にした発言が多い。
- 新しい知見やアプローチに対して、やや否定的なスタンスを取りがち。
- 経験が豊富なベテランPTに多いかもしれません。
コミュニケーションの一環「悪気なき雑談」型
【心理】
最もシンプルで、そして最も厄介かもしれないのがこのタイプ。特に深い意図はなく、会話のきっかけや挨拶のような感覚でリハビリ内容に触れているだけです。
【特徴】
- 指摘の内容が浅く、具体的な根拠がないことが多い。
- 言った本人はすぐに忘れているため、言われた側だけがモヤモヤを引きずってしまう。
モヤッとした時の処方箋!スマートな対処法4ステップ
では、実際にこのような場面に遭遇した時、私たちはどう対応すればよいのでしょうか。感情的にならず、プロとしてスマートに対応するための4つのステップをご紹介します。
ステップ1:まず“売り言葉に買い言葉”を避ける
「でも!」「だって!」と反射的に反論したくなる気持ちをぐっとこらえましょう。まずは「なるほど、そういう視点もあるんですね」と、一旦受け止めるクッション言葉を使うのが効果的です。深呼吸して、冷静になる時間を作りましょう。
ステップ2:「なぜ?」を「対話」に変える魔法の質問
一方的な指摘で終わらせないために、こちらからボールを投げ返します。
- ①自分の根拠を簡潔に伝える
「ありがとうございます。この方は〇〇という背景があるので、今は△△を目的にこの運動を選択しています。」 - ②相手に質問で返す
「先生なら、どういった点を考慮してアプローチされますか?」
このように尋ねることで、一方的な“口出し”を、患者さんのための建設的な“ディスカッション”に転換させることができます。
ステップ3:感謝を伝えて「学び」に変える
たとえ的外れな意見だと感じても、「ありがとうございます。一つの意見として参考にさせていただきます」とプロとして対応しましょう。もし少しでも有益な情報が含まれていれば、「その視点はなかったです!勉強になります!」と素直に感謝を伝えることで、相手との関係性も良くなり、自分の成長にも繋がります。
ステップ4:時には「戦略的スルー」も大切
患者さんの前で議論が長引くのは避けたいもの。「ありがとうございます。その件、また後でゆっくりお話聞かせてください」とその場をスマートに収めましょう。すべての意見に100%真剣に向き合う必要はありません。心を守るための**「戦略的スルー」**も立派なスキルです。
【まとめ】個人の問題から、より良い「チームの文化」へ
同僚からの「口出し」が頻発する職場は、個人の性格だけの問題ではないかもしれません。それは、チーム内で気軽に相談したり、症例検討をしたりする**「公式な対話の場」が不足しているサイン**ではないでしょうか。
お互いの専門性をリスペクトし合い、若手もベテランも建設的な意見交換ができるカンファレンスや勉強会があれば、「隣のリハビリ」に不意打ちで介入する必要も減っていくはずです。
隣のリハビリへの一言は、私たちのチームのあり方を映す鏡です。
明日から、その一言を一方的なアドバイスではなく、「〇〇さん(患者さん)のために、一緒に考えよう」というチームプレーのパスに変えてみませんか。その小さな意識の変化が、きっとあなたの職場の風通しを良くし、最終的には患者さんへのより良いリハビリテーションに繋がっていくはずです。