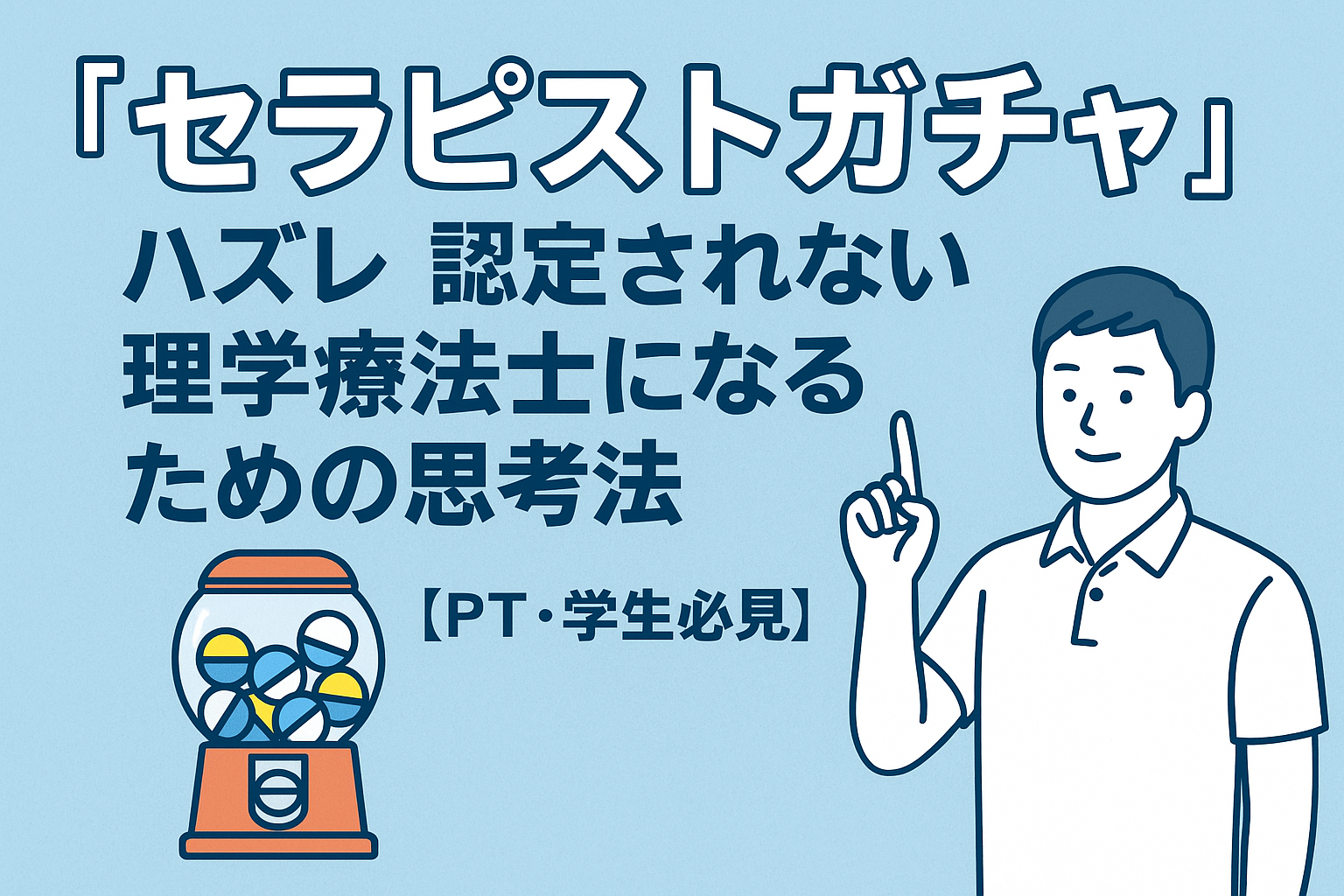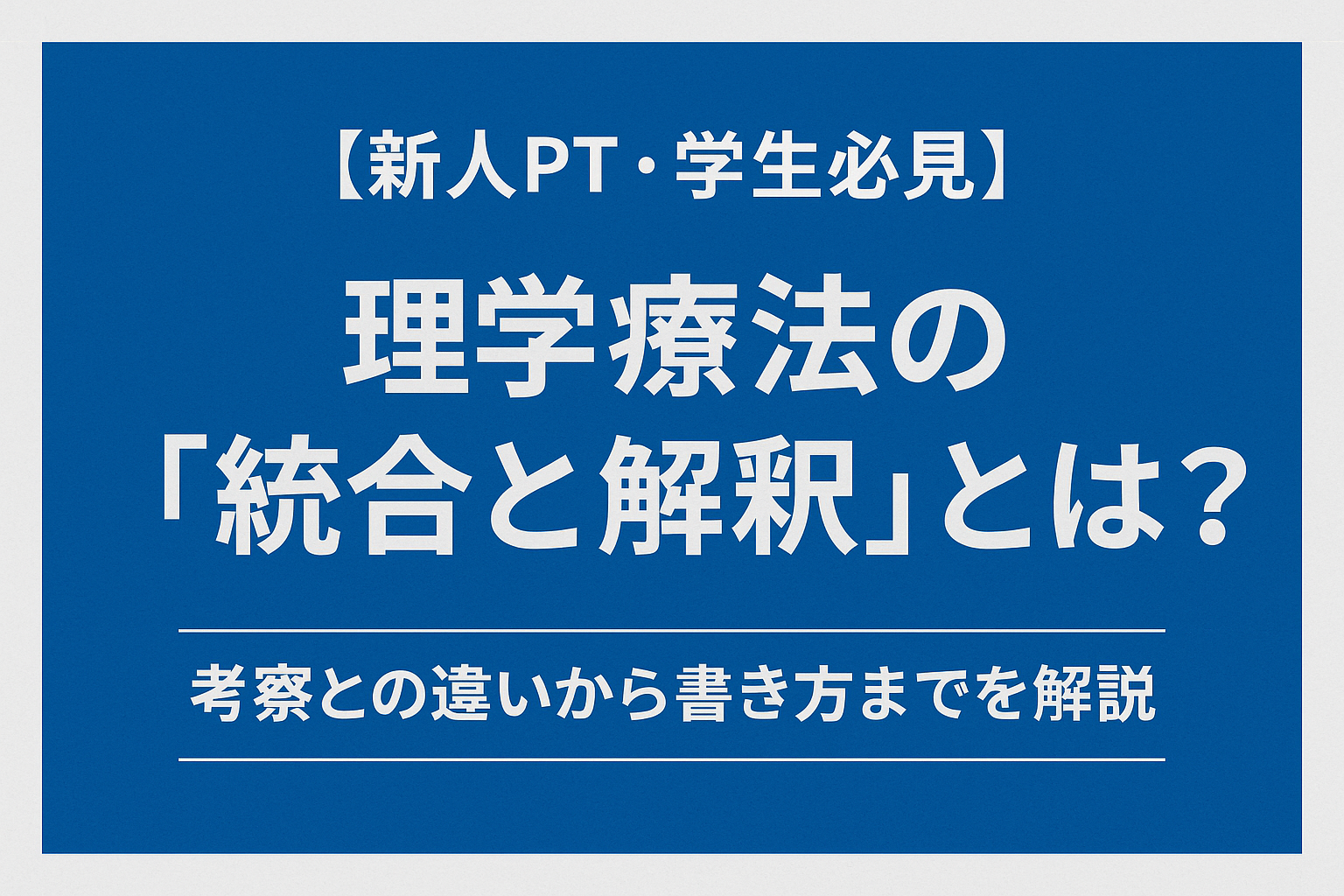はじめに:その言葉、他人事だと思っていませんか?
「今日の担当、ハズレだったな…」
もし、あなたの知らないところで、担当した患者さんがそう感じていたら…?
理学療法士(PT)として、あるいはそれを目指す学生として「セラピストガチャ」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
これは、担当するセラピストによってリハビリの質や満足度が大きく変わることを、患者さん側が揶揄して使う言葉です。
私たちは国家資格を持つプロフェッショナルです。しかし、患者さんが「当たり」「ハズレ」という物差しで我々を見ているという現実は、決して無視できませんよね。
この記事では、「セラピストガチャ」という耳の痛い言葉を、私たち自身の成長の糧とするために、なぜそう呼ばれてしまうのか、そして「当たり」と信頼されるセラピストになるためには何が必要かを、現場のリアルな視点から深掘りしていきます。
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

なぜ私たちは「ガチャ」と呼ばれるのか?目を背けてはいけない3つの理由
患者さんが担当者を自由に選べない制度上の問題は確かにあります。しかし、その責任を制度だけに押し付けてはいけません。私たち自身の「質」に差があることも、紛れもない事実です。
臨床スキルの「引き出し」の差
同じ国家試験を通過しても、臨床に出てからの学びでスキルには大きな差が生まれます。
- 知識のアップデート不足: 資格取得時の知識のまま、最新のエビデンスや治療アプローチを学んでいない。
- アセスメント能力の偏り: 自分の得意な評価や手技に固執し、患者さん一人ひとりに合わせた多角的な視点が欠けている。
- 引き出しの少なさ: いつも同じような運動メニューを処方し、患者さんの状態やニーズに合わせた工夫ができない。
この差は、患者さんには「説明の説득力」や「リハビリ内容の納得感」として明確に伝わってしまいます。
「治療的関係」を築くコミュニケーション能力の欠如
リハビリは技術を提供するだけの作業ではありません。患者さんとの信頼関係、すなわち「治療的関係」を築けているかどうかが、成果を大きく左右します。
- 一方的な「指導」: 患者さんの希望や不安を聞かず、「これが正しいから」と一方的にリハビリを進める。
- 共感性の欠如: 患者さんの訴えに対し、「痛いのは当たり前」「頑張りが足りない」といった態度で接してしまう。
- 説明不足: 専門用語を多用し、なぜこのリハビリが必要なのか、患者さんが理解・納得できる言葉で伝えていない。
「話しやすい」「この先生になら任せられる」と感じてもらえるかは、純粋な技術以上に重要な要素です。
プロフェッショナルとしての「姿勢」の差
日々の業務に追われる中で、プロとしての姿勢を保ち続けられているでしょうか。
- 目標共有の欠如: 患者さんと共に具体的な目標(Shared Decision Making)を設定せず、ただ漫然とリハビリを行っている。
- 振り返りの習慣がない: 自分の臨床が本当に正しかったのか、もっと良い方法はなかったのかを省みる(リフレクションする)習慣がない。
- マニュアル的対応: 患者さんを「〇〇疾患の人」と一括りにし、その人自身の生活や価値観に目を向けていない。
この「姿勢」の差が、患者さんにとっては「熱意」や「誠実さ」として映り、「当たり」「ハズレ」の印象を決定づけていきます。
【自己診断】あなたは大丈夫?「ハズレ」認定されがちなセラピストの共通点
もし、以下の項目に一つでもドキッとしたら要注意です。
- 患者さんから質問されると、少し面倒に感じてしまう。
- リハビリの目標を、患者さん本人の言葉で言える自信がない。
- ここ1年、新しい論文を読んだり、外部の勉強会に参加したりしていない。
- リハビリ中、患者さんより自分の話をしている時間の方が長い。
- 「前の担当者はどうでしたか?」と患者さんに聞くのが少し怖い。
これらは、いつの間にか「ハズレ枠」に分類されてしまう危険信号です。
「あなたで良かった」と言われるために。明日からできる3つのアクション
では、「ガチャ」と言わせない、選ばれるセラピストになるためには何をすべきでしょうか。
アクション1:臨床推論のプロセスを「言語化」する
なぜその評価を選んだのか?なぜその治療アプローチを行うのか?その根拠(エビデンス)は何か?
この臨床推論のプロセスを、患者さんにも、そして自分自身にも説明できるようになりましょう。
「今日は〇〇という目的で、この筋肉を鍛えるトレーニングをします。これが改善すると、階段昇降が楽になりますよ」
このように、一つひとつの介入に意味と目的を言語化して伝えるだけで、患者さんの納得度とモチベーションは劇的に向上します。
アクション2:「傾聴」から始めるコミュニケーションを徹底する
患者さんの口から出る言葉だけでなく、その裏にある**感情や生活背景、本当の願い(Needs)**に耳を傾けましょう。
- 「はい・いいえ」で終わらない質問(オープンクエスチョン)を心がける。
- (×)「痛みはありますか?」
- (○)「どんな時に、どんな風に痛みを感じますか?」
- 患者さんの言葉を要約して繰り返す(バックトラッキング)。
- 「なるほど、つまり〇〇という点が一番お困りなのですね」
- 沈黙を恐れない。 患者さんが言葉を探す時間を尊重する。
技術を提供する前に、まず相手を深く知ること。それが信頼関係の第一歩です。
アクション3:小さな「リフレクション(省察)」を習慣にする
一日の終わりに5分でも構いません。
- 「今日の〇〇さんへのアプローチは最適だったか?」
- 「もっと分かりやすい説明はできなかったか?」
- 「あの時、患者さんは本当は何を言いたかったのだろう?」
このように自分の臨床を客観的に振り返る習慣が、あなたを成長させ続けます。日々の小さな気づきと修正の積み重ねが、数年後、他のセラピストとの圧倒的な差を生み出すのです。
【理学療法士を目指す学生へ】「指導者ガチャ」を乗り越え、未来の「当たり」になるために
臨床実習では「どの指導者に当たるか(指導者ガチャ)」を心配するかもしれません。しかし、どんな指導者からも学べることは必ずあります。
- 「なぜ?」を考える癖をつける: 指導者の手技をただ真似るのではなく、「なぜこの手技なのか」「他の選択肢はなかったのか」を常に考えましょう。
- 最高の観察者になる: 患者さんから信頼されているセラピストの言動、表情、言葉選びを徹底的に観察し、良い点を盗んでください。
- コミュニケーションの練習台と心得る: 実習は、患者さんとのコミュニケーションを学べる絶好の機会です。失敗を恐れず、積極的に対話を試みましょう。
学生時代から「自分ならどうするか?」という当事者意識を持つことが、将来「当たり」と評されるセラピストになるための最短ルートです。
まとめ:「セラピストガチャ」は、私たちの成長を促す鏡である
「セラピストガチャ」という言葉は、私たち専門職にとって厳しい現実を突きつけます。しかし、それは同時に「患者さんは、私たちの人間性や努力をしっかり見ている」という証でもあります。
この言葉を単なる批判と捉えるのではなく、自らの臨床を見つめ直し、成長するための「鏡」として活用しましょう。
技術を磨き、知識を深め、そして何より一人ひとりの患者さんと真摯に向き合う。
その日々の積み重ねこそが、私たちを「ガチャの景品」ではなく、患者さんの人生を支える、かけがえのない「パートナー」へと変えてくれるはずです。