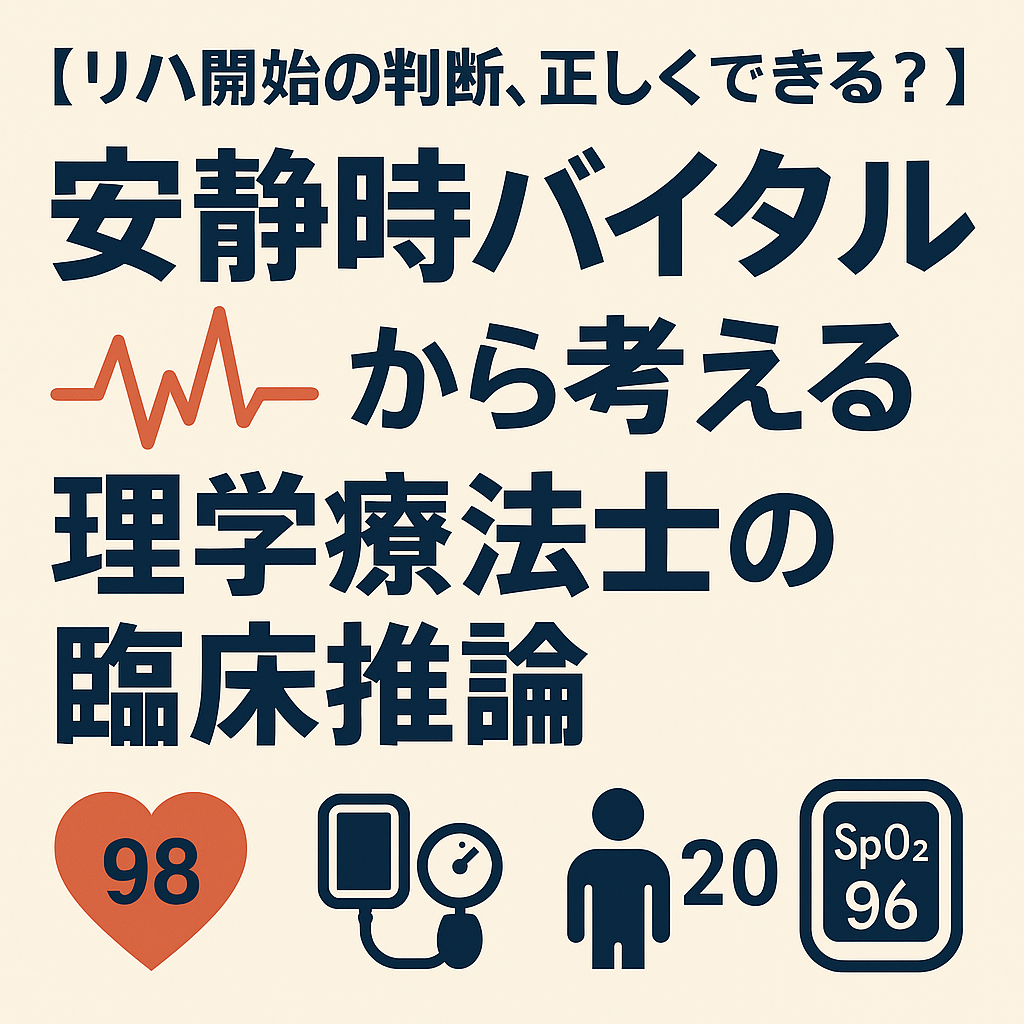はじめに
「バイタルは正常範囲だからリハOK!」
本当にそうでしょうか?
臨床の現場では、患者の心拍数(HR)、血圧(BP)、呼吸数(RR)、酸素飽和度(SpO₂)を確認し、リハビリの可否を判断するのが基本です。しかし、単に数値が正常範囲内だからといって、必ずしもリスクがないとは限りません。
例えば、同じ心拍数98 bpmでも、発熱による頻脈か、貧血によるものか、はたまた疼痛の影響かによって対応が異なります。また、血圧が140/90 mmHgであっても、降圧薬の影響や脱水によって低下する可能性があるため、離床後の変化に注意する必要があります。
- 安静時バイタルの評価ポイント
- それを基にした臨床推論
- ケーススタディで具体的な判断練習
本記事では、安静時バイタルの評価ポイントと、それを基にした適切な臨床推論について詳しく解説します。さらに、実際のケーススタディを交えて、安全にリハビリを進めるための具体的な判断方法を考えていきましょう。
⸻
大前提は主治医の指示に従おう!
いわゆる世間一般的な開始基準や中止基準的引っかかる場合は必ず主治医に確認し指示を仰ぎましょう。また、臨床では基準に引っかかるけどリハビリを進める必要がある場合もあります。
また、主治医からの指示で、

状態に応じてリハ継続してください。
そんな指示を受けることも少なくありません。
そのような時はリハビリを中断するか、進めるか、リスク管理をしながら自分で判断しなければなりません。
臨床でも役立つのがアンダーソンの運動中止基準(土肥変法)
運動を行わないほうがよい場合
安静時脈拍数:120/分以上
拡張期血圧(下の血圧):120mmHg以上
収縮期血圧(上の血圧):200mmHg以上
労作性狭心症を現在有するもの
新鮮心筋梗塞1ヶ月以内のもの
うっ血性心不全の所見の著しい不整脈
心房細動以外の著しい不整脈
運動前すでに動悸、息切れのあるもの
途中で運動を中止する場合
運動中、中等度の呼吸困難・めまい・嘔気・狭心痛などが出現した場合
運動中、脈拍が140/分を超えた場合
運動中、1分間に10個以上の期外収縮が出現するか、または頻脈性不整脈(心房細動、上室性頻脈など)あるいは徐脈が出現した場合
運動中、収縮期血圧40mmHg以上または拡張期血圧20mmHg以上上昇した場合
次の場合は運動を一時中止し、回復を待って再開する
脈拍数が運動時の30%を超えた場合。ただし、2分間の安静で10%以下に戻らない場合は中止にするかかなり負荷の少ない運動に切り替える。
脈拍数が120/分を超えた場合
1分間に10回以下の期外収縮が出現した場合
軽い動悸、息切れを訴えた場合
安静時バイタルの評価ポイントとリスク判断
① 心拍数(HR:Heart Rate)
1-1. 正常範囲とその意義
正常値:60~100 bpm
心拍数は、心臓のポンプ機能を示す重要な指標であり、交感神経・副交感神経のバランス、心機能、体液バランス、疼痛、ストレスの影響を受けます。
1-2. リスクのあるパターンと臨床推論
頻脈(HR >100 bpm)
• 考えられる要因:脱水、発熱、貧血、疼痛、ストレス、感染、不整脈、心不全増悪
• 注意点:HR >120 bpmでは心臓への負担が大きくなり、リスク管理が必要
徐脈(HR <50 bpm)
• 考えられる要因:β遮断薬、洞不全症候群、房室ブロック、アスリート心(スポーツ心)
• 注意点:HR <40 bpmでは意識障害や失神のリスクがある
1-3. リハビリの対応
✅ HR >100bpmなら離床負荷を軽減し経過観察しながら進める。HR>120なら中断もしくは中止を検討する。
✅ HR <50 bpmで血圧低下やめまいやふらつきを伴う場合は、リハビリを中止または低強度で開始
⸻
② 血圧(BP:Blood Pressure)
2-1. 正常範囲とその意義
正常値:100~140 / 60~90 mmHg
血圧は心拍出量と末梢血管抵抗のバランスで決まり、心臓・腎臓・自律神経の機能が密接に関与しています。
2-2. リスクのあるパターンと臨床推論
高血圧(SBP >180 mmHg or DBP >110 mmHg)
• 考えられる要因:高血圧症の増悪、降圧薬の中断、ストレス、疼痛
• 注意点:リハビリ中の血圧上昇リスクが高いため、負荷調整が必要
低血圧(SBP <80 mmHg or DBP <50 mmHg)
• 考えられる要因:脱水、降圧薬、心不全、出血、敗血症
• 注意点:起立性低血圧のリスクが高く、転倒や脳血流低下に注意、最悪の場合失神につながります。
2-3. リハビリの対応
✅ SBP >180 mmHgなら、運動負荷を最小限にし、バイタル変化を監視
✅ SBP <90 mmHgで起立性低血圧が疑われる場合は、仰臥位での運動から開始。離床後でのSBP>80mmHgでは積極的な離床はさけるべきでしょう。
※急性期リハビリでは早期離床を図るため他の全身状態が安定していれば許容して進める場合もあります。
⸻
ケーススタディ:バイタルから臨床推論を導く
ケース①:安静時頻脈を呈する心不全患者
【患者情報】
• 80歳男性、心不全(HFrEF)、高血圧、腎機能低下
• 安静時バイタル:HR 121bpm、BP 135/85 mmHg、RR 22 回/分、SpO₂ 94%
この症例における理学療法臨床推論
本症例は、心不全(HFrEF)を基礎疾患とし、高血圧および腎機能低下を合併している80歳男性である。安静時バイタルサインは以下の通りであった。
• HR:121bpm
• BP:135/85 mmHg
• RR:22 回/分
• SpO₂:94%
まず注目すべきは安静時心拍数が120bpmを超えている頻脈状態である。高齢かつHFrEF患者であることを踏まえると、頻脈は予後不良因子であり、リハビリの進行判断において慎重な対応が求められる。
【頻脈の要因分析】
安静時頻脈の原因として以下が考えられる:
• 交感神経亢進:心不全による代償反応として、心拍出量低下を補うために交感神経系が亢進している可能性が高い。
• 軽度の脱水:腎機能低下により水分調整能が低下し、体液不足が生じている可能性。頻脈と呼吸数増加を説明できる。
• 貧血:腎機能低下に伴うエリスロポエチン産生の低下が関与し、酸素運搬能の低下を補うための代償的頻脈。
これらの背景を踏まえると、単なる不整脈や新規の心イベントではない代償性の頻脈と判断されるが、運動による負荷追加でさらに心負担が増大するリスクも否定できない。
【リハビリ実施に対するリスク評価】
リハビリを行うことで交感神経刺激がさらに増加すれば、心拍数はより増大し、虚血・心筋酸素需要の増大を招く可能性がある。特にHFrEF患者では、心拍出量の余力が乏しいため、軽度の運動でも症状増悪のリスクがある。
また、脱水や貧血が関与している場合、循環血液量が不十分な中での運動は危険性が高い。これらの要因が改善されない限り、離床や運動は心血管イベントの引き金になり得る。
【現時点での対応方針】
• リハビリは一時中止とする。
• 原因の検索(血液検査による貧血の有無確認、水分状態の評価、心不全のコントロール状況確認)を優先。
• 安静時心拍数が120bpm未満(可能であれば100bpmが望ましい)に安定し、かつ呼吸状態や血圧が安定してから再評価の上で再開を検討する。
【今後のリハビリ再開に向けた観察ポイント】
• 安静時HRが100bpm未満に安定しているか
• 呼吸数の正常化(RR < 20)
• 心不全に伴う症状(浮腫、起坐呼吸、体重変化など)の改善
• 水分出納と貧血の評価結果
⸻
【結論】
本症例においては、頻脈を呈する背景が代償性である可能性が高いものの、現時点ではリスクが高いと判断される。安静時心拍数が120bpm以上であることは、運動時にさらに増加するリスクがあり、心不全の増悪を招く可能性があるため、原因精査と全身状態の安定化を優先し、現時点ではリハビリを一時中止とする判断が妥当である。
✔ 離床時の血圧・心拍数の変化をチェックし、段階的に負荷を調整
✔ 脱水リスクを考慮し、水分補給状況を確認
✔ 自覚症状(息切れ、倦怠感)がないか評価しながら実施
⸻
まとめ:バイタルを見極め、臨床推論を深めよう

安静時バイタルの評価は、単に「正常範囲内だからOK」ではなく、患者の病態や全身状態を考慮しながらリスク管理を行うことが重要です。
✅ 心拍数・血圧・呼吸数・酸素飽和度の変化を統合的に評価
✅ 疾患ごとの特徴や薬剤の影響を考慮してリスクを判断
✅ バイタル変化を見逃さず、安全なリハビリを計画する
本記事を通して、バイタルの評価をより深く理解し、実践的な臨床推論を高めるヒントになれば幸いです。安全かつ効果的なリハビリのために、日々の評価力を磨いていきましょう!
臨床理学Lab
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇