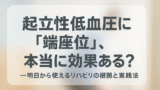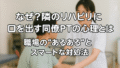廃用症候群のリハって難しい…
先輩から「この患者さん、廃用だからリハよろしく!」と言われたけど、具体的に何から始めればいいんだろう…?
廃用症候群って言葉は知っているけど、全身にどんな影響があるのか、全体像がイマイチ掴めていない…。
臨床に出たばかりの新人理学療法士(PT)なら、誰もが一度はこんな悩みを抱えるのではないでしょうか。
この記事では廃用症候群の「全体像」から、明日からの臨床ですぐに使える「リハビリの基本」まで、お話していきます。
自信を持って患者さんに関わり、多職種にリハビリの必要性を説明できるようになるための第一歩を、ここから踏み出しましょう!
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

そもそも廃用症候群とは?【病気ではなく症候群】
まず大前提として、廃用症候群は特定の「病気」の名前ではありません。
一言でいうと、「“過度な安静”や“動かないこと”によって、心身に起こるあらゆる不調の集まり」のことです。専門的には「生活不活発病」とも呼ばれます。
なぜ起こるのか?主な原因
原因は非常にシンプルで、「活動性の低下」です。具体的には、以下のような状況で起こりやすくなります。
- 手術後のベッド上安静
- 骨折によるギプス固定
- 肺炎や心不全などの内部疾患による安静指示
- 集中治療室(ICU)での長期臥床
- 痛みや意欲低下による閉じこもり
なぜPTにとって重要なのか?
廃用症候群は、私たち理学療法士が最も得意とする分野の一つです。なぜなら、薬では治すことが難しく、「動かすこと=リハビリ」が最も有効な治療法であり、最高の予防法だからです。
患者さんのADL(日常生活動作)低下を防ぎ、生活の質を守るために、廃用症候群の正しい知識は不可欠なのです。
【全体像を掴む】身体に何が起こる?全身への影響を徹底解説
「廃用」が怖いのは、その影響が全身のあらゆる器官に及ぶ点です。ここでは代表的な症状を系統別に整理して見ていきましょう。
① 筋骨格系
最もイメージしやすい部分ですが、非常に深刻な影響が出ます。
- 筋萎縮・筋力低下: 特に重力に抗して身体を支える「抗重力筋(お尻や太もも、背中の筋肉など)」は、1週間の安静で10~15%も筋力が低下すると言われています。
- 関節拘縮: 関節を動かさないことで、関節周りの組織が硬くなり、動かせる範囲(関節可動域)が狭くなります。特に股関節や足関節は拘縮が起きやすい部位です。
- 骨萎縮(骨粗鬆症): 骨は、体重という負荷がかかることで強度を保っています。寝たきり状態が続くと骨密度が低下し、骨折しやすいもろい骨になってしまいます。
② 循環器系
心臓や血管にも大きな影響が及びます。
- 心機能低下: 全身に血液を送るポンプ機能が低下し、少し動いただけでも息切れや動悸が起こりやすくなります。
- 起立性低血圧: 長時間寝ている状態から急に起き上がると、血圧が急低下して立ちくらみやめまい、ひどい場合は失神を起こします。
- 深部静脈血栓症(DVT): いわゆる「エコノミークラス症候群」。特に足の静脈に血の塊(血栓)ができやすくなります。この血栓が肺に飛ぶと、命に関わる「肺塞栓症」を引き起こすリスクがあり、最も注意すべき合併症の一つです。
③ 呼吸器系
- 呼吸筋の筋力低下: 呼吸に使う筋肉も衰え、換気量が低下します。
- 誤嚥性肺炎のリスク増大: 痰を出す力(喀出力)が弱まり、唾液や食べ物が気管に入りやすくなることで、肺炎のリスクが高まります。
④ 精神・神経系
身体だけでなく、精神状態にも影響が出ます。
- 認知機能低下: 外部からの刺激が減ることで、思考力や記憶力が低下します。
- うつ・せん妄: 活動が制限されるストレスや不安から、うつ状態になったり、時間や場所が分からなくなる「せん妄」という状態に陥ることがあります。
⑤ その他
- 褥瘡(じょくそう): いわゆる「床ずれ」。同じ部位に圧力がかかり続けることで皮膚の血流が悪くなり、組織が壊死してしまいます。
- 便秘: 腸の動きが悪くなったり、腹筋の力が弱まったりすることで便秘になりやすくなります。
新人PTがやるべきリハビリの基本3ステップ
では、具体的にどうアプローチすれば良いのでしょうか?明日から使える基本の3ステップを紹介します。
【ステップ1】まずは評価から!見るべきポイント
リハビリは、闇雲に動かせば良いわけではありません。安全に行うための「評価」がすべての土台です。
- 情報収集(カルテから)
- なぜ安静になったのか?(疾患名、術式)
- 安静期間はどれくらいか?
- 既往歴、合併症は?(特に心疾患や呼吸器疾患、糖尿病など)
- 全身状態の確認(ベッドサイドで)
- バイタルサイン(血圧、脈拍、SpO2): 介入前・中・後で必ず確認!
- 意識レベル: 声かけへの反応はどうか?
- 皮膚の状態: 褥瘡のリスクはないか?(特に仙骨部、踵部)
- 機能評価
- 関節可動域(ROM): 固くなっている関節はないか?
- 筋力(MMT): 特に下肢の主要な筋力はどうか?
- 座位・立位バランス: まずはベッドに座ってもらい、ふらつきがないか確認。
- リスク評価
- DVTの評価: ふくらはぎの腫れ、熱感、痛み(ホーマンズ徴候)などを確認。
- 起立性低血圧の評価: 臥位と座位・立位での血圧変化を測定。
【ステップ2】目標設定とプログラム立案の考え方
評価で得た情報を基に、リハビリ計画を立てます。
- 目標設定のコツ
患者さん本人やご家族の希望をヒアリングし、「ベッドからポータブルトイレまで安全に移れるようになる」「10m先の食卓まで歩いて行けるようになる」など、生活に直結する具体的な動作を目標に設定しましょう。 - プログラムの原則
- 安全第一: 絶対に無理はさせない。特に離床の初回は慎重に。
- 漸進性(ぜんしんせい)の原則: 少しずつ負荷を上げていく。「できること」を積み重ねて自信に繋げます。
- 基本的な流れ: 臥位 → 座位 → 立位 → 歩行 という段階をしっかり踏むことが重要です。
【ステップ3】明日から使える!具体的なアプローチ例
ここでは、各段階での代表的なリハビリメニューを紹介します。
- ベッド上で行うこと(臥位)
- 良肢位保持(ポジショニング): 関節拘縮や褥瘡を予防するための基本。看護師と連携しましょう。
- 関節可動域訓練: 全身の関節を他動的・自動的に動かし、拘縮を予防します。
- 呼吸練習: 深呼吸や腹式呼吸で換気量を増やし、痰を出しやすくします。
- 筋力トレーニング: ブリッジ(お尻上げ)や足首の運動など、ベッド上でできる簡単な運動から開始します。
- 起き上がる練習(座位)
- 端座位(たんざい)訓練: ベッドの端に足を下ろして座る練習。まずは背もたれのある椅子から始め、バランス能力を高めます。起立性低血圧の予防にも極めて重要です。
- 座位でのリーチ動作: 座ったままテーブルの上の物を取るなど、バランスを取りながら手足を動かす練習をします。
- 立つ・歩く練習(立位・歩行)
- 段階的な起立訓練: まずはベッドサイドで立ち、その場で足踏みなどから開始します。必要に応じてティルトテーブル(徐々に身体を傾けていくベッド)を活用するのも有効です。
- 平行棒内歩行 → 歩行器・杖歩行: 患者さんの能力に合わせて補助具を選択し、歩行距離を少しずつ伸ばしていきます。
最も大切なのは「予防」という視点
ここまで治療法について解説してきましたが、理学療法士として最も大切な視点は**「廃用症候群をいかに予防するか」**です。
- 早期離床の重要性
「離床」とは、ベッドから離れること。術後や発症後、医師の許可が出たら一日でも早く、一分でも長くベッドから離れる時間を作ることが、あらゆる廃用症候群の症状を予防する上で最も効果的です。 - 多職種連携
リハビリはPTだけの仕事ではありません。看護師とポジショニングや離床時の注意点を共有したり、医師にDVTのリスクを報告したりと、チームで患者さんを支える視点が不可欠です。 - 環境設定
ナースコールやテレビのリモコンを患者さんの手の届く範囲に置く、ベッドの高さを調整するなど、患者さんが少しでも自分で動けるような環境を作ることも、立派なリハビリの一つです。
まとめ
最後に、この記事の要点を振り返りましょう。
- 廃用症候群は「動かないこと」で起こる全身の不調の集まり。
- 筋力低下や関節拘縮だけでなく、起立性低血圧やDVT、認知機能低下などリスクは多岐にわたる。
- 新人PTはまず「評価」で全体像とリスクを把握することが最重要。
- リハビリは「安全第一」で「臥位→座位→立位」の順に、少しずつ進めるのが基本。
- 最高の治療は「予防」。早期離床と多職種連携が成功のカギを握る。
廃用症候群を正しく理解し、適切に対応できることは、急性期から生活期まで、すべての患者さんを診る上での土台となります。
最初は不安かもしれませんが、焦る必要はありません。この記事を参考に、まずは目の前の患者さんをしっかり評価することから始めてみてください。あなたの一歩が、患者さんの未来を大きく変えるはずです。応援しています!