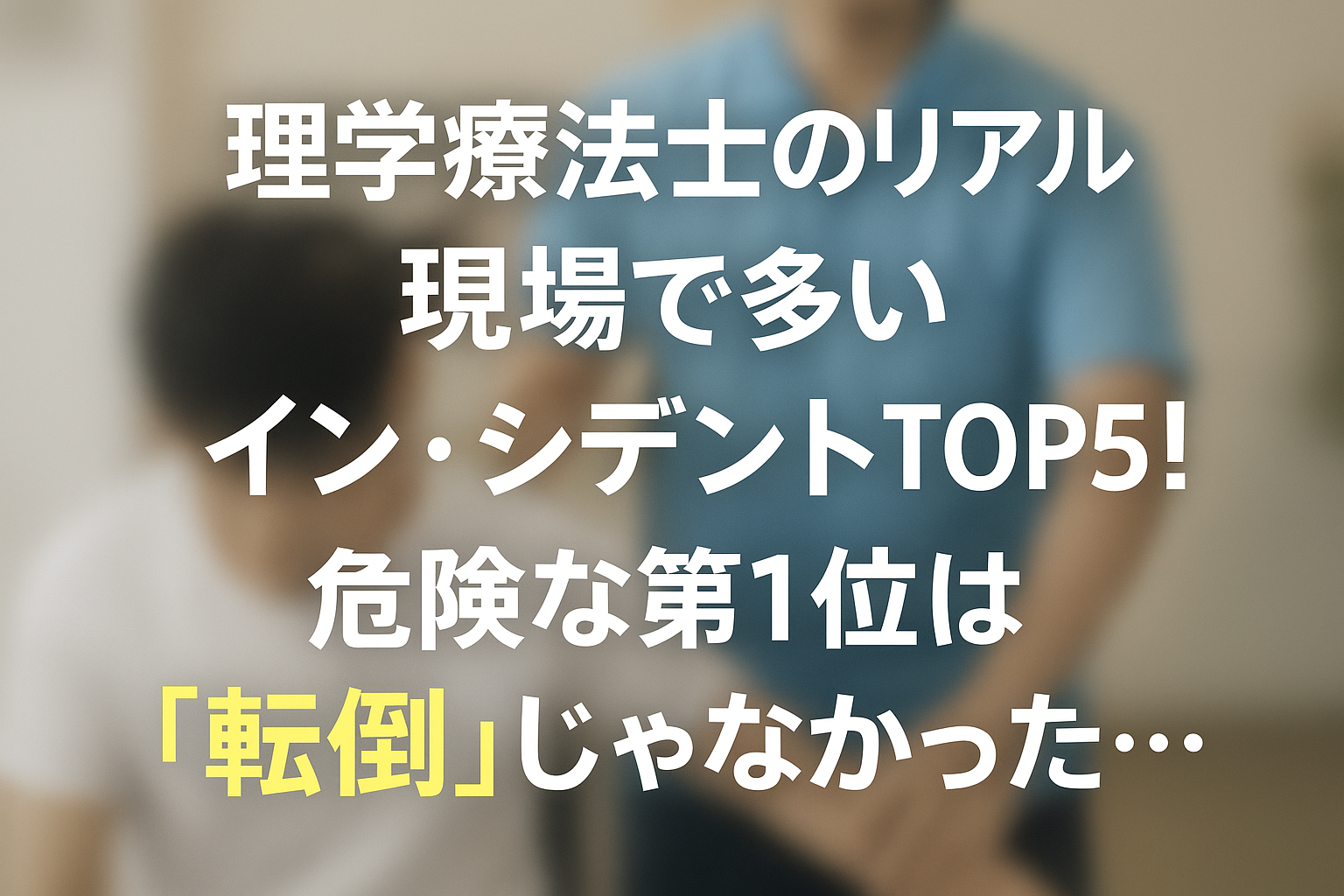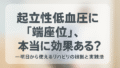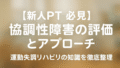そのインシデント、本当の原因を見えていますか?
「またインシデントレポートか…」
理学療法士(PT)として働いていると、ヒヤリハットやインシデントは避けて通れない問題ですよね。特に「転倒」させてしまった時の、血の気が引くような感覚は、一度は経験があるかもしれません。
しかし、本当に一番怖いインシデントは、目に見えやすい「転倒」だけなのでしょうか?
私の職場での経験上、数々のインシデントの根本をたどっていくと、実はもっと根深く、見過ごされがちな「ある原因」に行き着くことがほとんどです。
この記事では、現役理学療法士である私が現場で感じる「本当に多いインシデントTOP5」をランキング形式で紹介します。
この記事がインシデントの原因を理解し、明日からの臨床で患者さんと自分自身を守るための具体的な行動が見えてくるきっかけとなれば幸いです。
⚠️職場や職域によってランキングが前後する場合、他の事象が起こり得ることも十分に考えられます。
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

現場で本当に多い!理学療法士のインシデントTOP5
第5位:自己判断・過信によるリスク
「これくらい大丈夫だろう」「いつもやっているから…」
特に経験を積んだ中堅PTが陥りやすいのが、この「自己判断」と「過信」です。慣れは、時に最も危険なリスク因子となります。
【具体的な事例】
- 相談の省略: 判断に迷う場面でも「今さら聞けない」と自己判断でリハビリを進め、医師の指示と異なる運動をしてしまった。
- アセスメント不足: 「前回と同じでいいや」と十分な評価をせず、患者さんの状態変化(血圧、倦怠感など)を見逃してしまう。
- 自身の体調不良: 疲れているのに無理をしてしまい、注意力が散漫になって介助中にヒヤリとする。
「自分は大丈夫」という慢心は、基本的な確認作業を怠らせ、重大な事故につながる第一歩です。
第4位:機器・物品の取り扱いミス
物理療法機器や福祉用具など、私たちは多くの「モノ」を使います。毎日触れるものだからこそ、油断が生まれやすいポイントです。
【具体的な事例】
- 物理療法: ホットパックの温度確認を怠り、患者さんが低温やけどに。
- 医療機器: リハビリ中に点滴チューブが絡まったり、抜針に繋がったり、酸素ボンベの残量がギリギリだったりする。
- 福祉用具: 車椅子のブレーキのかけ忘れ、歩行器の高さ調整の固定が甘く、使用中にガクンと下がってしまう。
一つひとつの操作は単純ですが、その一つを怠るだけで、患者さんを危険に晒してしまいます。
第3位:皮膚トラブル(擦過傷・皮膚剥離・打撲)
「ちょっとぶつけちゃっただけ」では済みません。特に高齢の患者さんの皮膚は非常にデリケートで、軽い接触が大きなアザや皮膚剥離につながることがあります。
【具体的な事例】
- 移乗・介助時: ベッド柵や車椅子のアームレストに、患者さんの腕や足をぶつけてしまう。
- 関節可動域訓練: 自分の爪が伸びていて、患者さんの皮膚を引っ掻いてしまう。
- ポジショニング: 長時間同じ姿勢でいたため、仙骨部が赤くなっているのを見逃す。
丁寧な介助は、患者さんの尊厳を守る上でも不可欠なスキルです。
第2位:転倒・転落
やはり「転倒・転落」は、理学療法士にとっても報告件数が多く、代表的なインシデントです。患者さんのADLを向上させるという私たちの仕事と、常に隣り合わせのリスクと言えます。
【具体的な事例】
- 介助量の見誤り: 「もう一人で立てるだろう」という思い込みから介助の手を離した瞬間に、膝折れ。
- 環境整備の不備: 床が濡れていたり、コードが落ちていたりすることに気づかず、患者さんや自分が足を滑らせる。
- 能力評価のミス: 評価ではできていた動作が、体調の変化でできなくなり転倒につながる。
しかし、よく考えてみてください。これらの転倒は、「もし〇〇という情報を知っていれば防げた」と思いませんか?
そう、これからお話しする第1位が、これらのインシデントの黒幕であることも多いのです。
第1位:情報共有不足によるエラー
堂々の(そして、最も根絶すべき)第1位は「情報共有不足」です。
なぜこれが1位なのか?それは、2位以下のすべてのインシデントの引き金になりうる根本原因だからです。
「知らなかった」「聞いていなかった」「見落としていた」
この一言で、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
【具体的な事例】
- 医師の指示変更の見落とし: 「本日よりリハビリでも離床は禁止」の指示に気づかず、起立、歩行訓練を実施してしまった。
- 内服薬の副作用の未把握: 降圧剤が変更されたことを知らず、いつも通り離床させたら強いめまいが出現し、転倒しそうになった。
- 他職種からの口頭申し送りを聞き流す: 看護師さんからの「昨夜、少しせん妄気味で…」という一言を軽視し、リハビリ室で混乱させてしまった。
どんなに優れた技術や知識があっても、最新の「患者情報」がなければ、それは宝の持ち腐れ。情報が途切れた瞬間、私たちの行うリハビリは安全な治療から危険な行為へと変わりうるのです。
インシデントを防ぐための明日からできる3つのアクション
では、どうすればこれらのインシデントを防げるのでしょうか。「気をつける」だけでは不十分です。具体的な行動レベルでの対策が必要です。
個人の意識改革:指差し声出し確認を習慣に
- リハビリ前: カルテの最終記載を確認。「指示変更なし、OK!」「昨日の看護記録、OK!」
- 動作介助前: 「ブレーキ、OK!」「フットレスト、OK!」「点滴ルート、OK!」
- リハビリ後: 「ベッドの高さ、OK!」「ナースコール、OK!」
単純ですが、声に出して確認することで、脳は活性化され、見落としが劇的に減ります。
チームの連携強化:「何か変わりありませんか?」の一言
- リハビリ前に看護師に声をかける: カルテには書かれていないリアルタイムの情報を得る絶好の機会です。「変わりないですよ」と言われれば安心できますし、重要な情報を得られることも多々あります。
- 自分の記録を丁寧に書く: 次に担当するスタッフは「未来の自分」かもしれません。「〇〇の動作でふらつきあり、要注意」など、具体的な情報を残しましょう。
職場の仕組み化:ヒヤリハットを「学び」に変える
- インシデントレポートを共有する: 誰かを責めるためではなく、「どうすればチームとして防げたか?」を議論する文化を作りましょう。
- 危険予知トレーニング(KYT)を行う: リハビリ室の写真などを見て「どこに危険が潜んでいるか」をスタッフみんなで話し合うのも効果的です。
まとめ:失敗から学び、最高の安全を届けよう
理学療法士のインシデントランキング、いかがでしたか?
多くのインシデントは、たった一人の不注意だけでなく、チームの「情報共有のズレ」から生まれます。逆に言えば、情報の流れをスムーズにすることこそが、最強のリスク管理なのです。
インシデントは誰にでも起こりうること。大切なのは、それを隠さず、原因を分析し、二度と繰り返さないための仕組みをチームで作ることです。
この記事が、あなたの臨床の安全意識を高め、患者さんにより質の高いリハビリテーションを届ける一助となれば幸いです。