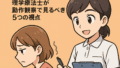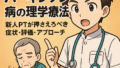はじめに|「脊椎の知識、使えていますか?」
「脊椎の構造や運動学って、一通り学んだはずなのに、実際の評価や治療にどう活かすべきかがわからない…」
そんな風に思ったこと、ありませんか?
理学療法士として、患者の姿勢や動作の異常を読み取るには、脊椎の機能解剖とキネシオロジー(運動学)の知識が不可欠です。
本記事では、脊椎に関わる基本構造から臨床での評価・介入まで、現場で使える形で整理しました。新人〜中堅のPTにとって、臨床力アップのベースになる内容ですので、ぜひ保存版として活用してください。
\臨床理学Labでは有料記事が読み放題/

脊椎の基本構造とその役割
脊椎は、以下の5つのパートに分類され、全部で33〜34個の椎骨で構成されています。
| 部位 | 節数 | 特徴 |
| 頸椎(C1~C7) | 7個 | 回旋と屈伸に富み、頭部の可動性を確保 |
| 胸椎(T1~T12) | 12個 | 肋骨と関節をなし、安定性が高い |
| 腰椎(L1~L5) | 5個 | 体幹の支持と柔軟な運動に関与 |
| 仙椎 | 5個(癒合) | 骨盤の一部、体重を下肢へ伝える |
| 尾椎 | 3~5個(癒合) | 退化した構造 |
特に椎間関節や椎間板は、脊椎の可動性・支持性の鍵となる構造です。
椎間板は中心の髄核と、その外側を囲む線維輪から成り、クッションの役割を果たします。
臨床POINT
構造が見えると、**「なぜここで痛みが出るのか」**を解剖的に説明できるようになります。
脊椎のキネシオロジー(運動学)|部位別の運動特性
それぞれの脊椎レベルで、得意な運動方向は異なります。
| 部位 | 主な運動方向 | 特徴 |
| 頸椎 | 屈曲・伸展・側屈・回旋 | 特にC1(環椎)とC2(軸椎)は回旋の中心 |
| 胸椎 | 側屈・回旋 | 肋骨との連動で安定性が強く、可動性は中等度 |
| 腰椎 | 屈伸 | 回旋は制限されているが、前後の動きに優れる |
臨床POINT
可動性が失われた部位の代償運動として、他の部位に過剰なストレスがかかることがあります。
例:胸椎伸展制限 → 頸椎や腰椎の過剰伸展 → 頭痛・腰痛の原因に
脊椎運動に関わる主な筋肉と評価の視点
脊椎の運動を制御する筋は、深層筋(インナーマッスル)と表層筋(アウター)に分けられます。
| 運動方向 | 主な筋 |
| 屈曲 | 腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋 |
| 伸展 | 脊柱起立筋(最長筋・腸肋筋・棘筋) |
| 回旋 | 腹斜筋、多裂筋、回旋筋 |
| 側屈 | 腰方形筋、腹斜筋、脊柱起立筋 |
臨床POINT
体幹の「弱さ」は筋力ではなく制御やタイミングの問題かもしれません。
体幹機能評価には、筋力+協調性の視点が必要です。
脊椎評価に役立つ視点|姿勢・動作観察のヒント
脊椎のアライメントや可動性は、日常動作にも大きく関わります。
代表的な評価の例
- 立位での頭部〜骨盤のアライメント
- 屈伸・側屈・回旋の可動域テスト(例:Schober test)
- 歩行中の体幹の回旋・側屈パターン
臨床POINT
「なんとなく違和感がある動き」の正体を、脊柱の構造・運動制限から読み解く力が重要です。
呼吸と脊柱の関係性にも注目しよう
呼吸は、胸郭だけでなく脊椎全体に関わるダイナミックな運動です。
特に胸椎・肋骨の可動性制限があると、呼吸パターンが変化し、体幹の安定性や筋活動にも影響します。
臨床POINT
呼吸評価は、脊柱の可動性や体幹制御能力の指標にもなります。
呼吸介入(例:呼吸トレーニング、胸郭モビライゼーション)は、体幹機能改善にも有効です。
おすすめ参考書・学習リソース
- 『関節の生理学(カパンジー)』:運動学の王道、ビジュアルで理解しやすい
- 『運動機能障害の「なぜ?」がわかる臨床解剖学』:動作と構造を結びつけて解説
- 『姿勢と動作の機能解剖』:臨床評価や介入に即した実践書
- 『筋骨格系キネシオロジー』:ジェネラリスト向け
- アプリ:Visible Body、Kenhub などで3D解剖を視覚化
まとめ|構造×機能×臨床がつながると評価が変わる
- 脊椎の知識は、姿勢異常や運動障害の背景を読み解く“土台”
- 解剖学やキネシオロジーを、“臨床でどう活かすか”が重要
- 明日からの患者評価・治療に、今回の知識をぜひ活かしてみてください!