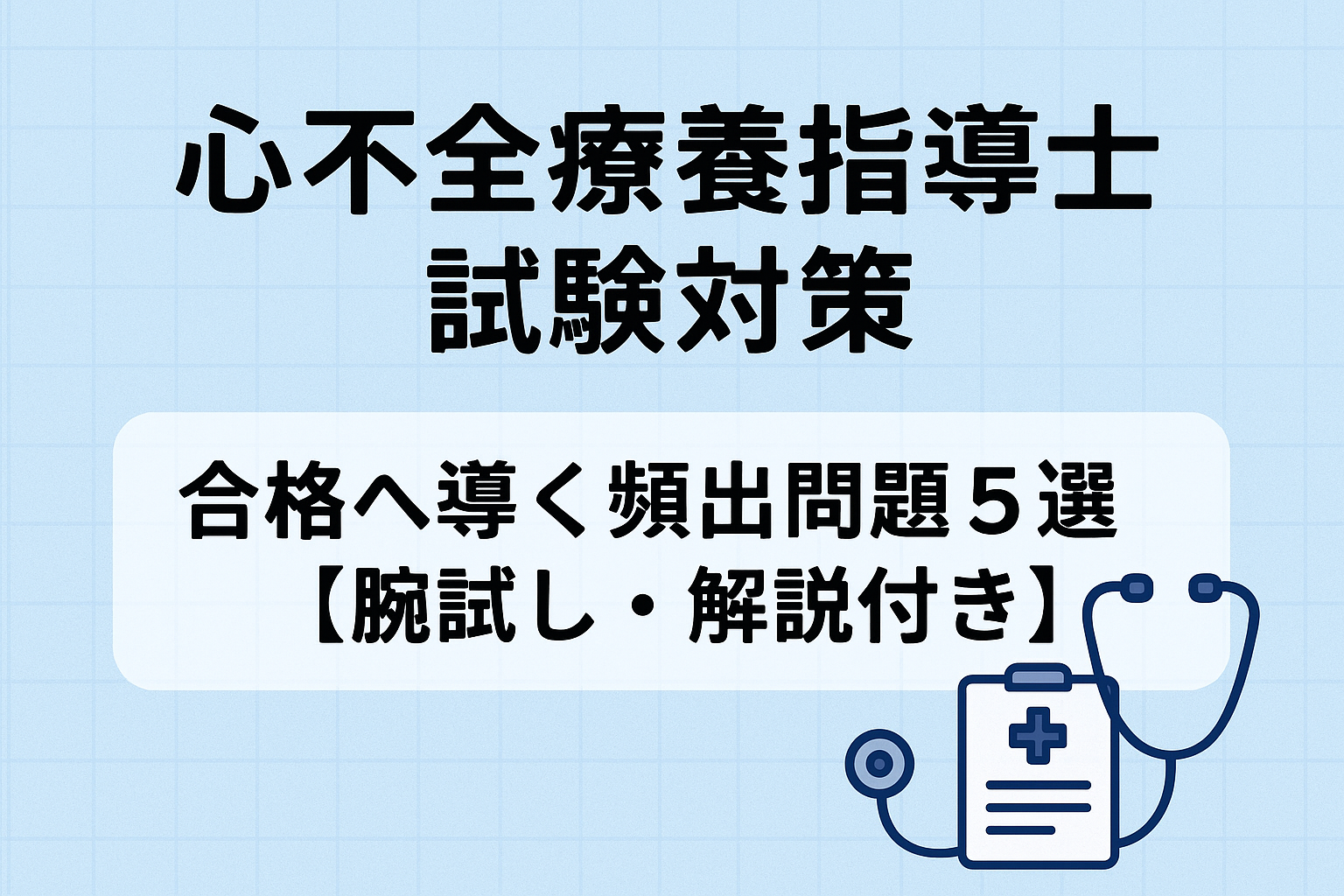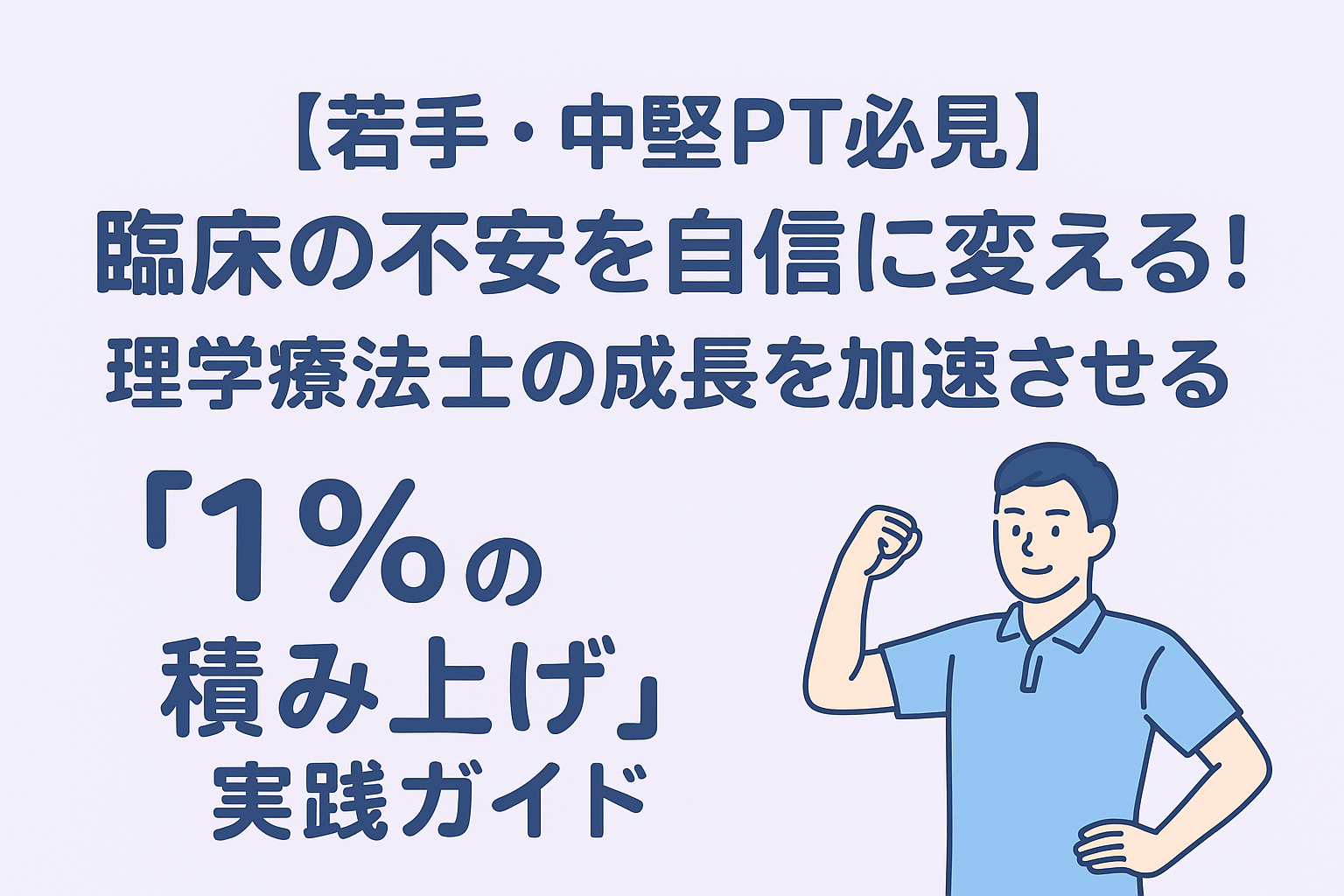はじめに:心不全療養指導士の試験勉強、順調ですか?
こんにちは!
心不全療養指導士の合格を目指して、日々学習に励んでいる皆さん、本当にお疲れ様です。
「試験範囲が広すぎて、どこから手をつけていいか分からない…」
「仕事と両立しながらの勉強で、効率の良い対策法を知りたい」
「自分の実力が今どのくらいなのか、力試しがしたい」
きっと、多くの方が同じような悩みや思いを抱えているのではないでしょうか。
この記事を読めば、
- どんな感じの問題なのか体験できる
- 試験で問われる重要ポイントが理解できる
- 明日からの勉強のヒントが見つかる
はずです。ぜひ最後までチャレンジしてみてください!
【腕試し】心不全療養指導士 対策問題に挑戦!
それでは早速、問題に挑戦してみましょう!
5問出題します。まずはじっくり考えて、自分なりの答えを出してみてください。解答と詳しい解説は、このすぐ下にあります。
問題1
心不全における利尿薬使用の目的として最も適切なのはどれか。
- 心筋収縮力の増強
- 末梢血管抵抗の低下
- 体液貯留の改善
- 心拍数の減少
- LVEFの即時改善
問題2
HFpEF患者の治療で推奨される第一選択薬はどれか。
- ACE阻害薬
- β遮断薬
- 利尿薬(症状改善目的)
- ARNI
- 心筋刺激薬
問題3
HFrEF患者でARBとACE阻害薬の併用は原則避ける理由として正しいのはどれか。
- 血圧上昇を招く
- 重篤な腎障害や高カリウム血症のリスク増
- 効果が減弱する
- 心拍数が過度に低下する
- 利尿作用が消失する
問題4
心不全患者に対する心臓再同期療法(CRT)の適応として最も正しいのはどれか。
- HFpEFでQRS幅正常
- HFrEFで左脚ブロックかつQRS ≥130ms
- HFrEFで安定している症状なし
- 急性心不全発症時のみ
- 右心不全単独の場合
問題5
急性心不全で酸素投与が必要となる条件として適切なのはどれか。
- SpO₂ < 90%
- BNP上昇のみ
- 体液貯留の有無にかかわらず
- LVEF 55%以上
- NYHAⅠ相当症状
【解答と解説】あなたの理解度をチェック!
皆さん、お疲れ様でした!何問正解できましたか?
ここからは解答と解説です。「なぜその答えになるのか」をしっかり理解することが、合格への一番の近道ですよ。
問題1:解答 3
- 【出題頻度】★★★★★
- 【ひっかけポイント】 利尿薬=症状改善(浮腫・肺うっ血)であり、予後改善効果は限定的
- 【解説】 これは絶対に押さえておきたい基本問題ですね。利尿薬の主な役割は、体内に溜まった余分な水分(体液貯留)を尿として排泄させ、心臓の負担を軽減することです。これにより、息切れやむくみ(浮腫)、肺うっ血といったうっ血症状を改善します。心筋収縮力や心拍数に直接作用する薬ではありません。
問題2:解答 3
- 【出題頻度】★★★☆☆
- 【ひっかけポイント】 HFpEFでは予後改善薬は限られ、症状緩和が中心
- 【解説】 HFpEF(ヘフペフ:左室駆出率が保たれた心不全)の薬物治療は、HFrEF(ヘフレフ:左室駆出率が低下した心不全)とはアプローチが異なります。HFpEFでは、生命予後を改善するエビデンスが確立された薬剤がまだ少なく、まずは利尿薬による症状緩和(うっ血のコントロール)が治療の中心となります。
問題3:解答 2
- 【出題頻度】★★★★☆
- 【ひっかけポイント】 ACE阻害薬+ARBの二重阻害は腎機能障害のリスク
- 【解説】 薬物療法の安全性を問う重要問題です。ACE阻害薬とARBはどちらもレニン-アンジオテンシン-アルドステロン(RAA)系に作用しますが、作用点が異なります。この2剤を併用すると、RAA系を強力に抑制しすぎる(二重阻害)ことで、高カリウム血症や腎機能障害といった重篤な副作用のリスクが著しく高まるため、原則として併用は禁忌とされています。
問題4:解答 2
- 【出題頻度】★★★☆☆
- 【ひっかけポイント】 CRTは左室同期障害+低LVEF(HFrEF)で検討
- 【解説】 心臓再同期療法(CRT)は非薬物療法の代表格です。適応を正しく理解しておきましょう。CRTは、**HFrEF(低LVEF)で、かつ心電図のQRS幅が延長(特に左脚ブロック)**している症例が主な対象です。心室の収縮タイミングのズレ(同期障害)をペーシングによって補正し、心臓のポンプ機能を改善させる治療法です。
問題5:解答 1
- 【出題頻度】★★★★☆
- 【ひっかけポイント】 酸素投与は低酸素血症を改善する目的
- 【解説】 急性増悪時の対応も頻出です。酸素投与の目的は、あくまで**「低酸素血症の改善」**です。そのため、SpO₂が90%を下回るような場合に適応となります。逆に、低酸素血症がない患者へのルーチンな酸素投与は、血管収縮を引き起こし心拍出量を低下させる可能性が指摘されており、推奨されません。検査データや症状だけで判断しない点がポイントです。
試験対策問題集を作成しました!
いかがでしたか?
心不全療養指導士を目指す皆さんや、試験対策をしっかり行いたい方に向けて、私自身の学習経験をもとに試験対策問題集を作成しました。
できるだけ分かりやすく、重要ポイントを押さえながら学習を進められるよう工夫しています。ぜひ日々の勉強にお役立てください。

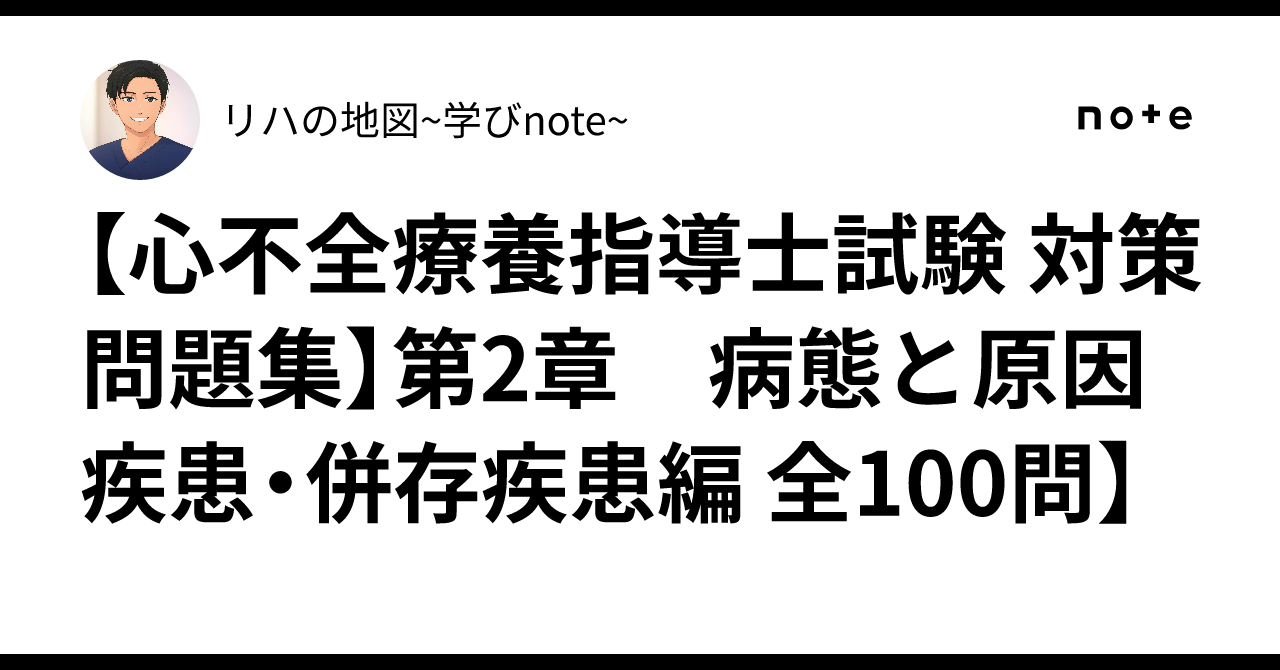

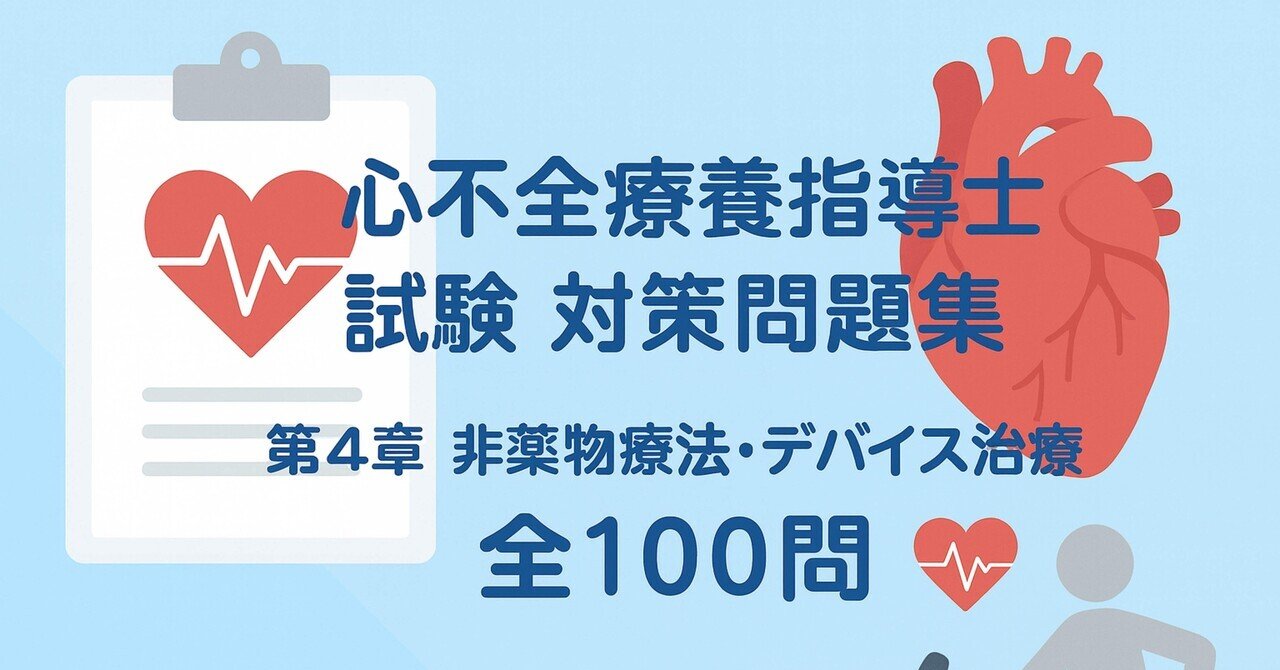
💡この問題集でできること
この心不全療養指導士対策問題集は、単に“問題を解くだけ”ではなく、
試験合格に向けた理解と自信を積み上げることを目的に作成しています。
以下のような学習効果が期待できます👇
✅ ① 出題傾向をつかめる
過去の出題内容やガイドラインの要点をもとに構成しているため、
「どんな分野がよく問われるのか」がひと目で分かります。
効率的に勉強を進めたい方に最適です。
✅ ② 重要ポイントを整理できる
単なる暗記ではなく、臨床に結びつく形で重要項目を整理。
「なぜそれが大事なのか」を理解しながら学習できます。
✅ ③ 苦手分野を可視化できる
問題ごとに理解度をチェックできるので、
自分の弱点を明確にし、重点的な復習が可能です。
✅ ④ 解説で“つまずきポイント”を解消できる
ただ答えを覚えるのではなく、
「なぜその答えになるのか」を丁寧に説明。
理解しながら解けるようになることで、記憶の定着がぐっと高まります。
✅ ⑤ スキマ時間でも学習できる
1問1答形式で構成しているため、
通勤・通学中や休憩時間など、ちょっとした時間でも学習可能。
継続しやすい設計になっています。
✅ ⑥ 試験直前の総まとめにも使える
要点を凝縮しているので、試験直前の“確認用教材”としても最適。
本番前の知識整理や自信づけに役立ちます。
📘 この問題集が目指すのは、「点を取るための勉強」ではなく、「理解を深めて臨床にも活かせる学び」。
試験勉強を通して、心不全の理解をより実践的に広げていきましょう。
もし、あなたが問題集選びで迷っているなら、ぜひ一度手に取ってみてください。合格への最短ルートを示してくれる、最高の相棒になるはずです。
まとめ:今日から始める次の一歩
今回は、心不全療養指導士の対策問題集から厳選した5問をご紹介しました。
全問正解できた方も、間違えてしまった問題があった方も、今日の学習が合格への大きな一歩です。特に、今回間違えた問題こそ、あなたの知識を確実なものにするための「伸びしろ」です。ぜひ、解説をもう一度読み返して、ご自身の言葉で説明できるまで理解を深めてみてください。
心不全療養指導士の試験は簡単ではありませんが、正しい知識を身につければ、必ず道は開けます。
このブログでは、今後も試験対策に役立つ情報や勉強法を発信していきます。
一緒に合格を目指して頑張りましょう!応援しています!