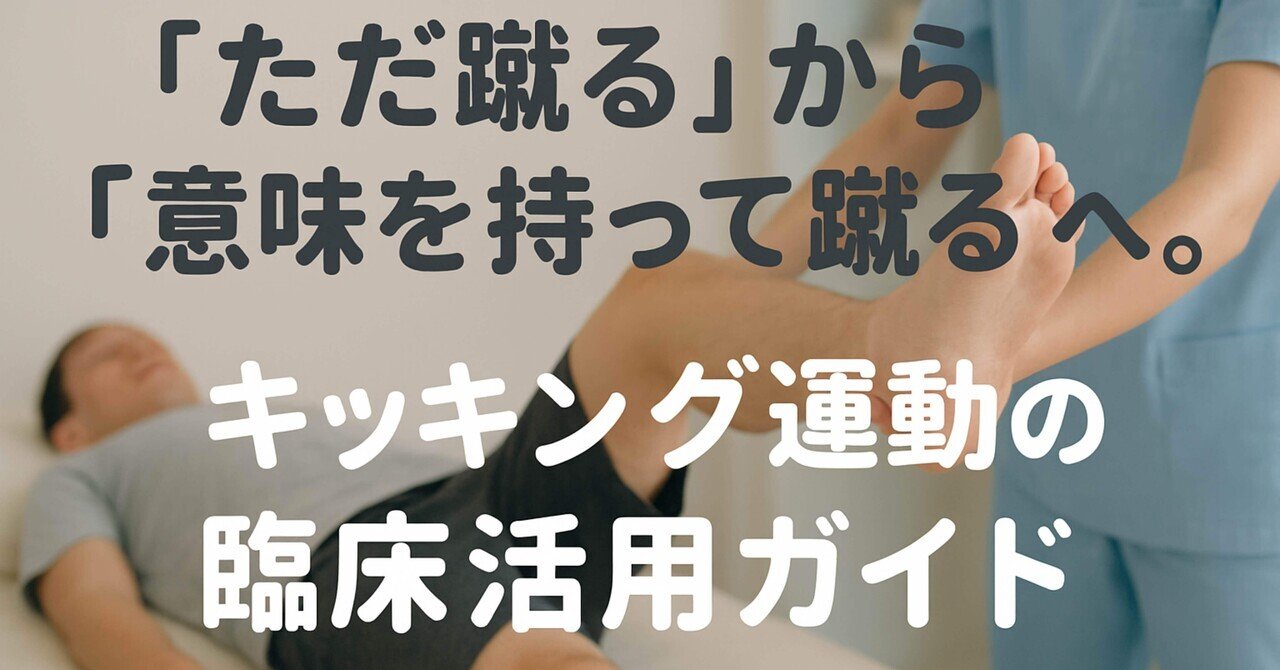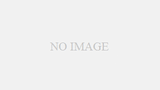はじめに
「じゃあ、ベッドで少し足を蹴る運動(キッキング)をしましょうか」
臨床現場で、ごく当たり前に使っているこの言葉。
でも、心のどこかでこんな風に思っていませんか?

このキッキング運動、本当に効果あるのかな…?

目的を聞かれたら、ちゃんと根拠を持って説明できるだろうか?

ただ動かしているだけで、自己満足になっていないか?
もし一つでも当てはまったなら、この記事はあなたのためのものです。
多くの理学療法士が“なんとなく”で使ってしまいがちな「キッキング運動」を、患者さんの未来を変える“意味のある一手”に変えるためのヒントがここにあります。
【問題提起】あなたのキッキング運動が「もったいない」3つの理由
毎日の臨床で何気なく行っているキッキング運動。しかし、そのやり方次第では、効果が半減するどころか、意図しない代償動作を学習させてしまう可能性すらあります。
理由①:目的が「筋トレ」だと勘違いしている
「キッキング=大腿四頭筋の筋トレ」というイメージが先行し、ただ膝を伸ばすだけの単調な運動になっていませんか?それでは、歩行に必要な協調性や感覚入力といった重要な要素が抜け落ちてしまいます。
理由②:評価と結びついていない
なぜ、その患者さんにキッキング運動が必要なのか。骨盤の動きは?足底の感覚は?歩行のどのフェーズを改善したいのか?評価に基づかない運動は、ただの“作業”になってしまいます。
理由③:「なんとなく」が自信のなさに繋がっている
根拠を持ってプログラムを説明できないことは、患者さんからの信頼を損なうだけでなく、セラピストとしての自信も揺るがせます。
この「もったいない」状況から抜け出し、自信を持ってリハビリを提供したくありませんか?
【解決策】『ただ蹴る』から『意味を持って蹴る』へ思考をシフトする
実は、キッキング運動は正しく使えば、私たちの想像以上にパワフルなツールになります。
重要なのは、「歩行に必要などの要素を、どのタイミングで、どのように刺激するか」という視点です。
例えば、
- 足趾や足底の感覚を意識させることで、バランス能力や転倒予防に繋げる。
- 股関節・膝・足関節の協調性を引き出すことで、脳卒中後の歩行リズムを再学習させる。
- 「蹴る」という運動イメージを活用し、中枢神経の活性化を促す。
このように、目的を明確にするだけで、いつものキッキング運動は、多角的な視点を持つ戦略的なアプローチへと進化するのです。
【記事紹介】あなたの臨床を変える一冊がここにあります

理屈はわかったけど、具体的にどうすればいいの?
そんなあなたの疑問に、真正面から答えてくれるのが、今回ご紹介するnote記事『『ただ蹴る』から『意味を持って蹴る』へ。キッキング運動の臨床活用ガイド』です。
この記事を読めば、あなたのキッキング運動は劇的に変わります。
▼まずはここまで読めます!
記事の前半(無料部分)だけでも、
- なぜ今、キッキング運動を見直すべきなのか?
- 臨床で使える4つのキッキングバリエーションと目的
- 「大腿四頭筋を鍛えるだけ」という誤解の解消
など、日々の臨床にすぐに役立つ知識が満載です。
▼有料パートでは、さらに深い世界へ
この先が、あなたの臨床をネクストレベルに引き上げる核心部分です。
✅ 第4章:エビデンスで効果を科学的に理解できる
「キッキング運動が足趾把持力や歩行に効くって本当?」そんな疑問に、国内論文をベースとした科学的根拠で答えます。もう「なんとなく良さそう」とは言わせません。
✅ 第5章:「効果が出ない」原因が明確になる
うまくいかない症例の原因を徹底分析。「目的の誤解」「単調な運動方向」「タイミングのずれ」など、あなたが陥りがちな“ワナ”とその改善策がわかります。
✅ 第6章:明日から使える評価・プログラム立案法
キッキング動作を“歩行の縮図”として捉える評価の視点から、回復段階に応じたプログラム立案、さらには脳卒中やパーキンソン病など疾患別の応用例まで、実践的なノウハウを公開しています。
このnoteは、単なるテクニック集ではありません。
「なぜ、この運動を選択するのか?」という理学療法士としての“思考のOS”をアップデートするためのガイドブックです。
この記事は、こんな理学療法士のあなたに読んでほしい
- 日々の臨床に追われ、自分のアプローチに自信が持てない若手の方
- 「とりあえずキッキング」という指示に、もやもやを感じている方
- 後輩指導で、運動療法の根拠をしっかり伝えたいと思っている方
- 患者さんの変化をもっと引き出したいと熱意を持っているすべてのセラピスト
まとめ:あなたの臨床を「根拠ある一手」に変えませんか?
キッキング運動は、古い手技ではありません。
理学療法士の「設計力」次第で、患者さんの歩行能力を劇的に変える可能性を秘めた、洗練されたアプローチです。
「なんとなく」の毎日から卒業し、一つひとつの運動に意味と自信を持つ。
そんな理想のセラピスト像へ、この記事が一歩近づけてくれるはずです。
患者さんの「歩けた!」という笑顔のために。
そして、あなた自身の成長のために。
あなたの臨床を変える扉を開けてみませんか?