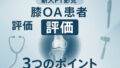はじめに
「脳卒中リハビリは早期離床が鉄則!」
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の皆さんなら、学生時代から何度も聞いてきた言葉ですよね。
「一日でも早くベッドから離れて、座って、立って…」
「廃用を防ぐために、どんどん動かしていこう!」
その信念のもと、毎日汗を流して患者さんのリハビリに取り組んでいることと思います。
しかし、臨床でこんな経験はありませんか?
- 昨日より少し長めに座位訓練をしたら、なんだか患者さんの活気がなくなった…
- 頑張って歩行練習をした翌日、看護師さんから「少し麻痺が強くなった気がする」と言われた…
- 離床を進めているのに、なぜか思うように機能が改善しない…
もし、一つでも「あるある…」と感じたなら、少しだけ立ち止まってこの記事を読んでみてください。
あなたのその“良かれと思って”やっている積極的なリハビリが、実は患者さんの脳にダメージを与え、回復を妨げている危険なサイン**かもしれません。
なぜ?「早く動かす」が裏目に出る衝撃の研究結果
私たちセラピストの常識を揺るがす、ある有名な研究があります。
「AVERT」という大規模な臨床試験です。
この研究では、脳卒中になってすぐ(24時間以内)の患者さんを2つのグループに分けました。
- 超早期・積極的リハビリグループ(より早く、より長くリハビリをする)
- 標準的リハビリグループ(通常のケア)
常識で考えれば、①のグループの方が回復は良さそうですよね?
しかし、結果は衝撃的でした。
なんと、①の積極的リハビリグループの方が、3ヶ月後の経過が「悪かった」のです。
「え、どうして?早く動かすのは良いことじゃないの?」
「じゃあ、急性期のリハビリって、何を信じればいいの…?」
そう混乱するのも無理はありません。
この謎を解くカギは、私たちが普段のリハビリで直接見ることのできない**『脳血流』**に隠されていました。
あなたの患者さんの脳は「壊れたダム」と同じ状態かもしれない
健康な人の脳には、「脳自動調節能」という素晴らしい機能が備わっています。
これは、血圧が上がったり下がったりしても、脳に送る血液の量を常に一定に保ってくれる「安全装置」のようなものです。
しかし、脳梗塞や脳出血を起こした患者さんの脳では、この安全装置が壊れてしまいます。
これを例えるなら、「放水ゲートが壊れたダム」。
- 少し血圧が下がれば、脳に流れる血液は一気に減ってしまう(脳が干上がる危険!)
- 少し血圧が上がれば、脳に過剰な圧力がかかってしまう(脳が水浸しになる危険!)
私たちがリハビリで行う「ベッドを起こす」「車椅子に移る」「立ち上がる」といった何気ない動作。
これらの一つひとつが、この壊れかけたダムの水位(=脳血流)を大きく揺さぶり、ダメージを受けた脳にさらなる追い打ちをかけてしまう危険性があるのです。
患者さんが離床中に見せる「少しボーっとする」「あくびが増える」「呂律が回りにくい」といった些細な変化。
それは、脳が「血流が足りないよ!」と叫んでいる悲鳴なのかもしれません。
【要注意】特にリスクが高い患者さんの“危険なサイン”とは?
「じゃあ、どんな患者さんに特に注意すればいいの?」
そのヒントは、MRIの画像に隠されています。
専門的で難しいと感じるかもしれませんが、この2つのキーワードだけは覚えておいてください。
- DWI/MRAミスマッチ
- 簡単に言うと、「血管は詰まってるのに、まだ脳梗塞になっていない部分がたくさんある」状態。いわば**脳梗塞の“時限爆弾”**を抱えているようなもので、少しの血流低下が大規模な脳梗塞の引き金になりかねません。
- 虚血性ペナンブラ
- 「血流は悪いけど、まだ死んでいない。でも、今助けないと死んでしまう」という、救えるかどうかの瀬戸際にある脳組織のこと。非常にデリケートで、血流の変化に極めて弱い状態です。
もし、あなたの担当患者さんのカルテにこれらの言葉があったら、それは**「離床は最大限の注意を払うべし!」**という主治医からのメッセージです。
画一的なリハビリ計画ではなく、その患者さんだけの、オーダーメイドのリスク管理が求められます。
“安全なリハビリ”の新常識|明日からできること
「リスクがあるのは分かった。でも、何もしないわけにはいかない…」
「じゃあ、一体どうすればいいの?」
その答えは、リハビリの”発想”を転換することにあります。
これまでの**「量(時間)」を追求するリハビリから、「質」と「頻度」**を重視するリハビリへ。
例えば…
【旧来の発想】
「1回40分、しっかり車椅子に座り続けよう!」
→ リスク: 長時間の座位で血圧が下がり続け、脳血流が低下するかも…
【新しい発想】
「1回15分の座位訓練を、午前と午後で2回に分けてみよう!」
→ メリット: 1回あたりの脳への負担は最小限。でも、トータルの刺激量は確保できる!
この**「短時間・高頻度」**のアプローチこそが、脳血流を守りながら、安全に機能回復を促すための新しいスタンダードになりつつあります。
もっと詳しく知りたいあなたへ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
- 脳血流が不安定になるメカニズムを、図解でしっかり理解したい!
- リスクの高い患者さんの画像所見(DWIや灌流画像)を、もっと具体的に知りたい!
- 「短時間・高頻度」リハビリの具体的な実践例や、体制づくりのヒントが欲しい!
- NIRS(近赤外分光法)など、最新のモニタリング技術を臨床にどう活かすかを知りたい!
もし、あなたがそう感じているなら、きっとお役に立てるはずです。
今回お話しした内容を、医学論文**「脳血流と理学療法 脳卒中急性期の臨床から」**を基に、さらに深く、明日からの臨床に直結する形で徹底解説したnote記事をご用意しました。
▼▼▼ 記事はこちらから ▼▼▼
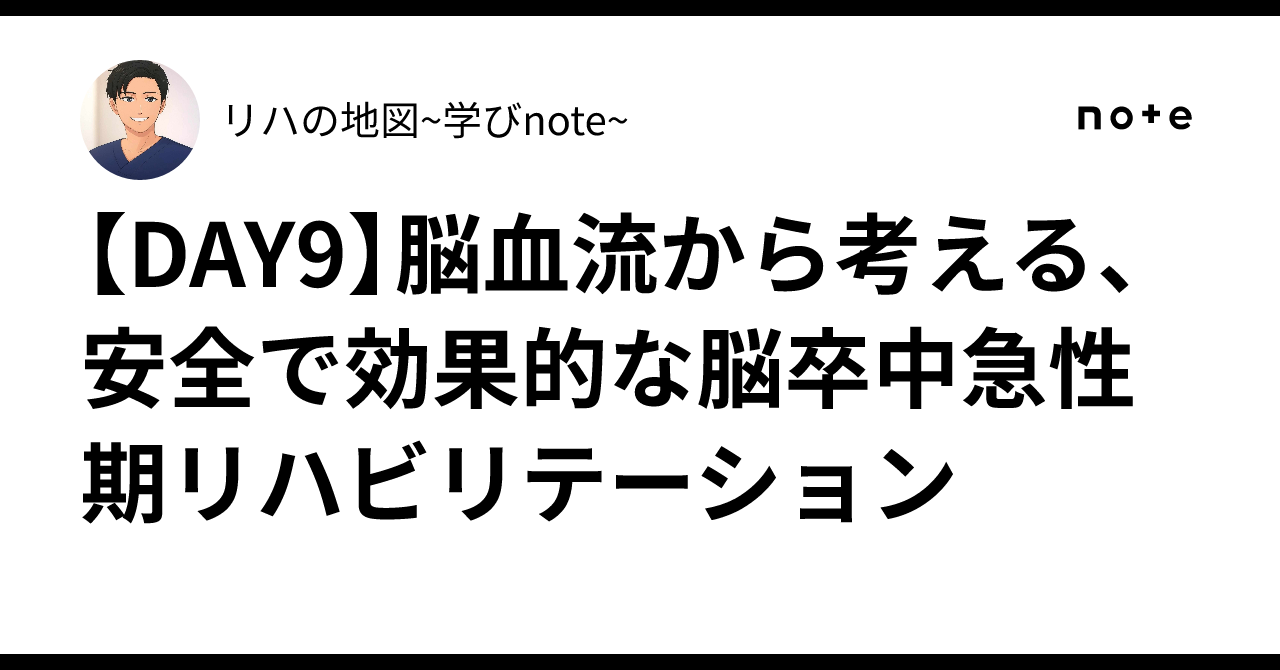
この記事を読めば、あなたの脳卒中急性期リハビリに対する視点がかなり広がります。
患者さんの“本当の”状態を理解し、自信を持って安全かつ効果的なリハビリを提供できるようになるための一歩を、踏み出してみませんか?
もう、「良かれと思って」が、患者さんの未来を奪うことはありません。
科学的根拠に基づいたリスク管理で、患者さんの可能性を最大限に引き出すセラピストになりましょう。