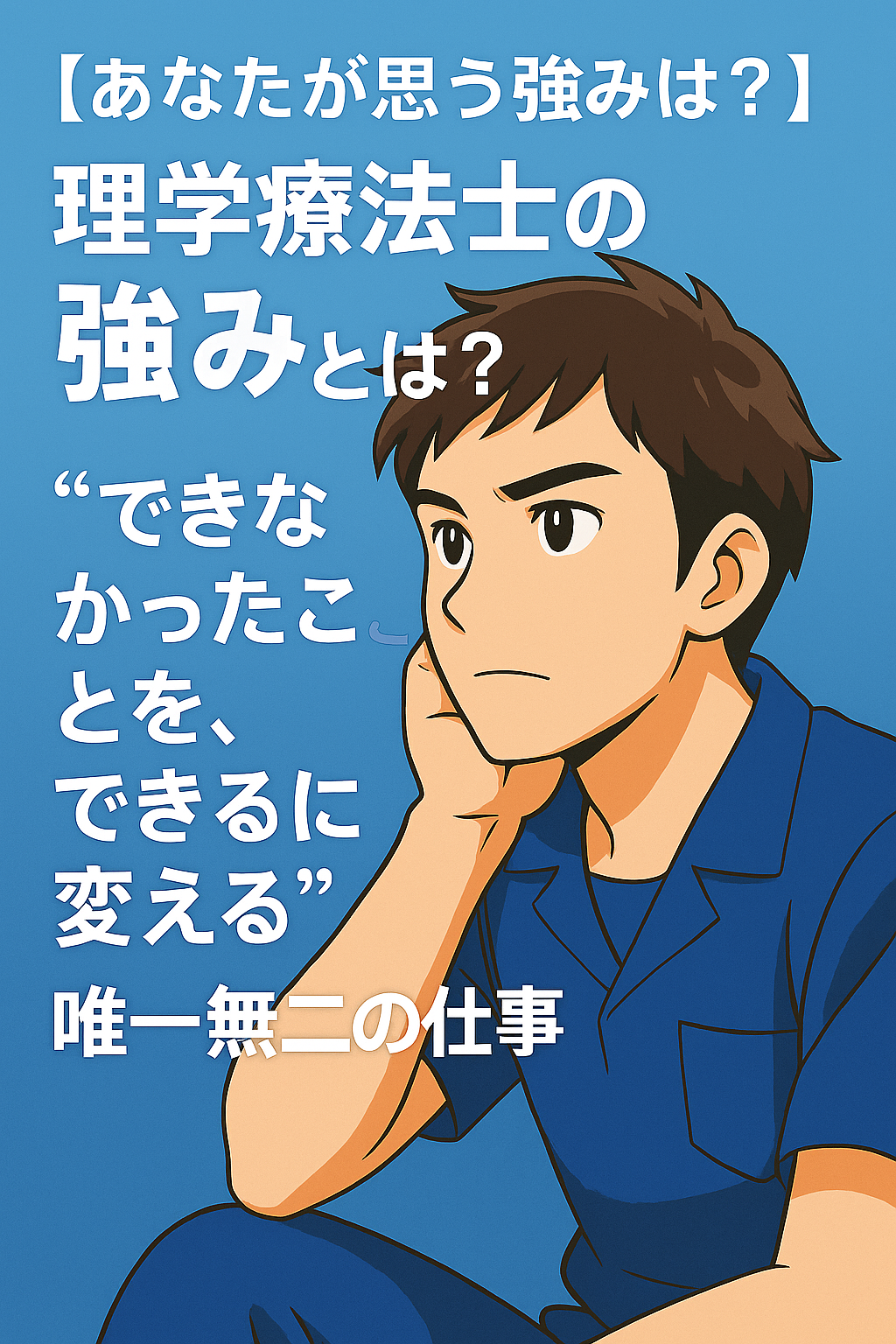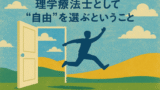はじめに
「良かれと思ってフィードバックしたのに、新人が不満そうな顔をしている…」
「評価面談でしっかり説明したはずが、少しも行動が改善されない…」
「『今回の評価には納得できません』と言われてしまい、どう返せばいいか分からなかった…」
新人の指導を担当するOJT担当者やメンター、管理職の方なら、一度はこんな悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。
その原因は、決してあなたの説明が下手だからではありません。多くの場合、指導者と新人の間にある「認識のズレ」が、評価の説明が伝わらない根本的な原因なのです。
この記事では、その「ズレ」を解消し、新人の成長を効果的に促すための「3つの視点」を、具体的な会話例と共に解説します。明日からの新人とのコミュニケーションが変わり、育成に自信が持てる一助となれば幸いです。
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「もしあなたが担当していたら、どう考えたか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、
臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みに特化したリハ評価のフレームワーク解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

なぜ評価の説明は新人に伝わらないのか?よくある3つの原因
まず、なぜ一生懸命な説明が空回りしてしまうのか。その背景にある、新人指導で陥りがちな3つの原因を見ていきましょう。
原因1:前提のズレ:「当たり前」の基準が違う
指導者には、これまでの経験から培われた「仕事とはこういうもの」「これくらい出来て当然」という暗黙の基準があります。
しかし、新人はまだその基準を知りません。この経験値の差から生まれる「当たり前のズレ」が、評価の受け止め方に大きなギャップを生みます。指導者が「当然できていないこと」を指摘しても、新人にとっては「そもそも何が正解かすら分からなかったこと」かもしれません。
原因2:感情の壁:「人格否定」と受け取られてしまう
「なんで出来ないの?」「もっと考えて行動して」といった抽象的で、少し感情の乗った言葉。これらは指導者側からすれば「奮起を促すため」の言葉かもしれません。
しかし、受け取る新人側は、具体的な行動ではなく「自分の能力や人格そのものを否定された」と受け取ってしまいがちです。一度心を閉ざされてしまうと、どんな的確なアドバイスも響かなくなってしまいます。
原因3:行動の迷子:「で、どうすればいいの?」が不明確
評価の結果や「ここがダメだった」という点だけを伝えても、新人は「次に何をどう改善すれば良いのか」が分かりません。課題を指摘されただけで具体的な次のアクションプランが示されなければ、新人は道に迷ったまま立ち尽くすことしかできず、結果として行動変容には繋がりません。

新人の行動を変える!評価説明で見直したい3つの視点
では、どうすればこれらの壁を乗り越え、新人の納得感と成長を引き出すフィードバックができるのでしょうか。ここからは、評価の説明で見直したい「3つの視点」を、NG例とOK例を交えて解説します。
視点1:「主観」から「客観的な事実」へ切り替える
評価の納得感を高める上で、最も重要なポイントです。「ダメ」「良い」といったあなたの主観的な評価を伝える前に、誰もが「そうだね」と認められる客観的な事実(ファクト)から話しましょう。
- NG例:
「君は報告が遅いよね。もっと早くしてくれないと困るよ。」- (→「遅い」は主観であり、反発を招きやすい)
- OK例:
「【事実】先週水曜の症例報告会の件だけど、抄録提出が締め切りの翌日木曜の午前中になっていたよね。【影響】あれが遅れると、運営全体の資料作成がストップしてしまうんだ。【相談】もし何か作業で困っていることがあれば、教えてくれないかな?」
このように、「事実」から入ることで、相手は冷静に話を聞く態勢になります。
TIPS:フレームワーク「SBIモデル」このテクニックは「SBIモデル」というフレームワークで説明できます。
- S (Situation):状況 → 「先週水曜の症例報告会の件で」
- B (Behavior):行動 → 「提出が締め切りの翌日だった」
- I (Impact):影響 → 「運営の資料作成がストップしてしまう」
この順番で伝えるだけで、フィードバックは驚くほど伝わりやすくなります。ポジティブな評価にも使えるので、ぜひ覚えておきましょう。
視点2:「過去の評価」と「未来への期待」をセットで伝える
評価は、過去の行動をジャッジするだけの場ではありません。未来の成長を促すための「未来志向のコミュニケーション」と捉えましょう。
評価結果と共に「だからこそ、次はこうなってほしい」という未来への期待を具体的に伝えることで、新人のモチベーションを引き出すことができます。
- NG例:
「今回の評価はCでした。特に報告の遅れが課題です。以上です。」- (→ただの「通達」。新人は落ち込むだけで次が見えない)
- OK例:
「今回の評価はC。理由は、さっき話した報告の件が影響している。でも逆に、患者さんへの説明の丁寧さ(△△)はすごく良くて、科内でも評判だよ。だからこそ、次は報告のスピード(〇〇)を克服すれば、次はB評価が絶対に見えてくる。そこを一番期待しているよ。」
良い点と改善点を必ずセットで伝え、未来の成長にフォーカスすることで、新人は「自分のことを見てくれている」「次も頑張ろう」と感じることができます。
視点3:「一方的な通達」から「対話による合意形成」へ変える
評価の説明は、指導者のプレゼン大会ではありません。指導者が一方的に話して終わりにするのではなく、新人の考えを引き出し、次のアクションを「一緒に」考える姿勢が何より重要です。本人の口から目標や改善策を言わせることで、行動への主体性が生まれます。
- NG例:
(説明後、沈黙する新人に対して…)
「…分かった?じゃ、そういうことで。来週から頑張って。」- (→新人は何も理解・納得していない可能性がある)
- OK例:
(説明後…)
「ここまで聞いて、率直にどう感じたかな?」
「この課題を乗り越えるために、明日から具体的に何ができそうか、アイデアを一緒に考えてみようか。」
「まずは『報告が遅れそうなときは、締め切りの半日前に相談する』ことから始めてみるのはどうかな?」
このように問いかけることで、新人が何につまずいているのかを正確に把握できます。評価の場を「ジャッジの場」から「心理的安全性の高い作戦会議の場」へと変える意識を持ちましょう。
まとめ:評価の説明は「育成のための対話」である
今回は、新人に評価の説明が伝わらない理由と、その解決策となる3つの視点について解説しました。
- 評価が伝わらない3つの原因
- 前提のズレ: 指導者と新人の「当たり前」が違う
- 感情の壁: 人格否定と受け取られてしまう
- 行動の迷子: 次の具体的なアクションが不明確
- 見直したい3つの視点
- 客観的な事実から始める(主観→事実)
- 「評価」と「期待」をセットで伝える(過去→未来)
- 「対話」で次のアクションを一緒に考える(一方通行→対話)
評価の説明は、新人を「判断する」だけの場ではありません。新人の現在地を確認し、未来の成長を後押しするための、指導者と新人にとって**最も大切な「対話の機会」**です。
完璧なフィードバックを目指す必要はありません。まずは次の1on1や面談で、この3つの視点のうち1つだけでも意識してみてください。きっと、新人の反応が変わり、あなたの指導はより効果的なものになるはずです。