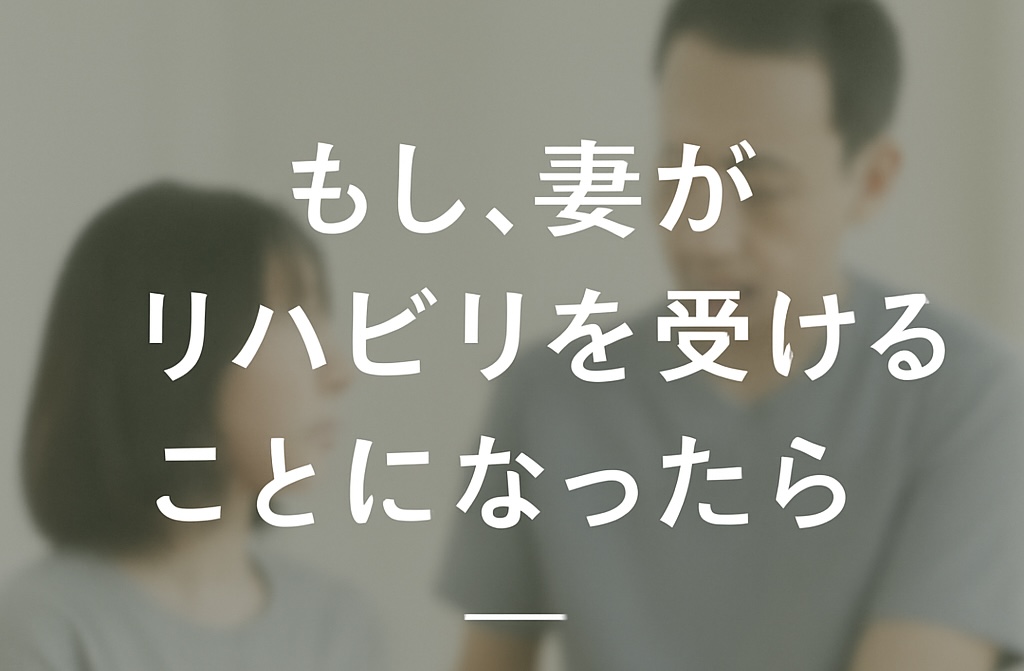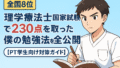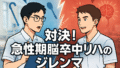はじめに:ずっと胸の中にある問い
「例えば、自分が、もしくは自分の大切な人がリハビリを受けることになった場合、
あなたは今と同じようなリハビリを継続しますか?」
この問いは、突発的に浮かんできたものではありません。
僕が理学療法士として臨床現場に立ち続けるなかで、いつの間にか常に頭のどこかで反復している“自問”のようなものです。
たとえ目の前の臨床がどれほど忙しくても、治療プログラムを淡々とこなす日であっても、この問いは小さな違和感や引っかかりとなって、自分に問いかけ続けます。
「今、自分のやっていることは本当にこの人のためになっているのか?」
「目の前のこのリハビリは、自分の妻だったとしても納得して任せられる内容なのか?」
この問いが、僕にとっての“臨床の軸”であり、“良心のセンサー”であり続けています。
技術や知識の精度だけでなく、人としての誠実さを測るための、静かだけれど確かな基準なのです。
⸻
忙しさに流されそうになる日常の中で
理学療法士の現場は、決してゆとりのある環境とは言えません。
時間に追われ、スケジュールに追われ、点数や制度の枠組みに縛られながら、1日に何人もの患者さんと関わる日々が続きます。
それでも、どんなに忙しくても、やっぱり僕はこの問いを自分に投げかけてしまいます。
「このリハビリ、本当にこの人にとって意味のある時間になっているだろうか?」
時に、形式的な評価や治療を“こなす”ことで日々を終えそうになる瞬間もあります。
そんなときこそ思い浮かぶのが、「この方がもし妻だったら?」という視点。(自分の子ども、親、の時もありますが。)
身近な人のことを思い浮かべると、自然と行動が変わります。
説明ひとつとっても、「ただ伝える」のではなく、「どう伝えれば不安が軽減するか」を考えるようになります。
リハビリ内容に対しても、「制度の範囲内だから」ではなく、「本当にこの方に必要な刺激とは何か?」という視点で再評価するようになります。
この問いがあることで、僕は単なる作業者にならずにすんでいるのかもしれません。
そして、誰かの“大切な人”を任されている責任を、現場の喧騒の中でも忘れずにいられるのです。
⸻
妻がこのベッドにいるとしたら
この問いを最も強く実感するのは、「自分の妻が、いまこのベッドにいるとしたら」と想像したときです。
僕はきっと、どんなに時間がなくても、どんなに効率が求められていても、彼女が安心できる言葉をかけるでしょうし、心から納得できる説明を丁寧に繰り返すと思います。
彼女が抱える小さな不安や痛みにも、もっと敏感になるだろうし、治療内容にも常に「この選択は彼女にとって最善か?」と立ち返りながら対応するはずです。
もちろん、患者さん全員に100%同じようなエネルギーを注ぐことは現実的には難しい。
けれど、そうありたいと願い続ける姿勢こそが、理学療法士としての“原点”ではないかと思っています。
この想像は、感情に流されるということではありません。
むしろ、僕たちが無意識に効率や慣習の中で置き去りにしてしまいがちな「個別性」や「尊厳」に立ち戻るための、極めて実践的な問いだと感じています。
⸻
自分の中にある“軸”としての問い
「もし、妻だったらどう関わるだろう?」
この問いは、僕の臨床の“羅針盤”です。
外部環境に左右されず、自分の対応を客観的に振り返らせてくれるもの。
自信がなくなる日も、迷う日も、傷つく日も、この問いだけは消えずに残ってくれています。
理学療法士という職業は、医療技術職であると同時に、
一人の人間として、人と向き合い、共に歩む仕事だと僕は思います。
どんなに技術が進化しても、AIが診断をサポートする時代が来ても、「この人と、どう関わるのか?」という本質的な問いは、僕たち自身にしか答えられません。
だからこそ、問いを持ち続けること。
それ自体が“プロフェッショナリズム”であり、関わりの質を支える土台になっているのではないでしょうか。
⸻
おわりに:あなたにも、問いがあるなら
この記事をここまで読んでくださった方の中には、
「自分も同じような思いを抱えながら臨床に立っている」と感じた方がいるかもしれません。
問いを持ち続けることは、ときにしんどいことでもあります。
答えが出ないまま、試行錯誤を繰り返す日々。
制度の壁、時間の制約、チームとの温度差──そうした現実の中で、心が擦り減ることもあるでしょう。
それでも、あなたが問いを持っている限り、
そのリハビリには“温度”があります。
ただ機能を改善させるだけでなく、その人の人生を支える関わりになっていく可能性を秘めています。
僕も、完璧な関わりなどできていません。
けれど、「妻だったら、どうするか?」という問いを胸に持ち続けることで、
今日の関わりを、少しでもあたたかく、丁寧なものにしたいと、心から思っています。
⸻
✍あとがき:理学療法士として、人として
僕たちが提供するのは“医療行為”であると同時に、
誰かの人生の一部に関わるという、“かけがえのない時間”です。
誰かの大切な人と関わっているという意識を持てるかどうか。
それだけで、目の前のリハビリの意味合いは大きく変わるのだと思います。
あなたの問いも、きっと誰かの力になります。
僕の問いと共に、これからも一緒に悩み、考え続けていきませんか?
ここまで読んで頂きありがとうございました。