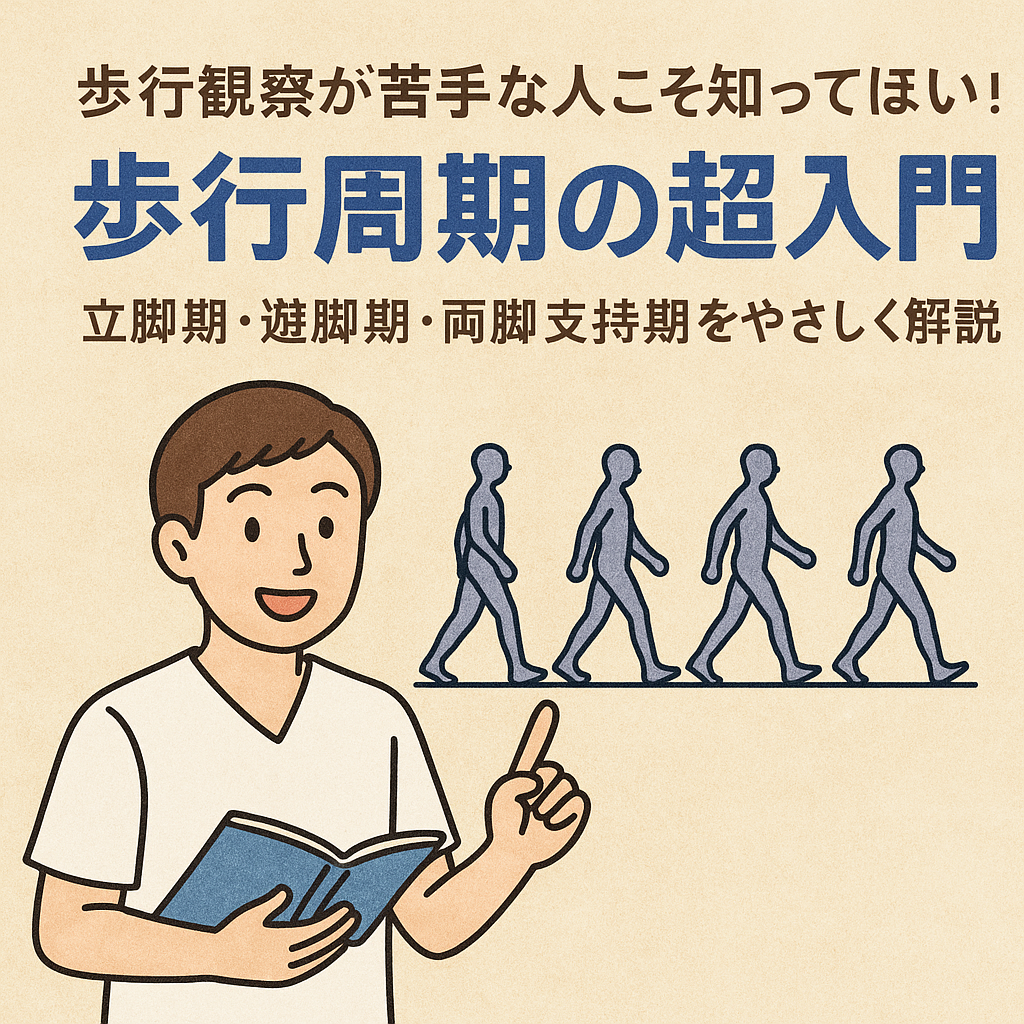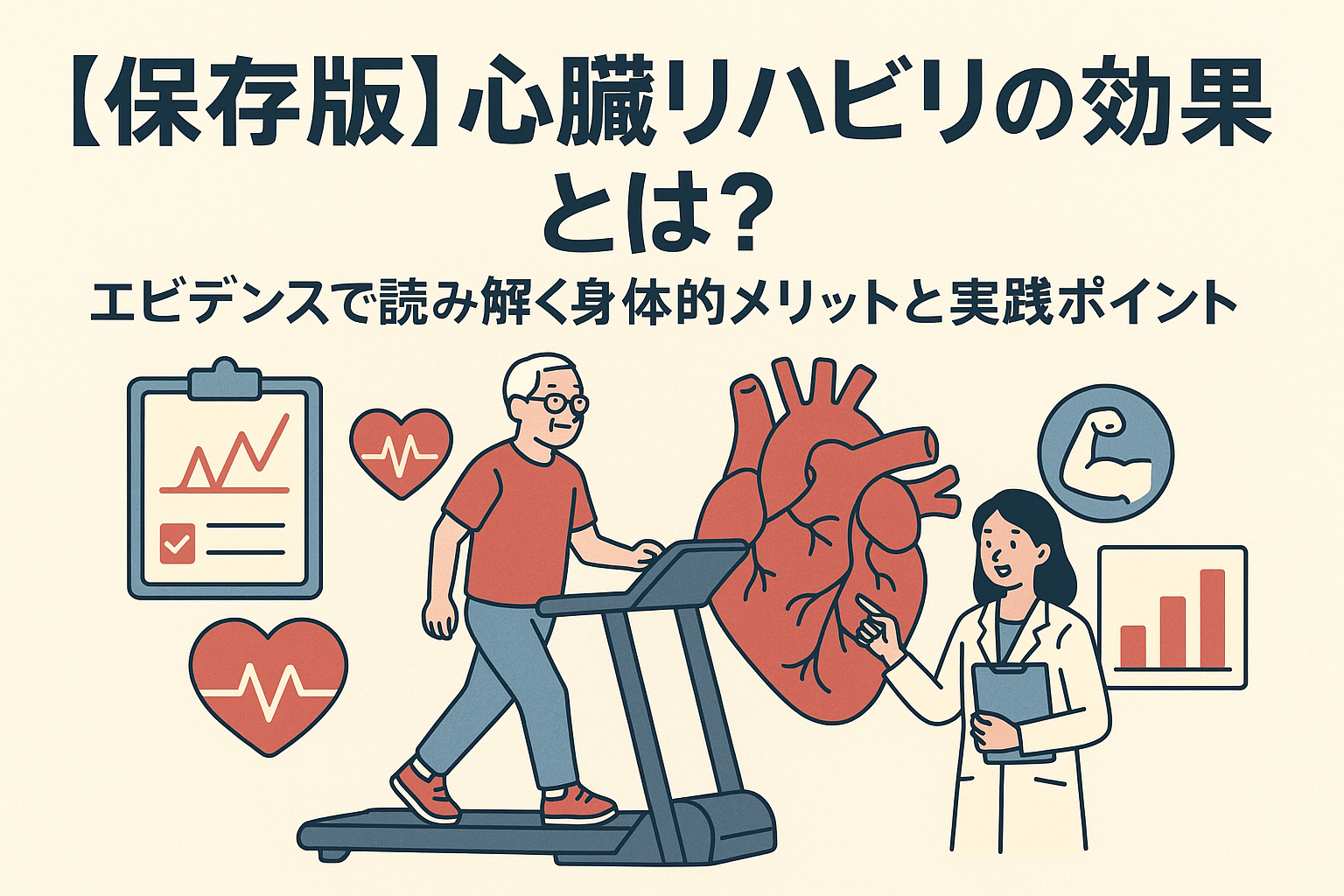はじめに
歩行周期(gait cycle)は、リハビリテーション、特に歩行分析において欠かせない重要な概念です。理学療法士や作業療法士はもちろんのこと、リハビリテーションを志す学生、介護職、スポーツ指導者などにとっても、「歩く」ことの仕組みを理解することは非常に大きな意味を持ちます。
本記事では、歩行周期の全体像からその内訳、臨床での応用の一歩手前までを丁寧に解説していきます。
\より専門的な記事はこちら/

歩行とは何か? 〜単なる「移動」ではない複雑な全身運動〜
歩行はどんな動作なのか言語化できますか?
歩行とは、“姿勢の安定を保ちながら、下肢の運動によって身体を前進させる運動”です。
一見するとシンプルな「前に進む動き」に見えるかもしれません。しかしその実態は、姿勢の安定性を保ちながら下肢を交互に運び、重心を移動させる極めて高度な運動制御で複雑な運動パターンで成り立っています。
歩行中には、
- 姿勢の維持
- 下肢の交互運動
- 重心の左右移動
- 地面反力の制御
といった多数の要素が連動しています。さらに、これらの要素は反復的かつ周期的に繰り返されており、その単位が「歩行周期(Gait Cycle:GC)」です。
歩行周期とは?〜歩行の“1サイクル”を定義する〜
歩行周期は、片方の足が地面に接地してから再び接地するまでの一連の流れを指します。たとえば右足を基準にするなら、「右足が地面についた瞬間」から始まり、「再び右足が同じように地面につく」までが1サイクルになります。
この周期には、
- 立脚期(stance phase):地面に足が接している時間
- 遊脚期(swing phase):足が地面から離れ、次の一歩を出す準備をする時間
という2つの大きなフェーズが存在します。この2つのフェーズを正確に理解することで、歩行の正常・異常を見極める力が身につきます。
歩行周期の2大フェーズ:立脚期と遊脚期
立脚期(stance phase)
歩行周期の約**60%**を占めるこのフェーズは、足が地面について体重を支えている状態です。
立脚期はさらに以下のサブフェーズに分けられます(解剖学的な分類)
- 初期接地(initial contact)
- 荷重応答期(loading response)
- 立脚中期(mid stance)
- 立脚終期(terminal stance)
- 前遊脚期(pre swing)
この間、足は体重を支持しながら重心の移動を可能にし、かつ次の一歩へとスムーズにつなげる役割を果たします。
臨床では、支持性・疼痛・荷重制限の評価がこの時期の観察ポイントとなります。
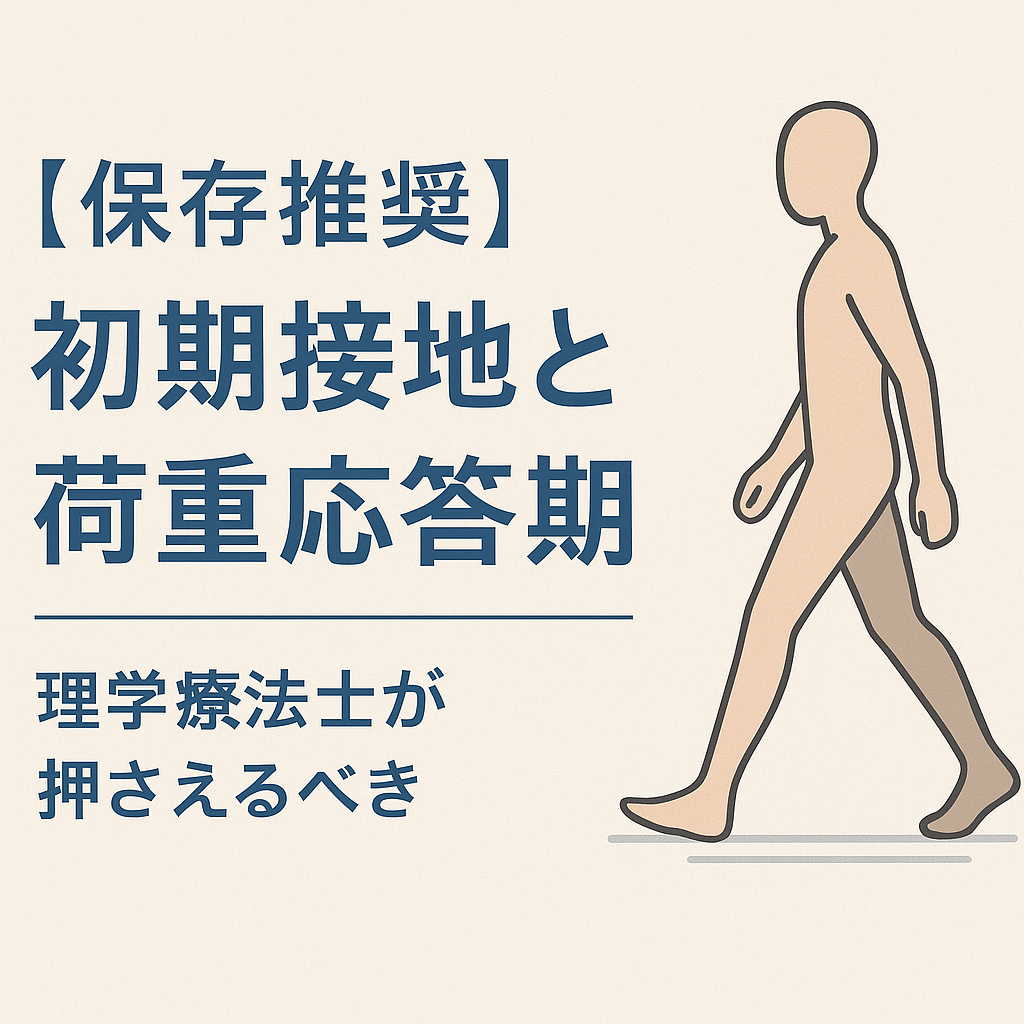
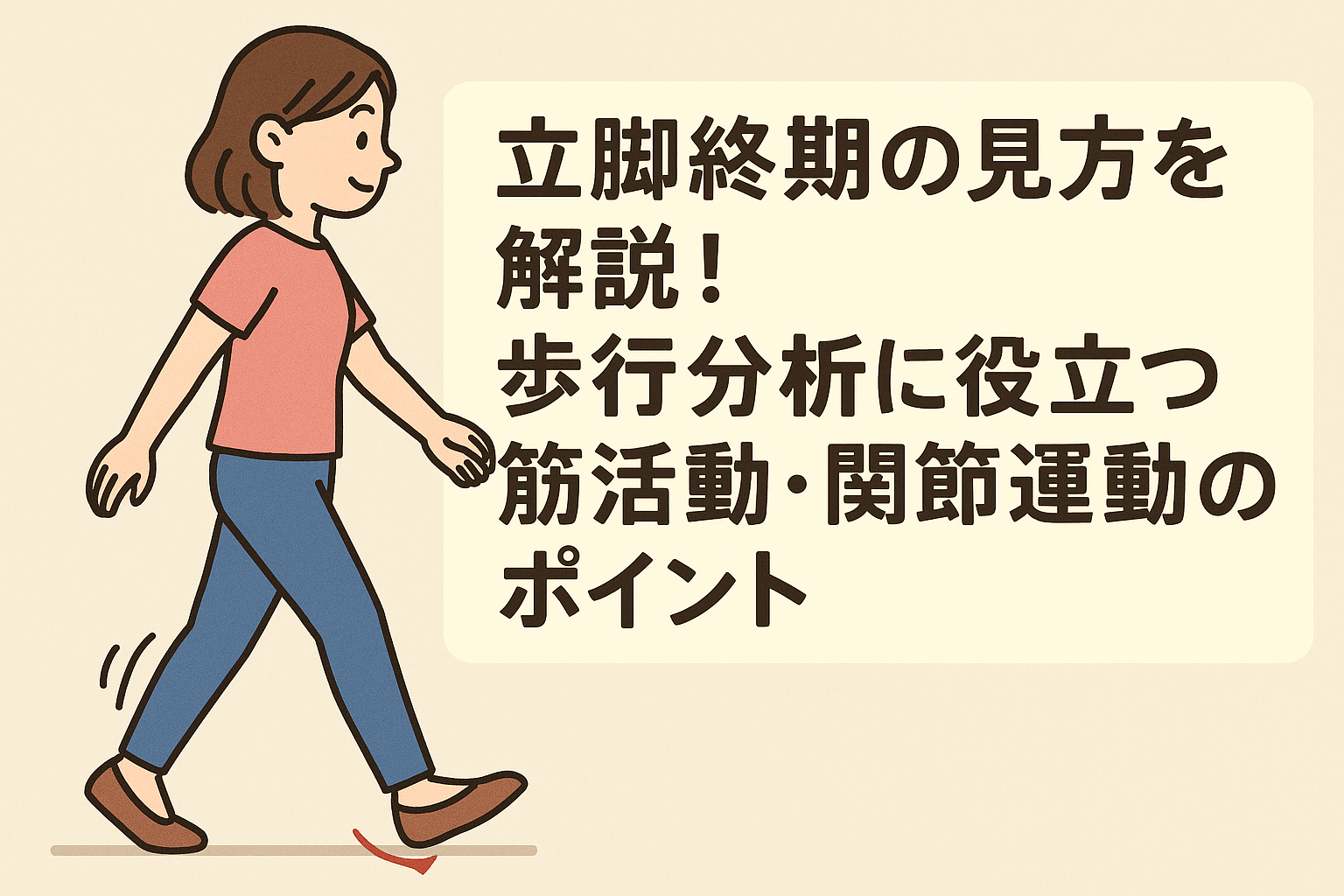
遊脚期(swing phase)
歩行周期の残り**40%**を占める遊脚期は、足が地面から離れ、次の接地へ向けて振り出される期間です。
こちらも以下のサブフェーズに分けられます
- 初期遊脚(initial swing)
- 遊脚中期(mid swing)
- 終期遊脚(terminal swing)
この時期には、足部の振り出し能力や関節可動域、筋力、協調運動が重要になります。歩幅や歩行速度にも大きく関与するため、評価や治療の焦点になりやすい部分です。
両脚支持期と片脚支持期:バランス評価の鍵となる概念
歩行周期の中では、**両脚が同時に地面に接している「両脚支持期(double stance phase)」**が2回存在します。
これは主に
- 初期接地〜荷重応答期
- 前遊脚期の終わり
に該当し、全体の約20〜24%を占めています。加齢や神経疾患では、この両脚支持期が長くなる傾向にあり、バランス不安定性の指標にもなります。
一方、片脚支持期(single limb support:SLS)は、片足で体重を支える期間であり、筋力や姿勢制御能力が強く求められます。評価では、骨盤の安定性や股関節周囲筋の働きに注目します。
歩行周期の始まりは「初期接地」からが基本
臨床や教育現場で一般的に用いられる歩行周期のスタート地点は、「初期接地(initial contact)」です。これは、かかとが地面に接触した瞬間であり、視認しやすく、モーションキャプチャや映像分析でも取り扱いやすいタイミングです。
反対に、「どこから歩行周期を数えるか」は学派や分野によって異なる場合がありますが、初期接地を基準とすれば一貫した評価が可能になります。
まとめ:歩行周期の理解はリハビリの第一歩
歩行周期を理解することは、単に知識を得るだけでなく、「どこで異常が起きているのか?」を見極めるための基盤になります。
- 立脚期では「支持性」「疼痛」「体重移動」
- 遊脚期では「振り出し」「可動域」「タイミング」
など、歩行分析は評価の宝庫です。
リハビリテーションや動作分析、スポーツ科学に関わるすべての人にとって、この「歩行周期」の基本をしっかり身につけることが、臨床の質を高める第一歩となります。