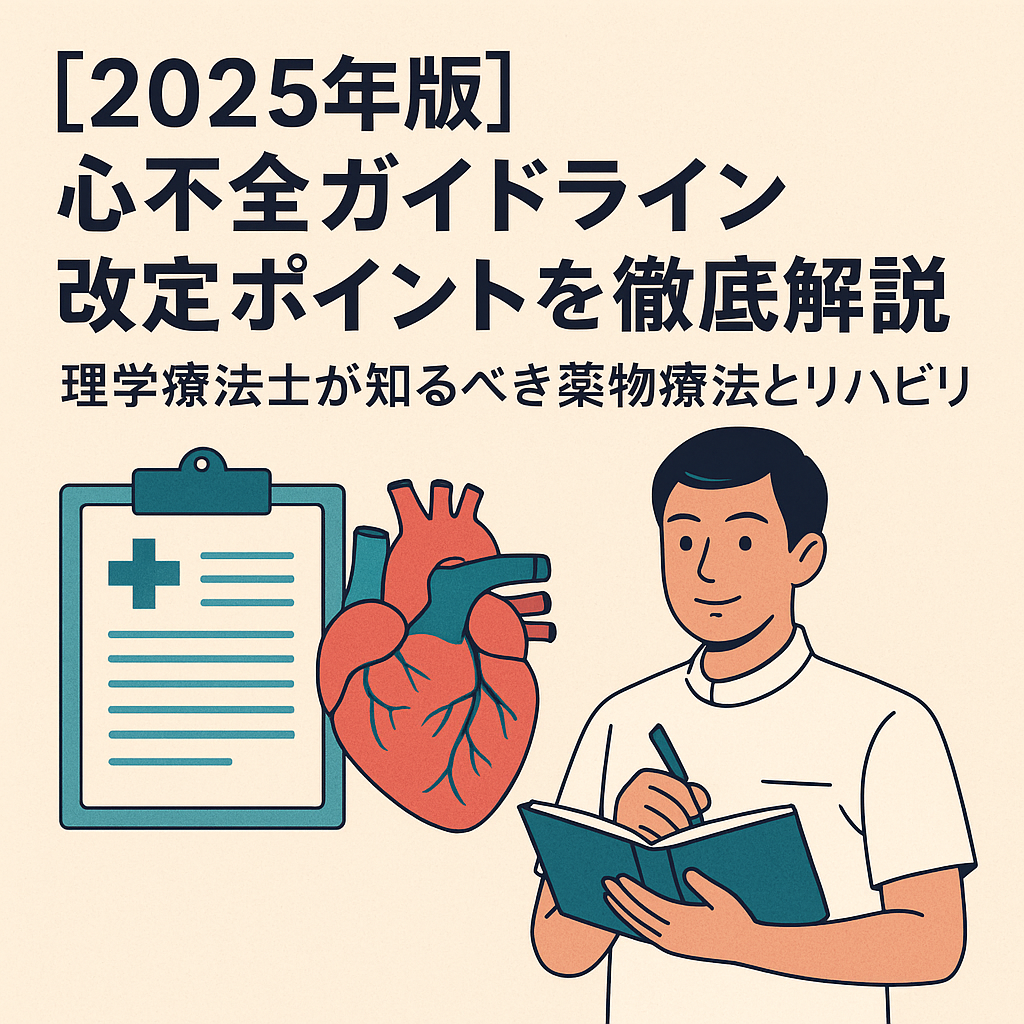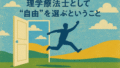はじめに
ゴールデンウィークが終わると、なぜか心が重たくなる――。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ職種の皆さんも、そんな感覚を味わったことはありませんか?
「仕事に集中できない」
「患者さんへの声かけもいつものように元気が出ない」
――それは決してあなただけではなく、多くの人が直面する 5月病 という心身のリズムの乱れかもしれません。
特にリハビリ現場は、患者さん一人ひとりの状態に向き合い、細かい変化を見逃さない集中力が求められます。
だからこそ、この時期の モチベーション低下 は、自分だけでなく現場全体、ひいては患者さんのリハビリ進度にまで影響を及ぼしかねません。
この記事では、なぜこの時期にやる気が落ち込むのか、考えられる理由と背景を整理したうえで、対策となりえる方法をを「個人編」と「チーム編」に分けてご紹介します。
明日からの現場でのヒントとして、ぜひ役立ててください。
5月病・モチベーション低下はなぜ起こる?
5月病とは、春の新生活や人間関係の疲れ、環境の変化によるストレスが、
ゴールデンウィーク明けに表面化しやすくなる現象を指します。
医療職やリハビリ職では特に以下のような事情があります。
- 4月の緊張が一気に緩む
新年度が始まる4月は、職場異動、新人教育、新しい担当患者さんとの関わりなど、何かと緊張感の連続です。
「気が張っていた分、連休で一気に反動がくる」というのは、むしろ自然なことです。
- 新人・若手の「壁」の時期
入職1か月が過ぎ、最初の勢いが落ち、壁にぶつかりやすいのがこの時期。
「自分はこの仕事に向いていないんじゃないか」と悩む新人も多いのです。
- 患者さん側のリズムも乱れがち
連休中は入院患者さんもご家族の面会が増えたり、病院内のスケジュールが変則的になったりします。
そのため生活リズムが崩れ、連休明けのリハビリ参加意欲が低下するケースもよくあります。
つまり、個人の問題ではなく 「現場全体のリズムが乱れやすい時期」 と捉えることが、必要以上に自分を責めないための第一歩です。
リハビリ現場の「モチベ低下あるある」
リハビリ現場でよく見かける光景をいくつか挙げてみましょう。
- 新人スタッフが急に元気をなくす
4月は新しい知識や技術を吸収するだけで手いっぱい。
5月になると「失敗」「できない自分」を強く意識し始め、気持ちが沈む新人が目立ってきます。
指導する側としても、この変化を察して早めの声かけが必要です。
- ベテラン勢もリズムが戻らず空回り
ゴールデンウィーク中はスタッフのシフトが変則的になり、勘やペースを取り戻すのに数日かかります。
「本来ならもっと効率的に回せるのに」と焦って余計に疲れる――そんな悪循環に陥る人もいます。
- 患者さんがリハビリに乗り気じゃなくなる
特に高齢の患者さんでは、連休中の面会疲れや、スタッフの顔ぶれの変化で不安が強まることがあります。
「リハビリなんて今日はいいや」と消極的になるのも、自然な反応といえるでしょう。
こうした「現場の空気の重さ」を感じたら、
「今は特別な時期だから」と一歩引いて客観的に状況を見つめることが大事です。
個人でできる!モチベーション低下の対策
ここからは、私自身が日々の中で意識している、個人で実践できるモチベーション対策を紹介します。
小さな成功体験を意識的に拾う
一気に元通りのパフォーマンスを目指すのは難しいです。
たとえば、
「今日は患者さんから1回でも笑顔を引き出せた」
「1つの介入で効果が見えた」など、
小さな達成感に焦点を当てることで、自己肯定感を少しずつ積み上げます。
無理なスケジュール調整を避ける
周りが忙しそうだからと、自分に無理なタスクを積むと、結局は質が落ちて自己嫌悪に陥ります。
今の自分のエネルギーレベルを冷静に見つめ、「今週は6割ペースで進めよう」など、調整する勇気も必要です。
短期の気分変動ではなく長期目標を持つ
「6月末までに○○の技術を身につける」「夏までにこの疾患に詳しくなる」など、
短期的な気分の浮き沈みに左右されない長期目標を意識します。
これは特に新人・若手にとって、目の前の失敗に過剰反応しないための大事な指針になります。
休日や趣味で「自分をリセット」する
これは意外に大事なポイント。
僕の場合では、休日に外で愛犬と一緒に散歩をする、好きなカフェで本を読む、映画を一気見するなど、
完全に「仕事モードを切る時間」を意識しています。
また、趣味がある人はそれに没頭する時間を取るのもおすすめです。
楽器を弾く、スポーツをする、旅行に行く、推し活をする――なんでもOK。
休日を充実させることは、仕事のモチベーションを保つための重要なエネルギー源です。
休日に自分と向き合う視点を入れる

僕のイチオシはこれ!
5月病やモチベーション低下は、ただの「悪い時期」ではありません。
むしろ、自分の心身の疲れに気づき、休日の過ごし方や趣味、休む勇気の大切さを再確認できるチャンスです。
理学療法士・リハビリ職は患者さんを支える立場だからこそ、
自分自身の心と体のケアも欠かせません。
休日の過ごし方を見直し、しっかりリフレッシュできれば、きっと仕事場でのあなたの笑顔や集中力にもつながります。
僕が実際にしている「自分との向き合い方」についての記事は今後作成予定です。
チーム全体でできる!職場の対策
個人努力に限界を感じたときは、チーム全体でできる対策を考えましょう。
気軽な雑談・声かけを増やす
「最近、調子どう?」という一言があるだけで、救われる人は意外と多いものです。
特に新人スタッフは、自分から相談しに行くのが苦手な場合も多いため、
ベテラン側からフラットな声かけを意識するようにします。
休憩時間に笑いや共感の場を作る
疲れているときほど、休憩時間がただの「沈黙の時間」になりがちです。
ときには冗談を言い合ったり、「僕も今週しんどいよ」と本音を共有することで、
職場全体が少しずつ柔らかい雰囲気に変わっていきます。
忙しい時期こそ、業務の分担と協力を明確にする
「手が空いたら助けて」ではなく、「この部分をお願いできますか」と具体的に頼む。
逆に自分も「ここは任せてください」と言えるようにする。
そうした小さな協力の積み重ねが、現場全体のモチベーションを支えます。
まとめ|5月病は成長のチャンスに変えられる
5月病やモチベーション低下は、悪者にされがちですが、
「疲れや不安に気づける時期」「自分の立て直し方を学べる時期」と前向きに捉えることもできます。
理学療法士やリハビリ職は、患者さんの心身の回復を支える立場ですが、
だからこそ自分自身の心のケアや、仲間同士の支え合いがとても重要です。
この記事で紹介した対策を、ぜひ一つでも実践してみてください。
あなたの成長は、きっと患者さんの笑顔やリハビリの成果につながります。
■ 最後に
ここまで読んでくださり、ありがとうございます!
あなたの職場では、連休明けのモチベーション対策、どんなことをしていますか?
この記事が役に立ったと思ったら、シェアも大歓迎です!