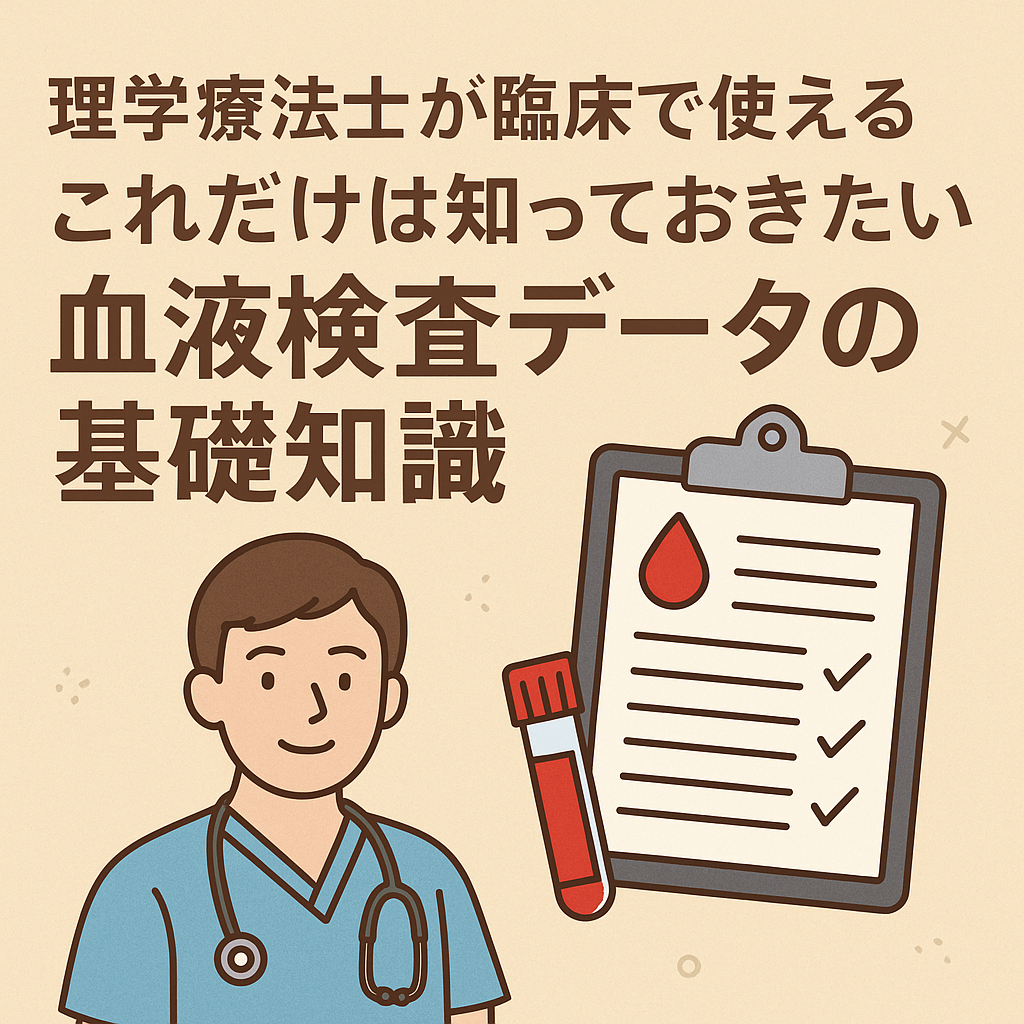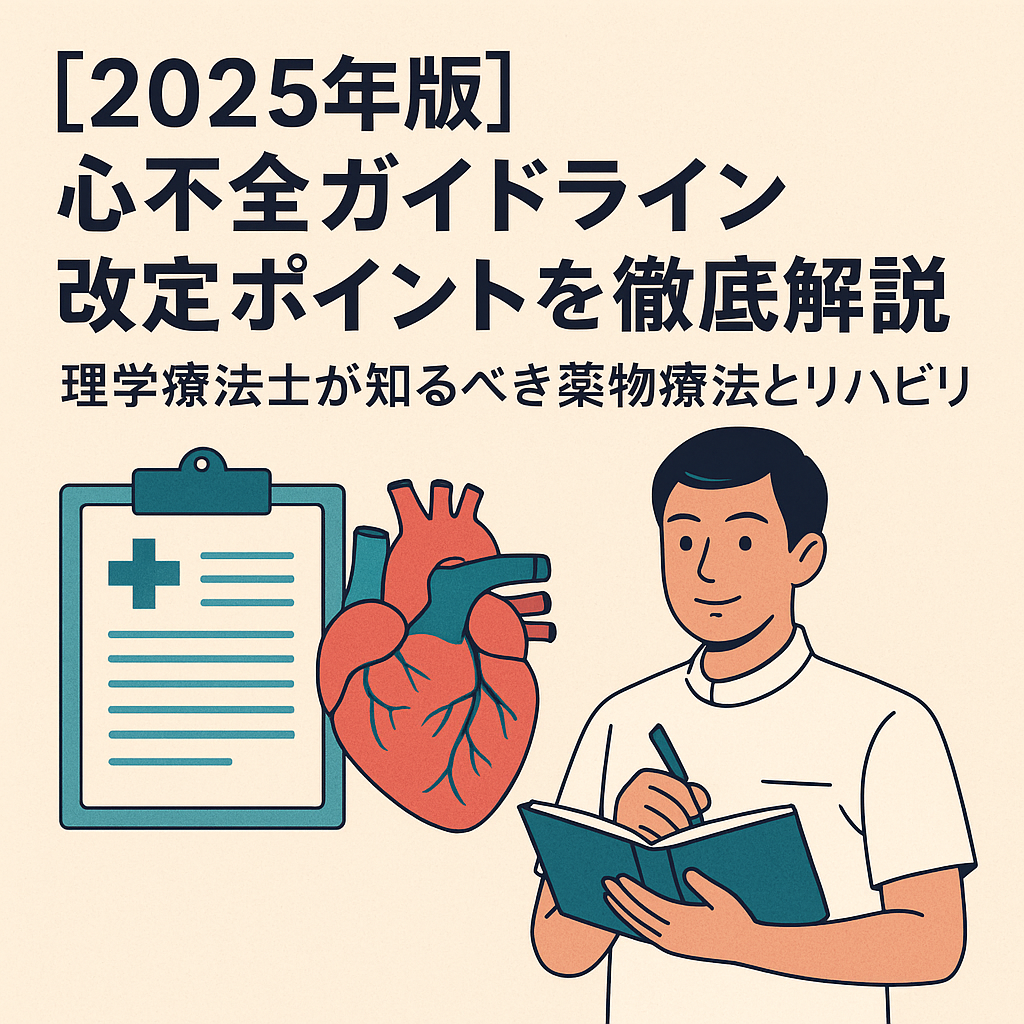はじめに

血液検査のデータって、理学療法士は見る必要あるの?

血液検査のデータって、理学療法士はどこを見ればいい?どうなってリハビリに活かすの?
新人や若手の理学療法士(PT)の方からたまにある質問です。
たしかに、血液検査結果の正式な評価や治療方針決定は医師の領域です。しかし実は、血液検査データはリハビリ場面でもとても重要な情報源になります。
患者さんの状態を知り、適切なリスク管理をするための「臨床力の土台」といえるでしょう。
理学療法士が血液検査を理解することで、以下のような臨床判断が可能になります。
- 運動負荷を安全にかけられるかの判断
- 離床の可否、安静度の調整
- 倦怠感・呼吸苦・不整脈などのリスク予測
- 医師・看護師への的確な情報共有
この記事では、「理学療法士が知って得する」「臨床ですぐ使える」血液検査データの見方・活かし方を、わかりやすく解説していきます。
血液検査データ、何を見ればいい?

血液検査項目って多すぎて、何を見たらいいかわからない
新人PTなら誰しも感じる悩みです。
正直なところ、僕もまだまだ十分に血液検査項目を把握し、リハビリに活かせることはできていません。
血液検査の結果票には、何十もの項目が並んでいますが、臨床の現場ですべてを完璧に覚える必要はありません。
リハビリ場面で役立つのは、リスク管理や運動療法の可否を判断するための主要項目です。医師のように診断目的で使うのではなく、リハビリの安全性評価と介入判断の補助情報として活用します。
具体的には、
- 炎症(感染症)を示す項目
- 酸素運搬能力を示す貧血関連
- 腎臓・肝臓の代謝・排泄機能
- 電解質バランス(心機能、神経伝達に重要)
- 凝固系(血栓・出血リスク)
まずは、これらに絞って覚えるのがおすすめです。
臨床でよく使う主要項目
では、理学療法士が知っておくべき主要な血液検査項目と、実際の臨床でどう役立つのかを詳しく見ていきましょう。
■ 炎症関連
CRP(C反応性タンパク)
炎症や感染症の指標。特に細菌感染で急上昇し、慢性炎症疾患(関節リウマチなど)でも持続的に高値を示すことがあります。術後や外傷後は一時的に上昇しますが、通常は経過とともに低下していきます。
基準値:0.3 mg/dL以下
CRPが著しく高値(10 mg/dL以上)の場合、全身状態悪化リスクがあり、無理な離床や運動負荷は避けましょう。発熱、全身倦怠感、意識状態の変化を伴う場合は、必ず医師に相談を。たとえば、肺炎で入院中の患者が「今日はしんどい」と言った場合、CRPの急上昇が隠れている可能性があります。
WBC(白血球数)
体の防御反応の主役。感染症や炎症で増加、逆に免疫抑制状態(がん化学療法中など)では低下します。
基準値:3,000–9,000 /μL
白血球が極端に低い場合(1,000 /μL以下)、感染リスクが非常に高くなります。理学療法士自身の手指衛生、マスク着用はもちろん、外来リハなら周囲の感染状況にも配慮が必要です。
■ 貧血関連
Hb(ヘモグロビン)
酸素を全身に運ぶ赤血球成分。貧血が進むと、運動時の酸素供給が不足し、息切れや動悸、めまいの原因になります。
基準値:男性13–16 g/dL、女性12–15 g/dL
Hb 7–8 g/dL以下では、離床・歩行時の呼吸苦や動悸に注意。急な立ち上がりや長距離歩行は避け、座位練習やADL練習を中心に調整します。実際、私が担当した高齢女性でHb 6.5 g/dLの方は、歩行練習で酸素飽和度が急低下し、即中止となった経験があります。
Ht(ヘマトクリット)
血液中の赤血球割合。脱水や貧血の指標。
基準値:男性40–50%、女性35–45%
Hbとセットで確認しましょう。脱水状態ではHtが高く出るため、数値の裏側にある患者の水分バランスも読み取ることが重要です。
■ 腎機能
BUN(尿素窒素)、Cre(クレアチニン)
腎臓の老廃物排泄機能を示す。腎不全が進行すると、全身倦怠感、意識障害、浮腫、高K血症などを引き起こします。
基準値:BUN 8–20 mg/dL、Cre 0.6–1.0 mg/dL
透析患者では、治療後の急激な脱水や電解質変動に注意。リハビリ前後の体調をよく観察し、場合によっては医師と相談して負荷量を調整します。特に透析当日は、立位訓練や歩行の負荷を軽めに設定することが多いです。
■ 肝機能
AST(GOT)、ALT(GPT)
肝細胞障害のマーカーですが、筋肉の損傷(外傷・過剰な運動)でも上昇します。
基準値:10–40 U/L
肝疾患のある患者では、筋疲労の回復遅延や全身倦怠感に注意が必要です。私が以前経験したケースでは、筋肉トレーニング負荷を上げすぎた結果、ASTが急上昇し、医師からリハ強度の再調整を求められたことがありました。
■ 電解質
Na(ナトリウム)、K(カリウム)、Cl(クロール)
細胞の浸透圧、神経伝達、筋収縮に関与。特にKは心筋の活動電位に直結するため、不整脈リスクに注意。
基準値:Na 135–145 mEq/L、K 3.5–5.0 mEq/L、Cl 98–108 mEq/L
Kが3.0未満または6.0以上の場合は危険域。不整脈の兆候(脈の乱れ、胸部違和感)があれば、ただちに運動を中止し、医療チームに報告を。
■ 凝固系
- PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)、Dダイマー
血液の固まりやすさを表す。Dダイマーは血栓溶解後の分解産物で、深部静脈血栓症(DVT)や肺塞栓症の疑い時に重要です。
基準値:PT 10–14秒、APTT 25–40秒、Dダイマー 0.5 μg/mL未満
臨床でのポイント:抗凝固療法中の患者は、ちょっとした打撲や転倒でも出血リスクが高まります。Dダイマーが高く、下肢の腫脹・痛み・呼吸苦がある場合は、緊急対応が必要です。
新人がやりがちな勘違い・ミス
新人理学療法士の臨床現場でよく見かけるのは、
- 基準値内だから安心だと誤解すること
- 数字だけを見て患者を評価すること
- 異常値を見つけても上司や医師に相談しないこと
血液検査は、あくまで患者の全身状態を補助的に把握するための情報です。バイタルサイン、症状、意識状態とセットで総合的に評価する力が大切です。
まとめ
血液検査データは、理学療法士にとって患者の状態を知る大切なツールです。診断や治療を行うためではなく、リスク管理やリハ介入の安全性を判断するために活用します。
新人・若手の理学療法士は、今回紹介した主要項目から覚え、臨床で繰り返し確認・活用することで、自然と読み方が身についていきます。焦らず、一歩ずつ学び、より安全で効果的なリハビリ提供を目指しましょう。
もっと知識を深めたい肩は「臨床理学Lab」
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇