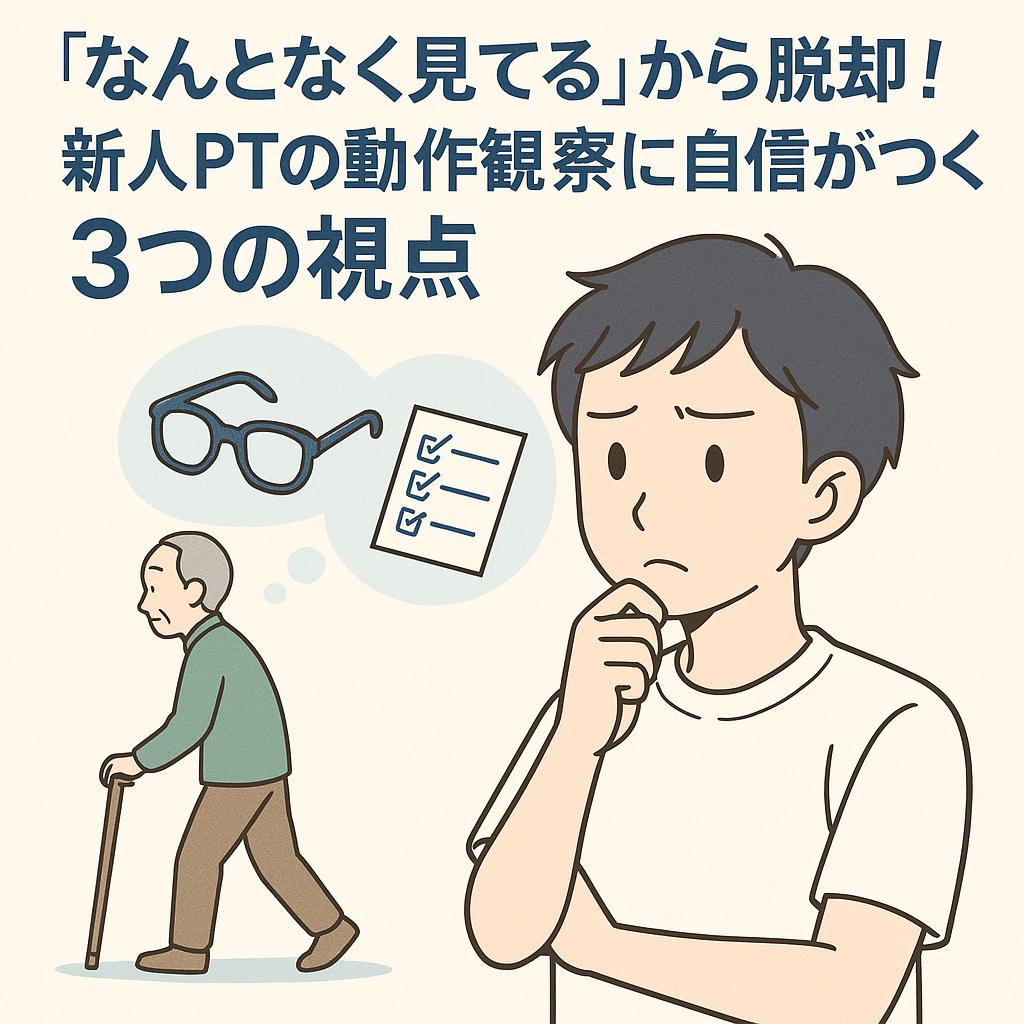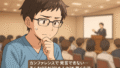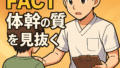はじめに|「動作観察って、何をどう見ればいいの?」
「もっとちゃんと患者さんの動きを見て」
「今の歩行、何が問題だった?」
先輩からそう言われるたび、「ちゃんと見てるつもりなんだけど…」と自信をなくしてしまう。
理学療法士(PT)にとって動作観察が重要なのは、学校や臨床実習で嫌というほど学んできました。
でも、いざ臨床の現場に立つと、「何を、どのように見ればいいのかわからない」と感じている新人・若手PTは、実はあなただけではありません。
学生時代はレポートのために“雰囲気”で乗り切れたかもしれませんが、臨床ではそうはいきませんよね。
この記事では、そんな「動作観察が苦手…」と悩むあなたに向けて、**臨床ですぐに役立つ、シンプルだけど効果的な“3つの視点”**を紹介します。
「どこを見ればいいか」が明確になり、明日からの動作観察に自信が持てるようになる一助とならば幸いです。
\臨床理学Labでは有料記事が読み放題/

なぜあなたは“動作観察が苦手”なのか?
そもそも、なぜ私たちは動作観察を難しく感じてしまうのでしょうか。その原因は、技術や知識不足だけではないかもしれません。多くの新人PTが抱える共通の原因は、主に次の3つです。
- 見るポイントが定まっていない:ただ漠然と患者さんの全身を眺めてしまい、どこに焦点を当てればいいかわからない。
- 評価項目と結びついていない:MMTやROM測定の結果と、目の前で起きている「動き」が頭の中でリンクしない。
- 動作の“意味”を考えられていない:その動きが代償なのか、痛みから逃れるためなのか、患者さんにとってどんな意味を持つのかまで深掘りできていない。
これらはすべて、**“視点の持ち方”**を知らないだけ。逆に言えば、見るべきポイントを定める“視点”を持つことで、これらの悩みは解決できます。
“見る力”を鍛える!臨床に効く3つの視点
ここからが本題です。複雑な分析は一度忘れて、まずは以下の3つの視点だけを意識してみてください。あなたの「見る力」を飛躍的に向上させるヒントが詰まっています。
視点①:「何ができているか」ではなく、「どこで代償しているか」を見る
私たちはつい、「立てた」「歩けた」という“できたかどうか”の結果に目を奪われがちです。しかし、本当に重要なのはその**“質”です。一見できているように見える動作にも、問題点を解決するためのヒント=代償動作**が必ず隠されています。
【観察例】
- 歩行:歩けているように見えても、歩行中に骨盤が過剰に左右に揺れていないか?(=トレンデレンブルグ徴候など、中殿筋の筋力低下を体幹の側屈で代償している可能性)
- 片脚立位:グラグラしながらも5秒保持できた、ではなく、保持するために体幹を傾けたり、遊脚側の股関節を大きく屈曲させたりしていないか?(=支持脚の安定性不足を、他の部位で補っている可能性)
「できた」で終わらせず、**「どうやってできたのか?」「どこを使って補っているのか?」**という視点を持つだけで、観察の解像度は一気に上がります。
視点②:静止と動きの“つなぎ目”を見る
動作の問題は、安定した動きの中よりも、**「動き出し」と「止まり際」**という“静から動へ”、“動から静へ”の移行期に現れやすい特徴があります。この“つなぎ目”に注目してみましょう。
【観察例】
- 立ち上がり:座った状態からお尻が離れる“瞬間”。お辞儀(体幹の前傾)が不十分なまま、無理やり立ち上がろうとしていないか?
- 歩き始め:静止状態から踏み出す“最初の一歩”。なかなか足が出なかったり、足踏みを繰り返したりしていないか?(=すくみ足の兆候?)
- 方向転換:歩行中に向きを変えるとき。スムーズに軸足でターンできず、細かくステップを刻んでいないか?(=バランス能力や身体イメージの問題?)
動作の開始(Initiation)と終了(Termination)は、モーターコントロールが最も要求される場面です。この“つなぎ目”を意識的に見ることで、患者さんの潜在的な問題を捉えやすくなります。
視点③:「なぜその動きなのか?」を仮説化するクセをつける
観察で捉えた現象を、ただの「現象」で終わらせないことが、臨床力を高める鍵です。観察した事実から、**「なぜ、この患者さんはこのような動きになっているのだろう?」**と常に仮説を立てる習慣をつけましょう。
これが臨床推論の第一歩です。
- その動きの原因は?
- 骨格・アライメント?(例:円背が強いから、立ち上がりで前方への重心移動が難しいのでは?)
- 筋力低下?(例:大腿四頭筋の筋力不足で、最後に膝が伸びきらないのでは?)
- 感覚障害?(例:足底の感覚が鈍く、床を探るように歩いているのでは?)
- 痛み?(例:股関節の痛みから逃れるために、患側への荷重を避けているのでは?)
- 心理的要因?(例:転倒への恐怖心から、過剰に手すりに頼っているのでは?)
この「観察→仮説→評価で検証→再考察」というループを回すことが、あなたの臨床推論能力を鍛え、リハビリの質を劇的に向上させます。
明日からできる!観察トレーニングの実践法
理屈はわかっても、すぐに実践するのは難しいもの。そこで、明日からすぐに取り組める具体的なトレーニング方法を3つ紹介します。
- 「見る前に仮説を立てる」習慣
患者さんのリハビリに入る前に、カルテ情報から「今日は〇〇の動作を見るけど、たぶん△△が原因で□□な動きになるだろう」と、たった1つでいいので仮説を立ててみましょう。答え合わせをする感覚で観察すると、見るべきポイントが明確になります。 - 「動画でスロー再生」練習
可能であれば、患者さんの許可を得てスマートフォンで動作を撮影させてもらいましょう(※施設のルールは必ず確認してください)。肉眼では追いきれない一瞬の動きも、スロー再生やコマ送りならはっきりと見えます。客観的に何度も見返すことで、新たな発見が必ずあります。 - 「他者の視点を聞く」勇気を持つ
自分の見方に自信がなくても、臆せず先輩や同僚に意見を求めてみましょう。その際は、「どう見えますか?」と丸投げするのではなく、**「私は〇〇と考え、△△という点に着目したのですが、先輩はどう思われますか?」**と、自分の考えを添えて質問するのがポイントです。カンファレンスは、自分の視点を発表する場ではなく、多様な視点を学ぶ絶好の機会です。
まとめ|“なんとなく見る”から抜け出して、臨床を楽しもう!
動作観察は、経験を積めば誰でもうまくなるわけではありません。**「何を」「どのように」見るかという“意識”**が、成長のスピードを大きく左右します。
今回ご紹介した3つの視点を、もう一度おさらいしましょう。
- 「できているか」ではなく「どこで代償しているか」を見る
- 静止と動きの“つなぎ目”を見る
- 「なぜその動きなのか?」を仮説化するクセをつける
最初はすべてを意識できなくても構いません。まずは1つでもいいので、明日の臨床で試してみてください。昨日までとは違う世界が、きっと見えてくるはずです。
“なんとなく見る”から卒業し、根拠のあるリハビリを提供できるPTを目指して、一歩ずつ進んでいきましょう!