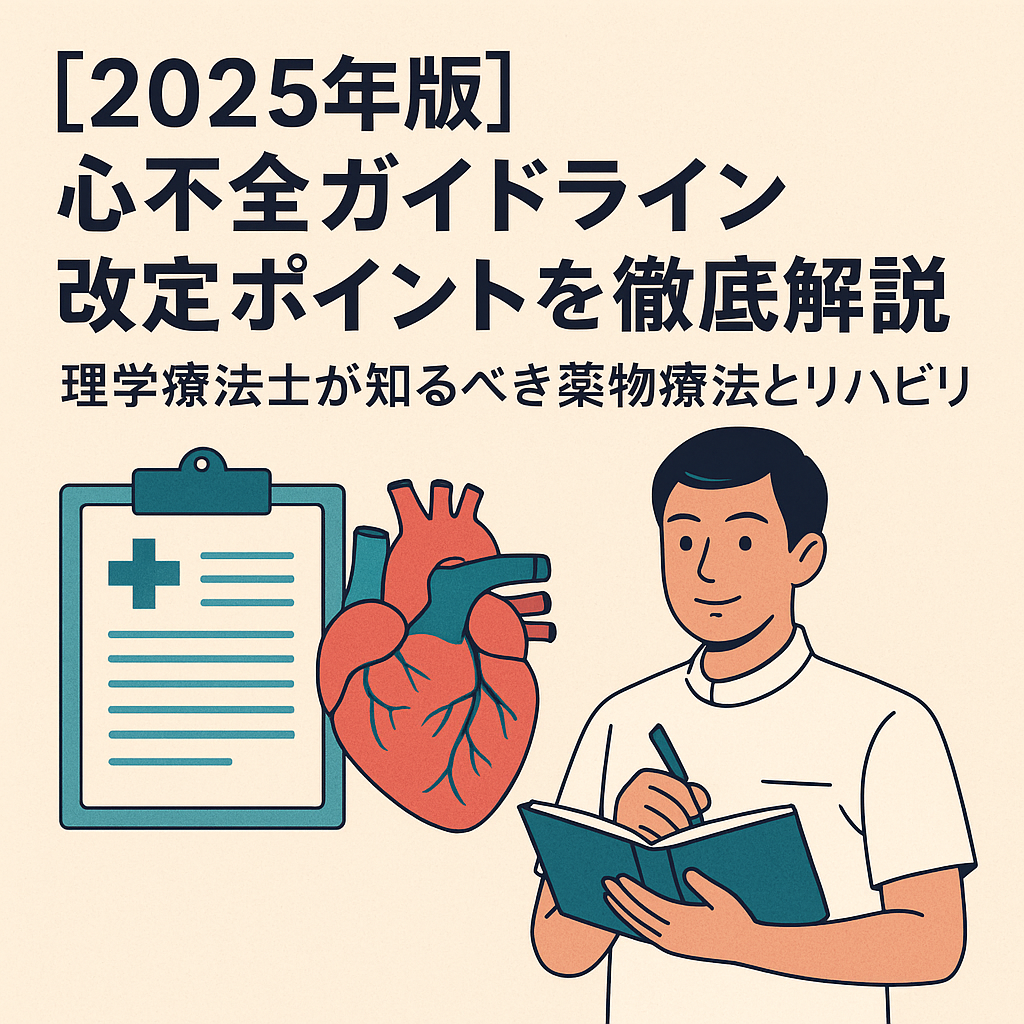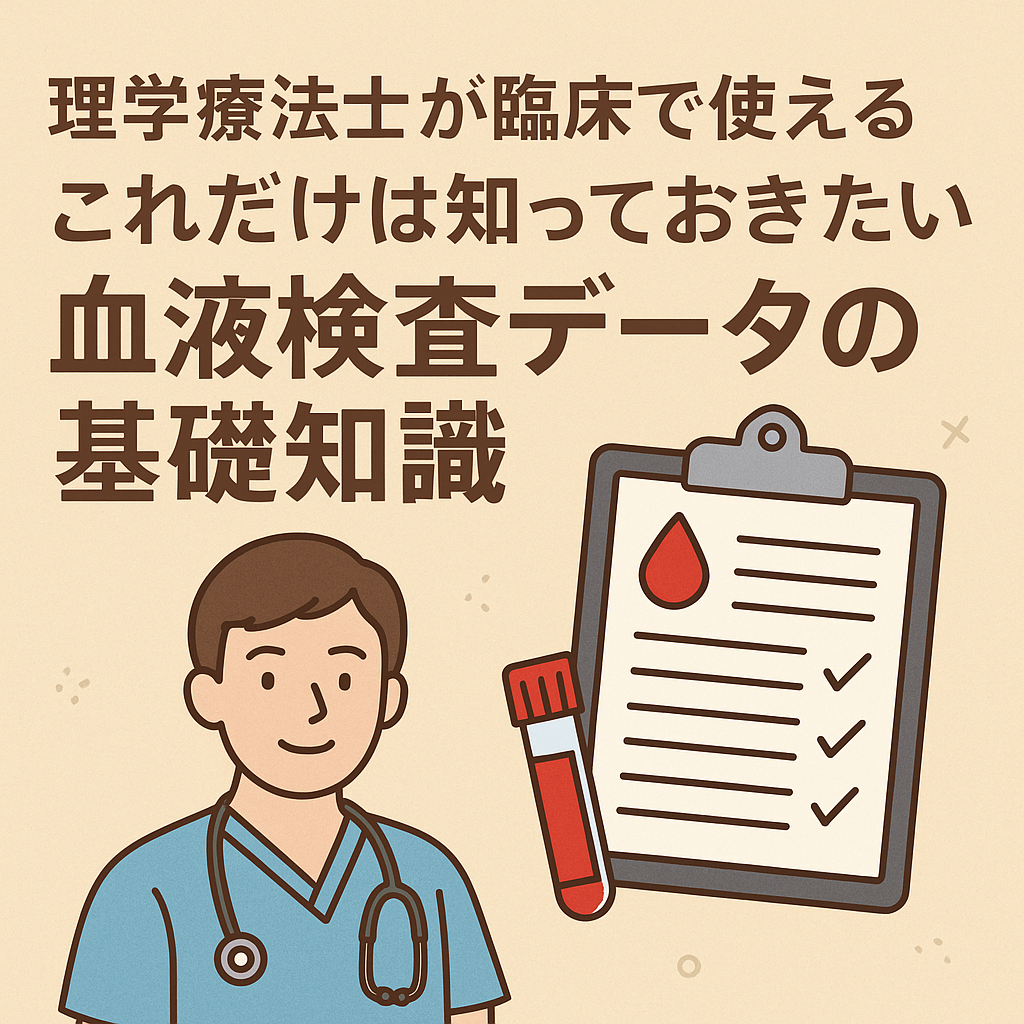2025年心不全ガイドライン改定の要点と臨床での活用ポイントを徹底解説。理学療法士が理解すべき薬物療法とリハビリの連携実践をわかりやすく紹介。
はじめに
2025年の心不全診療ガイドライン改定は、リハビリテーション業界でも今、大きな注目を集めています。心不全患者は年々増加し、高齢化社会の日本ではまさに“国民病”の一つともいえる疾患です。理学療法士はこれまで、運動療法や生活指導を中心に介入してきましたが、近年の薬物療法の進歩とともに、その役割は進化を求められています。新たな薬剤の登場は、患者の循環動態や身体状態に微細な変化をもたらし、リハビリ現場に影響を与えることが少なくありません。
本記事では、2025年版ガイドラインの改定内容をわかりやすく整理し、理学療法士として臨床現場で即実践できる視点や行動指針を具体例とともにご紹介します。ぜひ最後まで読み進め、最新知識を臨床に活かしてください。
1. 2025年心不全ガイドライン改定の全体像
今回のガイドライン改定は、これまでの標準治療を一歩進める大規模な内容です。背景には、日本国内の心不全患者数の増加だけでなく、高齢者特有の多病態・多剤併用、治療選択肢の多様化といった現場の複雑化があります。
特に改定の柱となるのは以下の4点です
包括的心不全管理プログラム(HFMP)の強化
心不全の再入院や急性増悪を減らすためには、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士など多職種が連携し、患者・家族を包括的に支えることが不可欠です。リハビリ職はこれまで以上に、生活背景や退院後の予測を見据えた介入が求められます。
運動療法の再評価
安全性・有効性の裏付けとなるエビデンスが蓄積され、軽症例から重症例まで、個別化した運動療法が強く推奨されました。とくに高齢者やフレイル患者では、筋力低下防止や身体活動量維持が生活の質(QOL)に直結します。
最新薬物療法の標準治療化
これまで一部症例に限られていた新薬が、主要治療薬として位置づけられ、臨床での使用頻度が大幅に増加します。
患者中心の意思決定の推進
エビデンスだけでなく、患者の価値観や希望を尊重した医療を提供する流れが強まりました。理学療法士は目標設定や介入の場面で、患者の声を積極的に取り入れる姿勢が大切です。
この改定をただ知識として理解するだけでなく、自施設の体制や自分の役割に照らし合わせて考えることが、理学療法士には求められています。
2. 薬物療法のアップデートと理学療法士の関わり
今回の薬物療法の目玉は、SGLT2阻害薬の適応拡大です。元々は糖尿病治療薬として登場しましたが、心不全治療薬としても心筋保護作用、利尿作用が注目され、いまや駆出率低下型(HFrEF)、中間型(HFmrEF)、保持型(HFpEF)のすべてで使用されるようになりました。
要点まとめ
- SGLT2阻害薬は糖尿病治療薬から心不全治療薬へ適応拡大し、全心不全タイプで使用されるようになった
- 臨床では脱水、低血圧、電解質異常に注意が必要
- ARNIは再入院・死亡率低下に寄与するが、血圧低下・腎機能悪化のリスクがある
- β遮断薬・MRAは心拍抑制や電解質異常の管理が重要
- 理学療法士は薬物療法の作用・副作用を理解し、多面的な評価と臨床推論を行う必要がある
臨床では、SGLT2阻害薬の影響による脱水、低血圧、電解質異常に注意が必要です。例えば、立ち上がり時のめまいや歩行中のふらつきがあれば、すぐに介入強度を調整しなければなりません。
ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)は、ACE阻害薬・ARBを超える効果が期待され、特に再入院予防や死亡率低下に寄与しますが、血圧低下・腎機能悪化のリスクもあります。リハ中は血圧・腎機能データの把握が重要です。
β遮断薬やMRAは既存治療として定着していますが、心拍抑制や電解質異常を伴うため、運動強度設定は心拍数だけでなく、呼吸数、Borg Scale、顔色・表情・訴えといった多面的評価が求められます。
ある70代男性患者では、ARNI導入後に立ち上がり時の血圧が80/50mmHgまで低下し、軽度のめまいが出現。看護師・医師に報告後、薬剤調整を経て、リハ中は段階的に座位・立位時間を延ばしつつ、症状が改善するまで負荷を抑える対応を行いました。このように、薬物療法の知識を持ち、臨床推論を行える理学療法士がいるかどうかで、リハビリの安全性と質は大きく変わります。
3. リハビリ現場での具体的連携ポイント
新薬の導入や増量は、患者にとって身体的ストレスになります。理学療法士は、医師・看護師・薬剤師との情報共有を密にし、以下の具体的連携を意識する必要があります:
- 起立性低血圧の確認
立位・歩行前後の血圧、脈拍、SpO₂を測定。フレイル高齢者では、わずかな血圧低下でも転倒リスクが上がるため注意。 - 脱水・電解質異常の管理
特にSGLT2阻害薬では、脱水による腎機能悪化、ナトリウム異常に注意。リハ中の口渇訴え、皮膚の乾燥、尿量減少を見逃さない。 - 運動強度設定の再検討
β遮断薬投与中の患者では、最大心拍数の予測が不正確になるため、RPE(主観的運動強度)、呼吸数、表情、訴えを指標とした負荷設定が必要。 - 多職種カンファレンスでの発言・報告
リハビリ中に見つけた異常所見(血圧低下、失神兆候、浮腫増悪など)を迅速にチーム内で共有し、薬物調整やリハ計画変更を提案する姿勢が求められます。
臨床では「理学療法士は運動だけを見る人」ではなく、「運動中の全身状態を評価し、最適な治療バランスを提案できる人材」であることが強く求められています。現場では、あなたの気づきが患者の安全・治療の質を左右するのです。
4. まとめと理学療法士が今後取るべき行動
心不全診療は、薬物療法と非薬物療法が連携する総合治療の時代に入りました。理学療法士は、薬物治療の基礎知識を持ち、臨床での実践力を高める必要があります。
今後の具体的アクションとして
- 定期的なガイドライン学習会・院内勉強会の開催・参加
- チームカンファレンスでの積極的な発言、薬物影響を踏まえた提案
- 患者教育(生活指導、運動療法)の際、薬物療法との関連を説明できるスキルの習得
- 個別症例での臨床推論力の強化(「なぜこの症状が出ているのか?」を常に考える習慣)
「薬は医師の仕事」という受け身の姿勢では、もはや臨床で存在感を発揮できません。ぜひ今日から一歩踏み出し、あなたの専門性を深めてください。
もっと知識を深めたい方は「臨床理学Lab」
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇