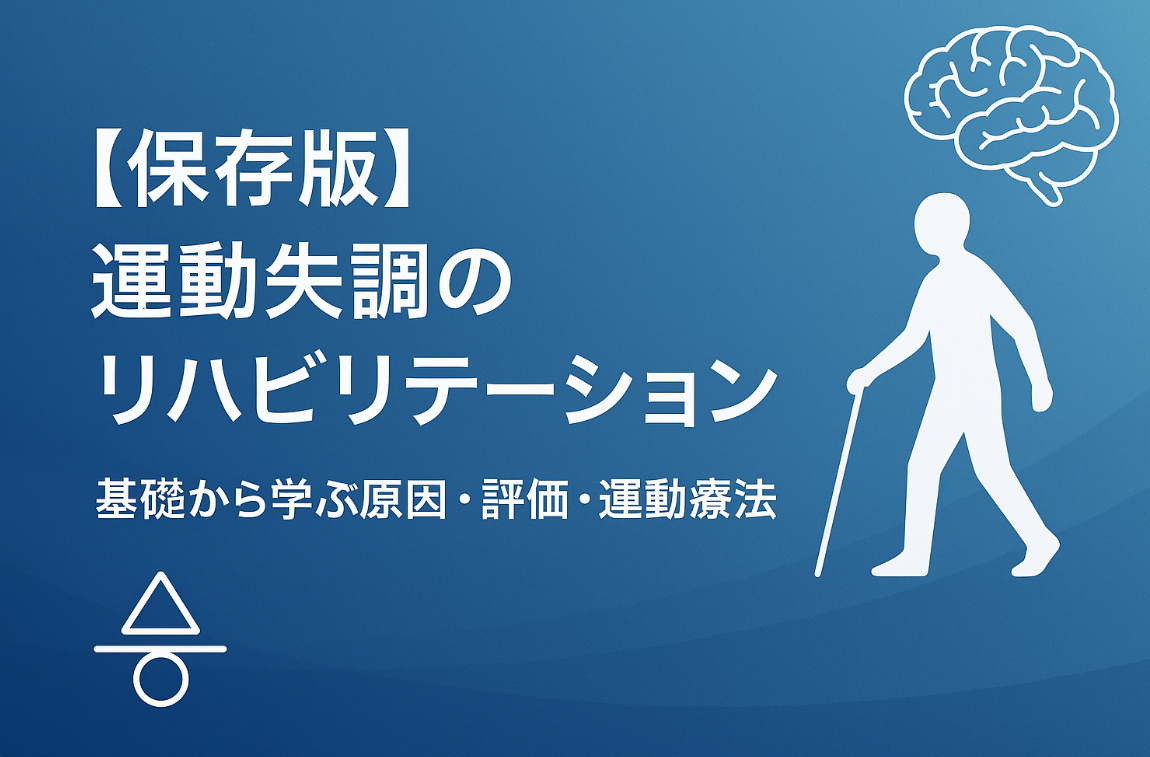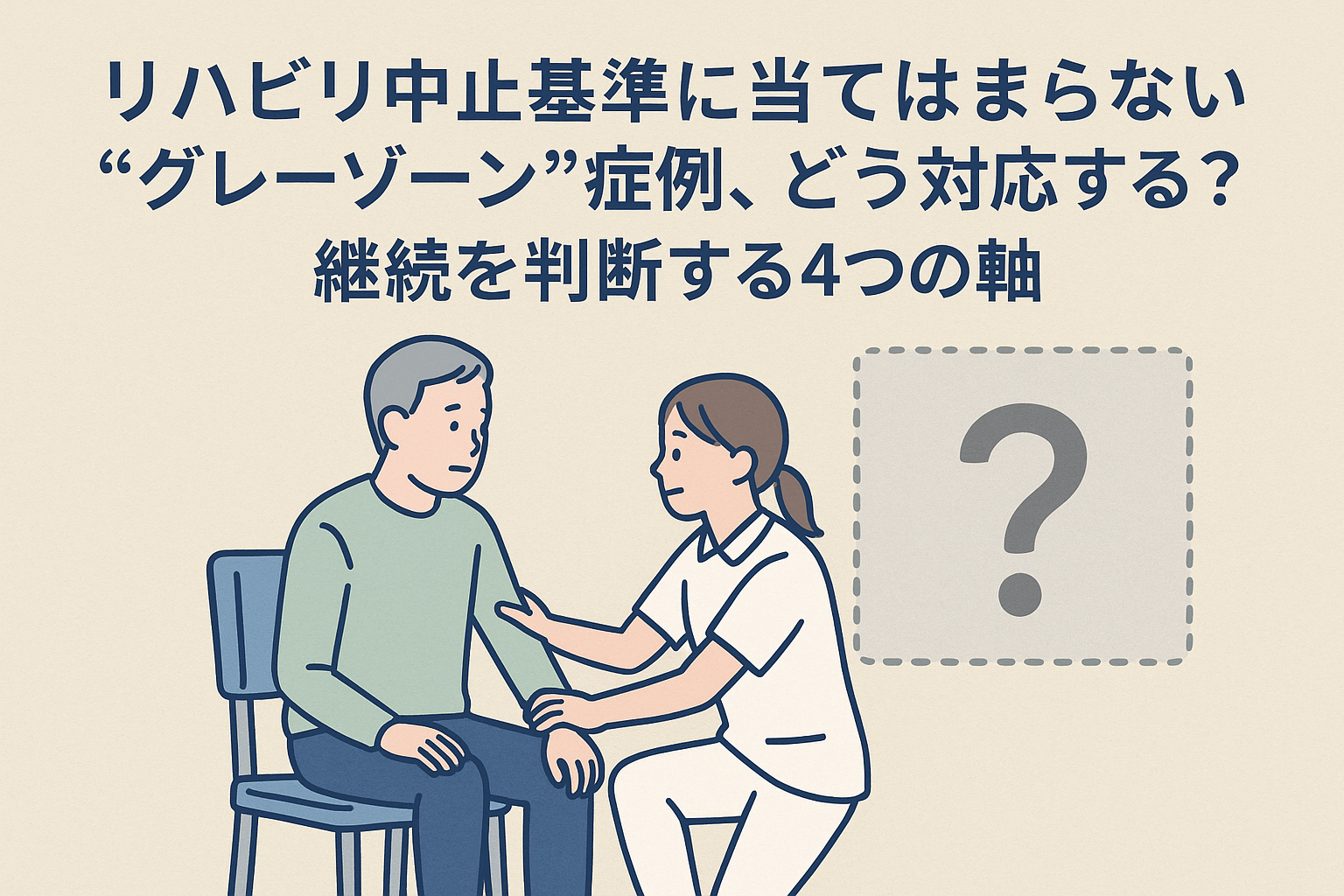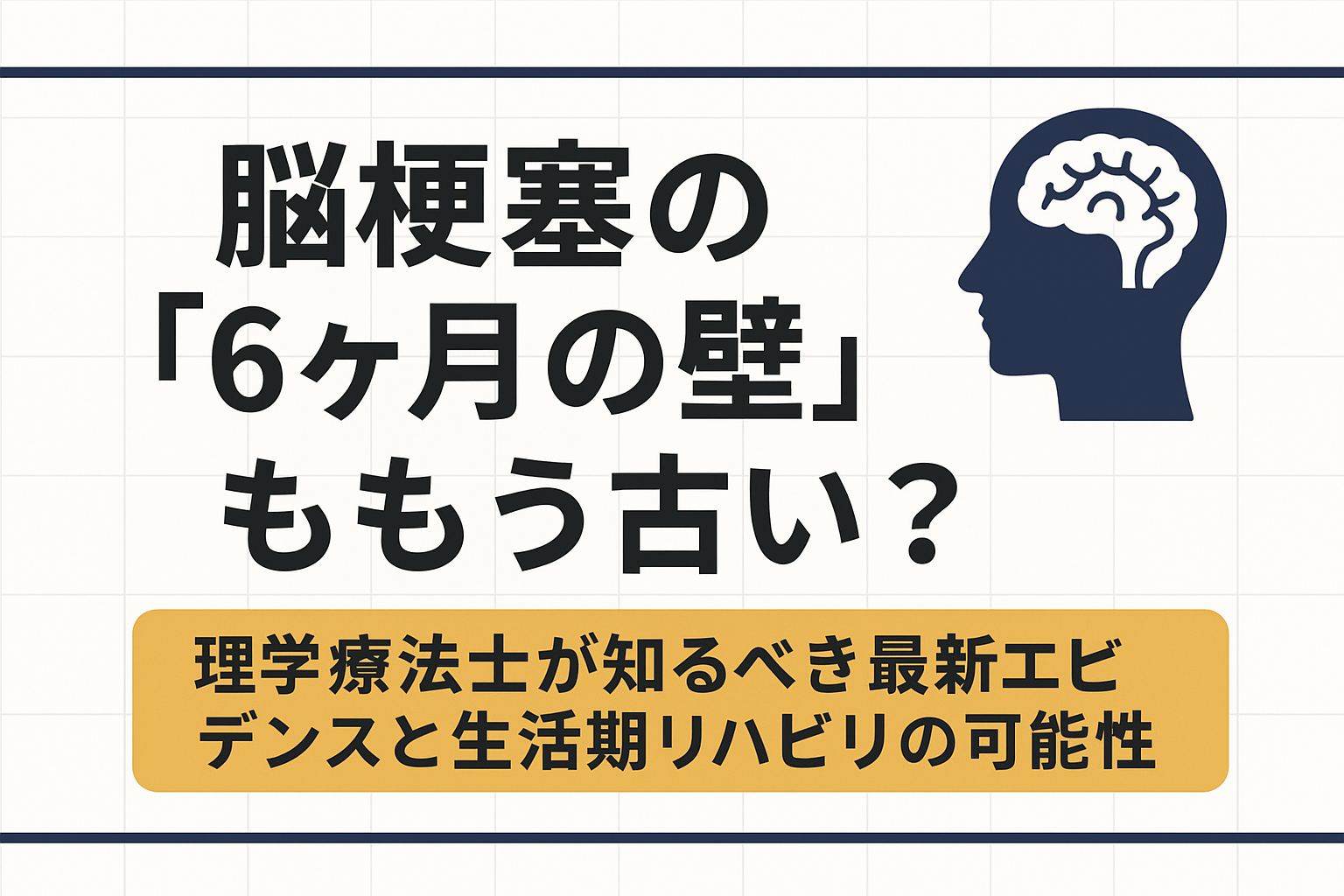はじめに
「運動失調の患者さん、麻痺とはアプローチが違うけど、どう介入すればいいんだろう…」
「動きのぎこちなさに対して、どんなリハビリが効果的なのか悩んでいる…」
運動失調のリハビリテーションは考え方が独特なため、このように悩んでしまう療法士の方は少なくありません。
そこで今回は、運動失調の基礎となる病態や原因の整理から、臨床で明日から使える評価のポイント、具体的なリハビリテーションの方法までを網羅的に解説します。
日々の臨床の一助となれば幸いです。
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事

そもそも運動失調とは?-「ぎこちなさ」の正体-
運動失調とは、「筋活動の秩序の崩壊、協調性の不全状態」と定義されます。簡単に言うと、運動をスムーズに、協調させて行うことができなくなった状態全般を指します。
この本質は「共同運動」の障害にあります。
ふ私たちが滑らかに動けるのは、主動作筋(動かす筋)、拮抗筋(反対の筋)、共同筋(補助する筋)といった多くの筋肉が、絶妙なタイミングと力加減で連携しているからです。この連携プレーが「共同運動」です。
そして、この共同運動のプログラムを作成している司令塔が「小脳」です。小脳が何らかの原因で障害されると、この運動プログラムがうまく作れなくなり、筋肉や神経がバラバラに作用してしまいます。
これがいわゆる「ぎこちない動き」の正体であり、共同運動不全と呼ばれる状態です。
【原因別】運動失調の分類と特徴
運動失調は、障害される部位によって特徴が異なり、アプローチも変わってきます。代表的な4つの分類を理解しておきましょう。
① 小脳性失調
最も代表的な運動失調です。司令塔である小脳の機能不全によって、運動のプログラムそのものが障害されます。
- メカニズム: 共同運動不全
- 代表的な症状:
- 測定異常(ジスメトリア): 物を取ろうとして行き過ぎる、または届かない。
- 変換運動障害: 手の回内・回外のような素早い反復運動ができない。
- 運動分解: 滑らかな一連の動きができず、関節を一つずつ動かすようなカクカクした動きになる。
- 企図振戦: 目標に近づくほど、手や指が震える。
- 時間測定障害: 運動の開始や停止のタイミングがずれる。
- 筋トーヌス低下: 筋の張りが低下する。
- 原因疾患: 脳梗塞・出血(特に中脳・橋・延髄)、**脊髄小脳変性症(SCD)**など。
- ※脊髄小脳変性症は進行性の疾患であるため、症状の変化に合わせてリハビリプログラムを柔軟に変更していく視点が重要です。
② 脊髄性失調(感覚性失調)
身体の位置や動きを感じ取る「固有覚」の通り道である脊髄後索が障害されることで生じます。運動プログラムは正常ですが、身体がどう動いているかのフィードバック情報が脳に届かないため、動きのコントロールが困難になります。
- メカニズム: 固有覚の障害によるフィードバック制御の破綻
- 鑑別のポイント:
- 視覚による代償が可能: 目で動きを確認している間は、ある程度スムーズに動ける。
- ロンベルグ徴候が陽性: 目を閉じると立っていられなくなる。
- 原因疾患: 脊髄癆(せきずいろう)、脊髄圧迫性病変など。
③ 前庭迷路性失調
平衡感覚を司る内耳の前庭や三半規管が障害されることで生じます。
- メカニズム: 平衡感覚の障害
- 症状の特徴: 手足の細かい動きの失調ではなく、**起立や歩行時のふらつき(バランス障害)**が主体。
- 鑑別のポイント: 星型歩行(Babinski-weil徴候)…目を閉じて足踏みをすると、だんだんと同じ方向に回転してしまう。
- 原因疾患: メニエール病、前庭神経炎など。
④ 大脳性失調
前頭葉や頭頂葉など、大脳の障害によっても小脳性とよく似た運動失調を呈することがあります。
臨床で何を見るか?運動失調の評価のポイント
運動失調の評価では、「共同運動障害がどの程度、どのような形で現れているか」を多角的に捉えることが重要です。
| 評価項目 | 具体的な評価方法・観察ポイント |
| 体幹・バランス | ・座位/立位保持の安定性、体幹の動揺の有無・ロンベルグ徴候(閉眼での立位保持)・ファンクショナルリーチテスト |
| 四肢の協調性 | ・指鼻指試験 / 踵膝試験(測定異常、企図振戦)・手回内・回外テスト(変換運動障害)・跳ね返り現象(リバウンド現象) |
| 歩行 | ・失調性歩行の観察(酩酊様、歩隔の拡大、体幹の動揺)・継ぎ足歩行(タンデム歩行) |
| その他 | ・筋緊張(トーヌス)の評価・書字障害・言語障害(爆発性、断綴性言語) |
これらの評価を通して、患者さんの日常生活における困難さ(ADL)と結びつけ、リハビリテーションの目標を設定します。
考え方が鍵!運動失調のリハビリテーション戦略
小脳性失調では、運動を予測しプログラムする機能(フィードフォワード制御)が障害されています。そのため、リハビリテーションの基本戦略は、視覚や固有覚などの感覚情報(フィードバック)を最大限に活用し、運動を再学習させることです。
① フランケル体操 – 視覚で動きをコントロールする
19世紀末に考案された古典的な運動療法ですが、今なお非常に有効です。
- 目的: 視覚による代償を積極的に利用し、正確な運動制御を促通する。
- 方法:
- 背臥位や座位で、目標物(印や療法士の指)を目で追いながら、手や足を正確に動かす。
- 単関節の単純な運動から始め、徐々に複合的な共同運動へ移行する。
- 慣れてきたら立位や歩行練習(床の目印に沿って歩くなど)へ発展させる。
- 成功の3つのポイント:
- 注意を集中させる: 漫然と行わず、一つ一つの動きに集中する。
- 正確性を重視する: スピードよりも、正確に目標を捉えることを優先する。
- 反復する: 正しい運動パターンを繰り返し、脳に再学習させる。
② 重り負荷・弾性緊縛帯 – 身体に動きを“感じ”させる
手足の末梢や近位部に負荷を加えるアプローチです。
- 目的: 重りや圧迫によって固有感覚の入力を増強させ、脳が手足の位置や動きを認識しやすくする。また、過剰な動揺を重さで抑える効果も期待できます。
- 方法:
- 重り: 手首や足首に重錘バンドを装着する(上肢: 250g〜500g、下肢: 500g〜1,000gが目安)。
- 弾性緊縛帯: 上腕や大腿の付け根を弾性包帯で適度に圧迫する。
③ プレーシング – まずは“止まる”練習から
プレーシングとは、手足を空中で一定の位置に保持させることです。
- 目的: 動き出す前の「静的な筋の協調性(同時収縮)」を学習させる。円滑に動くためには、まず意図した位置でピタッと「止まる」能力が不可欠です。
- 方法: 療法士が患者さんの手足を特定の場所に誘導し、「はい、ここで止めてください」と指示し、患者さん自身にその位置を保持してもらう。
安全管理は最優先!転倒リスクへの対策
運動失調の患者さんは、予測不能なふらつきや動揺により、転倒リスクが非常に高いです。リハビリテーションを行う際は、安全管理を徹底しましょう。
- 座位・立位訓練では常に転倒に備え、介助できる位置につく。
- 必要に応じてハーネスや平行棒を使用する。
- 訓練スペースは広く確保し、周囲の危険物を片付けておく。
- 日常生活においても、手すりの設置や段差の解消といった環境調整を積極的に提案する。
まとめ
運動失調のリハビリテーションは、一朝一夕で改善するものではなく、根気強いアプローチが求められます。しかし、その病態を正しく理解することで、介入の糸口は必ず見つかります。
- 運動失調の本質は、小脳を中心とした「共同運動プログラム」の障害。
- 原因によって症状の特性が異なるため、評価による鑑別が重要。
- リハビリの鍵は「フィードバックの活用」。視覚や固有覚で動きを補い、再学習を促す。
- 常に転倒リスクを念頭に置き、安全管理を徹底する。
この記事が、運動失調の患者さんに関わる療法士の皆さんの、明日からの臨床のヒントになれば幸いです。