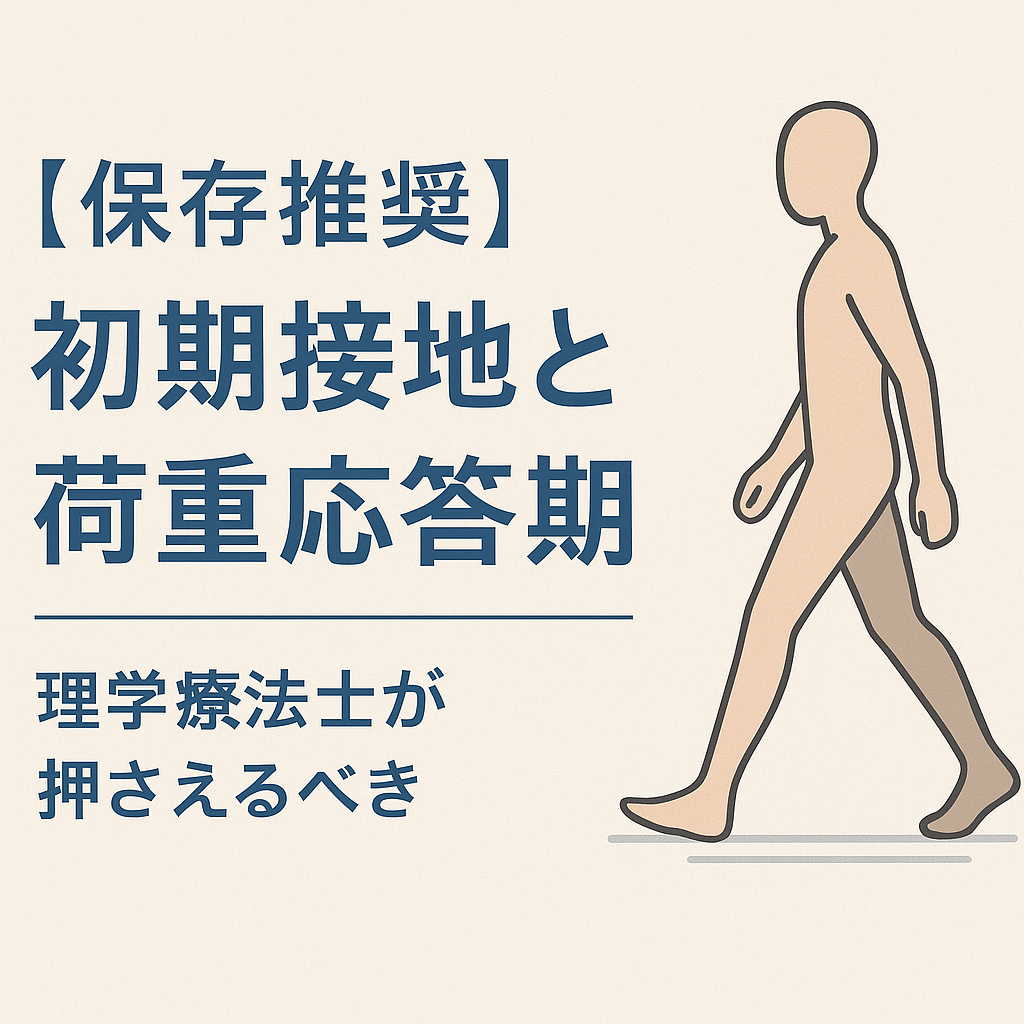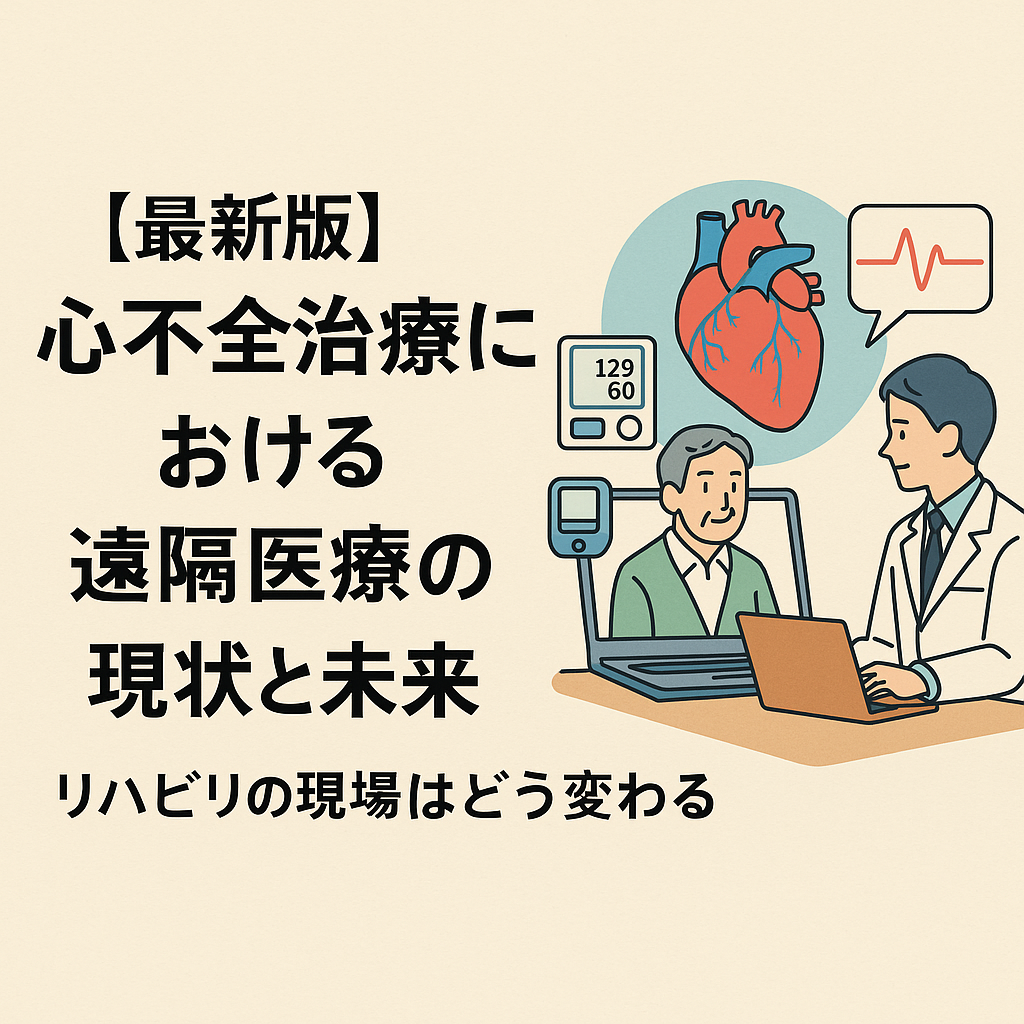はじめに
歩行観察や分析は、理学療法士にとって日常的かつ不可欠な臨床スキルの一つです。歩行周期の中でも重要なもののひとつが「初期接地」と「荷重応答期」。これらのフェーズは、患者さんの歩行の安定性と効率性を左右する要の場面であり、正確な評価と適切な治療介入が求められます。
この記事では、歩行周期において重要な「初期接地」と「荷重応答期」について、理学療法士向けに詳しく解説しています。
股関節・膝関節・足関節それぞれの具体的な角度や筋活動、衝撃吸収メカニズムなど、歩行分析の精度を高めるための臨床ポイントをまとめています。
新人理学療法士の方はもちろん、日々の臨床で歩行分析をさらに深めたい方にも役立つ内容です。

【この記事はこんな方におすすめ】
• 新人理学療法士で歩行分析の基礎をしっかり学びたい方
• 学生で国家試験や実習対策として歩行周期を復習したい方
• 臨床経験を積んでいて改めて歩行分析を深めたい方
• 歩行周期における関節角度や筋活動の理解を強化したい方
• 歩行障害を持つ患者さんのリハビリ評価・治療を精度アップさせたい方
これ一記事で、歩行周期の初動に関する知識を深め、臨床力アップにつなげられる内容になっていると思います。
⸻
歩行周期における「初期接地」 ― 歩行の第一歩を支える仕組み
初期接地(Initial Contact:0~2% GC)は、歩行周期の最初の局面で、踵(ヒール)が地面に接触する瞬間です。
一見単純な動作に見えますが、このタイミングは次のフェーズである荷重応答期への準備段階であり、身体全体のバランス調整と衝撃吸収の開始点として極めて重要な時期となります。
◆ 関節の具体的な位置と角度
• 股関節:約20°屈曲位で、骨盤は10°前傾・5°前方回旋しています。この屈曲と骨盤のポジションが、重心を前方に引き出し、安定した接地をサポートします。
• 膝関節:5°程度の軽度屈曲位。見た目には伸展しているように見えるものの、わずかな屈曲が関節内での衝撃吸収の準備を整えています。
• 足関節:中間位(0°)を保持しており、脛骨前筋が足部のコントロールを担います。
•距骨下関節:軽度回外~中間位。この「ロック機構」が足部の安定性を高め、踵のぶれを防ぎます。
◆ 筋活動と臨床的なポイント
足関節では、前脛骨筋が最も重要な働きを果たす。
踵接地の瞬間に底屈モーメントが発生するため、前脛骨筋は遠心性収縮でそれを制御します。ここが機能不全だと、フットスラップ(足がパタンと落ちる現象)が起きやすく、転倒リスクが高まります。
股関節・膝関節では、特に大殿筋や大腿四頭筋が安定性確保のための基盤を作り出します。
このフェーズでの問題は、歩行全体に波及すると言えます。
たとえば脳卒中患者のように足関節背屈がうまくできない場合は、足尖接地(つま先が先につく)→フットスラップ→膝折れ、といった連鎖的な不安定性が生じやすくなります。
こんな記事もあります!
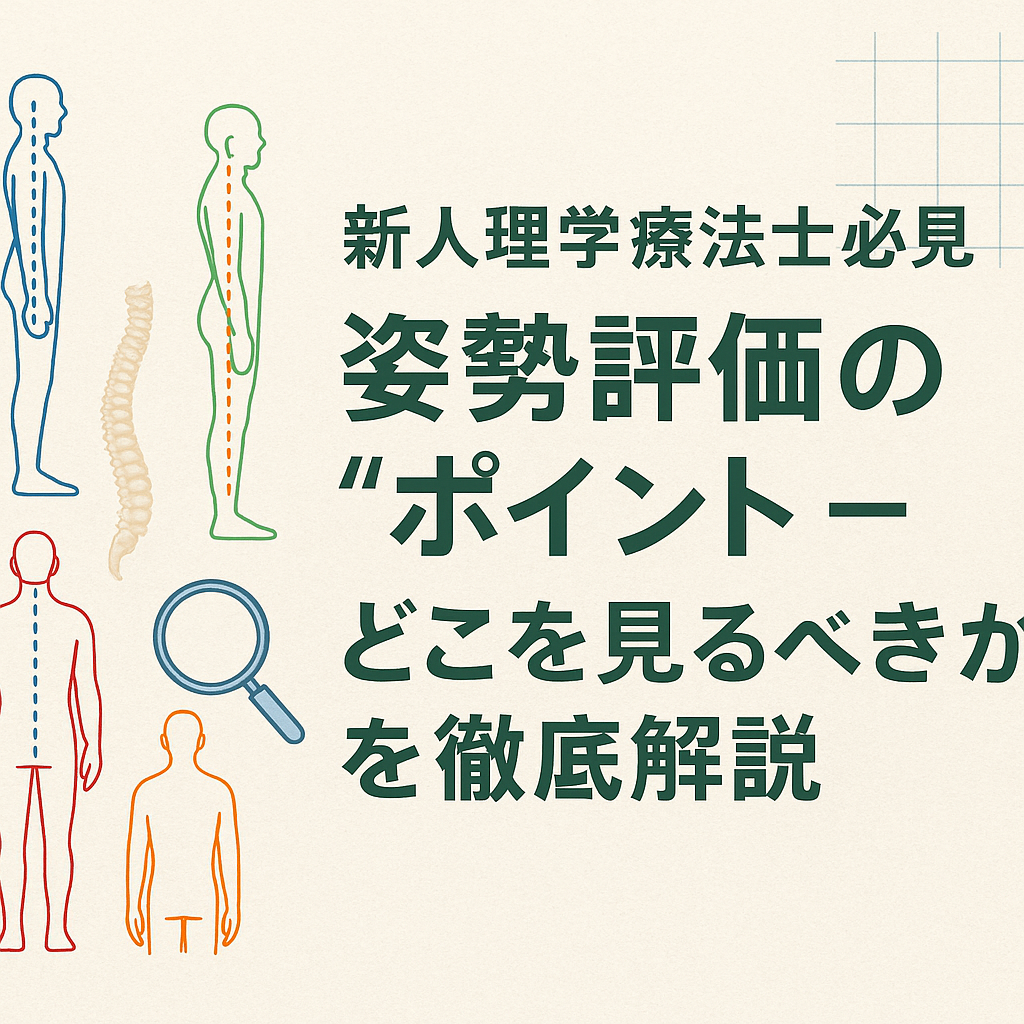
⸻
荷重応答期 ― 衝撃吸収と支持の両立を担うフェーズ
荷重応答期(Loading Response:2~12% GC)は、初期接地後に体重を片脚で支えるフェーズです。
この期間は歩行周期の中でもっとも不安定であり、かつ地面からの衝撃を効率的に吸収しなければなりません。
◆ 関節の具体的な位置と角度
• 股関節:依然として20°屈曲位を保持し、骨盤も10°前傾・5°前方回旋を維持します。股関節の安定は、体幹の過度な前傾や崩れを防ぐために不可欠です。
• 膝関節:初期接地時の5°屈曲からさらに屈曲が進行し、最大約20°まで屈曲。これにより、膝関節が衝撃を吸収する「ショックアブソーバー」の役割を果たします。
• 足関節:中間位からおよそ5°の底屈位へと移行し、足部が地面に安定して接地します。
• 距骨下関節:回内方向へと移行し、足の内側縦アーチが適度にたわむことで衝撃を吸収します。
◆ 筋活動と臨床的なポイント
• 膝関節では、大腿四頭筋が遠心性収縮で膝の屈曲を制御(最大24% MMT)。この働きが弱いと膝折れ現象が起きやすくなり、患者さんのバランスが一気に崩れます。
• 股関節は、大殿筋と半膜様筋が屈曲モーメントに抵抗(大殿筋12% MMT、半膜様筋27% MMT)。これが体幹の支持を支えます。
• 足関節では、前脛骨筋が引き続き活躍します。踵接地から続く底屈モーメントを遠心性に制御します。
◆ ヒールトランジットと衝撃吸収
この時期、地面からの反力による「ヒールトランジット(衝撃)」が垂直方向に発生し、体重の12~15%程度の衝撃が一瞬で下肢全体を通過します。この衝撃を適切に処理できないと、膝関節や股関節、さらに腰椎へと負担が蓄積し、慢性的な障害につながりやすいことが報告されています。
⸻
臨床応用:歩行分析の評価と治療戦略
歩行分析において「初期接地」と「荷重応答期」は、転倒リスクや歩行効率を評価する際の要点となります。
以下のポイントを押さえて臨床で活かしましょう
- 踵接地が正確に行えているか
- 膝関節の屈曲がスムーズでショックアブソーバー的な機能が働いているか
- 股関節周囲筋の筋活動で体幹が安定しているか
- 距骨下関節の回内・回外が適正で、足部アーチがしっかりと機能しているか
評価は「静的な関節角度の確認」だけでなく、「動的な観察」が重要です。たとえば、患者さんが恐怖感や不安を示している場合、それが無意識に動作に影響を及ぼしていることもあります。
⸻
まとめ ― 理学療法士に求められる歩行観察・分析力
歩行の「初動」である初期接地と荷重応答期は、歩行全体の安定性を左右する重要なフェーズです。
歩行の初動は、歩行全体の安定性と効率性を決定づける重要な局面です。初期接地ではまず「踵接地の正確性」がカギとなり、その後の荷重応答期では、全身の関節が連動して衝撃を吸収しながらバランスを維持します。
理学療法士としては、解剖学的・運動学的な視点からこれらの動作を正確に評価し、問題点を抽出していくスキルが不可欠です。この動きのメカニズムを正しく理解し、患者ごとの歩行パターンを的確に評価・指導していくことが重要となります。
本記事で紹介したような股関節・膝関節・足関節の関節角度や筋活動の理解を深め、歩行分析の実践に役立ててください。
より専門性を高めたい方は、メンバーシップをご確認ください!