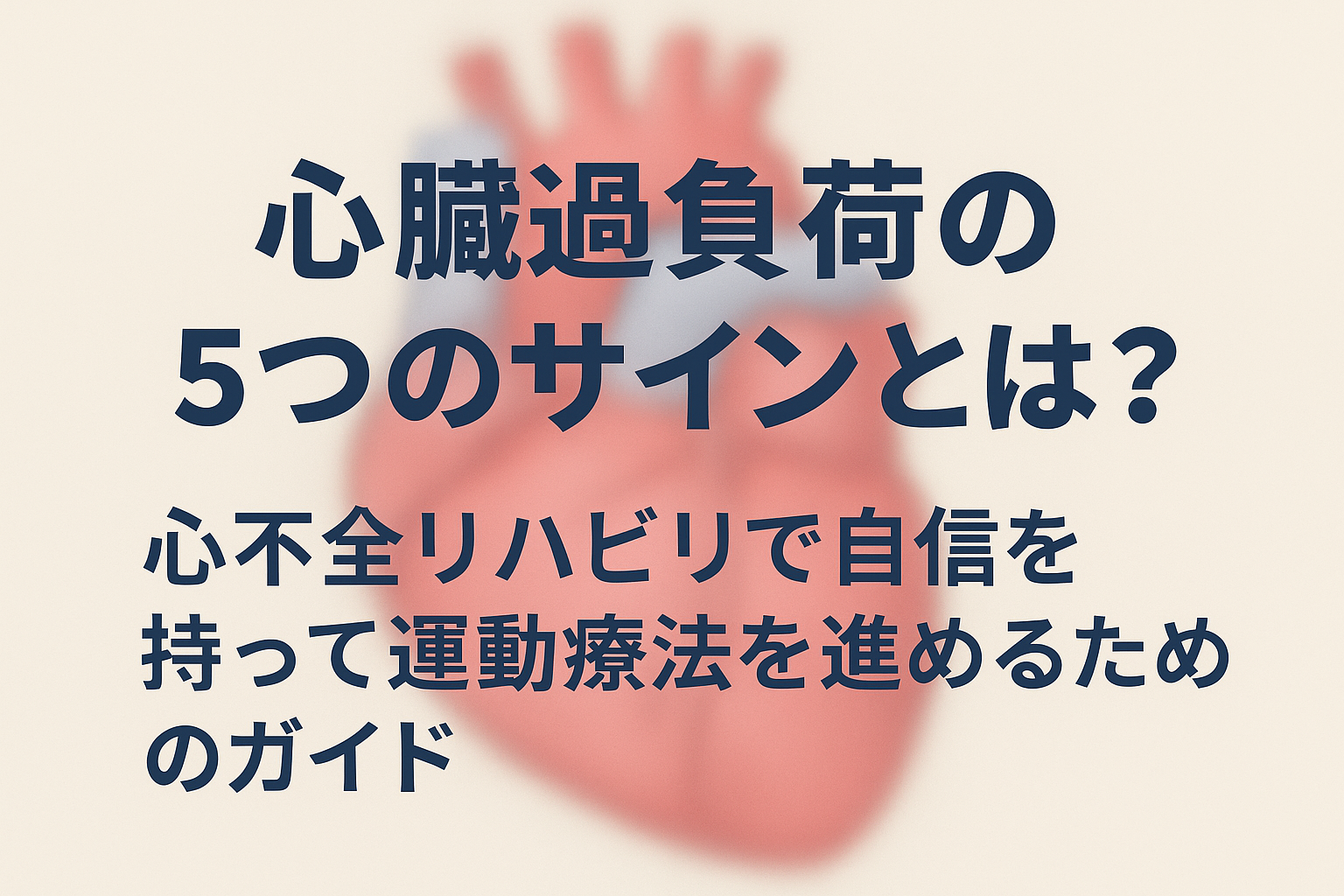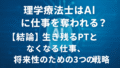はじめに:「この突っ張り感、何だろう?」臨床の“なぜ?”に答える新視点
理学療法士として臨床に立つ中で、こんな場面に出会ったことはありませんか?

関節可動域(ROM)制限の患者さん。筋をしっかりストレッチして、関節モビライゼーションも行った。確かに関節は柔らかくなったはずなのに、なぜか動きの最終域で“突っ張る感じ”が取れない…
筋や関節包といった“深部組織”にアプローチしても改善しきらない、もどかしい感覚。
多くのセラピストが経験するこの壁の原因は、もしかしたら私たちが見過ごしがちな**「皮膚」**にあるのかもしれません。
この記事では、関節可動域制限の新たな原因として「皮膚」に着目し、あなたの臨床推論を一段と深めるための視点について考えていきます。
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事

なぜ「皮膚」が可動域制限の原因になるのか?
「皮膚って、ただ身体を覆っている膜でしょ?」
そう思われがちですが、実は皮膚は身体の動きに合わせて滑走し、張力を調整する“動的な臓器”です。
皮膚が硬くなったり、下にある組織と癒着したりすると、その“滑り”が失われます。
すると、その下にある筋や関節が動こうとしても、皮膚がブレーキをかけてしまい、結果として可動域が制限されてしまうのです。
- 手術後の創部や瘢痕(はんこん)
- 火傷(やけど)による皮膚のひきつれ
- 慢性的な浮腫(むくみ)
- 加齢による皮膚の弾力低下
これらはすべて、皮膚の滑走不全を引き起こし、関節の動きを妨げる原因となります。
近年の研究でも、皮膚の伸展性が低下すると、関節を動かすために必要な力が増大し、運動効率が下がることが報告されています(Tiong et al., 2021)。
つまり、皮膚の柔軟性は“関節がスムーズに動くための大前提ということになります。
いくら深層の筋や関節にアプローチしても、表層の皮膚が動かなければ、根本的な改善には至りません。
あなたの臨床にもヒントが?皮膚由来の制限を疑うサイン
では、どのような場合に皮膚由来の制限を疑うべきなのでしょうか?
評価のポイントは、「どの“層”が動いていないか?」という視点を持つことです。
皮膚 → 皮下組織 → 筋膜 → 筋 → 関節包
この層構造を意識しながら、患者さんの身体に触れてみてください。
もし、以下のような所見があれば、皮膚が原因である可能性が高いです。
- ✅ 動きの最終域で、浅い層に「張り」や「突っ張り感」がある。
- ✅ 皮膚をつまんでみると、明らかに硬かったり、左右差があったりする。
- ✅ 筋をストレッチしても変化は乏しいが、皮膚を少しずらすだけで動きが楽になる。
- ✅ 制限がある場所に、過去の手術創やケガの痕、浮腫が存在する。
特に「筋は緩んでいるのに、何か引っかかる感じがする」という患者さんの訴えは、皮膚由来の制限を示唆する重要なサインです。
【一部公開】明日から使える!皮膚の評価方法とは?
「じゃあ、具体的にどうやって評価すればいいの?」
そう思われた方のために、有料noteで解説している評価方法の一部を少しだけご紹介します。
大切なのは、指先の感覚を研ぎ澄ませて「皮膚の滑り(滑走性)」を感じ取ることです。
🔹(1)皮膚スライドテスト
母指と示指で皮膚を軽くつまみ、上下・左右・斜めなど、様々な方向に滑らせてみます。
正常であればスムーズに動きますが、制限がある場合は特定の方向で「動かない」「硬い」といった抵抗を感じます。
🔹(2)皮膚ピックアップテスト
皮膚を軽くつまみ上げ、その高さを周囲と比較します。つまみ上げにくい場合、皮膚と下層組織が癒着している可能性が考えられます。
「もっと詳しく知りたい!」と思ったあなたへ
ここまで読んで、「なるほど、皮膚か!」「自分の担当患者さんも、もしかしたら…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
今回ご紹介したのは、皮膚アプローチのほんの入り口に過ぎません。
理学療法士・作業療法士向けのメンバーシップ『臨床理学Lab』で公開している有料note記事では、さらに踏み込んだ内容を解説しています。
▼この記事の続き(有料)では、こんなことが学べます▼
- 📌 【評価編】皮膚スライド/ピックアップテストの具体的な手技と観察ポイント
- 📌 【鑑別編】「筋・関節・皮膚」それぞれの制限を見分ける臨床的なコツ
- 📌 【実践編】スキンロール、クロスフリクションなど、皮膚の可動性を改善する3つの主要テクニック
- 📌 【根拠編】IASTMや温熱療法など、論文ベースで解説するアプローチの科学的背景
- 📌 【症例編】肘、体幹、股関節など、部位別の実践的なアプローチ例
「筋は柔らかいのに、突っ張る」
その“最後のひと押し”で悩んでいるなら、必ずあなたの臨床の武器になります。
メンバーシップにご登録いただくと、この記事を含む全ての限定コンテンツが読み放題になります。
単発でのご購入も可能です。
あなたの臨床を、もう一歩先へ進めてみませんか?
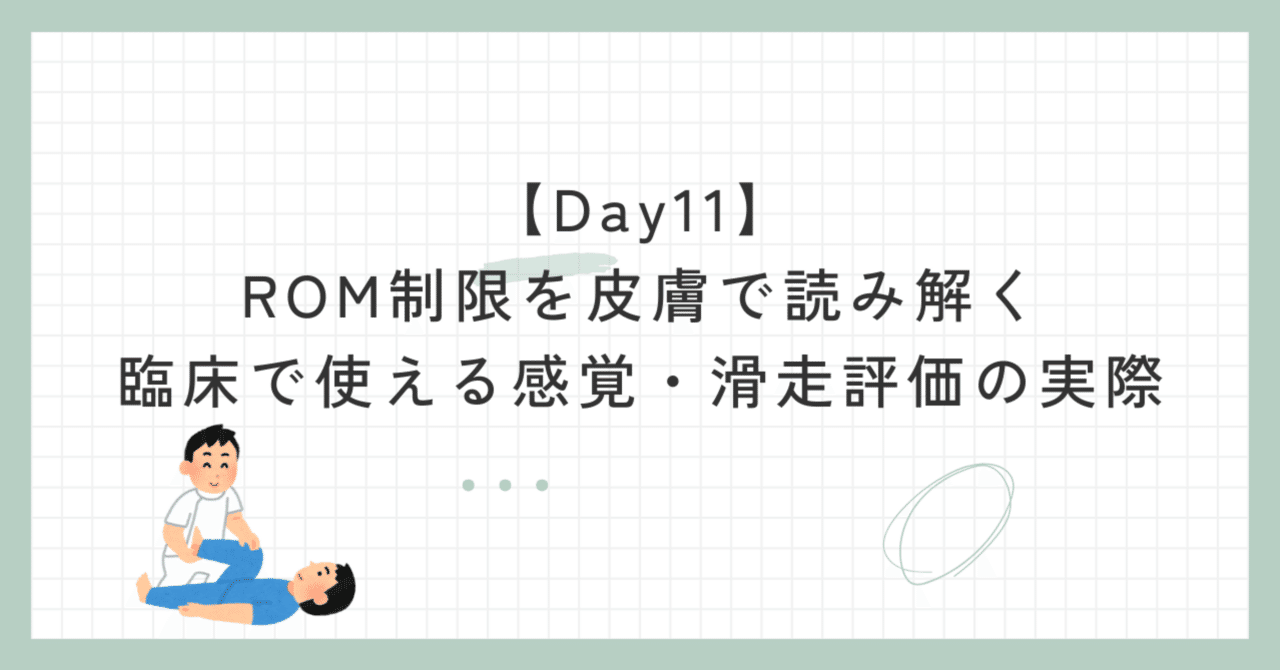

まとめ: “皮膚を見る”という新たな武器を手に入れよう
関節可動域制限の原因を「筋・関節」だけに限定せず、「皮膚」という層で捉える視点。
これを持つだけで、アプローチの選択肢は一気に広がります。
これまで「なぜか改善しない…」と悩んでいたケースの突破口が、きっと見つかるはずです。
明日からの臨床で、ぜひ患者さんの皮膚に触れ、その動きを感じてみてください。
そこには、動きを改善するための大きなヒントが隠されています。