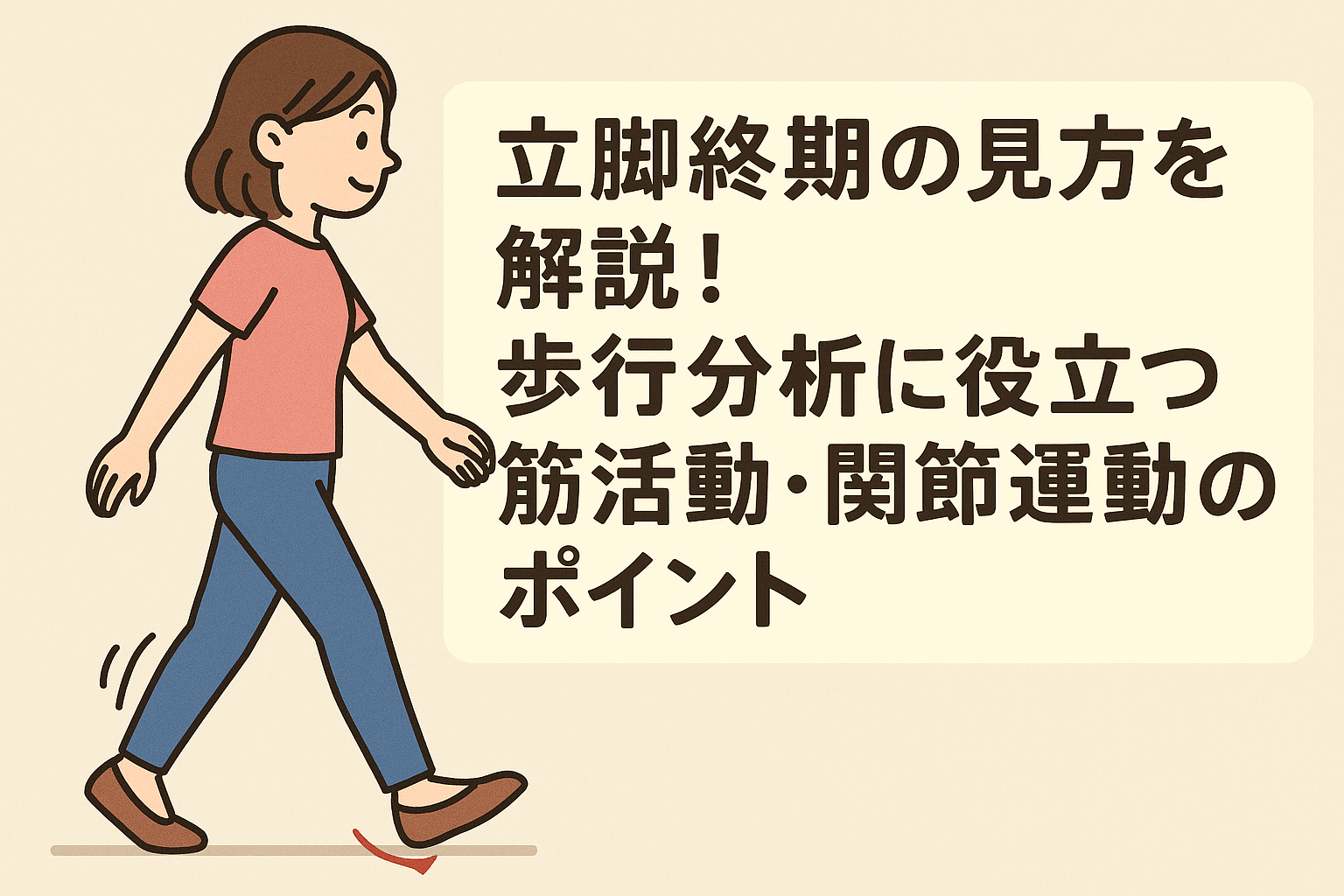はじめに
歩行動作において「立脚終期(Terminal Stance)」は、単なる「踵が離れる瞬間」ではありません。実はこの時期こそ、前方への推進力を最大限に生み出し、次の遊脚期へ移行するための重要な役割を担っています。
特に理学療法士にとっては、筋活動・関節可動域・モーメントの制御・重心移動など、多くの要素を評価・分析する上での鍵となる時期です。

この記事では、立脚終期の運動学的特徴から、臨床での見極めポイントなどを解説してみます。
\より専門的な勉強をしたい方はこちら!/

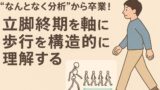
立脚終期とは? ― 歩行周期の中での位置づけ
立脚終期は歩行周期の中で「31%〜50% GC(Gait Cycle)」に相当するフェーズです。具体的には、踵が地面を離れてから、反対側の足が床に接地するまでの時間を指します。この間、支持脚は前方推進の主役を担い、体幹と骨盤を前へと移動させます。
役割の要点
- 前方への加速を生み出す:体重心の前方移動を支えながら、筋と関節が協調してエネルギーを伝達。
- 次相(前遊脚期)への準備:足関節・膝・股関節が順に姿勢を変え、振り出しやすいポジションへと遷移。
- 安定性と動的バランスの両立:一側の下肢支持で身体を保持しながら、次の動作へと移る精密なタイミング制御が必要。
このフェーズでは、単に筋力があるだけでなく、「タイミング」「協調性」「運動連鎖」がしっかりしていないと、歩行効率が落ちたり、代償動作を誘発してしまいます。
解剖学・関節運動から見る立脚終期
各関節の典型的な運動範囲(正常歩行)
- 股関節:10°〜20°の伸展、さらに5°程度の骨盤後方回旋を伴う。骨盤との協調的な動きにより、体幹の推進運動を助ける。
- 膝関節:屈曲5°程度(外見上はほぼ完全伸展に見える)。膝関節が安定することで体幹の前方移動がスムーズになる。
- 足関節:10°の背屈。距骨が脛骨の下で安定することで、前足部への荷重移動が円滑に進行。
- 距骨下関節:立脚中期の内反(回外)から、立脚終期にはやや外反方向へ戻り、適度な剛性と柔軟性を保持。
このように各関節が適切に連動することで、フォアフットロッカー(前足部支点)が形成され、効率的な前方推進が可能になります。
筋活動:主役はヒラメ筋と腓腹筋
立脚終期で最も活発に活動する筋群が「ヒラメ筋・腓腹筋」です。特にヒラメ筋は、重心が前方へ移動する際に足関節背屈モーメントに抵抗し、底屈モーメントを発生させる役割を担います。
ヒラメ筋の働き
- 等尺性収縮により足関節の安定性を維持
- 後足部を支点として前足部へ荷重移行を誘導
- 骨盤の前方移動に合わせて、遠心的にコントロール
一方で、腓腹筋は膝関節との二関節筋であり、膝関節伸展の保持にもわずかに寄与します。これらの筋群が協調して働くことで、踵離地からつま先離地にかけて、スムーズかつ力強い前進力が得られるのです。
観察ポイント:臨床で見逃したくない兆候とは?
立脚終期では、以下のようなポイントを観察・評価しましょう。
1. 踵の離地タイミング
早すぎても遅すぎても、推進力が効率的に得られません。腓腹筋・ヒラメ筋の収縮タイミングとの関連に注目。
2. フォアフットロッカーの形成
踵が離れてから前足部で重心を支える過程がスムーズかどうか。中足部・足趾の可動域も評価対象になります。
3. 体幹の前方移動と骨盤回旋
体幹が十分に前方へ移動しているか、また骨盤の水平回旋が左右で差がないかを観察。片麻痺などでは代償的な側屈が見られることがあります。
4. 下肢筋力と筋活動のパターン
特に下腿三頭筋の筋力低下があると、足関節が不安定になり、早期に踵が浮いてしまうことがあります。
臨床応用:歩行改善へのアプローチ例
理学療法での介入では、立脚終期の異常をどう評価・改善していくかが重要です。
- ヒラメ筋の筋力トレーニング:遠心性収縮を強調したエクササイズ(例:スローカーフレイズ)を取り入れる。
- 足部アライメント調整:距骨下関節の可動性や足趾の屈伸可動域を評価し、必要に応じてテーピングやインソールを活用。
- 歩行中のタイミング練習:トレッドミルやフロアマーカーなどで踵離地→つま先離地までの動作を意識づける。
また、神経筋電気刺激(NMES)や歩行補助装具の導入も一時的なサポートとして有効です。
まとめ:立脚終期は推進力の鍵
立脚終期は、歩行の質を左右する**「前進の決定的な一歩」**とも言える時期です。
- 骨盤と体幹の前進を助ける伸展運動
- 足関節底屈筋群の強力な収縮
- 正確なタイミングでの踵離地とフォアフット支点
- 遊脚期へのスムーズな移行
この時期を正しく評価し、介入することは、患者さんの歩行の安定性とスピードを大きく改善するための第一歩となります。
おわりに|理学療法士・学生へ
この記事が、「立脚終期って何となくしか分からなかった…」という方にとって、動作を構造的・機能的に理解するきっかけになれば幸いです。
今後の臨床評価や学生指導、さらには国家試験対策にも活用してみてください。