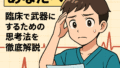はじめに
「患者さんの動きは見ているけど、問題点がうまく言葉にできない…」
「先輩から『もっとよく見て!』と言われるけど、具体的にどこをどう見ればいいんだろう?」
「動作観察で得た情報と、実際の治療プログラムがうまく繋がらない…」
臨床現場に立つ理学療法士、特に新人や若手の方なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
動作観察は、理学療法評価の根幹をなす重要なスキルです。しかし、ただ漠然と眺めているだけでは、貴重な情報は目の前を通り過ぎていくだけ。「なんとなく」の観察では、的確な臨床推論には繋がりません。
この記事では、**複雑な動作を構造的に捉え、質の高い臨床推論に繋げるための「5つの視点」**という思考のフレームワークをご紹介します。
この記事を読んだ後には、あなたの動作を見る「解像度」が格段に上がり、観察結果を根拠に、自信を持って仮説を立てられる一助とれば幸いです。明日からの臨床が、きっと変わるはず!
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

なぜ私たちは「なんとなく」見てしまうのか?
本題に入る前に、なぜ動作観察が「なんとなく」になりがちなのか、その原因を考えてみましょう。
- 基準がない: 「正常動作」のイメージが曖昧で、どこが逸脱しているのかに気づけない。
- 視点が多すぎる: 運動学、解剖学、神経学…考えるべきことが多すぎて、結局ぼんやりと全体像を見てしまう。
- 知識と現象が繋がらない: 教科書で学んだ知識と、目の前の患者さんのリアルな動きが結びつかない。
これらの課題を解決するのが、次にご紹介する「5つの視点」です。このフレームワークを使えば、見るべきポイントが明確になり、観察から仮説検証への道筋が見えてきます。
臨床推論に活かすための「5つの視点」
それでは、動作観察の精度を上げるための具体的な5つの視点を見ていきましょう。
視点1:【時間軸】で分解する(フェーズで見る)
動作は一連の流れですが、それを**「準備期・実行期・終末期」などのフェーズに区切って見る**ことで、どのタイミングで問題が起きているのかを特定できます。
- 観察例(椅子からの立ち上がり動作):
- 屈曲相: 殿部が離れる前。足部の位置は適切か?体幹の前傾は十分か?
- 殿部離床相: 殿部が離れてから、直立するまで。スムーズに立ち上がれているか?膝や体幹に過剰な代償動作はないか?
- 伸展相: 完全に立位になった後。ふらつきなく安定しているか?
- 推論のヒント:
「準備期で十分な体幹前傾ができないな…。もしかして、股関節の可動域制限があるのか?あるいは、恐怖心から前方に重心を移せないのかもしれない」というように、問題が起きているフェーズから原因の仮説を立てることができます。
視点2:【空間軸】で捉える(アライメントと重心で見る)
動作中の**支持基底面(BOS)と重心(COG)の位置関係や、身体各部の配列(アライメント)**から、安定性や力学的ストレスを評価する視点です。
- 観察例(歩行分析):
- 支持基底面: 歩隔(左右の足の幅)は広いか、狭いか?
- 重心移動: 重心の上下・左右への動揺は過剰ではないか?
- アライメント: 立脚相で骨盤が傾いていないか?体幹はまっすぐか?
- 推論のヒント:
歩行分析で「立脚中期に、遊脚側の骨盤が下に落ちる(トレンデレンブルグ徴候)な…。これは支持脚側の中殿筋の機能不全が原因ではないか?」と、アライメントの崩れから特定の筋機能低下を推論できます。
視点3:【質】を評価する(滑らかさと効率性で見る)
動作が「できるか・できないか」だけでなく、そのスピード、リズム、滑らかさ、努力の程度といった「質」に着目することで、潜在的な問題が見えてきます。
- 観察例(寝返り動作):
- スピード: 動作開始に躊躇はないか?動きが極端に遅くないか?
- 滑らかさ: ぎこちない、カクカクした動き(分解様運動)はないか?
- 努力性: 顔をしかめる、息を止める、手すりを強く握りしめるなどの努力的な様子はないか?
- 推論のヒント:
「すごく努力的に起き上がろうとしているな。主動作筋の出力が足りず、他の筋肉で過剰に代償しているのかもしれない。体幹の安定性低下が根本原因かも?」と、動作の質から運動戦略を推測します。
視点4:【比較】で気づく(左右・前後・理想と比べる)
問題点を客観的に浮き彫りにするために、「基準」との違いを見つける視点は非常に有効です。
- 観察例:
- 左右比較: 患側と健側の動きを比べる(例:歩行時のステップ長、腕の振り)。
- 前後比較: 介入前と介入後で、動きはどう変化したか?(治療効果の判定)。
- 理想との比較: いわゆる「正常動作」や、同年代の健常者と比べてどうか?
- 推論のヒント:
「健側に比べて、患側の立脚時間が明らかに短い。これは患側下肢の疼痛か、支持性の低下によって、無意識に荷重を避けている(逃避性跛行)のではないか?」と、比較から具体的な問題点を特定します。
視点5:【背景】を推測する(環境・心理・目的で見る)
動作は、患者さんの身体機能だけで決まるわけではありません。その人を取り巻く環境や心理状態、動作の目的といった「背景」を探ることで、より本質的なアプローチが見えてきます。
- 観察例:
- 環境: 滑りやすい床、履き慣れない靴、手すりの有無、部屋の明るさ。
- 心理: 転倒への恐怖心、人に見られていることへの緊張、痛みへの不安。
- 目的: 「急いでトイレに行く」時と「ゆっくり椅子に座る」時では、同じ「歩く」でも戦略が違う。
- 推論のヒント:
「リハ室では上手に歩けるのに、病棟ではすり足になる…。もしかして、病棟の人の多さや床の材質に不安を感じているのかもしれない。心理面への声かけや、環境設定の提案も必要だな」と、アプローチの幅を広げることができます。

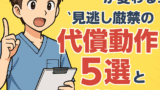
実践編:5つの視点を使った臨床推論のプロセス
では、これらの視点をどう臨床で使うのか。**「右片麻痺患者さんの立ち上がり動作」**を例に、思考プロセスを見てみましょう。
- Step1:観察(5つの視点で情報収集)
- 【時間】離殿のタイミングが遅く、時間がかかる。
- 【空間】体幹が健側(左)に傾き、麻痺側(右)への荷重が不十分。
- 【質】顔をしかめ、健側の手で手すりを強く引きつける努力的な動き。
- 【比較】健側に比べ、麻痺側の足部が後ろに引けていない。
- 【背景】患者さんから「転ぶのが怖い」という発言あり。
- Step2:問題点の解釈・統合
観察結果から、「麻痺側への荷重困難」「体幹の非対称性」「動作の非効率性」「転倒恐怖」といった問題点が浮かび上がる。 - Step3:仮説の立案(「なぜ?」を掘り下げる)
- 仮説①: 麻痺側の足関節背屈制限により、下腿を前傾させられないのでは?
- 仮説②: 体幹の深層筋機能低下により、前傾姿勢を安定して保持できないのでは?
- 仮説③: 転倒恐怖という心理的要因が、前方への重心移動を阻害しているのでは?
- Step4:仮説の検証
立てた仮説を確かめるため、足関節のROMテスト、体幹のMMT、バランス評価、詳細な問診などを実施し、どの仮説が最も妥当性が高いかを検証する。 - Step5:治療プログラムへ
検証結果(例:仮説②の妥当性が最も高かった)に基づき、「体幹の安定性を高めるエクササイズ」を重点的に行うなど、根本原因にアプローチする治療を立案する。
まとめ:明日から始める、動作観察の新しい一歩
「なんとなく見てる」状態から卒業するためには、意図を持った観察が不可欠です。
- 動作は「時間軸」「空間軸」「質」「比較」「背景」の5つの視点で見る。
- 観察から「問題点」を抽出し、「なぜ?」を問いかけて「仮説」を立てる。
- 評価によって「仮説」を検証し、根本原因に対する治療に繋げる。
この思考プロセスが、質の高い臨床推論の土台となります。
まずは1つ、自分が一番使いやすいと感じる視点から意識してみてください。今日の臨床で、担当患者さん1人に対して「時間軸で分解して見る」と決めて観察してみるだけでも、新しい発見があるはずです。
気づいたことや考えた仮説をカルテや自分のノートに書き出す習慣は、あなたの成長を加速させます。意図を持った観察は、必ずあなたの理学療法を豊かにします。ぜひ明日から試してみてください。