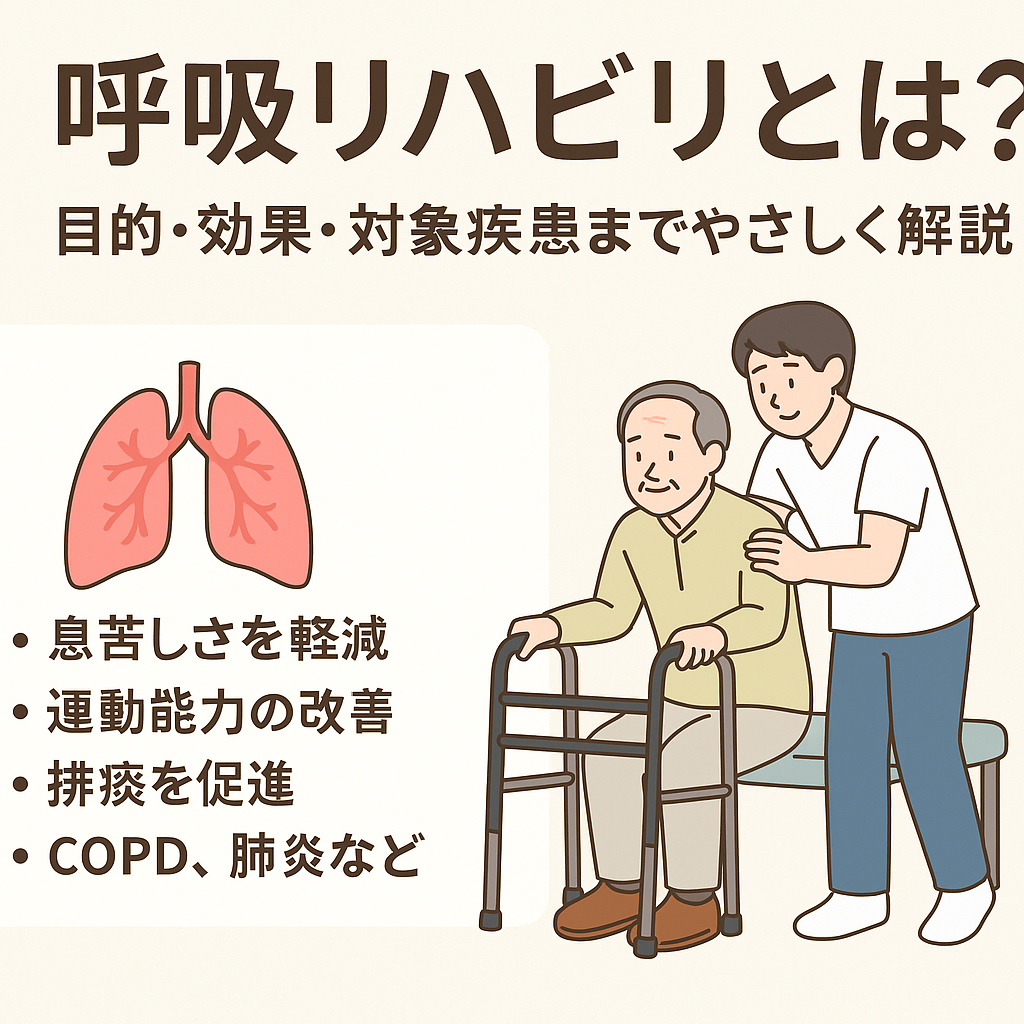はじめに
「廃用症候群」は、臨床の現場で理学療法士が非常によく出会う病態の一つです。ベッド上での生活が続いていたり、安静が長期に及ぶと、驚くほど早く筋力や心肺機能が低下してしまいます。
新人理学療法士にとって、「なぜこの人は歩けなくなったのか?」「どうすれば少しでも回復を促せるのか?」という視点を持つことは、質の高い介入の第一歩です。
この記事では、廃用症候群の定義から原因、症状、評価、そしてリハビリの進め方までを徹底的に解説します。臨床の現場で「すぐに使える知識」として役立つようにまとめました。
より専門的な記事はこちらから
今だけ初月無料キャンペーンしてます!

🔎 廃用症候群とは?
廃用症候群(Disuse Syndrome)とは、「身体を動かさない状態が続くことで、筋肉や関節、心肺機能、精神活動などのさまざまな機能が徐々に低下していく状態」のことです。
「動かないから弱る」というシンプルな話に見えますが、実際には非常に複雑で全身的な変化を伴います。筋肉が衰えるだけでなく、座ること・立つこと・排泄することなど日常生活のあらゆる動作が難しくなり、「動けない→寝たきり→さらに動けない」という悪循環に陥るのが特徴です。
理学療法士の介入が遅れると、廃用は加速度的に進行します。とくに高齢者では、わずか数日間の安静で顕著な機能低下が生じるため、早期離床・早期リハビリが廃用予防のキーポイントです。
🧠 廃用症候群の原因とメカニズム
廃用の原因は「身体を動かさないこと」ですが、その背景にはさまざまな要因があります。
主な原因
- 疾患による安静:心不全、骨折、脳卒中などの発症後、安静が必要とされた結果
- 医療的な制限:酸素療法、ドレーン、点滴などにより動きが制限される
- 疼痛や不安:動かすと痛い、転倒が怖い、など心理的要因も大きい
- 環境的要因:病室が狭い、ポータブルトイレが遠い、介助が少ない等
廃用が起きるメカニズム
- 不活動が始まる(例:手術直後でベッド上安静)
- 筋収縮の機会が減る → 筋タンパクの合成低下と分解亢進
- 筋萎縮、関節可動域の制限、血流低下 → 臓器機能や精神面にも影響
- 活動できなくなることで、さらに不活動が続く
このプロセスは非常に速く、入院して3日動かないだけで筋力が10〜20%低下するという報告もあるほどです。
🩺 廃用症候群による症状と影響
廃用症候群が進行すると、単に筋力が落ちるだけでなく、全身に多岐にわたる影響を及ぼします。以下に、代表的な影響を系統別にまとめます。
【筋骨格系】
- 筋萎縮(特に抗重力筋:腸腰筋、大腿四頭筋、ヒラメ筋など)
- 筋力低下(MMTで3以下になることも)
- 関節拘縮(関節を使わないことで、関節包や靭帯が硬化)
- 骨密度の低下(廃用性骨粗鬆症)
【循環器・呼吸器系】
- 心拍出量の減少 → 動作時に息切れ
- 起立性低血圧 → 立ち上がった瞬間にめまいや転倒
- 肺換気量の低下 → 無気肺、誤嚥性肺炎のリスク増加
【神経・精神系】
- 抑うつ傾向(意欲の低下)
- 見当識障害(場所や時間がわからない)
- 不安、幻覚、せん妄(特に高齢者)
【皮膚・消化・泌尿器】
- 褥瘡(仙骨部・踵部などに好発)
- 便秘、食欲不振
- 尿失禁・尿路感染症
新人理学療法士は、筋力や関節だけに注目しがちですが、全身の状態に目を向けることが大切です。
🧾 廃用症候群の評価ポイント
理学療法士が観察・評価すべき項目
| 評価項目 | 内容 |
| 筋力 | MMT(徒手筋力検査)で定量化し、経時的に比較 |
| 関節可動域 | 拘縮の有無、関節痛が動きを妨げていないか |
| 起立・バランス | TUG、FRTなどを用いて立位能力を評価 |
| 歩行能力 | 10m歩行・6分間歩行で体力や持久力をチェック |
| ADL能力 | FIM、BIなどを用いて日常生活の自立度を把握 |
| 認知・心理面 | 発語の有無、興味関心、抑うつ症状を観察 |
見逃しやすいが重要な視点
- 「何も訴えてこない」=気力が低下している可能性あり
- 「できない」のか「やりたくない」のかを見極める
- 看護記録や介護記録から活動量の変化を拾い上げる
💪 リハビリテーションの実践ポイント
廃用症候群への介入では、段階的に「活動量を上げる」ことが基本です。
急性期(ベッド上中心)
- 呼吸訓練(深呼吸、口すぼめ呼吸など)
- 関節可動域訓練(ROMex)
- 端座位保持訓練(離床の第一歩)
- 転倒リスク管理(モニター、スタッフ協力)
回復期(立位・歩行の獲得)
- 立位訓練(段階的に支持面を小さく)
- 平行棒歩行 → 歩行器 → 杖歩行へ
- 階段昇降・屋外歩行の導入
- ADL訓練(トイレ動作、更衣動作)
精神面のアプローチ
- 目標は「その人にとって意味のあること」にする
例:「家の庭をまた歩きたい」「孫と旅行に行きたい」 - 達成可能な短期目標を設定し、達成を共有する
- 声かけ・関係構築も重要な「介入」の一部
🧩 新人PTが現場で直面する壁と対処法
よくある新人の悩みとヒント
- 「ベッド上で何をすればいいのかわからない」
→ 端座位保持だけでも大きな一歩。ROM、深呼吸、簡単な自主トレから始めよう。 - 「高齢者に“やる気”が感じられない」
→ 動機づけが大事。話を聞く、過去の活動歴を探る、「意味」を見つける。 - 「動かして悪化しないか不安」
→ 医師・看護師と情報共有。病態把握とモニタリングで安全に進められる。
✅ まとめ
廃用症候群は、理学療法士の「ちょっとした介入の遅れ」が重大な機能低下につながる病態です。しかし、逆に言えば、小さな介入が大きな回復の第一歩になるということでもあります。
新人のうちは戸惑うことも多いですが、「観察」「気づき」「声かけ」「離床」など、すべてが重要な治療です。焦らず、確実に積み重ねていきましょう。