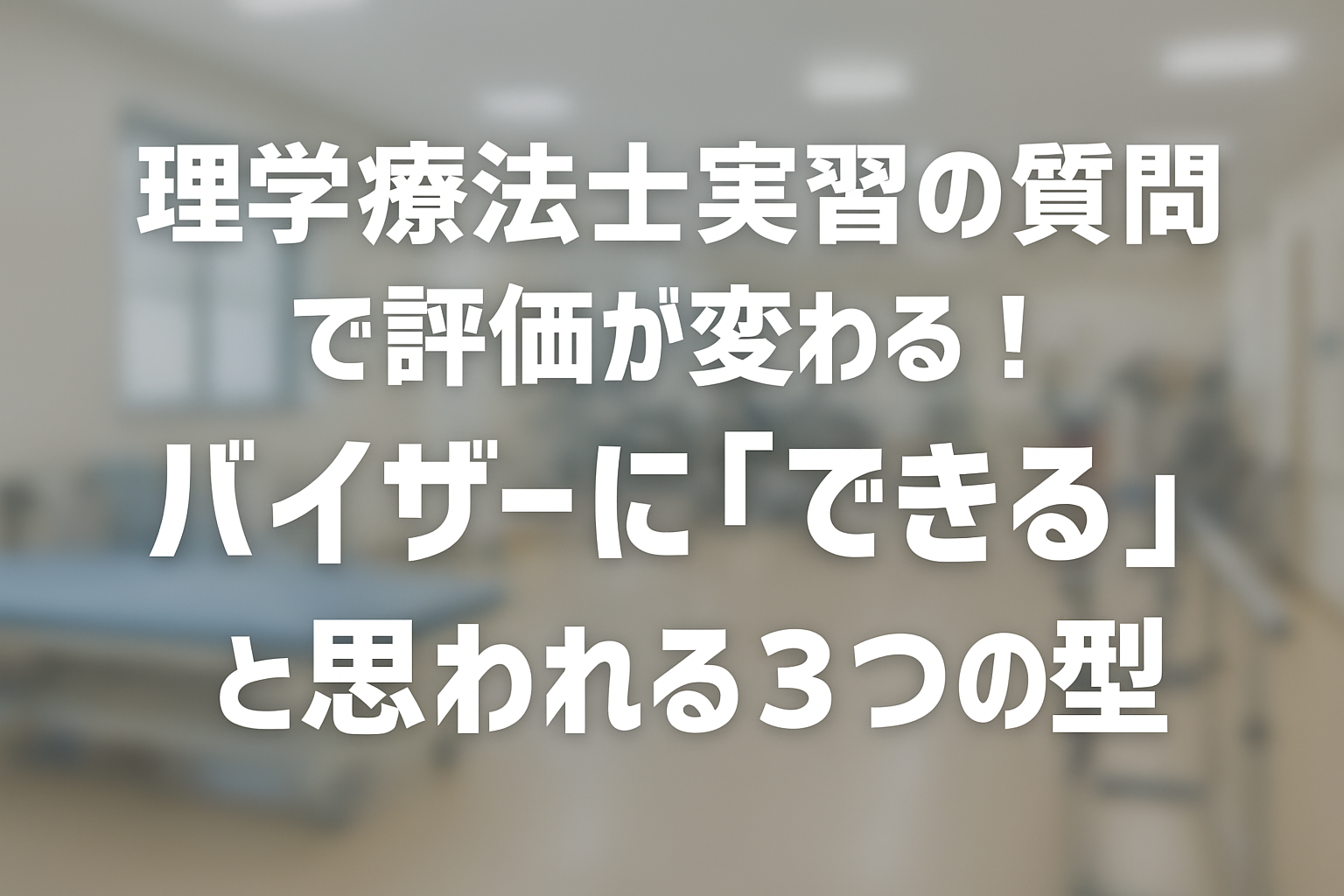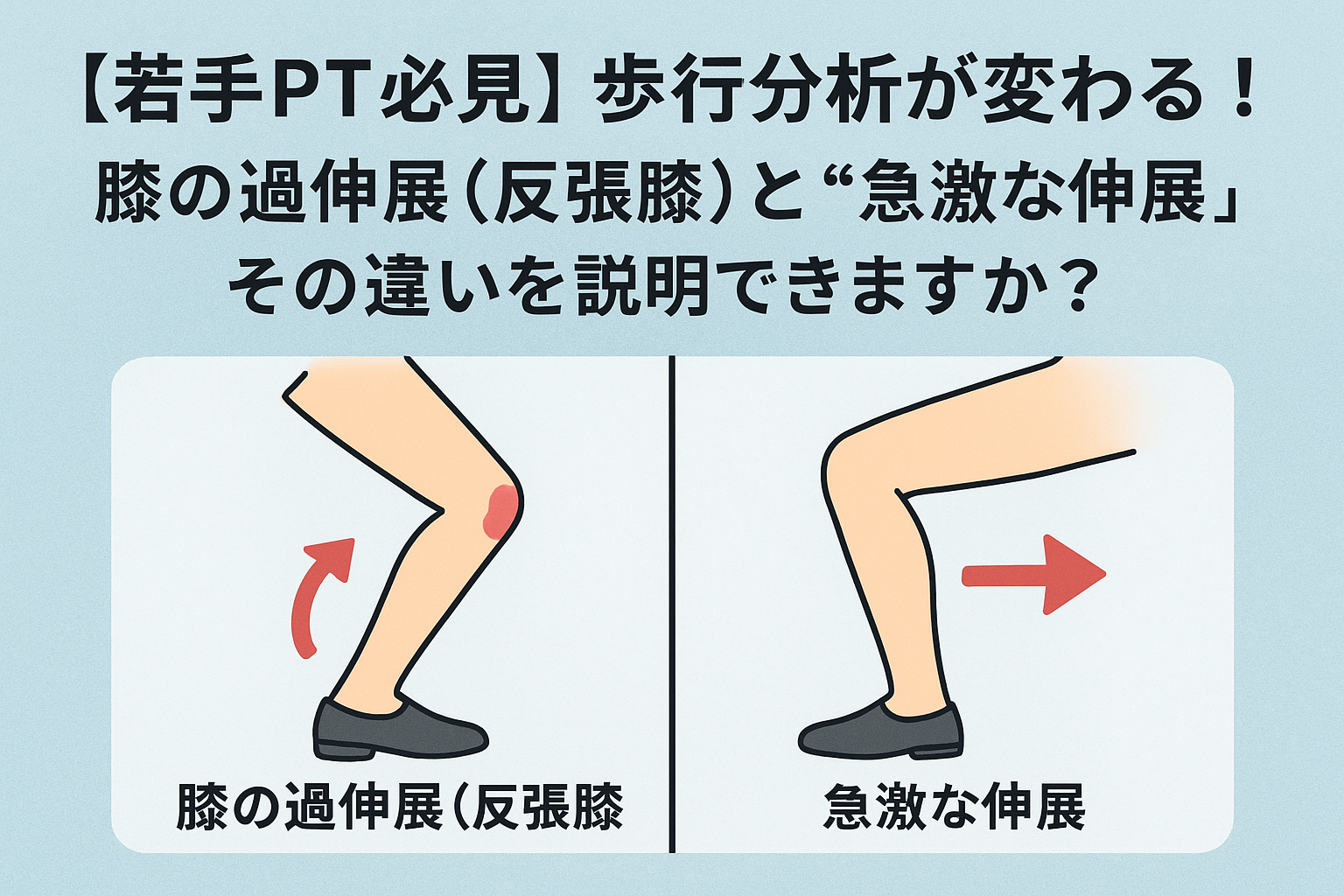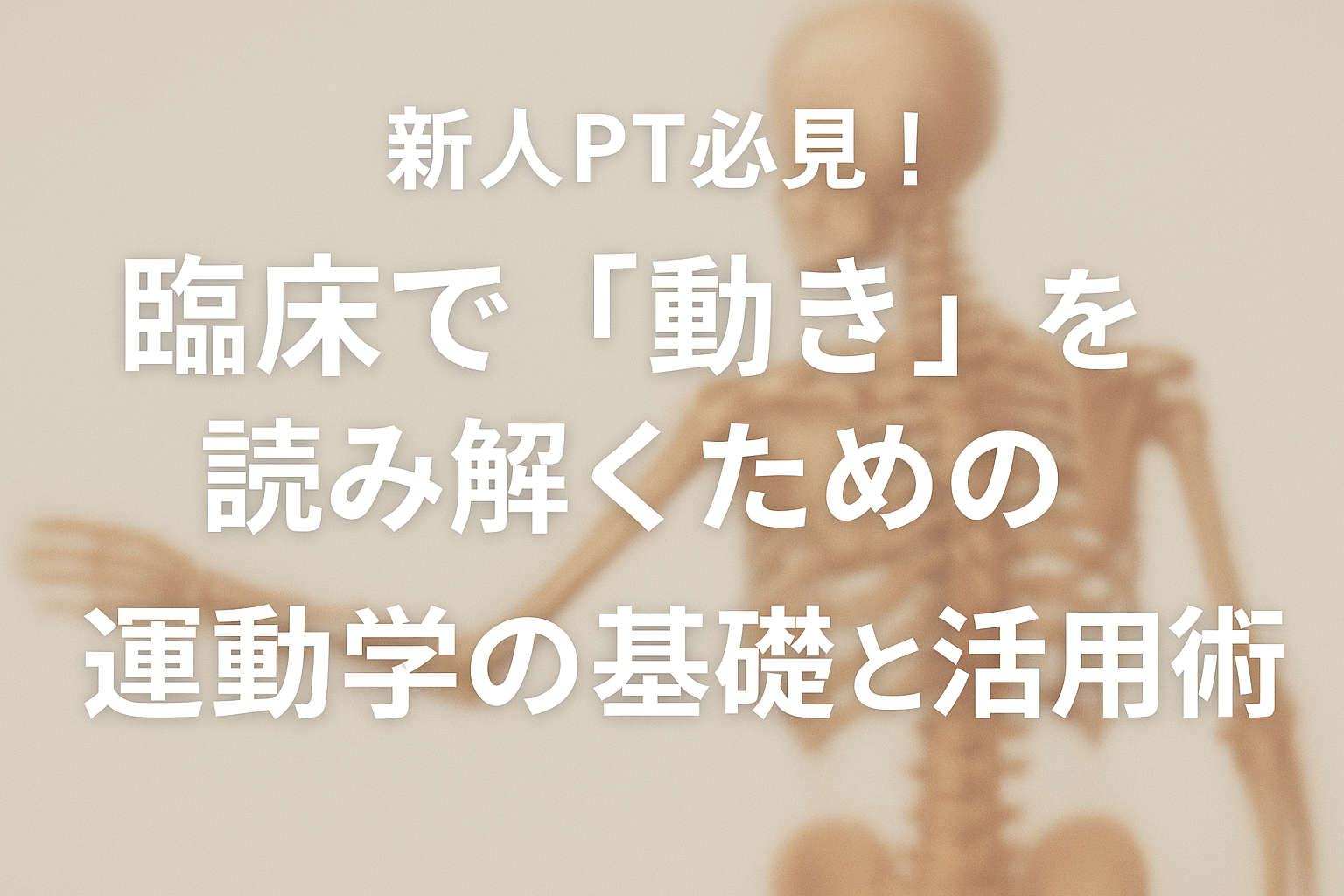この「何か質問ある?」が怖い学生さんへ

実習でバイザー(指導者)に質問するのが怖い…

『そんなことも知らないのか』と思われたらどうしよう…
そもそも、何を聞けばいいか分からない…
臨床実習に臨む理学療法士の学生さんなら、誰もが一度は抱える悩みではないでしょうか。
何を隠そう、私も学生時代は質問が苦手で、バイザーの「何か質問ある?」という言葉に何度フリーズしたか分かりません。
しかし、指導する立場になった今、断言できることがあります。
それは、実習生の評価は「質問の質」で大きく変わるということです。
この記事では、あなたの評価を下げてしまうNGな質問と、バイザーに「お、こいつは考えてるな」と思わせる質問の3つの型を、具体的な例文付きで徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、質問への恐怖心がなくなり、実習での学びを何倍にも加速させるヒントが手に入っているはずです。
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

【要注意】理学療法士の実習で評価を下げるNGな質問3パターン
まず、これだけは避けたい「NGな質問」から確認しましょう。無意識にやってしまうと、学習意欲が低いと見なされかねないので注意が必要です。
丸投げ質問「どうすればいいですか?」
最もやってしまいがちなのが、この思考停止型の質問です。
患者さんの評価やアプローチに悩んだ時、つい「この後、どうすればいいですか?」と聞いてしまいたくなりますが、これはNG。
指導者からすると「あなたはどう考えたの?」となり、指導のしようがありません。「自分で考えることを放棄している」という印象を与えてしまいます。
調べればわかる質問「腓腹筋の起始停止はどこですか?」
解剖学の教科書や参考書、スマホで検索すればすぐにわかることを質問するのも避けましょう。
もちろん、緊急時やどうしても見つからない場合は別ですが、基本的な知識を質問してしまうと「自分で調べる努力をしていない」と思われてしまいます。
貴重な質問の機会は、「その場でしか聞けないこと」に使いましょう。
思考停止の「特にありません」
バイザーから「何か質問ある?」と聞かれた際に、「特にありません」と答えてしまうのは、最ももったいない返答です。
本当に疑問がないのかもしれませんが、指導者側は「今日の学びに興味がないのかな?」「何も考えていないのかな?」と不安になってしまいます。たとえ小さなことでも、必ず何か一つは疑問点を見つけるクセをつけましょう。
【本題】バイザーに「できる実習生」と思われる質問の3つの型
それでは、本題です。明日からすぐに使える、あなたの評価をグッと上げる質問の型を3つご紹介します。ポイントは**「自分の思考プロセスをセットで伝える」**ことです。
【型1:仮説検証型】自分の考えをセットで伝える
これは最も基本的で、最も重要な型です。**「①自分の考え(仮説)」+「②その根拠」+「③指導者に聞きたいこと」**をセットで質問します。
「〇〇様の歩行時に見られる体幹の側屈についてですが、**(②根拠)トレンデレンブルグ徴候陽性であることから、(①自分の考え)支持脚側の中殿筋の筋力低下が一番の原因だと考えました。そこでアプローチとしてクラムシェルを検討しているのですが、(③聞きたいこと)**先生はこの評価と治療プランについてどのようにお考えになりますか?」
【ポイント】
自分の考えが合っているか間違っているかは問題ではありません。「ここまで自分で考えました」という姿勢を見せることで、バイザーは「なるほど、そこまでは理解できているんだな。じゃあ次はここを教えよう」と、的確なフィードバックをしやすくなります。
【型2:選択肢比較型】根拠をもって選択肢を示す
一つの考えに固執せず、複数の可能性を検討できていることをアピールできる型です。**「①考えられる選択肢AとB」+「②自分がAを選ぶ理由」+「③この判断で良いか確認」**という流れで質問します。
「〇〇様の肩関節の可動域制限に対して、**(①選択肢)関節モビライゼーションと、筋肉に対するストレッチが考えられます。(②選ぶ理由)まずは関節包の硬さを改善することが優先度が高いと考えたので、モビライゼーションから始めるのが良いかと思ったのですが、(③確認)**このアプローチの優先順位の付け方について、先生のご意見を伺ってもよろしいでしょうか?」
【ポイント】
視野の広さを示すことができます。「なぜそちらを選んだのか?」という根拠を明確にすることで、あなたの臨床推論のレベルをバイザーに伝えることができます。
【型3:知識深掘り型】調べた上で「臨床知」を求める
学習意欲の高さをアピールしつつ、教科書には載っていない「現場の知恵」を引き出すための質問です。**「①自分で調べた知識」+「②教科書にはない、臨床ならではの視点やコツを問う」**という構成です。
「**(①調べた知識)教科書でTKA(人工膝関節置換術)術後の屈曲可動域目標は120度と学びました。(②臨床知を問う)**先生が臨床で多くの患者様を見てこられた中で、スムーズに退院される方の特徴や、目標角度を達成するために特に工夫されている点などがあれば教えていただきたいです!」
【ポイント】
「ちゃんと勉強してきているな」という前提を与えつつ、バイザーの経験や知識に敬意を払う質問なので、指導者も気持ちよく答えてくれます。このような質問ができると、他の実習生と大きく差をつけることができます。
さらに評価アップ!質問の「タイミング」と「マナー」
質問の内容が良くても、タイミングやマナーが悪ければ台無しです。デキる実習生は、こうした気配りも忘れません。
- 質問のベストタイミング
- 1日の終わりのフィードバックの時間
- カンファレンスの後
- バイザーがカルテ記録を終えて一息ついている時
- 忘れてはいけないマナー
- **「今、少しお時間よろしいでしょうか?」**と必ず許可を取る。
- 質問したいことは、事前にメモにまとめておくとスムーズです。
- 教えてもらったら**「ありがとうございました!勉強になりました!」**と必ず感謝を伝える。
- 一番大事なのは、教えてもらったことを次の日の行動で示すことです。これが最高のお礼になります。
まとめ:質問は自分の「思考」を見せるプレゼンだ!
今回は、理学療法士の実習で評価が上がる質問の仕方について解説しました。
- NGな質問(丸投げ、ググればわかる、質問なし)は避ける
- 「仮説検証型」「選択肢比較型」「知識深掘り型」の3つの型を使いこなす
- 質問は、自分の思考プロセスを見せる絶好のプレゼンテーションの機会である
最初から完璧な質問をする必要はありません。大切なのは「自分で考え、それを伝えようとする姿勢」です。
失敗を恐れず、まずはこの記事で学んだ型を一つでも使ってみてください。その小さな一歩が、あなたの臨床実習を何倍も有意義にし、理学療法士としての成長を大きく後押ししてくれるはずです。
応援しています!