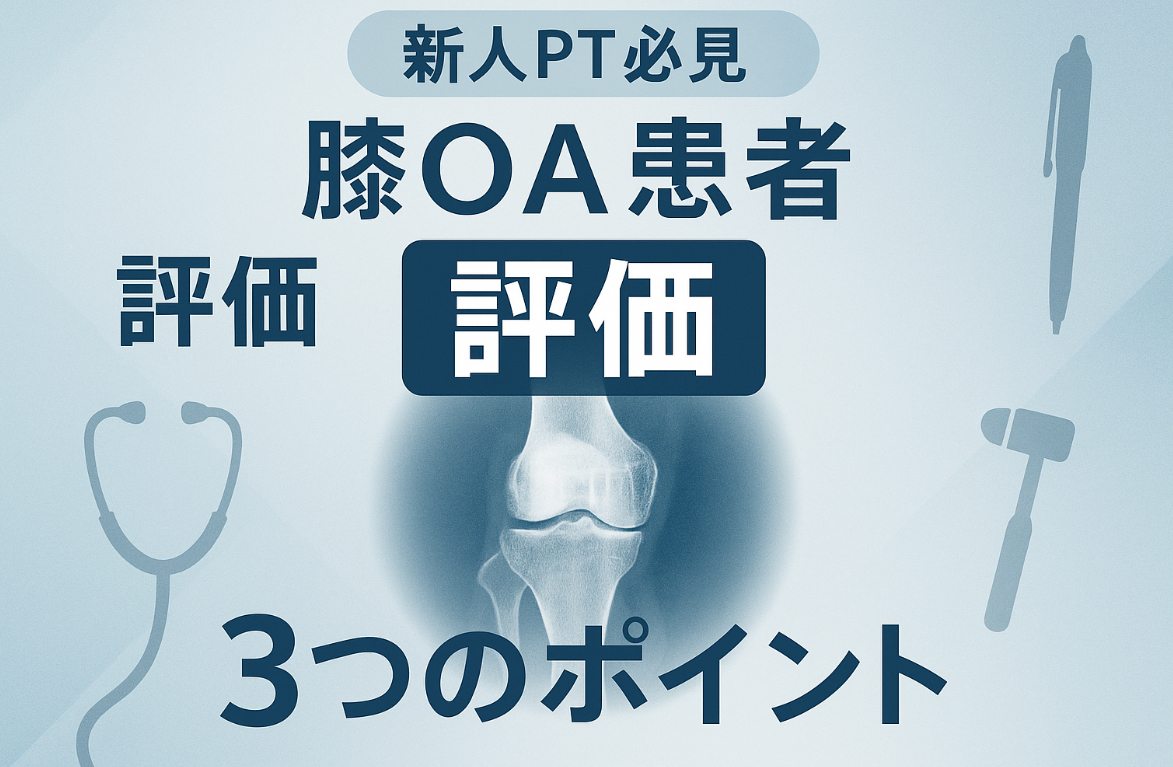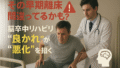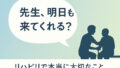はじめに
「膝OA(変形性膝関節症)の患者さんを担当することになったけど、どこから評価すればいいか分からない…」
「評価項目はたくさんあげれるけど、それらが治療にどう繋がるのかイメージできない…」
「先輩みたいに根拠のあるリハビリがしたいけど、ついマニュアル通りの運動になってしまう…」
臨床経験の浅い新人理学療法士(PT)や学生さんの中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
毎日多くの患者さんと向き合う中で、特に遭遇する機会の多い膝OA。だからこそ、自信を持って評価・アプローチできるようになりたいですよね。
この記事が、膝OA患者さんを評価する上での**「思考の軸」が手に入ります。評価結果を統合し、自分なりの治療プログラムを立てる「臨床推論のプロセス」**を学ぶきっかけとなれば幸いです。
日々の臨床の一助となりますように。
今回は、膝OAの評価で特に重要な「3つのポイント」に絞って、分かりやすく解説していきます。
臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

なぜ膝OAの評価は難しい? まずは「思考の土台」を整えよう
新人PTが膝OAの評価でつまずきやすいのは、痛みの原因が多岐にわたるからです。
膝の痛みは、必ずしも膝関節の中(軟骨や半月板)だけが原因ではありません。関節周囲の筋肉や靭帯、神経、さらには股関節や足関節といった膝以外の問題が、膝に過剰な負担(メカニカルストレス)をかけているケースが非常に多いのです。
だからこそ、闇雲に評価項目をこなすのではなく、「なぜこの患者さんの膝は痛むのだろう?」という仮説を立てながら評価を進めることが何よりも重要になります。
これから紹介する3つのポイントは、その「仮説」を立てるための強力な武器になります。一緒に学んでいきましょう。
評価で絶対に外せないポイント①:「痛みの原因」を特定する
評価の第一歩は、患者さんが最も困っている「痛み」の解像度を上げることです。痛みへのアプローチなくして、患者さんとの信頼関係は築けません。
- 問診の深掘り
「いつ、どこが、何をすると痛いですか?」という基本的な質問から、もう一歩踏み込みましょう。- タイミング: 歩き始め、長距離歩行後、安静時
- 部位: 膝の内側、お皿の下、膝裏など、指一本で示してもらう
- 動作: 階段(上り/下り)、椅子からの立ち座り、しゃがみ込み
- 圧痛所見の取り方
問診で得た情報を元に、痛みの発生源(発痛源)を探ります。ただ押すだけでなく、解剖学を頭に思い浮かべながら、どの組織を触っているか意識するのがプロの仕事です。- 内側関節裂隙: 内側半月板損傷の可能性
- 鵞足部(膝内側の下方): 鵞足炎(縫工筋・薄筋・半腱様筋腱の炎症)の可能性
- 膝蓋下脂肪体: Fat pad症候群の可能性
評価で絶対に外せないポイント②:「アライメントと動作」を観察する
次に、なぜその組織に負担がかかってしまうのか、という「メカニカルストレス」の正体を探ります。ここでは特に、立っている姿勢(静的アライメント)と歩き方(動的アライメント)が重要です。
- 静的アライメント評価
まずは立位姿勢を正面から観察しましょう。ここだけでも多くの情報が得られます。- Genu Varum/Valgus(O脚/X脚): 膝の内側/外側にストレスが集中しやすい状態です。
- 膝の過伸展(反張膝): 膝関節後方の組織にストレスがかかりやすいアライメントです。
- 動的アライメント評価(歩行観察)
歩行は、膝に体重の数倍の負荷がかかる動作です。膝OAの評価において歩行観察は必須です。特に注目すべきは**「ラテラルスラスト」**です。ラテラルスラストとは?
歩行の立脚期(足を地面についている時)に、膝関節が外側にグラっと揺れる現象のこと。これは、膝の内側に圧縮ストレスを増大させるため、内側型膝OAの痛みを増悪させる代表的な異常歩行です。「なぜラテラルスラストが起きるのか?」を考えることが、根本的な治療に繋がります。(ヒントはポイント③にあります)
評価で絶対に外せないポイント③:「膝関節以外の影響」を評価する
「木を見て森を見ず」という言葉があるように、膝の問題を解決するには、膝だけを見ていては不十分です。膝関節は、股関節と足関節に挟まれた「中間関節」。上下の関節の影響を強く受けます。
- 股関節の評価
- なぜ重要か?
股関節は、地面からの衝撃を吸収したり、体を安定させたりする重要な役割を担っています。この股関節の機能が低下すると、その分の負担がすべて膝にかかってしまうのです。(これを運動連鎖と呼びます) - 見るべきポイント
- 関節可動域: 特に伸展・内外旋の制限は、歩行や立ち上がり動作に大きく影響します。
- 筋力: 特に**中殿筋(お尻の横の筋肉)**の筋力低下は、先ほど説明したラテラルスラストの直接的な原因になります。
- なぜ重要か?
- 足関節・足部の評価
- なぜ重要か?
足部は体の唯一の土台です。この土台が崩れていれば、その上にある膝が不安定になるのは当然ですよね。 - 見るべきポイント
- 関節可動域: 特に足関節の背屈(つま先を上げる動き)制限は、しゃがみ込みなどの動作で膝への負担を増大させます。
- アライメント: **過回内足(偏平足)**は、下腿を内旋させ、膝関節にねじれのストレス(Knee-in)を生じさせる原因となります。
- なぜ重要か?
【臨床推論を体験!】評価結果を統合し、治療プログラムを立ててみよう
それでは、これら3つのポイントを使って、実際の臨床推論をシミュレーションしてみましょう。
【仮想症例】
- 70代女性、内側型変形性膝関節症。歩行時の膝内側の痛みが主訴。
【評価結果の例】
- 痛みの評価: 歩行開始時と長距離歩行後に膝内側が痛む。内側関節裂隙に著明な圧痛あり。
- 動作評価: 歩行時に明らかなラテラルスラストを認める。
- 他関節の評価: 股関節外転筋力(中殿筋)の低下(MMT 3レベル)。足部の過回内も認める。
【統合と解釈(ストーリー作り)】
さあ、これらの評価結果を繋ぎ合わせて、患者さんの「痛みの物語」を作ってみましょう。
「この患者さんは、股関節外転筋(中殿筋)の筋力低下がある(③)。そのため、歩行中に体をうまく支えられず、代償的に膝が外側に揺れてしまう(ラテラルスラスト)(②)。このグラつきが繰り返されることで、膝の内側に圧縮ストレスが集中し、半月板や軟骨に負担がかかり、痛みが出ているのではないか?(①)」
このように、評価結果を繋げることで、痛みの根本原因に対する仮説が立てられました。
【治療プログラム立案】
この仮説に基づけば、アプローチすべきは痛い膝の内側だけではないことが分かりますよね。
- 短期アプローチ(対症療法)
- 痛みの軽減を目的とした物理療法(ホットパック、低周波など)
- 膝周囲の過緊張した筋肉(大腿四頭筋など)への徒手的アプローチ
- 長期アプローチ(根本改善)
- 股関節外転筋の筋力強化(最優先): クラムシェル、側臥位での股関節外転運動など。
- 歩行指導: ラテラルスラストを抑制するように、お尻の筋肉を使う意識付けを行う。
- 足部機能の改善: タオルギャザーなどの足趾運動、インソール(足底挿板)の検討を提案。
このように、「なぜ痛むのか?」という仮説があるだけで、治療プログラムに一本の太い幹が通ります。
まとめ
今回は、新人理学療法士が膝OAの評価で迷わないための3つの重要ポイントと、それらを治療に繋げる思考プロセスについて解説しました。
- ポイント①:痛みの原因を特定する(問診・圧痛)
- ポイント②:アライメントと動作を観察する(特にラテラルスラスト)
- ポイント③:膝関節以外の影響を評価する(特に股関節・足関節)
大切なのは、これらの評価結果をバラバラに捉えるのではなく、**「なぜ痛むのか?」という一連のストーリーとして繋ぎ合わせる(臨床推論)**ことです。
最初から完璧にできる人はいません。この記事で紹介した「評価 → 仮説 → 治療」というサイクルを、日々の臨床で意識して繰り返すことが、理学療法士としての成長の何よりの近道です。
目の前の患者さんと真摯に向き合い、考えるリハビリを楽しんでいきましょう!