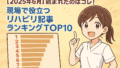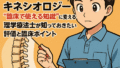はじめに
若手理学療法士や学生の皆さん、こんにちは!臨床で患者さんの姿勢保持の崩れに直面し、その原因究明に悩んだ経験はありませんか?
姿勢保持の崩れは、ADL(日常生活動作)の低下や二次的な問題に繋がりやすいため、その原因を正確に把握し、適切なアプローチを行うことが重要です。
しかし、「なんとなく姿勢が悪いな」と感じるものの、具体的にどこを見て、何を評価すれば良いのか迷ってしまうことも少なくないでしょう。
そこで、この記事では、姿勢保持が崩れる原因について考え、、さらに皆さんが明日からの臨床で実践できる、動作観察で注目すべき5つの視点を詳しくご紹介します。
\臨床理学Labでは有料記事が読み放題/

姿勢保持が崩れる主な原因を理解しよう
姿勢保持が崩れる原因は多岐にわたりますが、大きく以下の3つの要素に分けられます。これらを理解することで、より深く患者さんの状態を分析できるようになります。
身体構造の問題:骨・関節・筋・神経のトラブル
- 骨・関節の問題: 脊柱の変形(例:側弯症、後弯症)、関節拘縮、不安定性などが挙げられます。これらは物理的に正しい姿勢を保つことを困難にします。
- 筋の問題: 特に抗重力姿勢を保つために重要な筋力低下(例:腹筋群、脊柱起立筋、殿筋群)、筋の短縮や過緊張、左右の筋力アンバランスなどが関与します。
- 神経の問題: 脳卒中やパーキンソン病といった中枢神経疾患による姿勢反射の障害、感覚障害、末梢神経障害なども姿勢保持に大きな影響を与えます。
身体機能の問題:バランス・協調性・感覚入力の障害
- バランス能力の低下: 静的バランス(静止している時)だけでなく、動的バランス(動いている時)の障害も姿勢保持を不安定にします。
- 協調性の低下: 複数の筋群が連携して滑らかに動作を行う能力が低下すると、不自然な姿勢になりがちです。
- 感覚入力の障害: 視覚、前庭覚(平衡感覚)、体性感覚(体の位置や動きの感覚)からの情報入力に異常があると、適切な姿勢調整が困難になります。
- 認知機能の問題: 姿勢を維持するために必要な注意や判断力が低下することも、姿勢保持の崩れに繋がることがあります。
環境要因・心理的要因:意外な落とし穴
- 環境要因: 長時間使用する椅子やベッドが身体に合っていない、活動環境が不適切であるなども姿勢に悪影響を与えます。
- 心理的要因: ストレス、不安、うつなどが原因で筋緊張が変化したり、活動性が低下したりすることで、姿勢保持が難しくなることもあります。
これらの原因が単独で、あるいは複数組み合わさることで姿勢保持の崩れが生じます。
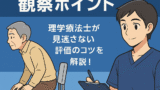
明日から使える!理学療法士が動作観察で見るべき5つの視点
では、実際に患者さんを目の前にした時、どこに注目して姿勢保持の崩れの原因を探れば良いのでしょうか?ここでは、私が日々の臨床で実践している動作観察で見るべき5つの視点を具体的に解説します。これは、理学療法士として患者さんを姿勢評価する上で非常に重要なポイントです。
支持基底面と重心動揺の関係性
姿勢保持の基本は、支持基底面内に重心を保つことです。ここが不安定だと、姿勢は容易に崩れます。
どこを見るのか?
- 支持基底面の広さ: 立位であれば足部、座位であれば臀部や大腿部の接地面積は適切か?広すぎたり、狭すぎたりしていないか?
- 重心の位置: 重心は支持基底面のどのあたりに位置しているか?前方、後方、左右に偏っていないか?
- 重心動揺のパターン: 静止立位・座位で過剰な前後左右への揺れがないか?動きの中で重心がどのように移動しているか?
- 代償動作: 支持基底面を確保するために、体幹や四肢で過剰な代償動作(例:足を広げすぎる、手で支持する)をしていないか?
各関節のアライメントと可動性
各関節のアライメントが崩れると、筋への負担が増加し、姿勢保持が困難になります。また、可動性の制限は、適切な姿勢を取ることを妨げます。
どこを見るのか?
- 頭部・頚部: 前方突出、側屈、回旋がないか?
- 肩甲帯・上肢: 肩甲骨の挙上、下制、外転、内転がないか?左右差は?上肢の不必要な筋緊張はないか?
- 体幹・骨盤: 脊柱の過度な彎曲(後弯、前弯)、側弯はないか?骨盤の前傾、後傾、回旋、側方偏位はないか?
- 股関節・膝関節・足関節: 屈曲拘縮、伸展制限はないか?膝関節の過伸展(反張膝)はないか?足部の内反、外反はないか?
活動のタイミングと出力
姿勢保持には、適切な筋群が適切なタイミングで活動し、必要な出力を発揮することが不可欠です。特に体幹機能は重要です。
どこを見るのか?
- 抗重力筋の活動: 腹筋群、脊柱起立筋、殿筋群、大腿四頭筋、下腿三頭筋などの活動は十分か?触診で確認できるか?
- 筋のアンバランス: 特定の筋群だけが過活動になっていないか?拮抗筋とのバランスはどうか?
- 共同収縮の有無: 安定性を保つために不必要な共同収縮が起きていないか?(例:歩行時の大腿四頭筋とハムストリングスの同時収縮)
- 動作開始時の筋活動: 動き出す瞬間に、姿勢を安定させるための筋が先行して活動しているか?(例:上肢挙上時の腹横筋の先行活動)
感覚入力と姿勢調整の関連
視覚、前庭覚、体性感覚からの情報は、姿勢を調整するために非常に重要です。これらの入力に問題があると、姿勢保持が不安定になります。バランス能力にも直結する部分です。
どこを見るのか?
- 視覚の影響: 目を閉じた時と開けた時で姿勢の安定性に変化はあるか?一点を注視することで安定性が増すか?
- 前庭覚の影響: 頭部の位置変化や加速度の変化に対して、姿勢はどのように反応するか?めまいやふらつきはないか?
- 体性感覚の影響: 足底からの情報や関節の位置覚は適切か?感覚入力が少ない環境(柔らかいマットの上など)での姿勢変化は?
- 支持面の変化への対応: 床の硬さ、傾斜、不安定な環境(例:バランスクッション)での姿勢の適応能力はどうか?
呼吸パターンと姿勢筋活動
呼吸は、体幹の安定性や姿勢筋の活動と密接に関連しています。不適切な呼吸パターンは、姿勢保持の崩れに繋がることがあります。
どこを見るのか?
- 呼吸様式: 胸式呼吸が優位になっていないか?腹式呼吸は適切に行われているか?
- 呼吸と体幹筋の関係: 吸気時に腹部が膨らみ、呼気時にへこむような腹横筋の活動が見られるか?
- 努力性呼吸の有無: 首や肩の筋肉を使った努力性呼吸になっていないか?それが姿勢にどう影響しているか?
- 呼吸と動作の連動: 動作中に息を止めていないか?スムーズな呼吸と動作の協調性が見られるか?

まとめと今後のステップ
この記事では、姿勢保持が崩れる原因と、理学療法士が動作観察で見るべき5つの視点について解説しました。これらの視点を持つことで、皆さんは患者さんの姿勢保持の崩れをより詳細に分析し、問題の根源に迫ることができるはずです。
今回の内容を参考に、ぜひ日々の臨床で実践してみてください。そして、観察した結果から仮説を立て、姿勢評価の精度を高め、効果的な介入に繋げていきましょう。
【若手理学療法士や学生の皆さんへ質問です!】
今回の記事で挙げた5つの視点の中で、特に「これは明日から実践したい!」と感じた視点はありましたか?また、皆さんが普段の臨床で姿勢観察をする際に、他に意識しているポイントがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!