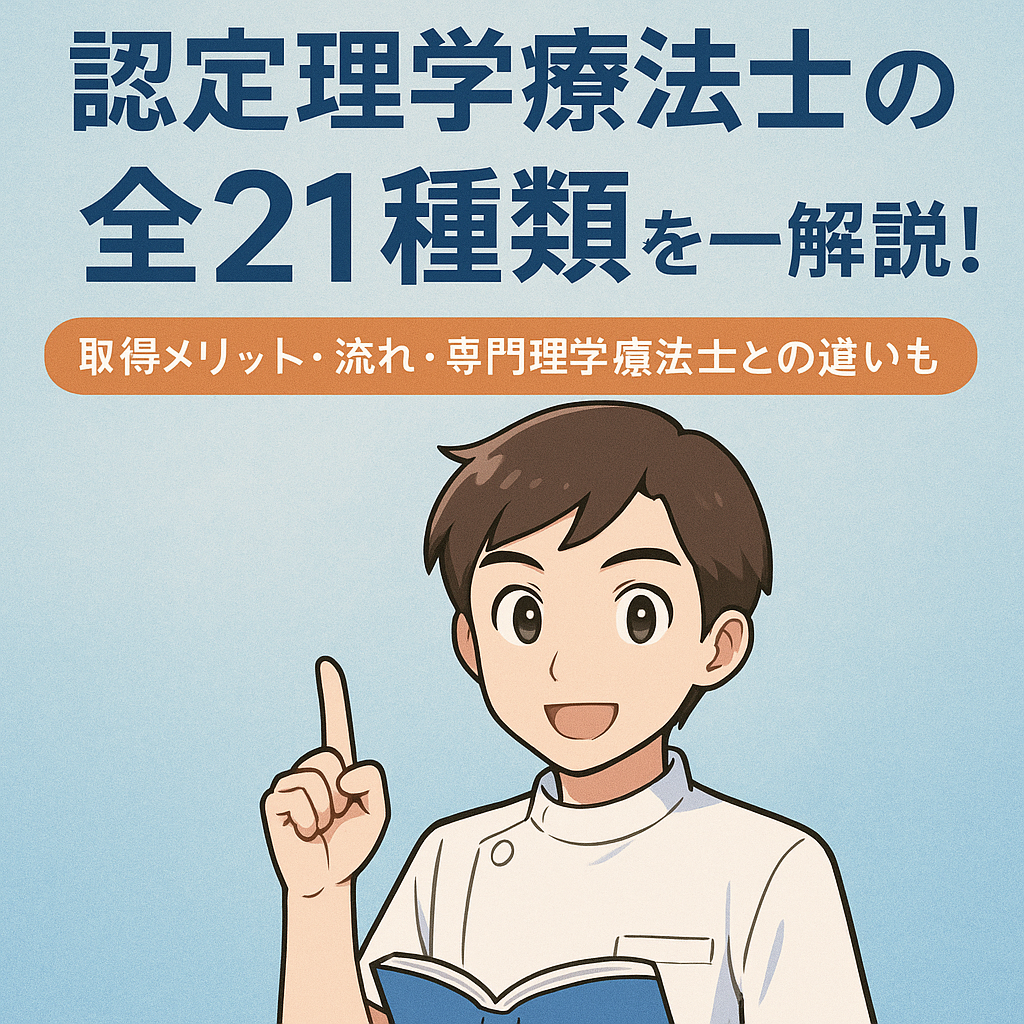はじめに
「日々の臨床に追われる中で、自分の専門性って何だろう?」
「将来のキャリアを考えると、何か強みになる資格が欲しいな…」
「認定理学療法士に興味があるけど、新制度になってよく分からない…」
「症例報告が不要になったって本当?具体的にどうすれば取れるの?」
キャリアを重ねるにつれて、あなたも一度はこんな風に考えたことがあるのではないでしょうか?
理学療法士としての専門性を高めるキャリアパスとして、「認定理学療法士」は非常に魅力的ですよね。
2022年度から生涯学習制度が全面的にリニューアルされ、取得方法や資格の位置づけが変わりました。
この記事では、日本理学療法士協会の公式資料に基づき、新制度における認定理学療法士の全てを、分かりやすく解説します!
- 新制度における全21分野の一覧
- 症例報告が不要になった新しい取得ステップ
- キャリアアップに直結する具体的なメリット
- 専門理学療法士との新しい関係性
この記事を読めば、新制度の認定理学療法士について正確に理解でき、あなたが次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてきます。ぜひ最後までご覧ください!
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

認定理学療法士とは?【新制度でこう変わった!】
まず、認定理学療法士の基本からおさらいしましょう。
認定理学療法士とは、「特定の専門分野において、質の高い理学療法を実践できる能力を有することを、日本理学療法士協会(JPTA)が認めた理学療法士」のことです。
そして、2022年度からの新制度で、この資格の役割はより明確になりました。公式資料によると、認定理学療法士は**「臨床実践分野において秀でている理学療法士」**と位置づけられ、認定看護師制度をモデルにしています。つまり、現場での実践力に特化したスペシャリストであることが強調されるようになりました。
新制度の主な変更点
- 名称の統一:「認定理学療法士(〇〇)」から「〇〇認定理学療法士」という呼び方に変わりました。
- 症例報告の廃止:取得の大きなハードルだった症例報告がなくなり、代わりに体系的な研修カリキュラムの履修と認定試験で評価される仕組みになりました。
- 前提資格の新設:認定を目指す前に、理学療法士の基礎的能力を担保する「登録理学療法士」の取得が必須となりました。
- e-learningの活用:研修の多くがe-learningで受講可能になり、時間や場所を選ばずに学習しやすくなりました。
認定理学療法士 全21分野を一覧で紹介
新制度では、旧制度の領域が見直され、21分野の認定理学療法士制度として再スタートしました。(※基礎理学療法は専門理学療法士へ移行)
あなたの興味や職場環境に合った分野がきっと見つかるはずです。
| 分野 | 認定理学療法士の名称 |
| 神経系 | 脳卒中認定理学療法士 |
| 神経筋障害認定理学療法士 | |
| 脊髄損傷認定理学療法士 | |
| 発達障害認定理学療法士 | |
| 運動器系 | 運動器認定理学療法士 |
| 切断認定理学療法士 | |
| スポーツ理学療法認定理学療法士 | |
| 徒手理学療法認定理学療法士 | |
| 補装具認定理学療法士 | |
| 内部障害系 | 循環認定理学療法士 |
| 呼吸認定理学療法士 | |
| 代謝認定理学療法士 | |
| 生活環境支援系 | 地域理学療法認定理学療法士 |
| 健康増進・参加認定理学療法士 | |
| 介護予防認定理学療法士 | |
| 物理療法・その他 | 物理療法認定理学療法士 |
| 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士 | |
| 疼痛管理認定理学療法士 | |
| 教育・管理系 | 臨床教育認定理学療法士 |
| 管理・運営認定理学療法士 | |
| 学校教育認定理学療法士 |
※注:本記事は2022年の新制度開始時の21分野を基に解説しています。協会は今後も社会のニーズに応じて分野の新規新設や統廃合を検討するとしており、最新の情報は必ず日本理学療法士協会の公式サイトでご確認ください。
理学療法士が認定資格を取得する5つの大きなメリット
大変な思いをして取得するからには、それに見合うメリットがなければ頑張れませんよね。認定理学療法士の取得には、あなたのキャリアを加速させる大きな価値があります。
メリット1:専門性の「見える化」で信頼度アップ
患者さんや他職種に対し、あなたの専門性を客観的に証明できます。「〇〇の専門家」として認知され、臨床現場での信頼性が格段に向上します。また、職場には「〇〇の専門家の理学療法士が在籍している」というように職場に対しても貢献できる形になります。
メリット2:キャリアアップの武器に!転職や昇進で有利に
履歴書に書ける公的な資格は、キャリア形成において強力な武器になります。特に専門性を重視する病院や施設への転職では、大きなアピールポイントとなるでしょう。
メリット3:資格手当による給与アップの可能性
実際にはまだまだ少ないですが、施設によっては、月数千円~1万円程度の資格手当が支給される場合があります。給与アップに直結するのは大きなモチベーションになりますよね。
メリット4:体系的な学習で、臨床での判断力・技術力が向上
認定取得の過程で、その分野の知識を基礎から応用まで体系的に学び直せます。これにより、日々の臨床での評価や治療における判断の根拠が明確になり、より質の高いリハビリテーションを提供できるようになります。
メリット5:同じ志を持つ仲間とのネットワークが広がる
研修会や学術大会を通じて、同じ分野の専門性を追求する全国の理学療法士と繋がることができます。情報交換や相談ができる仲間は、かけがえのない財産になるでしょう。
メリット6 : 学会発表や研修会講師への道が開ける
専門性が認められることで、学会での発表や、地域の勉強会で講師を依頼される機会が増えます。アウトプットすることで、さらに知識が深まるという好循環が生まれます。
知っておくべきデメリットと注意点
もちろん、良いことばかりではありません。取得を目指す前に、現実的な注意点も知っておきましょう。
- 取得にかかる費用と時間
研修会の受講料や受験料などで、総額10万円~20万円程度の費用がかかります。また、休日に研修を受ける必要がある等プライベートな時間も必要になります。 - 5年ごとの資格更新が必要
資格は取りっぱなしではありません。5年ごとに更新が必要で、そのためには学会参加や研修会受講などのポイントを貯めなければなりません。常に学び続ける姿勢が求められます。 - 資格取得が必ずしも給与に直結するわけではない
メリットとして給与アップを挙げましたが、残念ながら全ての職場で手当が付くわけではありません。事前に勤務先の就業規則を確認しておくことが大切です。
【新制度版】認定理学療法士になるための完全ロードマップ
それでは、新制度における認定理学療法士の取得までの具体的な流れを解説します。
- 【前提】日本理学療法士協会(JPTA)に入会する
認定制度は協会員向けの制度です。未入会の方はまず入会手続きを行いましょう。 - 【土台】登録理学療法士を取得する
認定を目指すための必須の土台資格です。前期・後期研修を修了することで取得できます。 - 【共通研修】指定研修カリキュラムを受講する(e-ラーニング)
協会が主催する**12コマ(18時間)**のe-ラーニングです。医療安全やチーム医療論など、認定理学療法士として必須の共通知識を学びます。 - 【専門研修】臨床認定カリキュラムを受講する
希望分野の専門知識を学ぶ中心的な研修です。協会が認定した教育機関(大学や病院など)で、**必須15コマ+選択5コマ以上(計22.5時間以上)**の講義を受けます。 - 【要件】日本理学療法学術研修大会に参加する
年に1度開催される学術大会に全日程参加することが申請要件の一つです。 - 【最終関門】認定試験に合格する
上記のステップを全てクリアすると、受験資格が得られます。全国のテストセンターで受験可能な**CBT方式(コンピュータ試験)**に合格することで、晴れて認定理学療法士となります。
「認定理学療法士」と「専門理学療法士」の違いとは?
新制度を理解する上で、専門理学療法士との関係性の変化は非常に重要です。
公式資料では、両者の関係は「階層性ではなく、並列性」と明記されました。つまり、単純な上下関係ではなく、役割が異なる専門家として位置づけられたのです。
- 認定理学療法士 = 臨床実践のスペシャリスト(認定看護師がモデル)
- 専門理学療法士 = 学問・研究・教育のエキスパート(専門医がモデル)
臨床での実践能力を極めたいなら「認定」、それに加えて研究や教育といった学術的な役割を担いたいなら「専門」を目指す、というキャリアパスが明確になりました。
ただし、専門理学療法士を受験するためには、関連分野の認定理学療法士資格の取得が前提となります。まずは臨床のスペシャリストである「認定」を取得し、その上で次のキャリアとして「専門」を目指すというステップは変わりません。
まとめ
今回は、2022年度からリニューアルされた新制度に基づき、認定理学療法士について解説しました。
【本記事のポイント】
- 認定理学療法士は全21分野で構成される(2022年時点)
- 役割は「臨床実践のスペシャリスト」と明確化
- 症例報告は不要になり、研修と試験中心の制度に
- 取得にはまず「登録理学療法士」になる必要がある
自分に合った認定分野はどれ?失敗しない選び方 3ステップ
「種類は分かったけど、結局どれを選べばいいの?」という方のために、選び方のヒントを3つのステップでご紹介します。
- Step1:これまでの臨床経験と「面白い」と感じる領域を棚卸しする
あなたが今までに担当してきた患者さんで、特に「もっと良くしたい!」と熱中したケースは何でしたか? 整形外科疾患ですか? それとも脳卒中の患者さんでしたか? あなたの「知的好奇心」が向かう先が、最も良い選択肢です。 - Step2:5年後、10年後の理想の働き方を想像する
将来、あなたはどこで、どんな理学療法士になっていたいですか?
「スポーツチームで働きたい」→ スポーツ理学療法
「地域で頼られる存在になりたい」→ 地域理学療法、介護予防
「病院で管理職を目指したい」→ 管理・運営
このように、未来の自分から逆算すると考えやすくなります。 - Step3:興味のある分野の研修会や勉強会にまず参加してみる
いきなり認定を目指すのではなく、まずは気になる分野の研修会に足を運んでみましょう。そこで得られる情報や出会いが、あなたの決意を固めるきっかけになるはずです。
認定理学療法士に関するQ&A
最後に、よくある質問にお答えします。
Q1. 取得までにかかる総費用はどれくらい?
A. 受講する研修会などにもよりますが、合計で15万円前後を見ておくと良いでしょう。(内訳:指定研修受講料 約7万円、症例指導料 約1万円、受験料 約2万円、その他諸経費など)
Q2. 働きながらでも取得できますか?勉強時間は?
A. ほとんどの方が働きながら取得しています。ただし、休日に研修を受けたり、仕事終わりにレポートを作成したりする必要があるため、計画的な時間管理が不可欠です。
Q3. 認定試験の合格率はどのくらいですか?
A. 分野にもよりますが、おおむね70%~80%程度と言われています。しっかりと準備すれば、十分に合格を狙える試験です。
Q4. 履歴書にはどのように記載すればアピールできますか?
A. 資格欄に「認定理学療法士(〇〇)」と正式名称で記載します。自己PR欄では、その資格を活かして「貴院の〇〇領域でどのように貢献できるか」を具体的に書くと、採用担当者に熱意が伝わります。
ここまで読んでいただきありがとうございました。