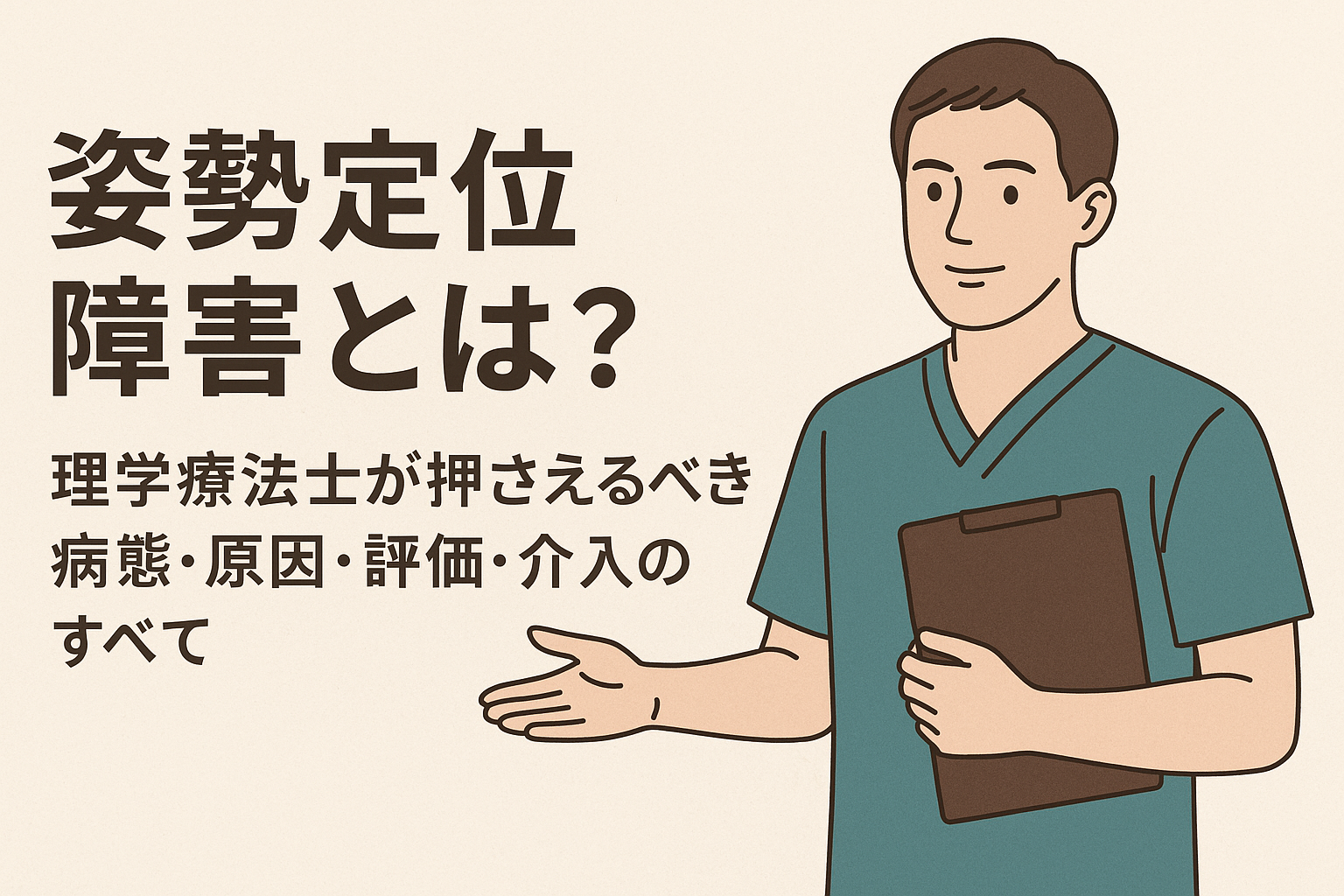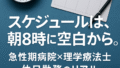はじめに
理学療法士として教育の現場に立つとき、学生や新人に効果的なフィードバックを提供することが、彼らの成長にとって非常に重要なことと思います。効果的なフィードバックは、ただの指摘ではなく、学びを深め、自信を持たせるための貴重な機会です。
この記事では、理学療法士教育者として、どのようにフィードバックを行えば学生や新人の成長を促すことができるのか、実践的な方法とコツを考えていきます。
フィードバックの重要性とは?
フィードバックは、学生や新人理学療法士の成長を支える非常に重要な要素です。理学療法士としての実技や知識を深めるためには、自己評価だけでなく、外部からのフィードバックが不可欠です。しかし、どのようなフィードバックが効果的なのか、どのタイミングで行うべきかを理解していることが、教育者にとって重要だと思います。
フィードバックの役割と目的
フィードバックは、学生や新人が自分の行動や知識を振り返り、改善するためのヒントを提供するものです。フィードバックの主な目的は以下の通りです。
• 自己認識の向上
フィードバックを受けることで、自分では気づかなかった課題や強みを認識することができます。
• 学びの方向性を示す
学生や新人が次にどのように取り組むべきか、学習の方向性を明確にすることができます。
• モチベーションの向上
ポジティブなフィードバックは、自信を持たせ、さらなる努力を促す効果があります。
不適切なフィードバックが引き起こす問題
フィードバックが不適切であると、学生や新人は自信を失い、成長にブレーキをかけてしまう可能性があります。例えば、ただ単に「できていない」といったネガティブな指摘だけでは、改善点が明確にならず、何をどうすべきかが分からなくなってしまいます。フィードバックは学びの手助けであるべきで、感情を逆撫でしないように注意する必要があります。
効果的なフィードバックの基本
具体的な指摘を心掛ける
フィードバックの基本は、具体的な指摘です。抽象的な表現や漠然とした評価では、学生や新人が何を改善すべきかを理解できません。「もっと頑張って」や「頑張りが足りない」というフィードバックは、学生にとっては方向性を見失わせる原因となります。
具体的なフィードバックを行うためには、観察した行動や結果に基づいた指摘を行いましょう。
以下に具体的なフィードバックの例を考えてみました。
例:

今日の実技では、患者さんの姿勢が崩れやすかった部分がありました。
特に立ち上がる際、足の位置が前に出過ぎているため、円背の方ではお尻を持ち上げる際に負担がかかっています。
この部分を意識して、次回は足部の位置をを少し後ろに引くようにするとスムーズに立ち上がり動作が可能になるかもしれませんね。
このように、具体的な動作や状況を指摘することで、学生や新人はどの部分を改善すべきかが明確になります。
ポジティブフィードバックと改善点のバランス
フィードバックはポジティブな面と改善点の両方を伝えることが大切です。ポジティブなフィードバックは、学生や新人に自信を与え、次のステップへの意欲を高めます。しかし、改善点も必ず伝えなければなりません。
バランスを取るための「サンドイッチ法」という手技が有効かもしれませんね。これは、ポジティブなフィードバック、改善点、再度ポジティブなフィードバックの順で伝える方法です。こうすることで、改善点を指摘しても、相手が受け入れやすくなります。
例:

今日は患者さんとのコミュニケーションが非常に良かったですね。特に、患者さんに安心感を与える対応ができていました。
しかし、実技の部分で少し動作が遅く、患者さんに負担がかかってしまいました。
次回は、動作をスムーズにするための練習をするとより良くなりますね。全体的に、患者さんの反応が良かったので、今後もその点を意識して取り組んでいきましょう。
フィードバックのタイミングを見極める
フィードバックのタイミングも非常に重要です。遅すぎるフィードバックは、学生や新人が自分の行動とフィードバックを関連付けるのが難しくなり、効果が薄くなってしまいます。
良いタイミングでフィードバックを行うためには、以下のポイントを意識しましょう。
• 即時性
実技後すぐにフィードバックを行うと、学生や新人がその時の行動とフィードバックを関連付けやすくなります。
• 反復的なフィードバック
一度のフィードバックで完璧な改善は難しいため、定期的にフィードバックを繰り返し行い、進捗を確認することが大切です。
フィードバックを上手に伝えるコツ
肯定的な言葉を使う
フィードバックの中で重要なのは、肯定的な言葉を使うことです。「できていない」「失敗」といったネガティブな表現は避け、ポジティブな改善点に焦点を当てましょう。批判的な言葉を使わずに、改善点を前向きに伝えることで、学生や新人の自信を損なうことなく、成長を促すことができます。
例:

今回の車椅子移乗介助では、ベッドと車椅子との距離が遠すぎたので、その点を意識して修正していけばさらに良くなりますよ。
具体的かつ簡潔に伝える
冗長にならないよう、伝えたいことを簡潔にまとめることも大切です。長々と説明をするよりも、要点を絞って伝える方が、学生や新人は理解しやすくなります。ポイントを絞り込むことで、フィードバックの効果を最大化することができます。
聴く姿勢を大切にする
フィードバックは一方通行ではなく、相手の意見や考えを聴く姿勢も重要です。学生や新人は、フィードバックを受けるだけでなく、自分の意見や質問を持っていることが多いです。対話の場を作り、相手の考えを尊重することで、より良いフィードバックのやりとりが可能になります。
フィードバックを受けた後の対応
フィードバックは、受け入れた後にどのように行動するかが最も重要です。学生や新人がフィードバックを受けてどのように改善するかを考え、実行に移すことが、成長の鍵となります。
自分で解決策を見つける
フィードバックを受けた学生や新人には、自分で解決策を見つけるように促しましょう。解決策を自分で考え、実行することで、学びが深まり、次のステップに進むための力を養うことができます。
例:

次回の車椅子移乗介助ではどうすれば動作が改善できると思う?さっき自分で考えた方法を試してみて、またフィードバックをしていこう。
定期的なフォローアップ
フィードバックは一度きりではなく、定期的にフォローアップを行うことが大切です。改善点に対してどのように取り組んでいるのかを確認し、次に進むための支援を行いましょう。
フィードバック成功例と失敗例との違い
成功例:良いフィードバックで成長を促進
ある新人理学療法士が、初めての実技後にフィードバックを受けた際、「今日の患者さんとの関わりは非常に良かったです」とポジティブなフィードバックを伝えました。さらに、改善点を明確に指摘し、その後数回の実技で大きな改善が見られました。
失敗例:フィードバックが効果的でなかったケース
一方で、過去にフィードバックが不十分だった事例では、この時、学生に対して抽象的なフィードバック(「もっと頑張ってください」など)しか伝えなかったため、学生は自分のどこを改善すべきかがわからず、同じミスを繰り返してしまいました。
このような状況では、学生が自信を失い、学びの意欲が低下する可能性もあります。具体的な指摘と明確な改善策を伝えることの重要性が浮き彫りになったケースでした。
このような失敗を防ぐためには、フィードバックを具体的で効果的に伝えること、そしてその後に適切なサポートを提供することが必要ですね。
学生や新人へのモチベーションの高め方
フィードバックを通じて学生や新人を成長させるためには、モチベーションを高めることも欠かせません。彼らが自ら進んで学び、成長するように導くためには、以下の方法を意識しましょう。
目標設定をサポートする
学生や新人に対して具体的な目標設定を行い、それに向かって進む方向性を明確に示すことが、モチベーションを高める鍵です。短期目標と長期目標を設定し、それを達成するためのステップを一緒に考え、進捗を定期的に確認することで、成長の実感を得られるようにしましょう。
例:

次回の実技では、患者さんとのコミュニケーションをスムーズにすることを目標にしましょう。
それに向けて、まずは自己紹介のタイミングを工夫し、患者さんに安心感を与えることから始めてみてください。
成長を認めること
小さな改善や努力でもしっかりと認め、称賛することが重要です。フィードバックの中で成長を認め、努力を褒めることで、学生や新人の自信を高め、次に進む意欲を引き出すことができます。
例:

少し前に比べて、患者さんに対する説明がとても明確になりましたね。その努力がしっかりと結果に繋がってきています。素晴らしい成長です!
失敗を恐れさせない
失敗は成長の一部であり、学びの過程において避けられないものです。学生や新人が失敗を恐れずに挑戦できるよう、失敗を受け入れる文化を作ることが大切です。失敗を次の成長のチャンスと捉え、どのように改善できるかを一緒に考えることで、ポジティブな学びの循環を作りましょう。
例:

今回の車椅子移乗介助では、少しうまくいかなかった部分もありましたが、それは学びの一環です。次回はその経験を活かして、より良いアプローチを試してみましょう。
フィードバック後の成長を促すために必要な環境作り
開かれたコミュニケーションの場を作る
フィードバックを受けた学生や新人が自由に質問でき、自己評価を話すことができる環境を整えることが重要です。開かれたコミュニケーションを促進し、疑問点や不安を共有できる場を提供することで、学生や新人は安心して学び、フィードバックを次に活かすことができます。
フィードバックを共有する文化を作る
フィードバックは一対一のやり取りだけでなく、グループ内で共有することも有効です。チームメンバーがフィードバックを共有することで、他の学生や新人がどのように成長しているのかを知ることができ、共に学び合う雰囲気を作り出せます。また、フィードバックを通じて、異なる視点を得ることができるため、より幅広い学びを提供することができます。
例:

今日の実技の後で、全員でフィードバックをシェアしてみましょう。
それぞれの学びがどのように成長に繋がったかを確認し合うことが、全員の成長を促すきっかけになります。
⸻
まとめ
効果的なフィードバックは、学生や新人理学療法士の成長を加速させる強力な手段となります。具体的で建設的なフィードバックを提供し、ポジティブな側面を強調しながら、改善点を指摘することで、学びの方向性を示すことができます。また、フィードバックを通じて学生や新人が自信を持ち、挑戦し続けることができるような環境を作ることが、教育者としての責任だと思っています。
フィードバックは単なる評価にとどまらず、成長のサポートであることを忘れず、学生や新人を導いていきましょう。そして、そのプロセスを楽しみながら共に学び合うことが、教育者としての最も大きな喜びとなるはずです。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
学びをより深めたい方へ
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇