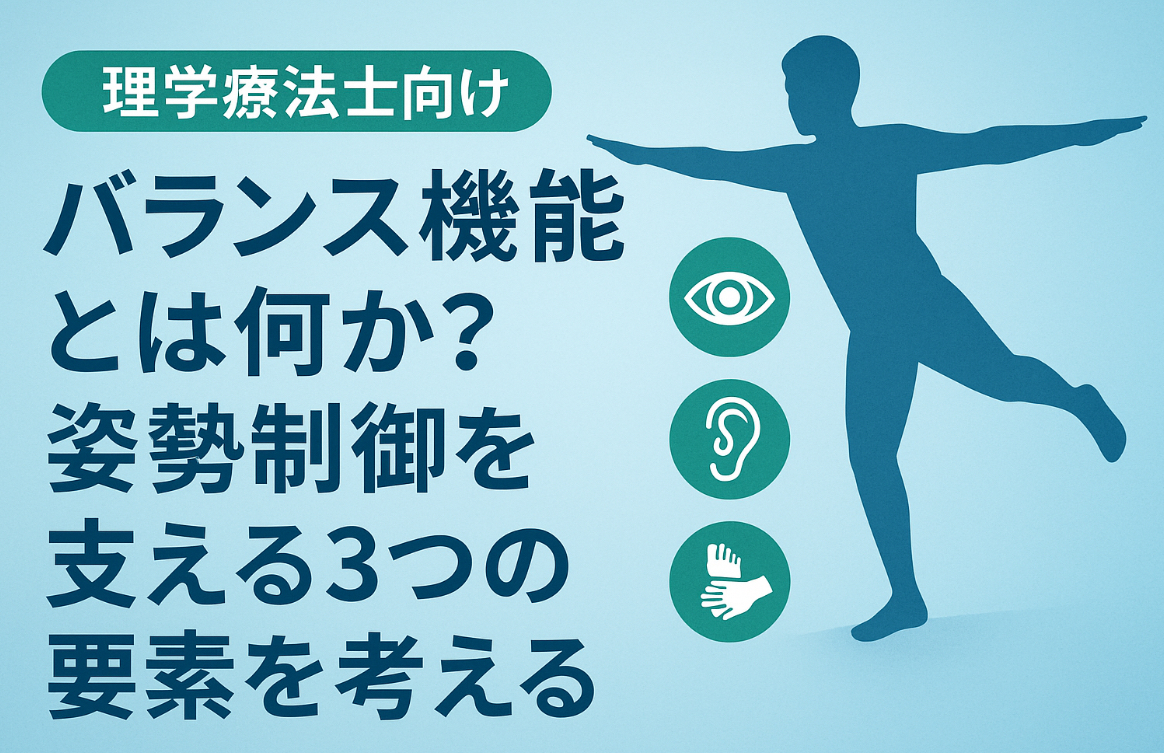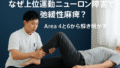はじめに
「この患者さん、なぜこんなにふらつくのだろう?」
臨床で、私たちは日々この問いに向き合います。筋力トレーニングをしても、体幹トレーニングをしても、なかなか改善しない「ふらつき」。その原因を解明する鍵は、**「バランス機能(姿勢制御)」**という複雑で精巧なシステムを正しく理解することにあります。
この記事では、理学療法の根幹とも言える「バランス機能とは何か?」というテーマに絞り、その仕組みを構成する3つの必須要素を徹底的に解説します。この知識は、あなたの臨床での観察眼を鋭くし、アプローチの質を格段に向上させるはずです。
臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

バランス機能(姿勢制御)の正体とは?
まず、言葉の定義から始めましょう。
**バランス機能(姿勢制御)」**とは、静止時(立位、座位など)や動作時(歩行、方向転換など)に、身体の重心を支持基底面(足の裏など体を支えている面)の中に安定して保つための、一連の神経筋システムのことです。
重要なのは、これが単なる「筋力」や「体幹の強さ」だけを指すのではないという点です。バランス機能は、例えるなら**「高精度センサー」「超高速な司令塔」「精鋭の実行部隊」**という3つの部門が連携して働く、身体の一大プロジェクトなのです。
バランスを成り立たせる3つの必須要素
それでは、このプロジェクトを構成する3つの部門を詳しく見ていきましょう。患者さんのふらつきが、どの部門の問題から生じているのかを考えることが、臨床推論の第一歩です。
① 感覚入力(インプット)- 身体の現在地を知る”高精度センサー”
脳が姿勢を制御するためには、まず「今、身体がどのような状態にあるか」という正確な情報が必要です。この情報を収集するのが「感覚入力」システムです。
- 視覚 (Visual System)
- 役割: 周囲の環境(床の水平、壁との距離など)を視覚的に捉え、身体の傾きや位置関係を脳に伝えます。最も情報量が多く、私たちは無意識に視覚に頼ってバランスを取っています。
- 臨床のヒント: 開眼時と閉眼時で立位の安定性に大きな差が出る場合、視覚への依存度が高く、後述する前庭覚や体性感覚の機能低下が隠れている可能性があります。
- 前庭感覚 (Vestibular System)
- 役割: 内耳にある三半規管や耳石器が、頭の回転や直線的な加速度を検知します。「平衡感覚」の要であり、視覚が使えない暗闇や、足場が不安定な場所で特に重要性を増します。
- 臨床のヒント: めまいを訴える患者さんや、頭を動かした時(例:振り返り動作)にふらつきが増強する場合、前庭系の機能評価が必要になります。
- 体性感覚 (Somatosensory System)
- 役割: 皮膚、筋肉、腱、関節にある**固有受容器(Proprioception)**が、身体の位置、動き、地面からの圧力などを感知します。特に立位では、足裏からの情報が極めて重要です。
- 臨床のヒント: 糖尿病性ニューロパチーなどで足裏の感覚が鈍い患者さんや、柔らかいマットの上で極端に不安定になる場合は、体性感覚の入力に問題があると考えられます。
② 中枢での統合(情報処理)- 情報を分析し指令を出す”司令塔”
センサーから送られてきた膨大な情報を瞬時に処理し、「次にどう動くべきか」という最適な運動プランを計画するのが、脳(特に小脳、脳幹、大脳基底核)の役割です。
このプロセスは、ただ情報を受け取るだけではありません。
- 情報の重み付け: 明るい場所では視覚を、足場の悪い場所では前庭覚を重視するなど、状況に応じて各感覚情報の優先順位を判断します。
- 予測的姿勢制御 (APA): これが非常に重要です。例えば、私たちが腕を前に伸ばす時、腕を動かす「前」に、身体が前に倒れないよう無意識に体幹や下肢の筋肉を収縮させています。このような動きを予測して先行的に姿勢を安定させる働きをAPAと呼びます。
- 臨床のヒント: デュアルタスク(何かをしながら歩くなど)で極端にパフォーマンスが落ちる場合、情報処理のキャパシティに問題があるかもしれません。また、動作開始時にふらつく患者さんは、この予測的姿勢制御(APA)の機能低下が疑われます。
③ 運動出力(アウトプット)- 指令を実行する”精鋭部隊”
司令塔からの指令に基づき、実際に筋肉や関節を動かして姿勢を修正・維持するのが「運動出力」です。この反応は、外乱(揺れ)の大きさや速さに応じて、いくつかの戦略を使い分けます。
- 足関節戦略 (Ankle Strategy)
- 概要: 床が硬く、比較的小さくゆっくりとした揺れに対して使われます。足関節を軸に、下腿の前後面の筋肉(前脛骨筋や下腿三頭筋)を使って身体全体を振り子のようにコントロールします。
- 臨床のヒント: 高齢者や足関節に問題を抱える患者さんでは、この戦略が使いにくくなっていることがあります。
- 股関節戦略 (Hip Strategy)
- 概要: より大きく速い揺れや、足場が狭い(平均台の上など)場面で使われます。股関節を素早く屈曲・伸展させることで、上半身と下半身を逆方向に動かし、重心を支持基底面内に収めます。
- 臨床のヒント: この戦略を過剰に使う患者さんは、足関節戦略がうまく使えていない代償である可能性も考えられます。
- ステッピング戦略 (Stepping Strategy)
- 概要: 上記2つの戦略でも対応できないほど重心が大きく移動し、転倒の危険が迫った時に使われる最終手段です。とっさに足を踏み出して支持基底面そのものを広げ、新たな姿勢を確保します。
- 臨床のヒント: この反応が遅れたり、足がうまく出なかったりすることは、転倒に直結します。パーキンソン病の「すくみ足」などは、この戦略の障害と深く関連します。
まとめ:なぜ「バランス機能」の理解が臨床を変えるのか?
ここまで見てきたように、「バランス機能」は単一の能力ではなく、「感覚入力」「中枢処理」「運動出力」という3つの要素が相互に連携しあって成り立つ、非常に複雑なシステムです。
このフレームワークを持って患者さんを観察することで、「ふらつき」という一つの現象を、
- 「センサー(感覚)の問題か?」
- 「司令塔(脳の情報処理)の問題か?」
- 「実行部隊(運動戦略)の問題か?」
というように、多角的に分析できるようになります。
「筋力がないから」という一つの結論で終わらせず、「なぜ、この場面で、このようにふらつくのか?」と一歩踏み込んで考えること。それこそが、私たち理学療法士の専門性です。まずはこの3つの要素を意識して、明日からの臨床に臨んでみてください。患者さんを見る目が、きっと変わるはずです。