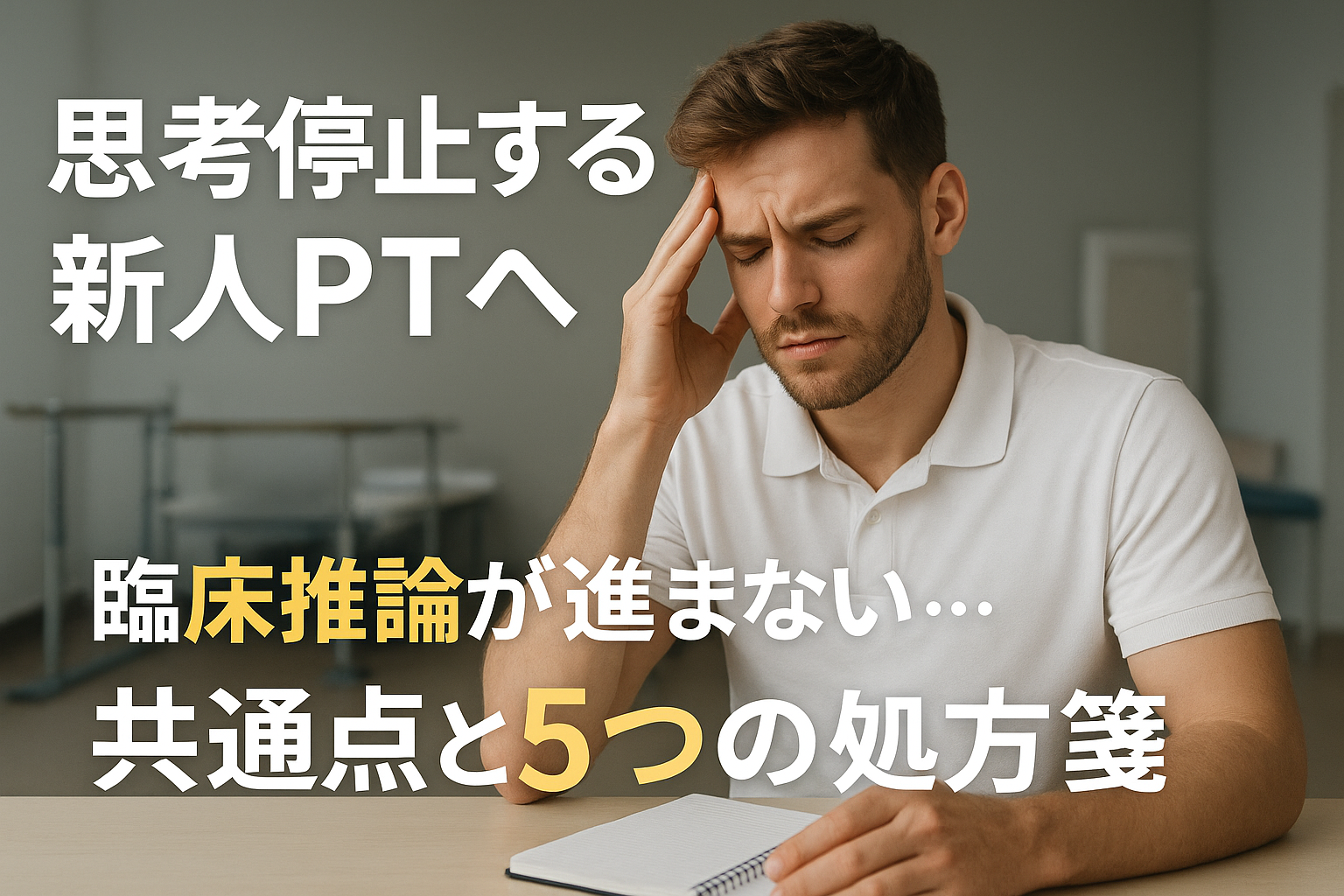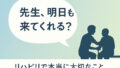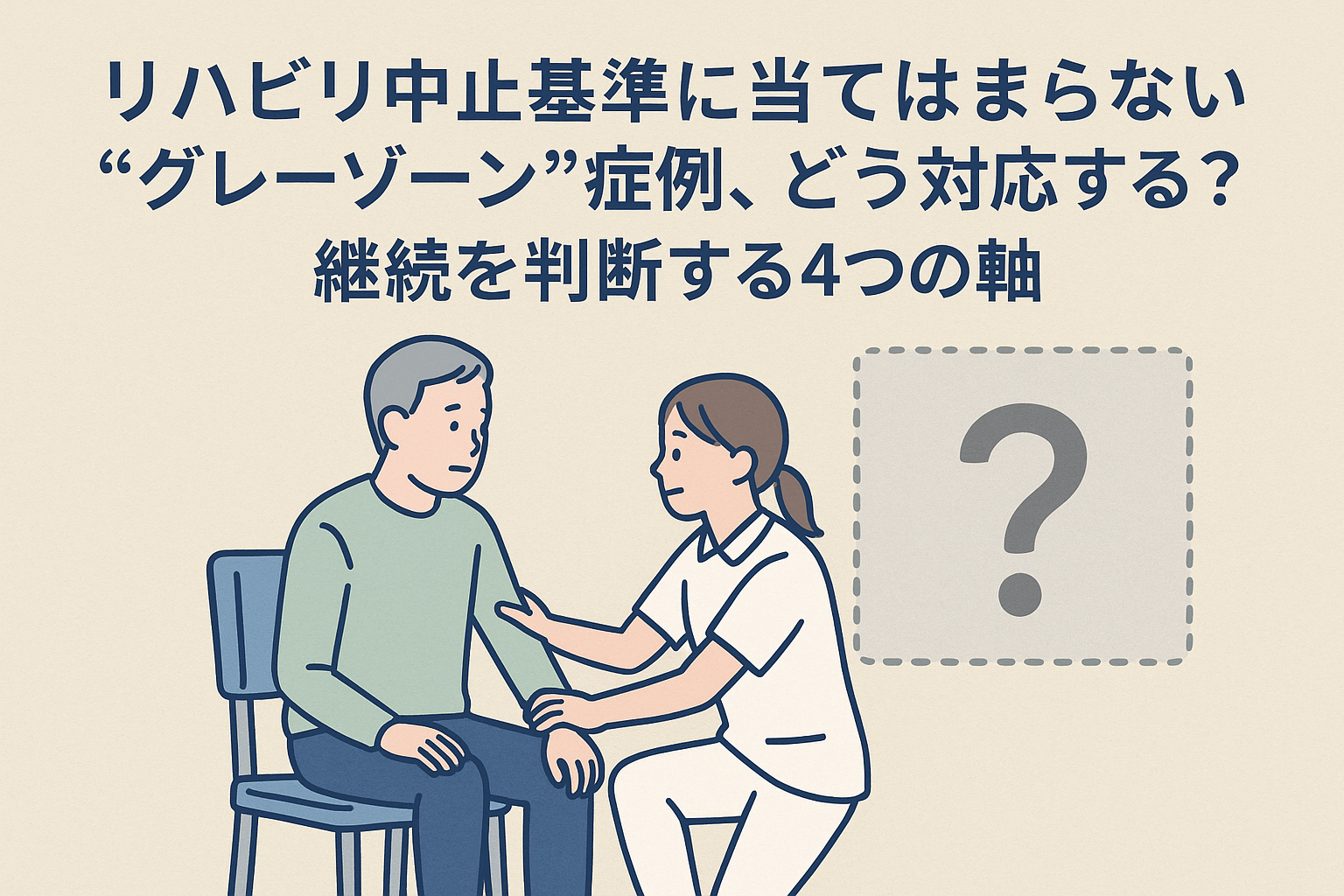その「頭が真っ白」、あなただけじゃありません
「患者さんを目の前にして、次に何を評価すればいいか分からなくなった…」
「集めた情報が多すぎて、何が問題なのか整理できない…」
臨床に出たばかりの新人理学療法士(PT)なら、一度はこんな経験があるのではないでしょうか。目の前の患者さんを良くしたいという気持ちは人一倍なのに、思考がフリーズしてしまう。
この「思考停止」は、多くのPTが通る道であり、決してあなただけが経験している悩みではありません。私自身、今もまだ陥ることがあります…。
この記事では、多くの新人PTが陥る「思考停止」の原因を深掘りし、明日からの臨床ですぐに使える具体的な5つの対策を「処方箋」としてご紹介します。
この記事を読み終える頃には、なぜ自分の思考が止まっていたのかが明確になり、自信を持って患者さんと向き合うための「思考のコンパス」を手に入れているはずです。
日々の臨床の一助となりますように。
臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

あなたはどのタイプ?臨床で思考が止まる「3つの典型場面」
まずは、多くの新人PTが「思考停止」に陥りやすい典型的な場面を3つに分けて考えてみます。まずは自分がどこに悩んでいるか、つまづいているかを知る必要があります。
「これ、自分のことだ!」と感じる場面があるかもしれません。
- 場面1:問診・情報収集「何を聞けばいいか分からない…」
カルテ情報は読んだけれど、患者さんを前にすると、的確な質問が思い浮かばない。会話が途切れてしまい、焦りだけが募る場面です。 - 場面2:評価・検査「どの手技を選ぶ?結果の解釈は?」
ROMやMMTなど基本的な評価はできるものの、「なぜこの評価が必要なのか」という目的が曖昧なまま進めてしまう。得られた結果をどう解釈し、次の評価に繋げればいいか分からなくなります。 - 場面3:考察・プランニング「情報が繋がらず、治療が立てられない…」
評価で得た情報がバラバラの点のまま。それらを線で結びつけ、患者さんの全体像を捉えられないため、的確な治療プログラムを立案できずに悩んでしまいます。
なぜ思考は停止するのか?新人が陥る「5つの思考の罠」
では、なぜこのような思考停止が起きてしまうのでしょうか。そこには、新人PTが陥りやすい5つの「思考の罠」が潜んでいます。
罠①:「完璧な正解」を探してしまう
教科書で学んだ「正解」を臨床現場で探そうとしていませんか?患者さんは一人ひとり異なり、教科書通りの症例は存在しません。完璧を求めるあまり、目の前の患者さんの小さな変化やサインを見逃し、思考が硬直してしまうのです。
罠②:「情報過多」で脳がパンク
「とにかく全部評価しなければ」と、あらゆる検査を網羅しようとしていませんか?情報が多すぎると、脳は処理能力の限界を超え、かえって重要な情報を見失ってしまいます。情報の洪水に溺れ、思考が停止するのは自然なことです。
罠③:「地図なき航海」状態
「この評価は何のために行うのか?」という目的が不明確なまま、ただ手順をこなすだけになっていませんか?ゴールが見えないまま進む評価は、まるで地図を持たずに航海に出るようなもの。すぐに道に迷い、立ち往生してしまいます。
罠④:「仮説なき評価」の悪循環
臨床推論の基本は「仮説→検証」のサイクルです。しかし、「とりあえず評価」から始めてしまうと、「なぜこの結果が出たのか」「次に何をすべきか」という思考に繋がりません。目的のない評価は、ただの作業になってしまいます。
罠⑤:「知識・経験の引き出し」が少ない
これは新人であれば誰もが抱える課題です。経験豊富な先輩PTは、無数の「引き出し(知識・経験のパターン)」を持っています。目の前の現象を見て、瞬時に類似ケースを引き出しから取り出し、仮説を立てることができるのです。引き出しが少ないうちは、目の前の現象と知識が結びつかず、思考が止まりがちになります。
思考停止から抜け出す!明日から使える「5つの処方箋(対策)」
お待たせしました。ここからは、思考停止という壁を乗り越えるための具体的な「処方箋」を5つご紹介します。すべてを一度にやる必要はありません。まずは1つ、試せそうなものから臨床に取り入れてみてください。
処方箋①:思考の羅針盤「ICF」に立ち返る
情報整理に困ったら、一度立ち止まって**ICF(国際生活機能分類)**のフレームワークに当てはめてみましょう。
「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の各レベルで情報を整理することで、患者さんの全体像がクリアになります。
「今、自分はどの部分を評価しているのか?」「この“活動”の制限は、どの“心身機能”の問題から来ているのか?」と、思考の現在地を確認する羅針盤としてICFを活用しましょう。
処方箋②:「仮説→検証」のミニサイクルを回す
壮大な仮説を立てる必要はありません。ごく小さな「もし〜なら」を繰り返すのです。
例:「もし、この患者さんの歩行時の膝折れが“大腿四頭筋の筋力低下”によるものなら、MMTで3レベル以下のはずだ」
→実際にMMTを測定して検証する。
この小さなサイクルを回すことで、評価が「作業」から「思考のプロセス」に変わります。
処方箋③:「今日のゴールは1つ」と割り切る勇気
「全部見よう」とする完璧主義を手放しましょう。特に初期評価では、**「今日は、患者さんが最も困っているADL動作を1つだけ分析する」**と目標を絞ることが有効です。
例えば、「立ち上がり」に絞ると決めれば、「そのために必要な関節可動域は?」「必要な筋力は?」「どんな代償動作が出ている?」と、見るべきポイントが自然と明確になります。
処方箋④:先輩の思考を「完コピ」してみる
優れた先輩PTの評価やアプローチは、思考の「型」の宝庫です。先輩が患者さんにかける言葉、評価の順番、触り方などを徹底的に観察し、真似てみましょう。
「なぜ、あの場面でその質問をしたんですか?」と直接聞いてみるのも効果的です。まずは「型」をインストールすることで、自分の中に思考のフレームワークが構築されていきます。
処方箋⑤:成長を加速させる「1行振り返りメモ」
評価や治療が終わった後、5分でいいので振り返りの時間を作りましょう。書くことはシンプルで構いません。
- 今日、思考が止まったのはどの場面?
- なぜ止まったんだろう?(例:仮説がなかったから)
- 次ならどうする?(例:最初にADL上の問題点を1つに絞る)
この「1行振り返り」を続けるだけで、自分の思考のクセが分かり、次への具体的な対策が立てられるようになります。これが最も効果的な成長のサイクルです。
【実践例】思考停止を乗り越えた、ある新人PTのケーススタディ
【Before】
脳卒中後遺症の患者さんを担当したAさん。麻痺側の上下肢機能、高次脳機能、ADLなど、評価項目が多すぎて何から手をつければいいか混乱。毎日、評価をこなすだけで精一杯になり、それらの情報が治療にどう繋がるのか分からず、思考停止に陥っていました。
【転機】
先輩から「処方箋③」と似たアドバイスを受けました。「この患者さんが退院後、自宅で一番やりたいことは何?そのために、今一番の壁になってる動作を1つだけ教えて」と言われ、Aさんは「トイレでのズボンの上げ下ろし」に絞ることを決意。
【After】
ゴールが明確になったことで、見るべきポイントがクリアになりました。「ズボンを上げるために必要な立位保持能力は?」「そのために必要な体幹と下肢の筋力は?」と、「仮説→検証」のミニサイクル(処方箋②)が回り始めました。結果、体幹機能へのアプローチが最も重要であると結論づけ、具体的な治療プログラムを自信を持って立案できるようになった。
まとめ:思考が止まるのは、あなたが真剣な証拠
臨床で思考が止まってしまうのは、あなたが患者さんと真剣に向き合い、何とかして良くしたいと考えているからです。それは、プロフェッショナルとして成長している何よりの証拠です。
大切なのは、「思考が止まったこと」を責めるのではなく、「止まった後にどう立て直すか」を知っていることです。
今回ご紹介した5つの処方箋は、あなたの臨床における強力な武器になります。まずは明日から、一番試しやすいものを1つだけ選んで、実践してみてください。その小さな一歩が、思考停止の壁を乗り越え、理学療法士としての成長を加速させてくれるはずです。