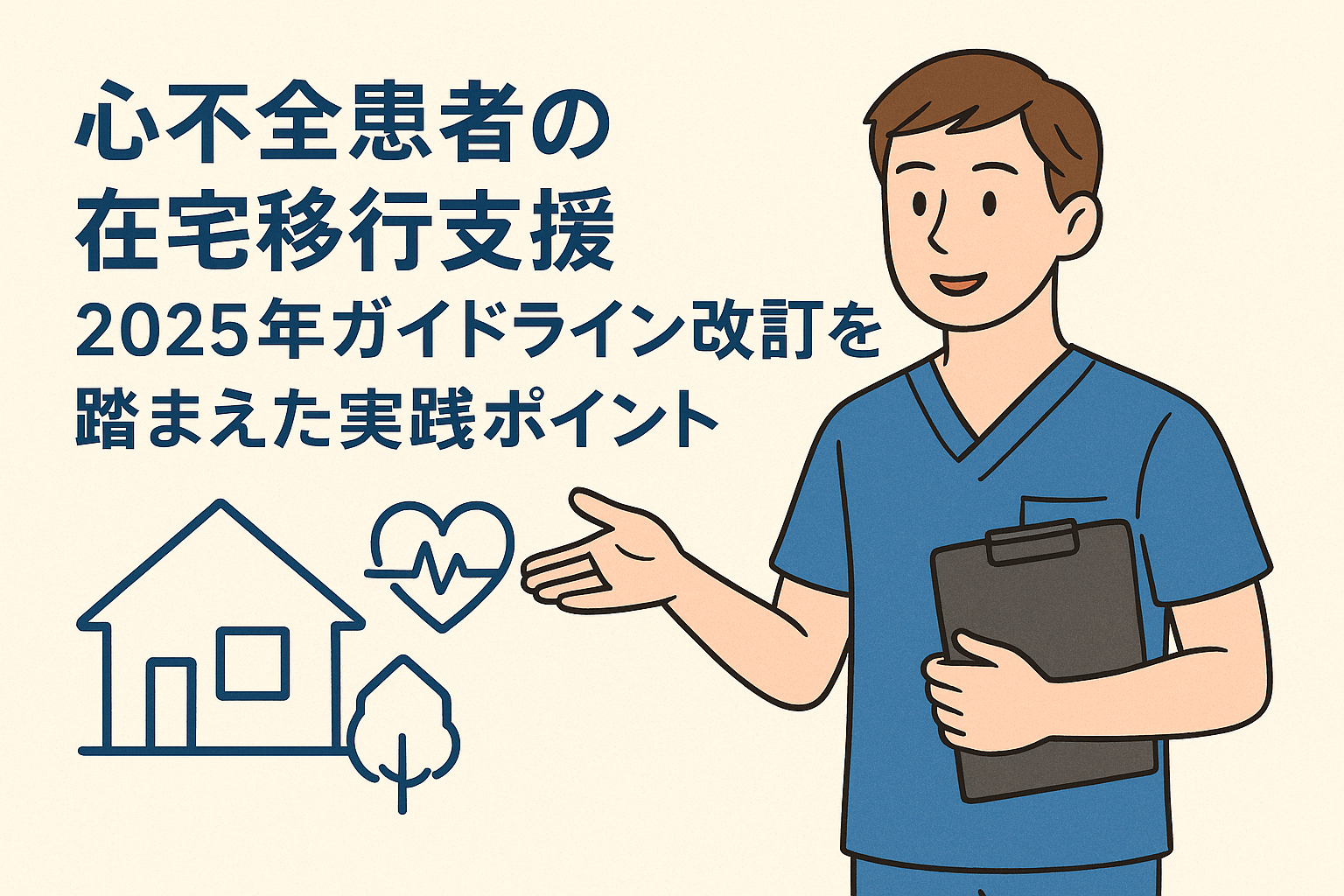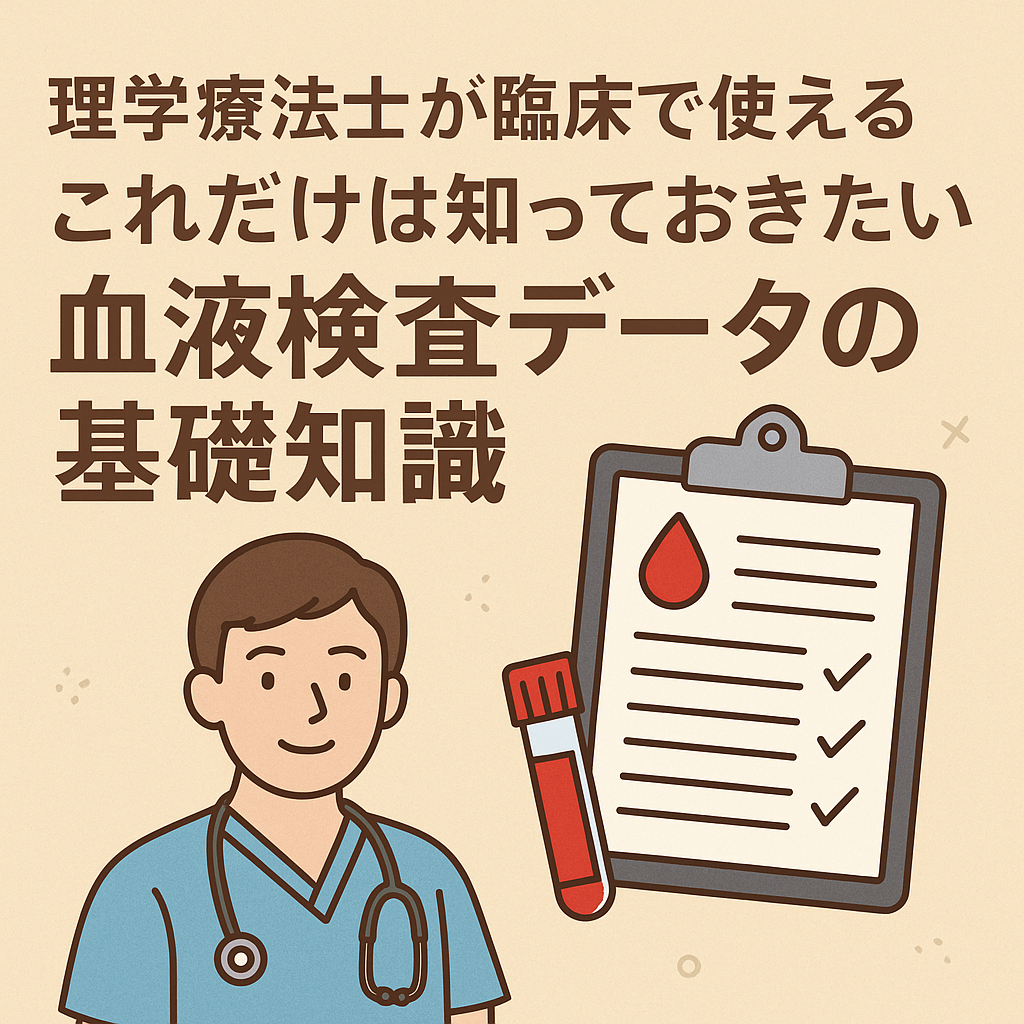1. はじめに:評価はできるのに“つながらない”という悩み
理学療法士として臨床に立ち始めたばかりの頃、多くの新人PTがぶつかる壁のひとつに、「評価はできるけど、それをどう臨床につなげればいいのかわからない」という問題があります。
ROM(関節可動域)、MMT(徒手筋力テスト)、歩行分析やバランステスト…。
たしかに評価項目は一通り行っているはずなのに、それらがバラバラに感じられ、「結局この人に何をすればいいのか」「どこが最も問題なのか」が見えづらい。
これは決してあなた一人の悩みではありません。
多くの新人や若手セラピストが同じ壁に直面しています。
僕自身も、評価表を前にして途方に暮れたことが何度もありました。(なんなら今でもあります。)
- 「評価をどう“つなげる”のか」
- 「統合と解釈はどう進めればいいのか」
について、3つの具体的なステップでわかりやすく解説していきます。
経験やセンスだけに頼らない、“考え方”の整理として活用してみてください。
2. Step1:評価項目を“因果関係”でつなげてみる
評価が“意味を持たない”ように感じられる一番の原因は、評価項目を「情報の羅列」として扱っていることにあります。
新人のうちは「すべての評価を抜けなく記録すること」が目的になりがちで、結果として情報同士がつながらず、何をどう解釈すればいいか分からなくなるのです。
たとえば、以下のような評価項目を想像してみてください。
- 中殿筋MMT:3(Fair)
- 立位保持時に体幹の左右揺れ
- 片脚立位:3秒未満(不安定)
- 10m歩行:側方偏位あり、左へ流れる
- TUG:21秒、起立時にふらつき
これをただ「筋力が弱い」「バランス不良」「歩行不安定」と断片的に見るのではなく、
**「中殿筋の筋力低下」→「骨盤の側方安定性の低下」→「立位や歩行時の重心コントロール不良」**というように、“因果関係”のストーリーを作ってみるのがポイントです。
こうした因果構造を意識することで、「この不安定さは中殿筋の筋力低下に起因しているのではないか」「介入するならまず骨盤の安定性からアプローチしよう」といった推論が生まれます。
評価項目に“矢印”を書き込んでストーリー化する癖をつけるだけでも、頭の中の整理がぐっとしやすくなりますよ。
3. Step2:仮説を立てて、評価で検証する視点を持つ
新人のうちは「評価=とりあえず一通り測るもの」という認識になりがちですが、評価の本質は「仮説検証」です。
つまり、

この人が〇〇できないのは□□が原因かもしれない
という仮説を持ち、それを評価によって検証していくプロセスです。
たとえば、ある患者さんの立ち上がり動作を観察してみると、「右側に大きく偏って立ち上がる」様子が見られたとします。
ここで、「右優位の起立は、左下肢の筋力低下が関係しているのでは?」という仮説が立ちます。
この仮説をもとに、以下のように評価を展開していきます。
- MMTで左大腿四頭筋や大臀筋の筋力を測定
- 立ち上がりの荷重量の左右差を簡易的に評価
- 重心動揺計などで荷重バランスを確認(可能であれば)
このように、**“仮説→評価→修正→再検討”**というサイクルがあると、評価項目が意味を持って機能します。
また、この流れは治療戦略を考える上でも非常に重要です。
評価を「とりあえず測るもの」から、「考えるための道具」に変えること。
それが、統合と解釈への第一歩です。
4. Step3:ICFで“全体像”を整理する
統合と解釈を行ううえで見落としがちなのが、「身体機能以外の要素」の整理です。
評価で収集した情報をどう構造的に捉えるか、そこで役立つのが**ICF(国際生活機能分類)**です。
ICFは、患者の状態を以下のような視点から整理します:
- 心身機能・構造(筋力・ROM・神経系の状態など)
- 活動(ADLや基本動作)
- 参加(仕事、趣味、社会活動など)
- 環境因子(住環境、支援体制、補装具など)
- 個人因子(年齢、性格、価値観など)
たとえば「杖歩行で自立している」方がいたとしても、
「段差が怖くて外出を控えている」「友人との外食をあきらめている」場合、活動や参加の制限が残っていることになります。
これを見落とすと、「歩ける=リハビリ終了」という早計な判断に陥ってしまいます。
ICFの視点を取り入れることで、患者の“生活全体”を視野に入れた統合と解釈が可能になります。
5. よくあるNGパターンとその処方箋
■ NG例1:すべての評価項目を網羅しようとする
→ 評価の目的が不明瞭になると、「情報収集が目的化」してしまいます。
→ まずは“何を知りたいのか”という仮説から、評価項目を選びましょう。
■ NG例2:解釈が「評価の羅列」で終わっている
→ 「筋力低下あり、関節可動域制限あり、歩行障害あり」では不十分です。
→ 「なぜそうなっているのか?」「その背景にある原因は?」をつなげましょう。
■ NG例3:優先順位がつけられない
→ 全部が問題に見えてしまい、どこから手をつけていいか迷う。
→ 因果関係で評価を整理することで、“上流の要因”が見えてきます。
6. おわりに ― 統合と解釈は、センスではなく思考の訓練である
統合と解釈という言葉には、「経験が必要」「センスが問われる」というイメージがつきまといがちです。
確かに、経験を積めば精度は高まります。
しかし、初学者であっても「考え方」を学ぶことで、その力は少しずつ育てることができます。
今回紹介した3つのステップは、私自身が臨床の中で悩み、試行錯誤しながら身につけてきた“地図”のようなものです。
- 評価を因果関係でつなぐ
- 仮説検証型で評価を行う
- ICFで全体像を俯瞰する
この3つを意識することで、「情報が整理され、解釈の糸口が見える」感覚が持てるようになります。
一つ一つの評価が“意味を持ち”、それが患者さんの生活にどうつながるのかを考える――それが本当の意味での“統合と解釈”です。
焦らず、ひとつずつ。
毎日の臨床を、少しずつ“つなげる”時間にしていきましょう。
もっと知識を深めたい方は「臨床理学Lab」
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇