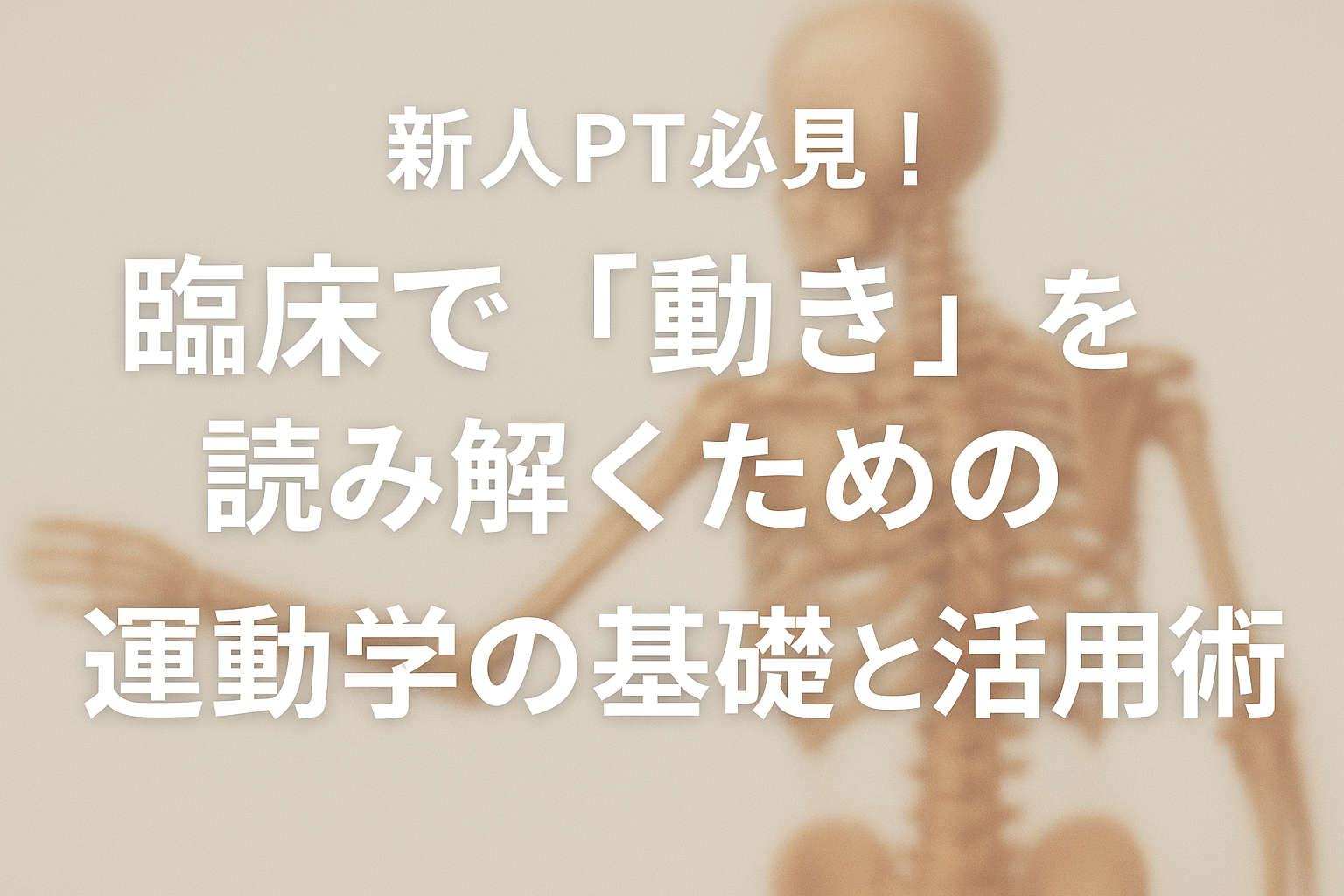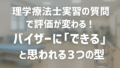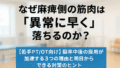はじめに
新人PTの皆さん、日々の臨床お疲れ様です。
学生時代、分厚い教科書で必死に覚えた運動学。しかし、いざ臨床現場に出てみると、「知識と目の前の患者さんがうまくつながらない…」と感じていませんか?
- 「関節可動域(ROM)は測れるけど、なぜその動作ができないのか説明できない」
- 「先輩から『この患者さんの問題点は何だと思う?』と聞かれて、うまく答えられない」
- 「筋力トレーニングやストレッチはしているのに、なかなか動作が改善しない」
もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。
この記事の目的は、運動学を単なる「暗記した知識」から、「患者さんの動きを分析し、治療方針を立てるための強力なツール」に変える方法をお伝えすることです。
この記事を読み終える頃には、あなたはきっと…
- 目の前の患者さんの「できない」原因が、より明確に分析できるようになる
- 「なぜこの評価・治療が必要なのか」を論理的に考え、自信を持ってプログラムを立案できるようになる
はずです。一緒に、臨床で本当に使える運動学を学んでいきましょう!
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

運動学の基礎を再確認!押さえるべき3つの視点
まずは、臨床で「使う」ために最低限押さえておきたい運動学の3つの視点をおさらいします。学生時代に学んだ知識を、臨床の視点でアップデートしていきましょう。
骨運動学(Osteokinematics):関節が「大きく」どう動くか
屈曲、伸展、外転、内転…。これらは関節が「骨レベル」でどのように動くかを示したもので、皆さんもよくご存じのはずです。
しかし、臨床で重要なのは、単に「膝伸展0°」という静的な角度を知ることだけではありません。大切なのは、「実際の動作の中で、必要な可動域が十分に確保されているか?」という視点です。
例えば、歩行の立脚初期(踵接地)では、膝関節がしっかりと伸展している必要があります。もし、膝の伸展制限があれば、踵から接地できずに足裏全体で着地したり、体幹が代償的に傾いたりといった「逸脱動作」につながります。
【臨床での視点】
ROM測定の結果と、実際の動作(歩行、立ち上がりなど)を見比べ、「この動作のこの局面で、必要な関節運動が起きているか?」を評価しましょう。
関節運動学(Arthrokinematics):関節内で「微細に」どう動くか
骨の大きな動き(骨運動学)をスムーズに行うためには、関節内での「微細な動き」が不可欠です。それが「滑り・転がり・回旋」といった関節運動学の要素です。
- 転がり (Rolling): タイヤが地面を転がるような動き
- 滑り (Gliding/Sliding): タイヤがロックして地面を滑るような動き
- 回旋 (Spinning): コマがその場で回るような動き
例えば、肩関節を挙上するとき、上腕骨頭はただ上方向に転がるだけではありません。同時に下方へ「滑る」ことで、骨頭が肩峰(屋根の骨)に衝突するのを防いでいます。
【臨床での視点】
もし、この「滑り」が不足すると、最終可動域で痛み(インピンジメント)が生じたり、可動域そのものが制限されたりします。ROM制限のある患者さんに対しては、「骨の動きだけでなく、関節内の微細な動きに問題があるのではないか?」と考えることが、治療のヒントになります。
筋の作用と「てこの原理」
「この動きの主動作筋は〇〇筋」と覚えるだけでは、臨床では不十分です。動作をコントロールするためには、筋肉の多様な役割を理解する必要があります。特に重要なのが「遠心性収縮」と「固定筋」の役割です。
- 遠心性収縮 (Eccentric Contraction): 筋が引き伸ばされながら力を発揮する状態。「ブレーキ」の役割を果たします。
- 固定筋 (Fixator): ある関節を安定させ、別の部分が効率よく動けるように土台を作る筋肉。
例えば、椅子からゆっくり立ち上がる動作を考えてみましょう。お尻を浮かせる瞬間、重力に負けてドスンと座らないように、大腿四頭筋は遠心性収縮でブレーキをかけながら膝関節の屈曲をコントロールしています。
【臨床での視点】
MMTで筋力は十分あるはずなのに、動作がぎこちない、コントロールが効かないという患者さんは、この遠心性収縮や固定筋の機能が低下している可能性があります。
臨床応用:動作分析で運動学を「使う」
基礎を再確認したところで、いよいよ本題です。日々の臨床で行う「動作分析」こそ、運動学の知識を総動員する応用問題なのです。
「動作分析」は運動学の応用問題
歩行、立ち上がり、寝返りといった一連の動作を、先ほど解説した**「①骨運動学」「②関節運動学」「③筋作用」**の3つの視点に分解して見る訓練をしましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、この視点を持つことで、現象の裏にある原因が見えてきます。
具体例で実践!「立ち上がりができない患者さん」を分析する
新人PTがよく遭遇する「椅子からの立ち上がりが困難な患者さん」を例に、3つの視点で分析してみましょう。
【観察される現象】
- お辞儀が浅く、なかなかお尻が浮かない。
- 手すりに強く頼らないと立てない。
- 立ち上がれても、膝がガクッと揺れる。
【運動学の3つの視点による分析】
| 視点 | 分析(仮説) |
| ① 骨運動学 | 体幹の前傾(股関節屈曲)が不十分ではないか?重心を足部(支持基底面)の上に移動できていないため、立ち上がりの推進力が得られないのかもしれない。 |
| ② 関節運動学 | 股関節や足関節の可動域制限があるのではないか?特に、体幹を前傾させるためには足関節の背屈が必要。ここが硬いと、重心の前方移動が妨げられる。 |
| ③ 筋作用 | 大殿筋や大腿四頭筋の筋力(特に求心性収縮)が不足しているのではないか?また、立ち上がり途中でふらつくのは、体幹の固定筋がうまく働いていない可能性も考えられる。 |
運動学から評価項目を決定する
このように分析(仮説立て)をすることで、次に行うべき評価が論理的に見えてきます。
- 「体幹の前傾が足りないのはなぜ?」→ 股関節や胸椎のROM測定
- 「足関節が硬いのかも?」→ 足関節背屈のROM測定
- 「筋力が足りないのかも?」→ 大殿筋や大腿四頭筋のMMT
- 「そもそも動作のやり方が分からない?」→ 動作パターンの確認、高次脳機能の評価
闇雲に評価するのではなく、**「動作分析で仮説を立て、それを検証するために評価を行う」**という流れを作ることが、デキるセラピストへの第一歩です。
運動学を極めるための具体的なステップ
最後に、日々の臨床で運動学のスキルをさらに高めるための具体的なアクションを3つご紹介します。
触診力を磨く
運動学の知識は、触診によって初めて「生きた知識」になります。教科書の図で見た骨のランドマーク(骨突起)や筋腹を、実際に患者さんや同僚の体で触れてみましょう。「知識」と「身体の感覚」をつなげる唯一の方法が触診です。これができると、関節の微細な動きや筋収縮の様子が手に取るようにわかるようになります。
正常動作を観察しまくる
異常を理解するためには、まず「正常」を知る必要があります。通勤中の電車内や街中で、色々な人の歩き方を観察してみましょう。同僚や友人の「立ち上がり方」を分析してみるのも良い練習です。
正常な動作にも様々なバリエーションがあることを知ることで、患者さんの**異常な動作(逸脱)**にいち早く気づけるようになります。
おすすめの参考図書・動画
知識を深めるためには、良質なインプットも欠かせません。新人PTにおすすめの定番書籍をいくつかご紹介します。
- 『カパンジー機能解剖学』: 関節運動学をビジュアルで理解するなら必読の書です。
- 『筋骨格系のキネシオロジー』: 動作と筋活動の関係を、科学的根拠に基づいて詳細に解説しています。
- 『観察による歩行分析』: 歩行分析の基礎から臨床応用まで、段階的に学べます。
- 『ペリー歩行分析 正常歩行と異常歩行』: 同じく歩行分析の基礎から応用、そして力学的な視点からより専門的に学べます。
まずは一冊、自分が「わかりやすい」と感じる本を手元に置いて、臨床での疑問をその都度調べる習慣をつけましょう。
まとめ:運動学は、あなたの臨床を支える最高の武器になる
今回は、新人PTが臨床で運動学を使いこなすためのヒントをお伝えしました。
- 運動学は「骨」「関節」「筋」の3つの視点で捉える
- 動作分析で「なぜ?」の仮説を立て、評価で検証する
- 触診や正常動作の観察で、知識と感覚をつなげる
運動学は、一朝一夕で身につくものではありません。地道な勉強と、日々の臨床での意識的な活用が必要です。しかし、患者さんの動きの「なぜ?」が解明できた時の喜びは、理学療法士としての大きなやりがいにつながるはずです。
この記事が、あなたの臨床のヒントになれば幸いです。