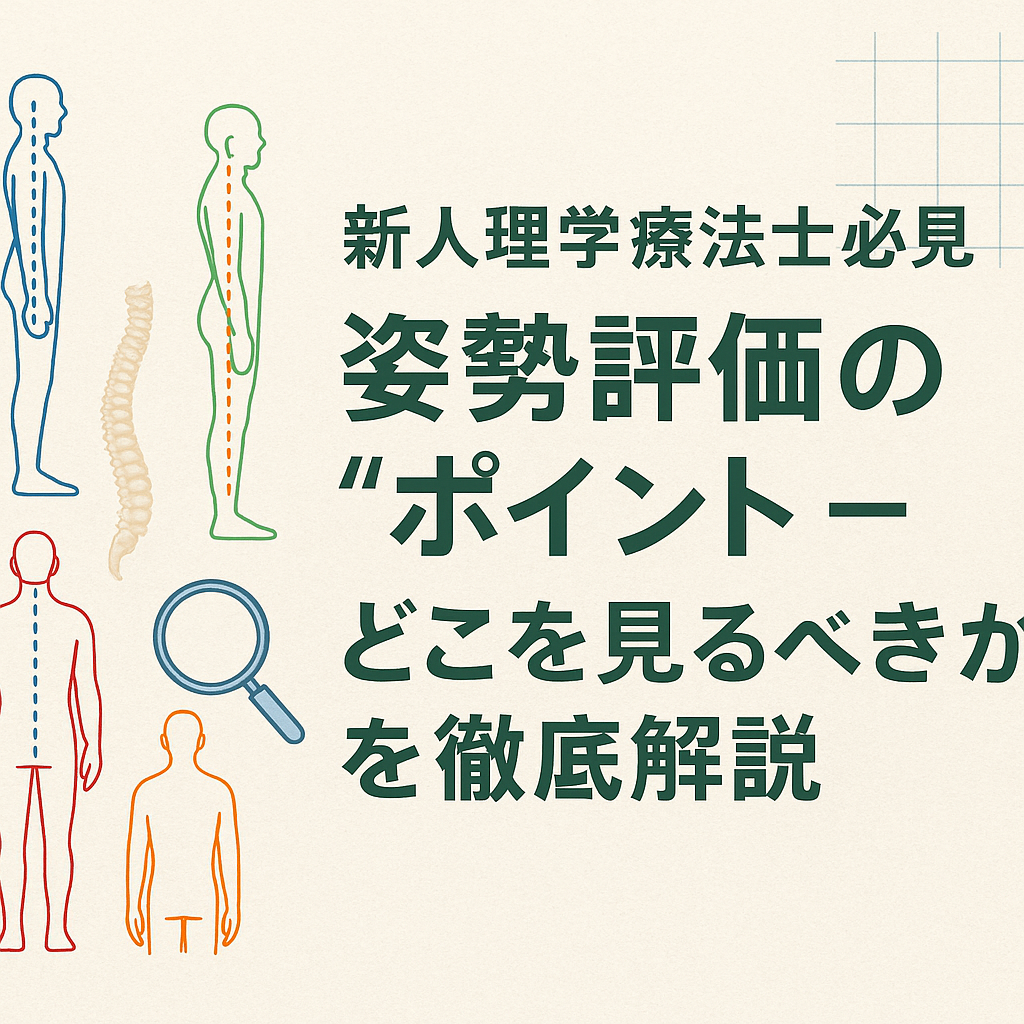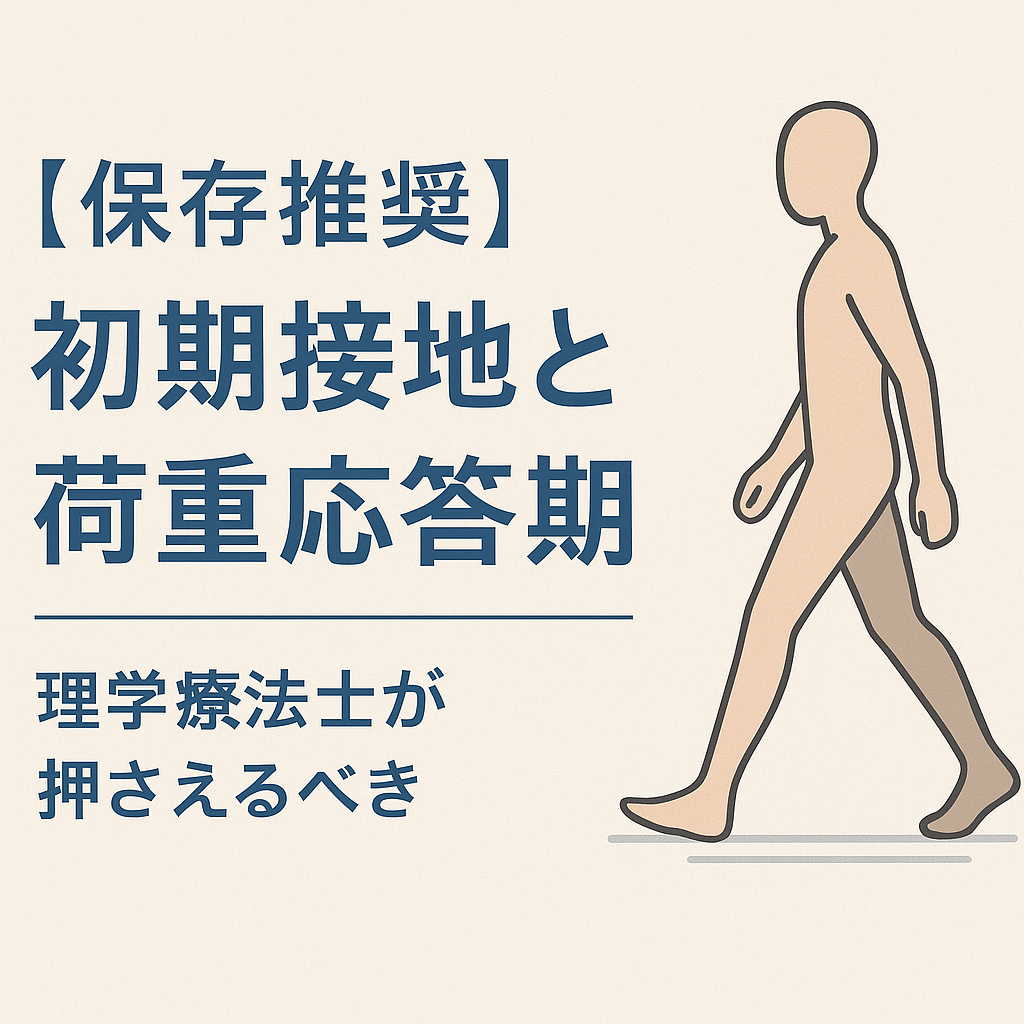先輩、今日も姿勢評価の練習したいんですけど…正直、どこを見ればいいのか全然わからなくて…。

お、いいね!でも“なんとなく”で見てるだけじゃダメだよ。姿勢評価って、言ってみれば“体の土台チェック”みたいなもんだからね。

土台チェック…ですか?

そう。家も土台が傾いてたら全部グラグラになるだろ?体も同じで、姿勢が崩れてると動き方もバランスも全部に影響するんやで。

なるほど…でもやっぱり、立ってるだけの姿勢って、どこをどう見ればいいか難しくて…。

大丈夫。今日は“どこを見るか”と“なぜそこを見るか”を一緒に整理していこう。見える世界が変わって行くと思うから。
はじめに
臨床現場では、一見わずかなアライメント異常が、慢性疼痛や機能障害の原因となることが少なくありません。姿勢評価は、理学療法士(PT)にとって基本であり、臨床推論の“入口”とも言えるスキルです。
この記事では、「理学療法」「姿勢評価」「どこを見る?」というキーワードを中心に、姿勢評価の基本的な理論と、臨床現場で即使える観察ポイントを詳しく紹介します。
新人PTはもちろん、中堅~ベテランの方にも「見落としがちな視点」を再確認していただける内容になっています。
姿勢評価の目的と理学療法での役割
姿勢評価とは、個体の静的アライメントを視診・触診で分析し、対象者の機能障害や疼痛の根本原因を推定するために行うものです。
目的
- 異常アライメントの特定
- 負担増加部位の推測
- 運動連鎖のパターン分析
- 介入プラン(治療方針)の立案
理学療法士が姿勢評価を行う意義
- 機能障害の背景にある“隠れた原因”を見抜く
- 動的評価と併用し、より精度の高いアセスメントを実現
- 対象者への説明に説得力を持たせ、治療へのモチベーションを高める
姿勢評価の3方向と評価手順
評価する基本の「3方向」:
- 正面(前額面)
- 側面(矢状面)
- 後面(背面)
標準的な評価の流れ:
- 対象者の準備:裸足+身体が見えやすい服装(例:タンクトップ、短パン)
- 立位姿勢のセットアップ:自然な立位を誘導し、対象者が緊張しすぎないよう声かけ
- ランドマークの確認:骨性ランドマーク(ASIS、PSIS、肩峰、耳垂など)を意識
- 視診+必要に応じて触診:特に深部筋・関節の位置は触診で補強
注意点:
- 対象者が「評価されている」と意識しすぎると、本来の姿勢が崩れることがあります。リラックスした環境づくりも大切です。
【正面】前額面での評価ポイント
主な評価項目と見るべきポイント
| 部位 | 評価項目 |
| 頭部 | 側屈、回旋、耳の高さ |
| 頸部 | 側屈の有無、胸鎖乳突筋の緊張左右差 |
| 肩甲帯 | 肩峰の高さ、肩甲骨の左右差 |
| 胸郭 | 肋骨の左右非対称、胸郭変形 |
| 骨盤 | ASISの高さ、左右傾斜 |
| 下肢 | 股関節・膝・足関節のライン(外反/内反) |
| 足部 | 回内/回外、足部アーチの崩れ |
例:側弯症が疑われる場合は、特に肩甲骨・骨盤の高さ差に注目。胸郭の回旋も合わせて確認すると精度が上がります。
【側面】矢状面での評価ポイント
重力線の確認
耳垂 → 肩峰 → 大転子 → 膝蓋後方 → 外果前方
各部位の評価項目
| 部位 | 評価項目 |
| 頭部 | 前方頭位(Forward Head Posture) |
| 頸椎 | 前弯の増減 |
| 胸椎 | 後弯の増強(円背) |
| 腰椎 | 前弯増強(反り腰)または減弱(平坦腰) |
| 骨盤 | 前傾/後傾 |
| 膝関節 | 過伸展(Genu Recurvatum) |
| 足関節 | ヒールアップ、足部アライメント |
臨床例:
- 腰痛患者で骨盤が過剰前傾している場合、腸腰筋の短縮+腹直筋の機能低下が背景にあることが多いです。
【後面】背面での評価ポイント
観察項目:
| 部位 | 評価項目 |
| 頭部 | 中心軸のズレ |
| 肩甲骨 | 挙上/下制、内外転、翼状肩甲 |
| 脊柱 | 側弯、回旋 |
| 骨盤 | PSISの高さ、仙骨の傾き |
| 下肢 | 膝窩の左右差、アキレス腱の傾き |
見落としやすい視点:
- **翼状肩甲骨(Scapular Winging)**は前鋸筋や僧帽筋の機能不全の兆候。
- アキレス腱の傾きは、足部のアライメント異常(回内/回外)を示す重要なサインです。
姿勢評価の臨床的落とし穴と対策
- 代償動作と本態的異常の区別:痛みや恐怖回避行動で一時的に現れるアライメント異常を見極めることが大切。
- 「正常範囲」にこだわりすぎない:個人差や生活歴をふまえた柔軟な評価が必要。
- 動的評価とセットで使う:静的評価だけでは不十分。歩行やファンクショナルタスク中の姿勢制御も併せて観察を。
姿勢評価を活かした臨床推論の実例
ケース①:肩関節障害
- 所見:前突頭位+肩甲骨挙上・前傾
- 推論:肩甲胸郭関節のアライメント異常→肩峰下インピンジメントが原因
ケース②:膝関節痛
- 所見:立位時に過回内足+膝外反
- 推論:下肢運動連鎖異常(回内足→脛骨内旋→膝外反)
まとめ:姿勢評価は「見る」から「読み解く」時代へ
姿勢評価は単なる“見た目”のチェックではなく、**機能障害の背景を読み解くための「臨床推論の起点」**です。日々の臨床で、評価→推論→介入のループを繰り返すことで、観察眼は確実にレベルアップしていきます。
今回はざっくりとにはなりましたが、姿勢評価のポイントについて解説していきました。
少しでも日々の臨床の一助となりましたら幸いです。