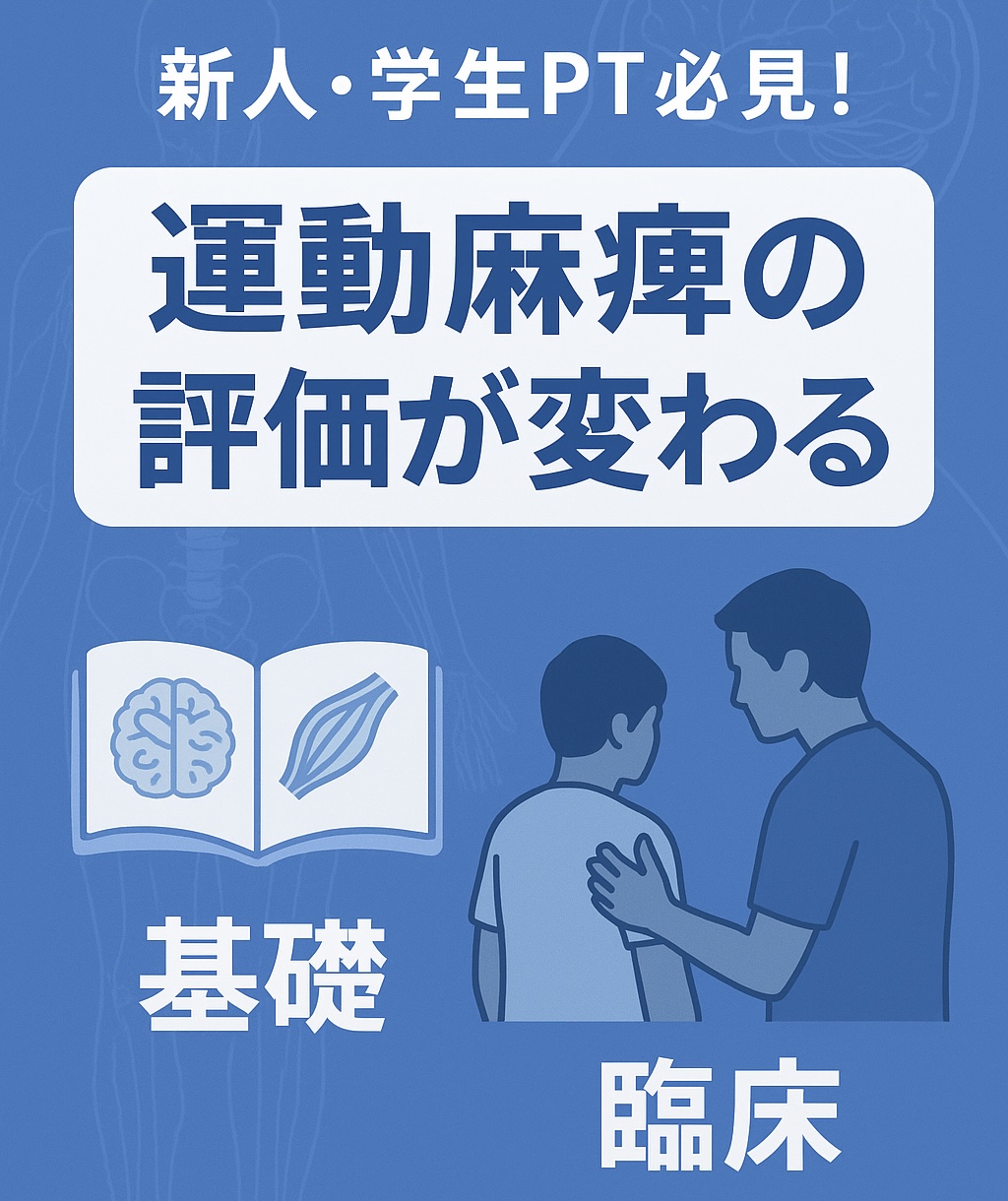【はじめに】
理学療法士(PT)や学生の皆さん、こんにちは!
臨床実習や日々の業務で「運動麻痺」の患者さんを担当する機会は非常に多いですよね。
しかし、
「上位運動ニューロン障害と下位運動ニューロン障害の違いが曖昧…」
「片麻痺の原因は脳卒中だけ?そもそも運動麻痺って?」
「麻痺の広がりから、どうやって障害部位を考えればいいの?」
と、知識の整理に苦労している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなお悩みを解決するため、運動麻痺の評価に不可欠な**「上位・下位ニューロン障害の鑑別」と「麻痺の分布による障害部位の推測」**という2つのテーマで解説します。
この記事を読めば、運動麻痺の評価における臨床推論の土台が固まり、自信を持って患者さんと向き合えるようになります。ぜひ最後まで読んで、明日からの学びに役立ててください!
りん
📢臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

運動麻痺の基本|まず押さえるべき2つの分類
まず、「運動麻痺」の基本的な定義と、その分類について理解しましょう。運動麻痺を正しく評価する第一歩は、障害が神経経路のどこで起きているかを見極めることです
運動麻痺とは?
運動麻痺とは、脳から筋肉まで続く運動の指令系統(運動神経路)のどこかに障害が起こり、自分の意思で体を動かせなくなった状態を指します。
麻痺の程度によって、以下のように分けられます。
- 完全麻痺 (paralysis): 筋肉が全く動かせない状態
- 不全麻痺 (paresis): 筋力は低下しているが、少しは動かせる状態
上位運動ニューロン障害(中枢性麻痺)
運動の指令を出す「司令塔」の役割を担う神経経路の障害です。
具体的には、**大脳皮質の運動野から出て、脊髄の前角細胞に至るまでの経路(皮質脊髄路など)**に問題が起きた状態を指します。
- 障害部位の例: 脳(大脳皮質、内包、脳幹)、脊髄
下位運動ニューロン障害(末梢性麻痺)
司令塔からの指令を筋肉に伝える「実行部隊」の役割を担う神経経路の障害です。
具体的には、脊髄の前角細胞から、末梢神経を通って筋肉に至るまでの経路に問題が起きた状態を指します。
- 障害部位の例: 脊髄前角、末梢神経、神経筋接合部
この2つを区別することが、理学療法評価のスタートラインとなります。
臨床推論のキホン!上位 vs 下位運動ニューロン障害を見分ける5つのサイン
臨床で運動麻痺の患者さんを評価する際、最も重要なのが「これは上位?それとも下位?」と鑑別することです。なぜなら、原因疾患や予後、リハビリのアプローチが大きく異なるからです。
以下の表で、5つの鑑別ポイントを比較しながら覚えましょう。
上位・下位運動ニューロン障害の鑑別点
| 評価項目 | 上位運動ニューロン障害 | 下位運動ニューロン障害 |
| 1. 筋緊張 | 亢進(痙性麻痺 spasticity) | 低下(弛緩性麻痺 flaccidity) |
| 2. 腱反射 | 亢進 | 減弱 または 消失 |
| 3. 筋萎縮 | 軽度(主に廃用性) | 著明 |
| 4. 病的反射 | 出現する(バビンスキー反射 +) | 出現しない(-) |
| 5. その他 | 粗大な共同運動パターン | 線維束性収縮(筋肉のピクつき) |
【コラム】なぜ上位運動ニューロン障害で腱反射は亢進するの?
不思議に思ったことはありませんか?実は、私たちの脊髄には、刺激に対して自動的に反応する「反射」の仕組みが備わっています。普段、上位運動ニューロン(脳)は、この反射が過剰に出すぎないように常に抑制をかけています。
しかし、上位運動ニューロンが障害されると、この抑制が効かなくなり、脊髄の反射がむき出しの状態になります。その結果、ハンマーで腱を叩くと、過剰な反応(腱反射の亢進)が起こるのです。
どこが悪い?麻痺の広がり(分布)から障害部位を考えよう
次に、麻痺が体のどの範囲に現れているか(分布)に注目します。麻痺の分布は、障害部位を推測するための非常に重要な手がかりです。
単麻痺 (Monoplegia)
四肢のうち、一つの手または足のみに麻痺がある状態です。
脳梗塞などで大脳皮質の運動野がごく限局的に障害された場合や、腕や足へ向かう単一の末梢神経(橈骨神経、腓骨神経など)が障害された場合にみられます。
片麻痺 (Hemiplegia)
身体の片側、つまり右半身または左半身の上下肢に麻痺がある状態です。
運動麻痺の中で最も多くみられ、原因として最も多いのは脳卒中(脳梗塞・脳出血)です。障害部位は、運動の神経線維が密集している内包が最多ですが、大脳皮質や脳幹の障害でも起こります。
【Point】交叉性片麻痺(こうさせいかたまひ)とは?脳幹が障害された場合に見られる特殊な麻痺です。片麻痺と、その反対側の脳神経麻痺(顔面神経麻痺など)が同時に起こるのが特徴です。例えば、「右片麻痺+左顔面神経麻痺」といった症状が出ます。これは脳幹レベルでの障害を強く示唆する重要な所見です。
対麻痺 (Paraplegia)
両方の下肢に麻痺がある状態です。
主に胸髄以下のレベルでの脊髄損傷でみられます。脊髄の障害レベルより下にある運動機能と感覚機能が失われるため、両下肢の麻痺が起こります。
四肢麻痺 (Quadriplegia / Tetraplegia)
両方の上下肢、つまり四肢すべてに麻痺がある状態です。
障害部位がより高位にあることを示唆しており、頚髄損傷が最も典型的な原因です。その他、脳幹の広範な障害や、両側の大脳半球の障害でも起こり得ます。
知識をつなげる|代表的な原因疾患
最後に、これまで学んだ「ニューロン障害の分類」と「麻痺の分布」を結びつけ、代表的な原因疾患を整理しましょう。
- 片麻痺をきたす疾患
- 上位運動ニューロン障害: 脳血管障害(脳梗塞、脳出血)、脳腫瘍、多発性硬化症
- 対麻痺をきたす疾患
- 上位運動ニューロン障害: 脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳性麻痺(痙性両麻痺)
- 下位運動ニューロン障害: ギラン・バレー症候群、ポリオ
- 四肢麻痺をきたす疾患
- 上位運動ニューロン障害: 頚髄損傷、脳幹梗塞
- 上位+下位混合: 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 下位運動ニューロン障害: 筋ジストロフィー、多発性神経炎
【まとめ】明日からの臨床に活かす思考プロセス
運動麻痺の患者さんを評価する際は、以下のステップで思考を整理することが大切です。
- Step1: 上位 or 下位?
まず、筋緊張、腱反射、病的反射などを評価し、上位運動ニューロン障害か下位運動ニューロン障害かを鑑別します。 - Step2: 麻痺の分布は?
次に、麻痺がどこに広がっているかを確認し、単麻痺・片麻痺・対麻痺・四肢麻痺のどれに当てはまるかを判断します。 - Step3: 障害部位と原因は?
最後に、鑑別の結果と麻痺の分布を組み合わせることで、障害されている部位を推測し、考えられる原因疾患を絞り込みます。
この思考プロセスが、的確な理学療法評価とアプローチ立案の第一歩となります。今回の基礎知識を土台に、さらに学びを深め、根拠のあるリハビリテーションを提供できる理学療法士を目指しましょう!