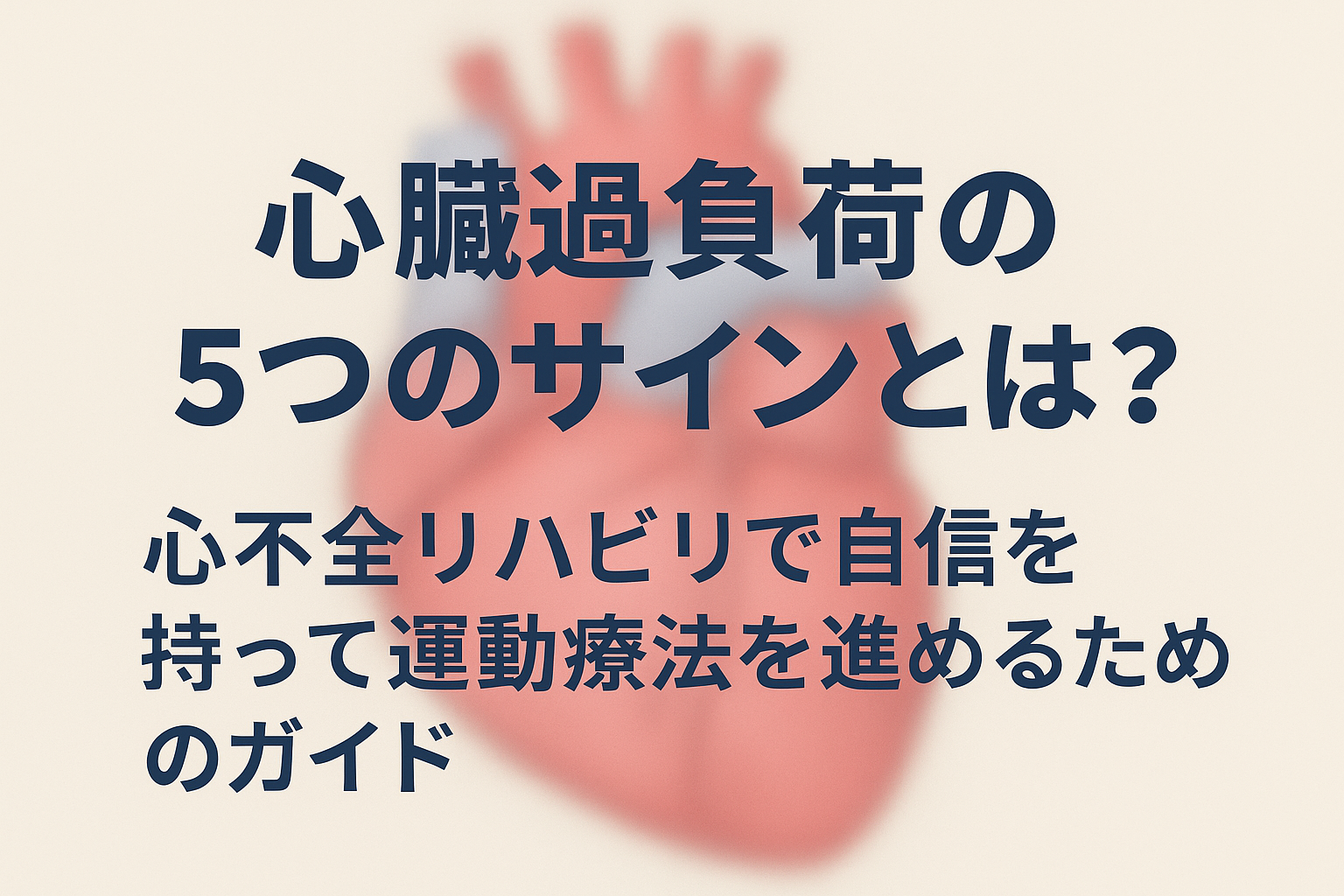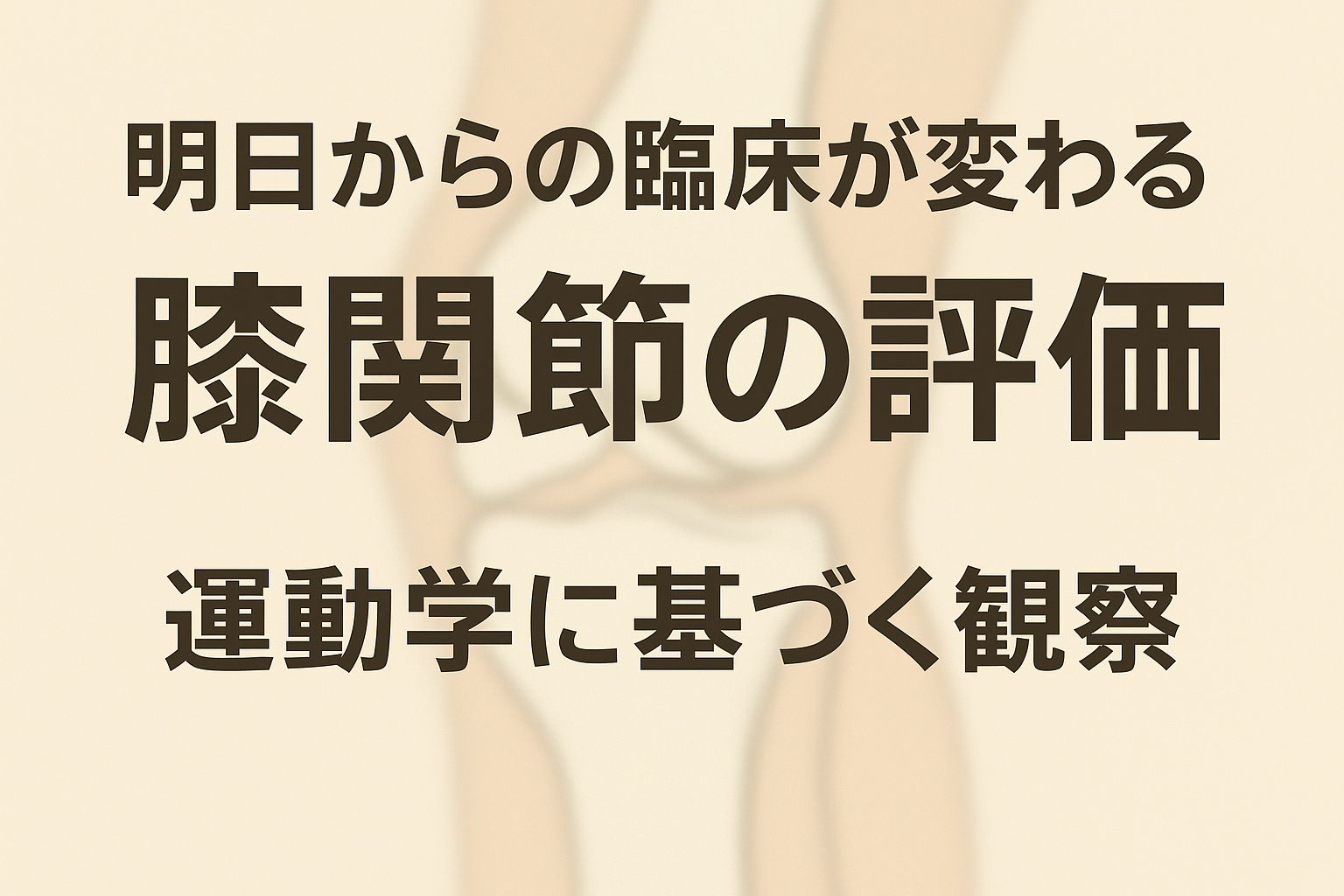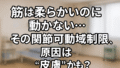はじめに
心不全や心臓術後の患者さんを担当したとき、「どこまで運動負荷を上げていいんだろう…」「心臓に負担をかけすぎていないか不安…」と感じた経験はありませんか?
先輩から「心負荷に注意して」とアドバイスされても、具体的に何をどう観察すれば良いのか、最初は戸惑いますよね。
この記事では、心臓リハビリテーションに苦手意識を持つ若手理学療法士や学生さんに向けて、臨床で必ず役立つ「心臓過負荷」の知識を解説します。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
- 「圧負荷」と「容量負荷」の違いが図解でスッキリわかる
- 臨床で見逃してはいけない心臓過負荷の5つのサイン
- 安全な運動療法を進めるための具体的なリスク管理と負荷設定
明日からの臨床で、自信を持って患者さんの評価とリハビリテーションを進められるよう、一緒に学んでいきましょう!
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

そもそも「心臓過負荷」とは?圧負荷と容量負荷の違いを理解しよう
「心臓過負荷」とは、文字通り、心臓に過剰な負担がかかっている状態のことです。心臓を「血液を全身に送り出すポンプ」に例えると分かりやすいです。
この過負荷には、大きく分けて「圧負荷」と「容量負荷」の2種類があります。
■ 圧負荷(Pressure Overload):硬いホースに無理やり水を送る状態
圧負荷とは、高い圧力に逆らって心臓が血液を送り出さなければならない状態です。
- 例えるなら: 先が詰まった硬いホースに、無理やり水を押し込んでいるイメージ。
- 主な原因: 高血圧、大動脈弁狭窄症 など
- 心臓の変化: ポンプ(心筋)は圧力に負けまいと、どんどん筋肉が分厚くなります(求心性肥大)。しかし、部屋(心室)の内側は狭くなり、一度に送り出せる血液量が減ってしまいます。
■ 容量負荷(Volume Overload):ポンプに血液が戻りすぎてパンパンな状態
容量負荷とは、心臓に戻ってくる血液量が多すぎて、処理しきれなくなっている状態です。
- 例えるなら: 送り出した水が逆流してきて、ポンプが常にパンパンに張っているイメージ。
- 主な原因: 僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症 など
- 心臓の変化: ポンプ(心筋)は風船のように引き伸ばされ、部屋(心室)が大きくなります(遠心性肥大)。最初は多くの血液を送り出せますが、伸びきったゴムのように、次第に収縮する力が弱くなっていきます。
担当患者さんがどちらのタイプの過負荷に陥りやすいのかを理解しておくことが、リハビリを進める上で最初の第一歩です。
臨床で見逃すな!理学療法士が観察すべき心臓過負荷の5つのサイン
リハビリ中に患者さんが発する心臓過負荷のサイン(SOS)を見逃さないことが、安全な運動療法に不可欠です。理学療法士が「五感」で評価できる5つの重要サインを確認しましょう。
サイン①:自覚症状(息切れ・倦怠感)
問診や会話の中から情報を引き出します。特に労作時の変化に注意しましょう。
- 息切れ(労作時呼吸困難):「病棟のトイレまで歩くだけでハァハァする」「横になると息苦しい(起坐呼吸)」
- 倦怠感・易疲労感:「リハビリの後、どっと疲れる」「以前より疲れやすくなった」
- 動悸・胸部不快感
【臨床のポイント】
Borg(ボルグ)スケールを活用し、「今のきつさは、この数字だとどれくらいですか?」と尋ねることで、患者さんの主観的な感覚を客観的に評価しましょう。
サイン②:顔色・口唇の色(視診)
血中の酸素が不足すると、皮膚や粘膜の色が変化します。
- チアノーゼ: 唇や爪が紫色になっていないか確認します。
- 顔色: 顔色が悪く、土気色になっていないか観察しましょう。
サイン③:頸静脈の怒張(視診)
右心系のうっ血(血液の渋滞)を示す重要なサインです。
- 確認方法: ベッドを45度にギャッジアップし、患者さんの顔を左側に向けてもらいます。首の右側にある内頸静脈が、鎖骨から2横指以上(約4cm)拍動していれば陽性です。
サイン④:下腿浮腫(触診)
体液が貯留し、うっ血しているサインです。
- 確認方法: 患者さんのすねの内側(脛骨前面)を指で5秒ほど圧迫し、離したときに指の痕が残るか(Pitting Edema)を確認します。左右差も評価しましょう。
サイン⑤:バイタルサインの変化(測定)
運動療法前後のバイタルサイン測定は、心臓の反応を客観的に知るための最も重要な情報源です。
- 体重: 「1週間で2kg以上の増加」は、心不全増悪による体液貯留を強く疑うサインです。必ず患者さんにセルフチェックを指導しましょう。
- 血圧: 運動中に収縮期血圧が上昇しない、または20mmHg以上低下する場合は、心拍出量が低下している危険な兆候です。
- 脈拍: 運動強度に見合わない過度な頻脈(頻脈)や、脈の乱れ(不整脈)が出現していないか確認します。
- SpO2: 運動によって90%未満に低下する場合は、運動強度が高すぎる可能性があります。
これらのサインを複数認める場合は、リハビリを中止または軽めに切り上げ、速やかに看護師や医師に報告・相談することが重要です。
安全第一!心臓リハビリテーションの運動療法とリスク管理
心臓過負荷のサインを理解したら、次は安全にリハビリを進めるための具体的な方法です。
■ まずは覚えよう!運動療法の中止基準
以下の症状が出現した場合は、無理をせず運動を中止し、患者さんを休ませてください。
| カテゴリ | 中止基準の例 |
| 自覚症状 | 中等度以上の胸痛・息切れ、めまい、ふらつき、強い疲労感 |
| 他覚所見 | 顔面蒼白、冷や汗、チアノーゼ |
| 血圧 | 収縮期血圧の異常な低下(20mmHg以上)、過度な上昇(220mmHg以上) |
| 脈拍 | 新たな不整脈の出現、過度な頻脈・徐脈 |
| その他 | SpO2が90%未満に低下 |
(参考:心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン)
■ 適切な運動強度の設定方法
安全かつ効果的なリハビリのためには、適切な運動強度の設定が欠かせません。
- 自覚的運動強度(RPE)
Borgスケールで**「11(楽である)~13(ややきつい)」**の範囲を目安に運動を行います。患者さんとコミュニケーションを取りながら調整するのが基本です。 - 心拍数(脈拍)
カルボーネン法を用いて目標心拍数を設定します。
目標心拍数 = (安静時心拍数) + (予備心拍数 × 運動強度)
※予備心拍数 = (最高心拍数) – (安静時心拍数)
※運動強度は40~60%が目安。
注意点: β遮断薬などを内服している患者さんは心拍数が上がりにくいため、カルボーネン法だけに頼らず、必ずBorgスケールと併用しましょう。
まとめ:心臓過負荷のサインは患者さんからのSOS
今回は、理学療法士が知っておくべき「心臓過負荷」について解説しました。
- 心臓過負荷には「圧負荷」と「容量負荷」がある
- 重要なサインは「自覚症状・視診・触診・バイタルサイン」で観察できる
- 安全なリハビリには「運動中止基準」と「適切な負荷設定」が不可欠
心臓リハビリは最初は難しく感じるかもしれませんが、今回ご紹介した心臓過負荷のサインは、患者さんの身体が発する「SOS」です。
まずは明日から、担当する患者さんの**「顔色」「呼吸」「むくみ」「体重の変化」**を意識して観察することから始めてみてください。その小さな気づきの積み重ねが、患者さんの安全を守り、質の高いリハビリテーションへと繋がります。