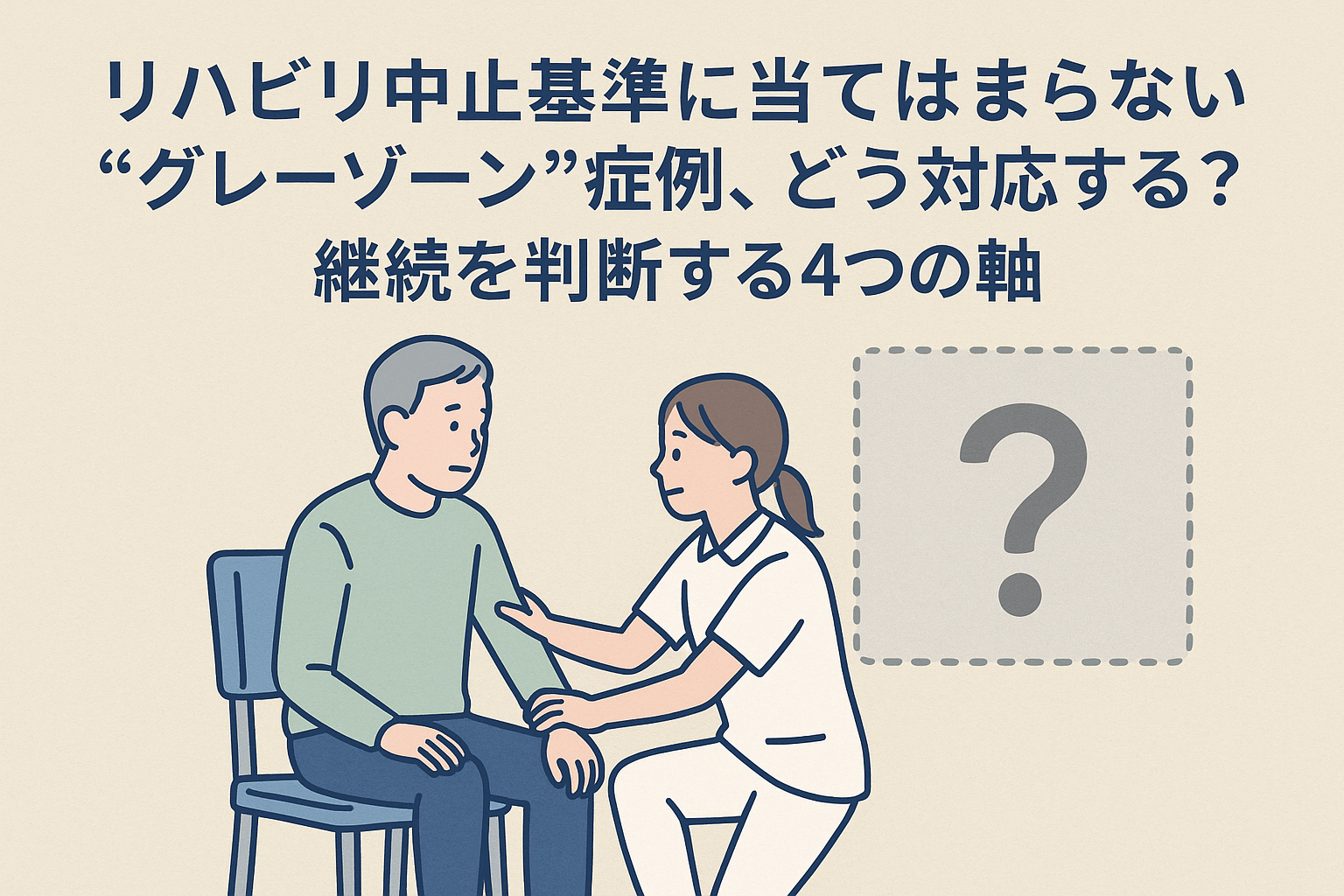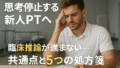はじめに
「血圧は基準値内だけど、なんだか顔色が悪い…」
「本人は『大丈夫』と言うけれど、明らかに呼吸が荒い…」
リハビリの現場で、このような**“グレーゾーン”**の状況に頭を悩ませた経験はありませんか?
明確なリハビリ中止基準には当てはまらないけれど、このまま継続して良いのか迷う瞬間。それは、患者さんの安全を守り、かつ最大限の効果を引き出すために、セラピストとしての臨床判断が最も問われる場面です。
この記事では、そんなグレーゾーン症例に対応するための**「4つの判断軸」と、明日から使える具体的な思考プロセス**を解説します。自信を持って「GO or STOP」を判断するための武器を手に入れましょう。
臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

おさらい:そもそもリハビリの「中止基準」とは?
まず基本の確認です。私たちが臨床で参考にする中止基準は、患者さんの安全を確保するための重要なセーフティーネットです。
- なぜ重要か?: 患者さんの安全確保はもちろん、インシデントや医療訴訟を避けるためのリスク管理として不可欠です。
- 代表的な基準: 日本リハビリテーション医学会などが示すバイタルサインの基準値(収縮期血圧180-200mmHg以上、脈拍120-140回/分以上など)が一般的です。
しかし、最も大切なのは**「基準はあくまで最低限のライン」**と認識すること。この基準値だけを頼りにしていると、グレーゾーンのサインを見逃す危険性があります。
なぜ判断に迷う「グレーゾーン」は生まれるのか?
教科書通りにいかないのが臨床の常。グレーゾーンが生まれる主な理由は2つです。
- 教科書通りにはいかない「患者の個別性」
基礎疾患(心疾患、呼吸器疾患など)、年齢、体力レベル、服用中の薬(β遮断薬など)によって、身体の反応は全く異なります。また、その日の睡眠時間や精神状態といった「変動要因」も大きく影響します。 - 数値(データ)だけでは捉えきれないサイン
バイタルサインは正常でも、患者さんの表情が曇っていたり、動作のキレが悪くなったり…。この**「客観的な数値」と「主観的・質的な情報」のズレ**にこそ、私たちが読み取るべき重要なヒントが隠されています。
【本題】グレーゾーンを乗り切るための4つの判断軸
では、具体的にどう判断すれば良いのでしょうか?ここでは、多角的に状況を評価するための4つの判断軸を提案します。
判断軸①:客観的指標の「変化」を捉える
「今の数値」という点で見るのではなく、「安静時からどう変わったか」という線で捉えることが重要です。
- 絶対値よりも変化量・変化パターン:
- いつもより軽い運動で心拍数が急上昇する。
- 運動後の血圧や心拍数の回復が普段より明らかに遅い。
- SpO2が95%でも、安静時99%から徐々に低下してきている。
- 複数の指標を組み合わせる:
バイタルサインだけでなく、RPE(自覚的運動強度)や修正Borgスケールを聴取し、「数値」と「本人の感覚」をセットで評価しましょう。
判断軸②:主観的・質的情報を「観察」する
セラピストの五感をフル活用します。数値には表れない「いつもと違う」サインを見逃さないでください。
- 言語的サイン(聴く):
「大丈夫です」という言葉を鵜呑みにせず、「胸が詰まる感じ」「頭がフワフワする」といった具体的な訴えに耳を傾けます。 - 非言語的サイン(見る):
- 顔色、表情、口唇色、冷や汗
- 呼吸様式(努力呼吸、肩で息をしていないか)
- 動作の正確性、集中力の低下、呂律が回らない
これらの質的情報は、時としてバイタルサイン以上に雄弁に患者さんの状態を物語ります。
判断軸③:リハビリの「目的」に立ち返る
「何のためのリハビリか」という原点に立ち返ることで、判断の精度が上がります。
- 今日のゴールは何か?:
今日の目的が「高負荷での筋力増強」なのか、それとも「安定したADL動作の再獲得」なのかで、許容できるリスクは変わります。 - リスクとベネフィットの天秤:
「このまま続けて得られる効果(ベネフィット)」と「万が一の事態が起こる危険性(リスク)」を天秤にかけます。少しでもリスクが上回ると感じたら、負荷を落とす、内容を変更する、中止するといった判断が必要です。長期的な視点で、今日無理をさせることが本当に患者さんのためになるかを考えましょう。
判断軸④:「チーム」で判断する(多職種連携)
最も重要なのが、一人で抱え込まないこと。判断に迷う時は、チームの力を借りるのが最善手です。
- 看護師からの情報収集:
「昨夜は眠れていましたか?」「食事は摂れていますか?」など、リハビリ前の病棟での様子は貴重な情報源です。 - 医師への報告・連絡・相談(報連相):
「〇〇様ですが、リハビリ中に血圧は140/80と基準内ですが、顔色が悪く冷や汗が見られます。RPEも15と高いため、本日のリハビリは中止(または軽めの内容に変更)したいのですが、よろしいでしょうか?」
このように、**観察した事実(S情報、O情報)と自分のアセスメント(A情報)**を添えて具体的に相談することで、的確な指示を仰ぐことができます。
実践編:「あれ?」と思ったら。明日から使える対応フローチャート
グレーゾーンに遭遇した際の、具体的な行動ステップです。
- 【一旦停止】
まずは運動を止め、患者さんを安全な姿勢(椅子に座らせる、ベッドに横になってもらう)にします。 - 【情報収集】
- 測る: バイタルサインを再測定し、安静時と比較します。
- 聴く: 「どこが、どのようにしんどいですか?」と具体的な症状をヒアリングします。
- 見る: 顔色や呼吸状態など、非言語的サインを注意深く観察します。
- 【アセスメント&判断】
上記の「4つの判断軸」を元に総合的に評価します。- A:継続可能(負荷調整): 休憩を挟む、運動強度を下げる、内容をADL訓練などに変更する。
- B:本日は中止: 無理は禁物。看護師や医師に状況を正確に報告し、記録に残します。
- C:緊急対応: 明らかな異常所見(意識レベルの低下、麻痺の出現など)があれば、即座にナースコールで応援を呼びます。
ケーススタディで学ぶ!グレーゾーン症例への対応例
【ケース】 心疾患の既往がある70代女性。歩行訓練中、SpO2は94%と基準値を下回らないが、会話中に息切れが見られ、口数も減ってきた。
- 悪い対応例: SpO2が基準内なので、そのまま目標距離まで歩行を続行させる。
- 良い対応例:
- 【一旦停止】すぐに椅子に座ってもらう。
- 【情報収集】SpO2と脈拍を再検。「息が苦しい感じはありますか?」とRPEを聴取。顔色や口唇色を確認。
- 【アセスメント】SpO2の数値は保たれているが(判断軸①)、息切れや口数の減少という非言語的サイン(判断軸②)が見られる。心疾患の既往を考慮するとリスクが高い(判断軸③)と判断。
- 【判断】歩行訓練は中止し、座位での呼吸練習に切り替える。終了後、看護師に「歩行中に息切れが見られたため、本日は途中で中止しました」と報告する(判断軸④)。
まとめ
リハビリ中止基準に当てはまらないグレーゾーン症例への対応は、マニュアル通りの思考停止ではなく、セラピストの**「臨床推論(クリニカルリーズニング)」**の真価が問われる場面です。
中止基準は安全を守るための最低ライン。その上で、
- 客観的指標の「変化」
- 主観的・質的情報の「観察」
- リハビリの「目的」
- 「チーム」での判断
という4つの判断軸を駆使し、患者さん一人ひとりに合わせた最適な選択をすることが求められます。
迷った時に立ち止まり、多角的に考える勇気が、患者さんの安全と未来を守ります。この記事が、あなたの臨床における自信に繋がることを願っています。