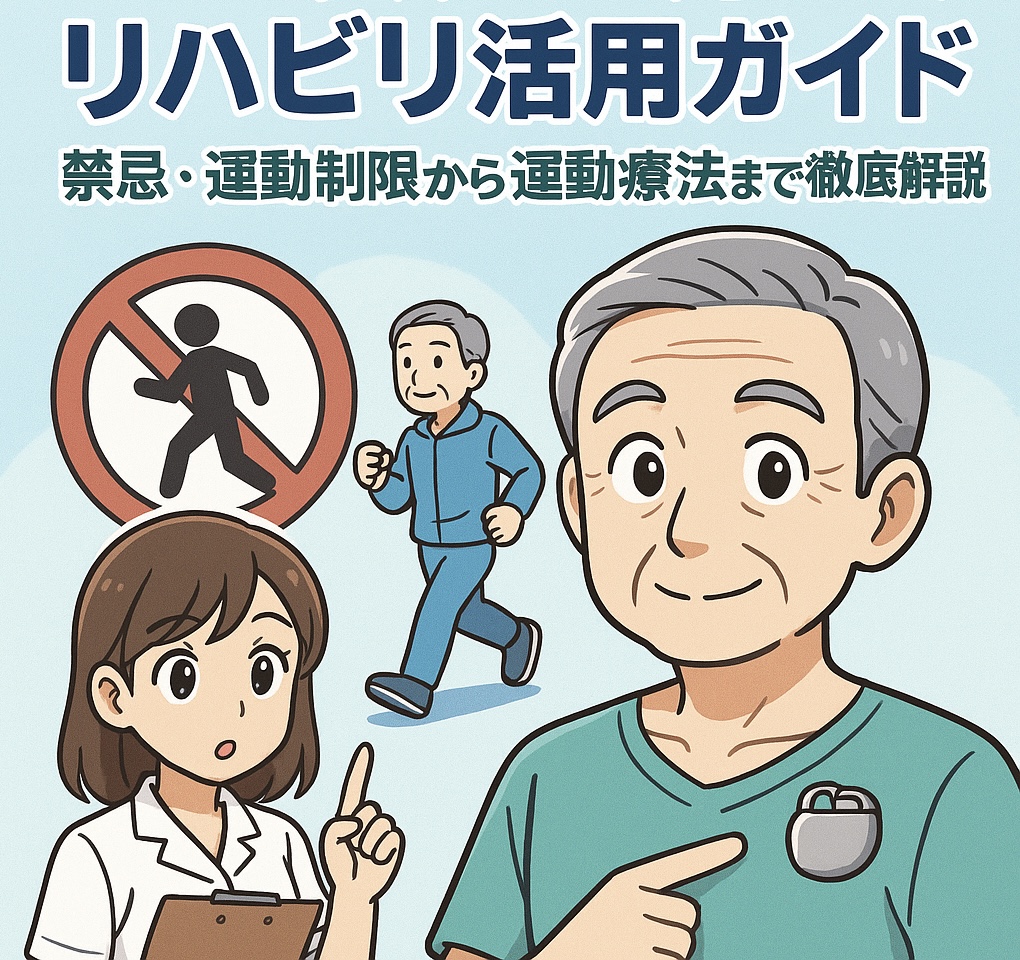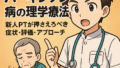はじめに
【こんな悩みありませんか?】
「初めてペースメーカーの患者さんを担当するけど、何に注意すればいい?」
「術後の運動制限って、いつまで?どこまで動かしていいの?」
「物理療法って、どれが禁忌なんだっけ…?」
循環器疾患のリハビリを担当する理学療法士(PT)なら、一度はこんな疑問や不安を感じたことがあるのではないでしょうか。
ペースメーカーは、患者さんの生命を守り、活動的な生活を支える重要な医療機器です。だからこそ、私たちセラピストは正しい知識を持って関わる必要があります。
この記事では、ペースメーカーの基礎知識から、理学療法士として絶対に押さえるべき術後の注意点、具体的な運動療法の進め方、そして医療事故を防ぐための物理療法の禁忌まで、明日からの臨床にすぐに活かせる知識を身につけるなめの内容です。
\臨床理学Labでは有料記事が見放題/

そもそもペースメーカーとは?初心に返る基礎知識
まずは基本の「き」からおさらいしましょう。
ペースメーカーの役割と仕組み
ペースメーカーは、心臓の脈が遅くなる「徐脈性不整脈」の治療に使われる機器です。心臓のリズムを24時間監視し、脈が遅くなった時や止まりそうになった時に電気刺激を送り、心臓のポンプ機能を補助します。まさに「心臓の司令塔」のような存在です。
- 本体(ジェネレーター): 鎖骨下の皮下に埋め込まれる小さな金属の箱。
- リード: 本体から血管を通り、心臓の内部(心筋)まで伸びる電線。
このリードが心臓の動きを感知(センシング)し、必要に応じて電気刺激を送る(ペーシング)仕組みです。
なぜ必要?対象となる心臓の病気
- 洞不全症候群(SSS): 心臓の自然なペースメーカー「洞結節」の機能が落ちる病気。
- 房室ブロック(AV block): 心房から心室への電気信号が途絶える病気。
これらの疾患により、めまい、失神、息切れ、強い疲労感などの症状が現れ、日常生活に支障をきたすため、ペースメーカーの植え込みが必要となります。
【最重要】理学療法士が絶対押さえるべき術後の注意点
ここからが本題です。特に術後早期は、私たち理学療法士の関わりが患者さんの予後を大きく左右します。
① 術後早期の上肢運動制限(なぜ?いつまで?何を?)
術後、最も注意すべき合併症が「リードディスロッジメント(リードのずれ)」です。植え込んだばかりのリードの先端は、まだ心筋にしっかりと固定されていません。この時期に腕を大きく動かすと、リードが心筋からずれてしまい、ペーシング不全を引き起こす危険があります。
これを防ぐため、以下の運動制限を徹底しましょう。
- 対象: 植え込み側の上肢
- 期間: 施設により異なりますが、術後数週間〜1ヶ月程度が一般的です。必ず主治医に確認してください。
- 制限内容:
- 肩関節の挙上(屈曲・外転)を90度以上行わない
- 腕を過度に後ろへ伸ばさない(過伸展)
- 重いものを持たない、強い力を入れない
この期間のリハビリは、下肢の運動や体幹トレーニング、反対側の上肢運動、そしてこの制限内でのADL指導が中心となります。
② 創部の観察ポイント
植え込み部分の創部からの感染も重大な合併症です。リハビリの前後には、必ず創部の状態を確認しましょう。
【感染の5徴候】
- 発赤(赤み)
- 腫脹(腫れ)
- 熱感(熱っぽさ)
- 疼痛(痛み)
- 浸出液(じゅくじゅくしていないか)
これらのサインを見つけたら、すぐに医師や看護師に報告してください。
ペースメーカー患者への運動療法の進め方
運動制限が解除されたら、いよいよ本格的な運動療法の開始です。ここでも重要なポイントがあります。
知らないと危険!「レートレスポンス機能」とは?
レートレスポンス機能(Rate Responsive Function)は、理学療法士が絶対に知っておくべき機能です。
これは、患者さんの身体活動(体の揺れや振動など)をセンサーが感知し、運動の強度に応じて心拍数を自動的に上げてくれる機能です。
【PTとしてのポイント】
この機能がONになっているか、事前にカルテや医師、臨床工学技士(ME)に確認しましょう。もしこの機能がOFFの場合、患者さんは運動しても心拍数が上がらず、すぐに息切れや疲労感を訴えることがあります。
運動強度のカギは「ボルグスケール」
レートレスポンス機能がONでも、ペースメーカーには安全のための上限心拍数(アッパーレート)が設定されています。そのため、心拍数だけを運動強度の指標にするのは危険です。
そこで活躍するのが**「ボルグスケール(自覚的運動強度)」**です。
患者さん本人が感じる「きつさ」を指標にすることで、より安全で効果的な運動負荷を設定できます。
- 目標: **「楽である(11)」〜「ややきつい(13)」**から開始し、徐々に強度を上げていきましょう。
- 方法: 有酸素運動(歩行、自転車エルゴメーターなど)を中心に、レジスタンストレーニングも組み合わせていきます。
運動中止の基準を頭に入れる
運動中は常に患者さんの状態をモニタリングし、以下の症状が出たら直ちに運動を中止し、医療スタッフに報告してください。
- めまい、ふらつき、失神
- 動悸、脈の乱れ
- 異常な息切れ
- 胸痛、胸部不快感
- 顔面蒼白、冷や汗
- 強い疲労感
【医療事故防止】物理療法の禁忌と注意点
ペースメーカーは精密な電子機器。外部からの電気や磁気の影響で誤作動を起こす可能性があります。物理療法の選択は特に慎重に行いましょう。
【原則禁忌】 本体やリードの近くでは絶対に使用しないでください!
- ジアテルミー(極超短波、マイクロ波): 強い電磁波で回路が破壊される危険性が極めて高いです。
- 電気刺激療法(低周波、干渉波など): ペースメーカーの作動を抑制したり、逆に不適切な刺激を誘発したりする危険があります。
【要注意】 使用前に必ず医師・MEに確認を!
- TENS、EMS: ペースメーカー本体から15cm以上離れた部位なら使用可能な場合もありますが、自己判断は絶対にNGです。
- 超音波: 本体直上への照射は禁忌です。離れた部位への使用は可能とされていますが、念のため確認しましょう。
もう一歩先へ!ICD・CRT-Dとの違いは?
臨床では、ペースメーカーと似たデバイスを植え込んだ患者さんも担当します。
- ICD(植え込み型除細動器): ペースメーカー機能に加え、致死性の不整脈(心室頻拍・心室細動)が起きた際に電気ショックで治療する機能を持つ。
- CRT-D(両室ペーシング機能付きICD): ICDの機能に加え、心臓の左右のポンプ機能を同調させる**心臓再同期療法(CRT)**の機能を持つ。重症心不全の治療に用いられます。
これらのデバイスを植え込んでいる患者さんは、より重篤な心疾患を抱えているため、さらに慎重なリスク管理とモニタリングが求められます。
まとめ:正しい知識で患者さんの安心とQOL向上を
最後に、ペースメーカー患者さんのリハビリで大切なポイントをまとめます。
- 【術後】上肢の運動制限を徹底し、リードのズレを防ぐ!
- 【運動】レートレスポンス機能を確認し、ボルグスケールを活用する!
- 【物理療法】電気・温熱療法の禁忌は絶対厳守!
- 【観察】自覚症状やバイタル、創部の変化を見逃さない!
- 【連携】迷ったら必ず医師・看護師・臨床工学技士に相談する!
ペースメーカーは、患者さんが再び自分らしい生活を取り戻すための希望のデバイスです。私たち理学療法士が正しい知識を持って安全なリハビリテーションを提供することが、患者さんの安心感とQOL向上に直結します。
この記事が、あなたの臨床の一助となれば幸いです。