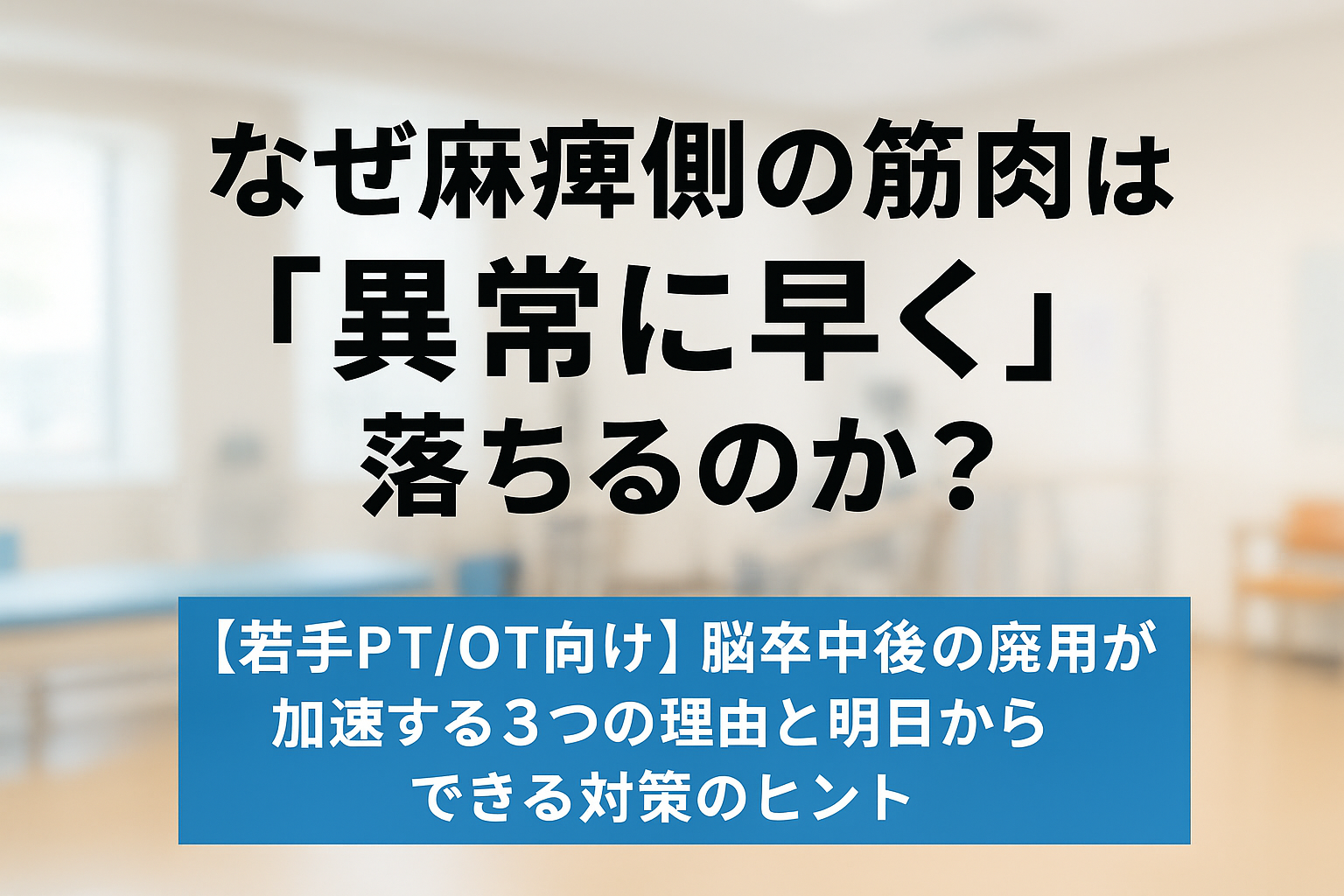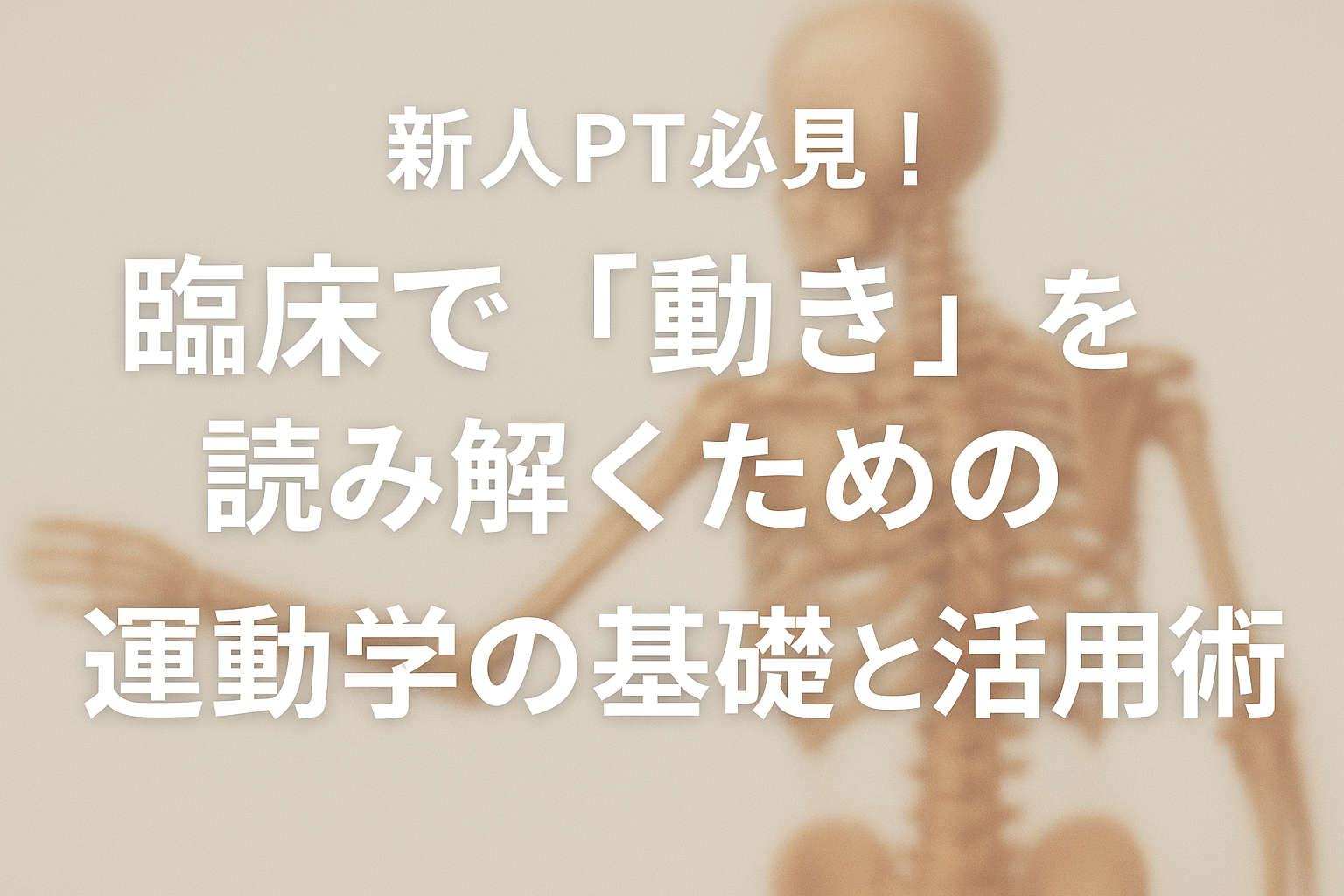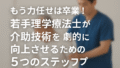はじめに
「あれ、数日前まであった麻痺側のふくらはぎの張りがない…」
「非麻痺側に比べて、麻痺側の腕や足だけがどんどん細くなっていく…」
脳卒中リハビリの現場で、こんな経験はありませんか?
多くの若手セラピストは、この「麻痺側の筋肉が“異常に早く”落ちていく現象」について考えたことがあるのではないでしょうか。
これは単に「使っていないから」という一言で片付けられる問題ではありません。その背後には、神経・代謝・筋線pureレベルで起こる、麻痺側特有の深刻な変化が隠されています。
なぜ、麻痺側の廃用は非麻痺側の2〜3倍の速度で進行してしまうのか?
今回の記事では、その病態生理学的な理由を、最新の研究知見と臨床の視点を交えながら解説していきます。この記事を読めば、明日からの患者さんへのアプローチが変わるはずです。
常識?麻痺側と非麻痺側、廃用進行の“圧倒的な速度差”
脳卒中後の筋萎縮は、私たちが思う以上に「時間との勝負」です。
多くの研究が、発症後わずか数日〜数週間で筋力・筋量が急激に低下することを示しています。特に衝撃的なのは、麻痺側と非麻痺側での進行速度の差です。
📘 最新研究から見る現実
- Desgeorgesら (2021): 発症からわずか3日で、麻痺側下肢の筋線維の太さが有意に減少。
- Ryanら (2023): 亜急性期(2〜6週)において、麻痺側の筋量減少率は非麻痺側の約2倍。
- Hunnicuttら (2020, Systematic Review): 慢性期には、麻痺側大腿部の筋量は非麻痺側より平均**約13%**も小さくなる。
実際に急性期病棟で働いていると、「まだ1週間しか経っていないのに…」と、麻痺側下肢が目に見えて細くなっていく現実に直面します。
非麻痺側も安静にしていれば筋肉は落ちますが、麻痺側は「動かせない(神経入力の途絶)+動かない(活動量の低下)」という二重の負荷がかかるため、廃用が“加速”してしまいます。
なぜ麻痺側の廃用は“加速”するのか?見逃せない3つの理由
では、なぜこれほどまでに麻痺側の廃用は早く進むのでしょうか?「使わないから」という言葉の裏にある、3つの重要なメカニズムを紐解いていきましょう。
理由①:脳からの“司令塔”が機能停止【神経入力のシャットダウン】
最も大きな原因は、脳から筋肉への司令塔である神経活動が途絶えることです。
随意運動の指令が来なくなると、筋肉は「自分はもう必要ない」と判断し、タンパク質の合成を止め、分解を始めてしまいます。これは、電気が通っていない家電がただの箱になってしまうのと同じです。
Matsumotoら (2021)の研究では、発症2週間以内で麻痺側の筋電図活動がほぼ消失していたと報告されています。
「神経興奮が減る → 筋収縮が減る → タンパク合成が減る → 筋量が減る」
この負のスパイラルが、驚くべき短期間で起こっているのです。
理由②:身体の“GPS”がオフになる【感覚入力の喪失】
運動麻痺だけでなく、感覚障害も廃用を加速させる大きな要因です。
麻痺側では、触覚・圧覚、そして関節の位置などを感じる固有受容感覚(Proprioception)の入力が著しく低下します。
自分の手足がどこにあるか感じられないと、脳は次第にその手足を「自分の身体の一部」として認識できなくなります。これが、脳内での身体地図(ボディスキーマ)の崩壊です。
結果として、患者さん自身も麻痺側を意識しなくなり、動かそうとする意欲さえ失われていきます。
理由③:心が身体を“見捨てる”【学習性不使用(Learned Non-use)】
動かそうとしても動かない、感じようとしても感じられない。
この経験が積み重なると、患者さんは無意識のうちに「麻痺側は使えないものだ」と学習してしまいます。
これが「学習性不使用(Learned Non-use)」です。
こうなると、たとえ回復の可能性が残っていたとしても、行動レベルで麻痺側を“放置”するようになり、廃用はさらに強化されるという悪循環に陥ります。
「神経入力の停止」「感覚入力の喪失」「心理的な使用回避」。
これら3つが複雑に絡み合い、麻痺側の廃用を非麻痺側とは比較にならないスピードで進行させているのです。
🔒 この先の内容に興味はありませんか?
ここまで、麻痺側の廃用がなぜ早く進むのか、その根源的な理由を解説してきました。
しかし、私たちセラピストが本当に知りたいのは、
「この加速する廃用に対して、具体的に何をすべきか?」
ということではないでしょうか。
- 廃用が引き起こす、筋組成の“質的”な変化とは?(脂肪浸潤・線維化)
- 拘縮はなぜ起こる?筋膜・関節包レベルでの変化
- 廃用を防ぐための具体的なリハビリ戦略(電気刺激・ロボット・荷重)のエビデンスは?
- なぜ非麻痺側へのアプローチも重要なのか?
- 理学療法士として、廃用という“時間との闘い”にどう向き合うべきか?
これらの問いに対する答えと、明日からの臨床に活かせる具体的な知識を、私が運営する有料noteとメンバーシップ「臨床理学Lab」で詳しく解説しています。
▼ 記事の続きはこちらから ▼
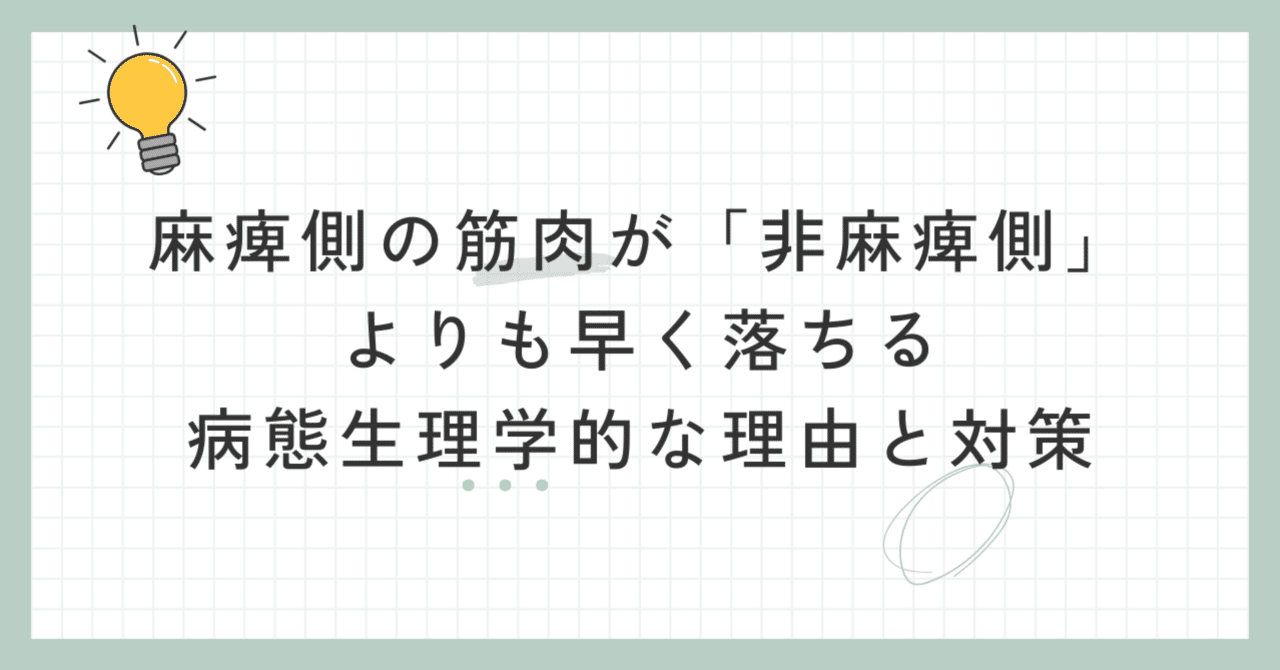
「臨床理学Lab」のメンバーシップ(月額プラン)にご登録いただくと、今回の記事を含む、エビデンスに基づいた実践的な全コンテンツが読み放題になります。
- 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
- 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
- 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
若手セラピストの「なぜ?」を「なるほど!」に変える、深い学びの場を提供しています。

まとめ:廃用は“防げる”合併症である
麻痺側の廃用は、避けられない現象ではありません。
そのメカニズムを正しく理解し、発症直後から適切な介入を行うことで、進行を遅らせ、回復の可能性を最大限に引き出すことができます。
私たち理学療法士・作業療法士の役割は、単に筋力を維持することではありません。
患者さんの身体に「再び動ける」という希望を再構築することです。
この記事が、あなたの臨床の一助となり、目の前の患者さんの未来を少しでも明るくするきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。