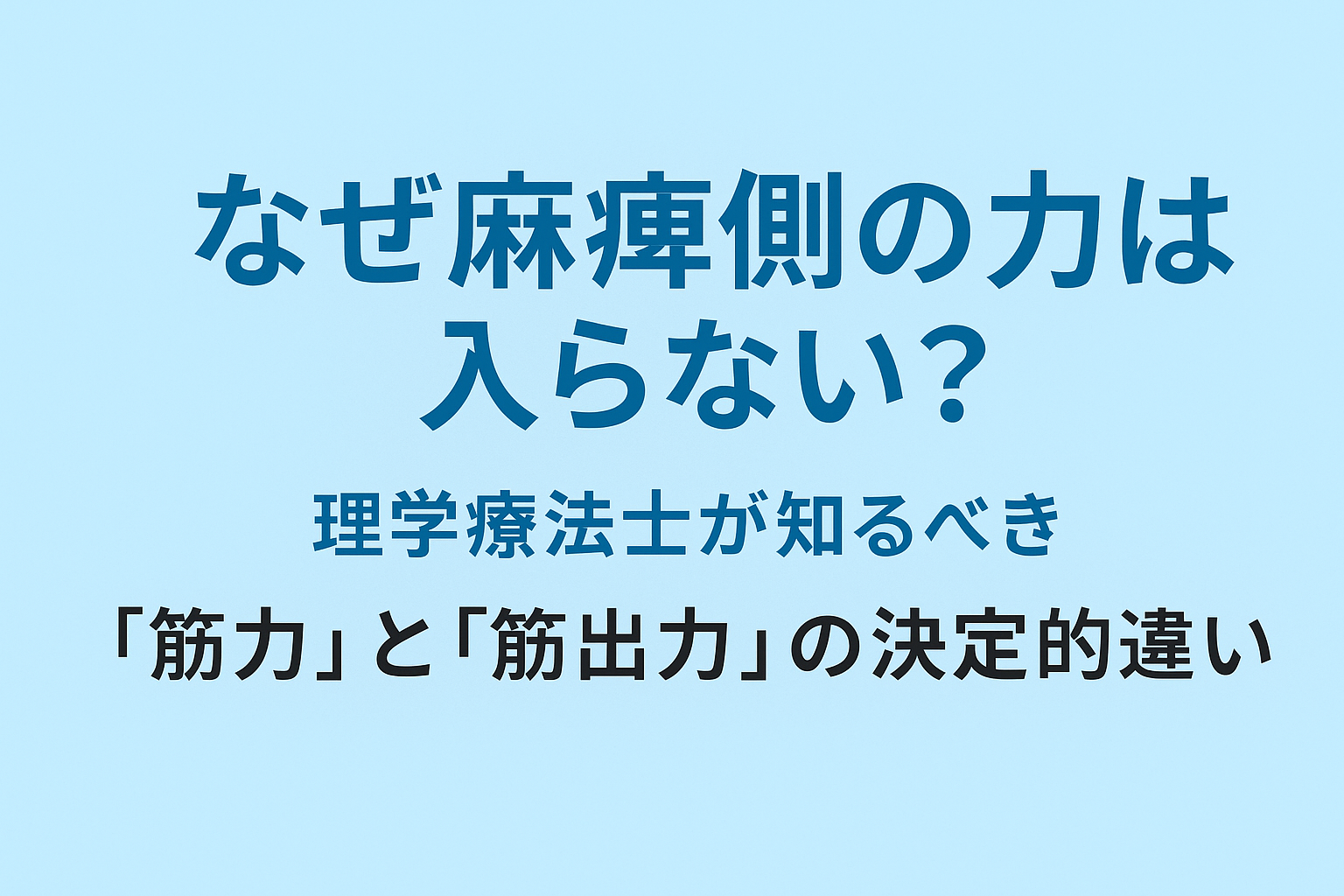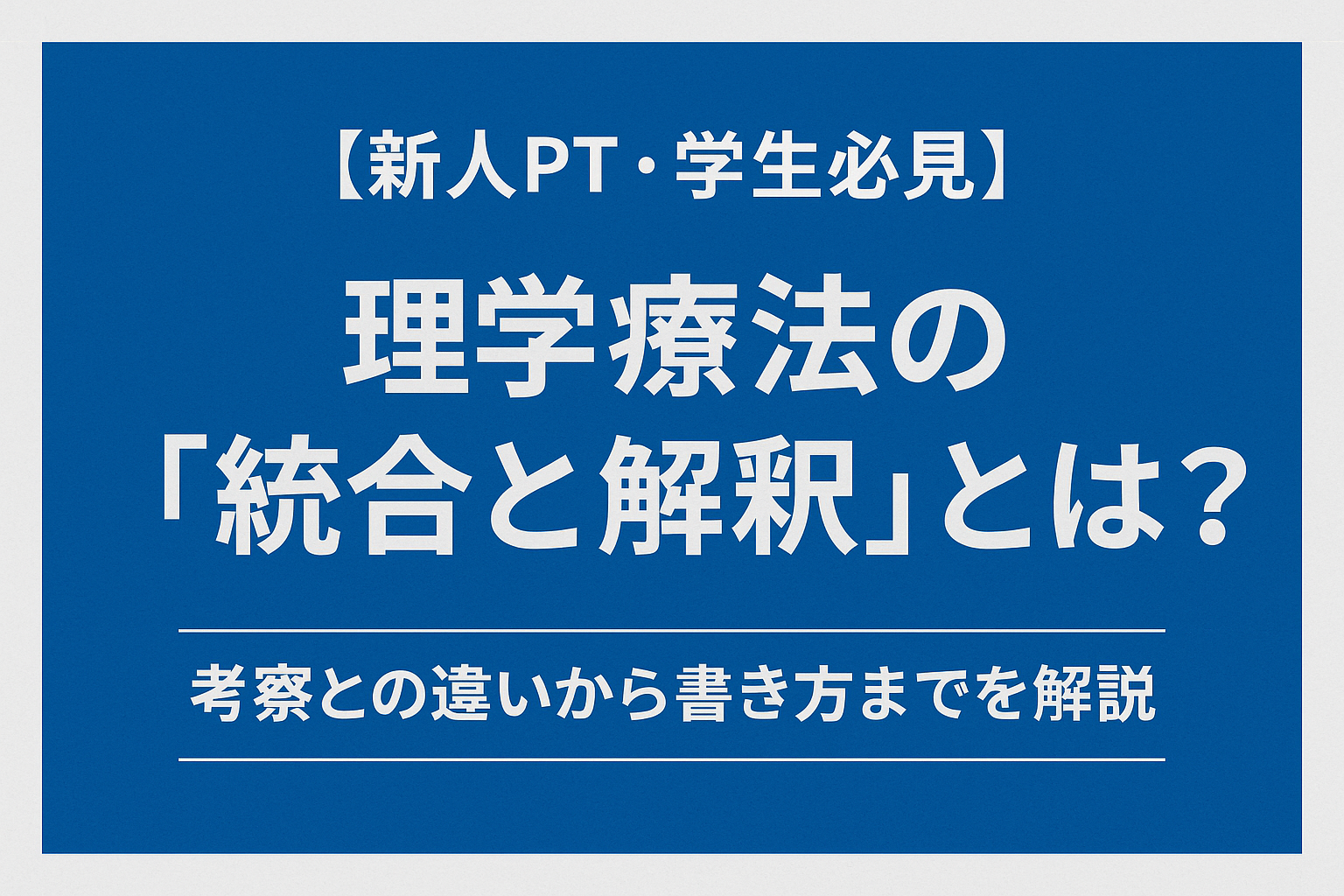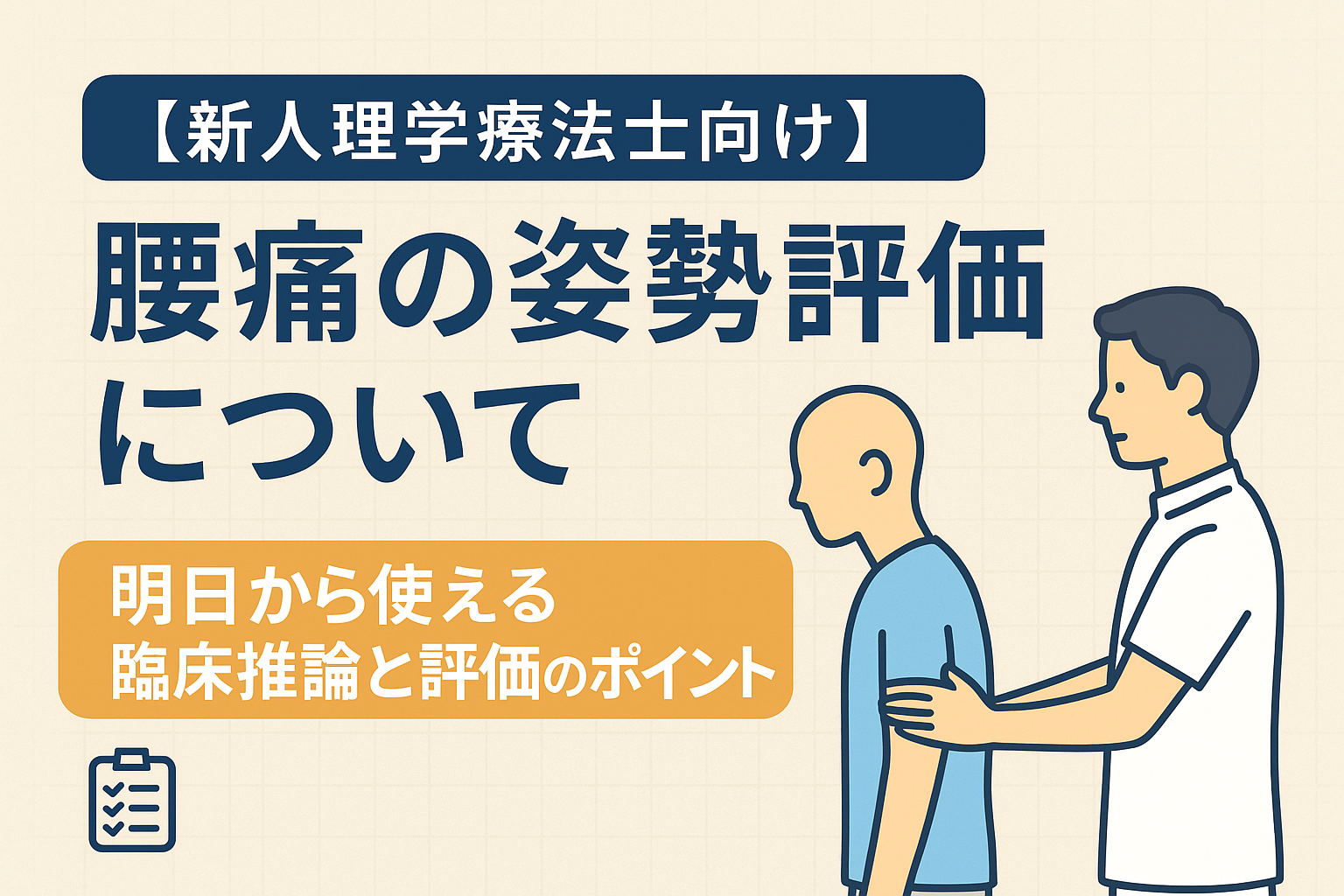はじめに
理学療法士の皆さん、日々の臨床でこんな疑問を感じたことはありませんか?
- 「脳卒中の患者さん。筋肉が痩せていない急性期から、なぜあんなに力が弱いのだろう?」
- 「術後の患者さん、明らかにMMTのスコアが落ちている…これは元々だっけ?」
- 「筋力、筋出力、何が違うんだろう。」
筋肉そのものの問題、つまり「筋力低下」という言葉だけでは十分に説明できないことがあります。その答えの鍵を握るのが、「筋出力」という概念です。
この記事では、似ているようで異なる「筋力」と「筋出力」の違いを基礎から整理し、明日からの評価とアプローチの質を一段階引き上げるための具体的な視点について考えていきます。
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

【基本の整理】筋力 vs 筋出力 – ハードウェアとソフトウェアの違い
まず、言葉の定義を明確に区別しましょう。この2つを混同していると、リハビリの方向性を見誤る可能性があります。
筋力 (Strength) とは? – 筋肉という”ハードウェア”の性能
筋力とは、筋肉が構造的に発揮できる潜在的な最大張力のことを指します。
主に、筋線維の断面積(筋肉の太さ)によって決まる、筋肉そのもののポテンシャルです。
- イメージ: パソコンのCPU性能や、自動車のエンジンの排気量
- 決まる要因: 筋断面積、筋線維タイプ組成など
- 評価指標: (純粋な筋力評価は難しいが)MMTやHHDが臨床では用いられる
筋出力 (Motor Output) とは? – “ソフトウェア”がハードウェアを使いこなす能力
筋出力とは、脳からの指令に基づき、実際に発揮される総合的な力のことです。
簡単に言えば、「持っている筋力を、どれだけ効率よく引き出せるか」という能力を指します。
- イメージ: 高性能なCPU(筋肉)を動かすためのOSやアプリケーション(神経系)の性能
- 決まる要因: 神経系の指令、筋肉の協調性、心理状態、姿勢など
- ポイント: 筋力が高くても、筋出力が低いというケースは、臨床で私たちが日々遭遇している現象そのものです。
なぜ力が出ない?筋出力を左右する4つの重要因子
では、なぜ「持っているはずの力」が出せなくなるのでしょうか。筋出力を低下させる代表的な要因を4つに分けて見ていきましょう。
① 神経系の指令(司令塔の質)
脳から筋肉への指令がうまくいかなければ、当然、力は発揮されません。
- 運動単位の動員: 脳は、必要な力の大きさに応じて、収縮に参加させる筋線維の数を調整します。この動員数が減ると、筋出力は低下します。
- 発火頻度: 運動単位へ送る指令の頻度を高めることでも、力は増強されます。
- 臨床例: 脳卒中による麻痺は、まさにこの神経系の指令が障害されることで生じる、典型的な「一次的な筋出力低下」です。
② 筋肉の協調性(チームワーク)
一つの動作は、多くの筋肉の連携プレーによって成り立っています。
- 主動作筋・協働筋・拮抗筋の連携: 目的の動作に対して、必要な筋肉が適切なタイミングと強さで働き、邪魔になる筋肉(拮抗筋)は適切に抑制される必要があります。
- 臨床例: 脳卒中後の共同運動パターンは、この協調性が乱れ、非効率でぎこちない筋出力しか生み出せない状態と言えます。
③ 心理・感覚系(環境の影響)
患者さんの心や感覚の状態は、筋出力にダイレクトに影響します。
- 痛み・不安・恐怖: これらは中枢神経系に強力な抑制をかけ、筋出力を著しく低下させます(関節原性筋抑制:AMI)。
- モチベーション・集中力: 患者さんの意欲もパフォーマンスを引き出す上で不可欠です。
- 臨床例: TKA術後の患者さんが「痛くて力が入らない」と言うのは、単なる甘えではなく、生理学的な筋出力の低下が起きている証拠です。
④ バイオメカニクス(身体の使い方)
物理的に効率の悪い姿勢では、筋肉は本来の力を発揮できません。
- 姿勢とアライメント: 適切な姿勢は、筋肉が最も効率よく力を発揮するための土台です。
- 関節角度と筋長: 筋肉には、最も力を発揮しやすい長さ(長さ-張力関係)があります。
- 臨床例: 円背姿勢の高齢者が立ち上がりにくいのは、股関節や膝関節の伸展筋群が力を発揮しにくいポジションにあるためです。
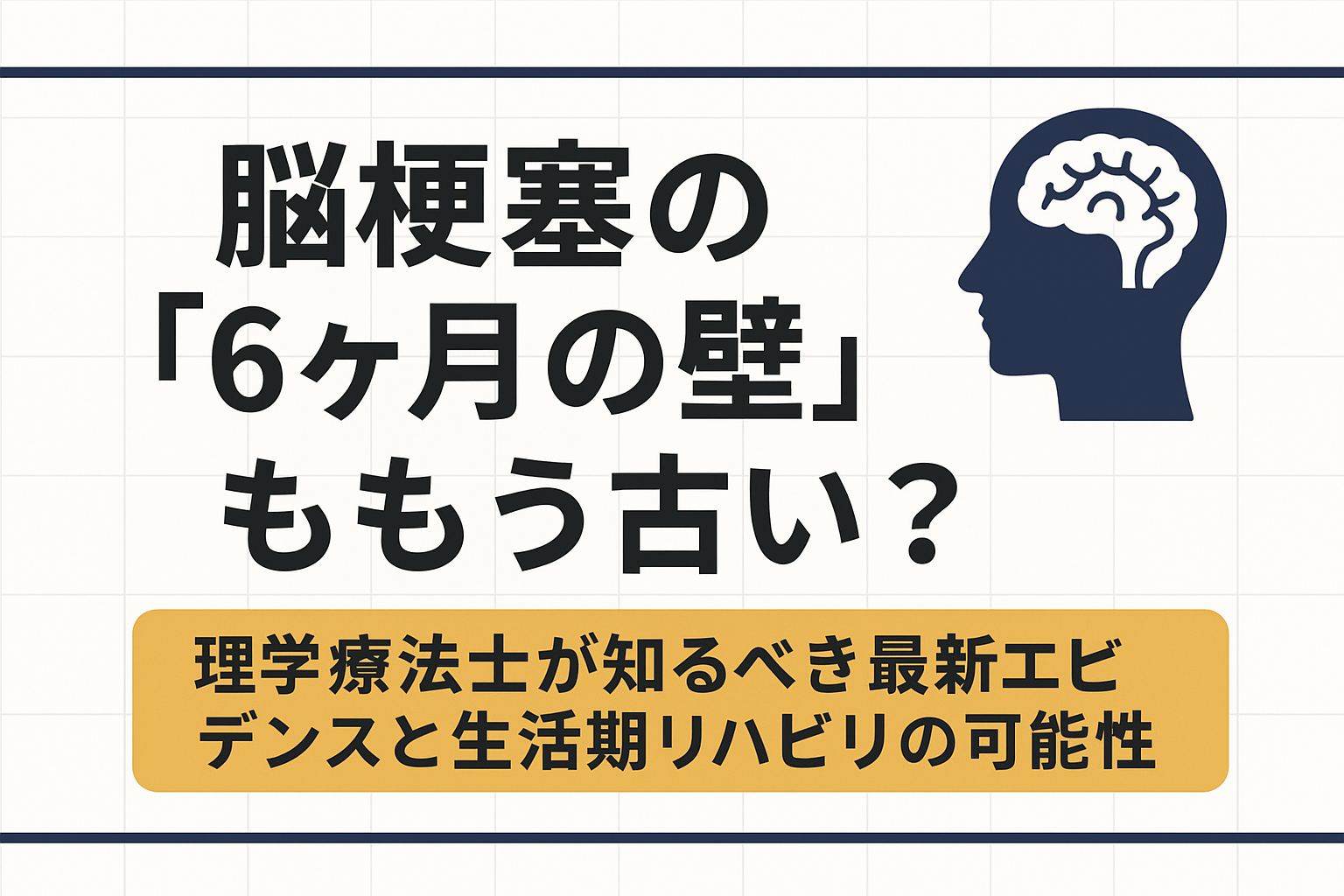

【臨床応用】評価とアプローチの視点を変える
「筋力」と「筋出力」の違いを理解すると、私たちの臨床はどのように変わるのでしょうか。
評価の視点:MMTの数値をどう解釈するか?
MMTは筋力を測る指標ですが、実際には患者さんの意欲、痛み、協調性といった「筋出力」の因子も色濃く反映されています。
「MMT3レベル」という結果が出たとき、
- 本当に筋繊維が萎縮して「筋力」が低下しているのか?
- 麻痺によって神経の指令が届かず「筋出力」が低下しているのか?
- 痛みや恐怖心によって「筋出力」が抑制されているのか?
このように結果の背景を考察することで、アプローチの的が絞られます。
アプローチの幅を広げる具体例
- 課題: 一次的な筋出力低下(神経系の問題)と、それに伴う二次的な筋力低下(廃用)
- アプローチ: 単純な筋トレだけでなく、神経路の再建を促す促通手技や課題指向型訓練で「脳からの指令の出し方」を再学習させることが最優先となります。
- 課題: 疼痛による神経性の筋出力低下(AMI)
- アプローチ: まずは疼痛管理を徹底し、神経の抑制を解除します。その上で**NMES(神経筋電気刺激)**なども活用し、意図的に筋肉を収縮させる感覚を取り戻してから、安全に筋力トレーニングへ移行します。
- 課題: 痛みへの恐怖や不適切な姿勢による筋出力のアンバランス
- アプローチ: 闇雲な体幹トレーニングではなく、リラックスできる環境で正しい身体の使い方(ボディメカニクス)を再学習させ、効率的な筋出力パターンを体に覚えさせることが重要です。
まとめ:患者さんの「発揮できる力」を最大限に引き出すために
今回は、理学療法士が知っておくべき「筋力」と「筋出力」の違いについて解説しました。
- 筋力は、筋肉のポテンシャル(ハードウェア)。
- 筋出力は、神経や心理状態なども含め、そのポテンシャルを引き出す能力(ソフトウェア)。
- 臨床で遭遇する「力が入らない」現象の多くは、後者の「筋出力の低下」が大きく関与しています。
私たちが対峙しているのは、単なる筋肉の衰えではありません。その背景にある脳、神経、心、そして身体の使い方全体を評価し、アプローチすることが求められます。
明日からの臨床で、ぜひ**「この患者さんの“筋出力”を妨げている根本原因は何か?」**という視点を持ってみてください。きっと、これまで見えなかった課題が見つかり、リハビリの質をさらに高めることができるはずです。