【この記事を読むと分かること】
- 上位運動ニューロン障害で「弛緩性麻痺」が起こる神経メカニズム
- 運動野(Area 4)と前運動野(Area 6)の機能と症状の違い
- 臨床での評価やアプローチに活かすための具体的な視点
脳卒中リハビリに関わる理学療法士・作業療法士の皆さん、こんにちは!
臨床現場で、こんな経験はありませんか?
「上位運動ニューロン障害の患者さんなのに、麻痺が弛緩性でフニャフニャだ…」
「教科書では“上位運動ニューロン障害=痙性麻痺”と習ったのに、どうしてだろう?」
この臨床でよく遭遇する疑問は、実は脳の運動野(Area 4)と前運動野(Area 6)の役割を理解することで整理することができます。
今回は、上位運動ニューロン障害における痙性麻痺と弛緩性麻痺の謎を解き明かし、明日からの臨床推論を一段と深めるための知識をお届けします。
なお、すべての症例に当てはまるわけではないため参考程度に日々の臨床の一助となれば幸いです。
お知らせ【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

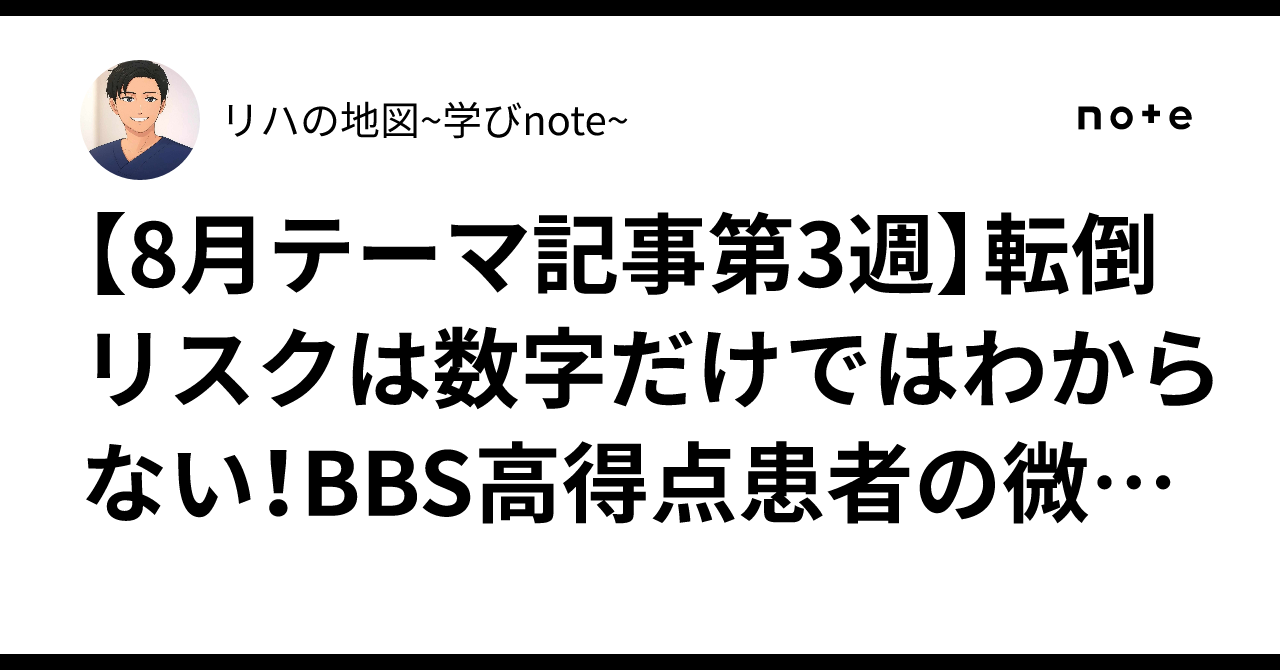
「上位運動ニューロン障害=痙性麻痺」は本当か?
まず、私たちが学生時代に学ぶ上位運動ニューロン障害の典型的な徴候を思い出してみましょう。
- 痙縮(Spasticity)
- 腱反射の亢進
- 病的反射(バビンスキー反射など)の出現
これらは確かに代表的な症状です。しかし、臨床では必ずしもこのパターンに当てはまらないケースに遭遇します。特に急性期では、麻痺が弛緩性(Flaccid)であることも少なくありません。むしろ、多いです。
この症状の多様性は、脳のどの領域が、どの程度ダメージを受けたかによって生まれます。そのカギを握るのが、Area 4とArea 6なのです。
謎を解くカギ:Area 4(運動野) vs Area 6(前運動野)
Fulton(1955)の実験によると、上位運動ニューロン障害は、障害された部位によって全く異なる症状を呈することが示されています。
以下の表は、Area 4、Area 6、そして両方が障害された場合の症状の違いをまとめたものです。(※出典の表9-2を基に要点を整理)
| 障害部位 | Area 4 単独障害 | Area 6 単独障害 | Area 4 + 6 混合障害 |
| 運動障害 | 完全片麻痺 | 不全片麻痺 | 片麻痺の増強 |
| 筋緊張 | 弛緩性(Flaccidity) | 痙縮(Spasticity) | 著明な痙縮 |
| 腱反射 | 減弱 | 中等度亢進 | 著明に亢進 |
| バビンスキー反射 | 陽性(+) | 陰性(-) | 陽性(+) |
| 主な経路 | 錐体路(皮質脊髄路) | 錐体外路系 | 錐体路+錐体外路系 |
この表から、驚くべき事実が見えてきます。
【Area 4(運動野)の単独障害】 → 弛緩性麻痺を引き起こす
Area 4は、随意運動の指令を出す中心的な役割を担い、その線維は主に**錐体路(皮質脊髄路)**を構成します。
驚くべきことに、この錐体路だけが純粋に障害されると、症状は「痙性」ではなく「弛緩性」になります。腱反射も亢進するどころか、むしろ減弱するのです。
ただし、錐体路障害の代表的な徴候であるバビンスキー反射は陽性となります。これが非常に重要なポイントです。
ポイント:純粋な錐体路障害 = 弛緩性麻痺 + バビンスキー反射陽性
【Area 6(前運動野)の単独障害】 → 痙性麻痺を引き起こす
一方、Area 6は運動のプログラミングや準備に関わり、錐体外路系への影響が大きい領域です。
Area 6が障害されると、運動の巧緻性(skilled movement)が損なわれると共に、痙縮や腱反射の亢進といった、私たちがよく知る「痙性」の症状が出現します。これは、皮質から脊髄の反射弓を抑制する経路(網様体脊髄路など)が障害されるためと考えられています。
面白いことに、Area 6単独の障害ではバビンスキー反射は陰性です。
ポイント:錐体外路系の障害 = 痙縮・腱反射亢進
臨床で見る「痙性片麻痺」の正体は?
「じゃあ、なぜ臨床で出会う多くの脳卒中患者さんは痙性片麻痺なの?」
その答えは、臨床でみられる脳梗塞や脳出血の多くが、Area 4とArea 6の両方を巻き込む広範囲な障害だからです。
例えば、中大脳動脈(MCA)領域の広範な梗塞では、運動野と前運動野の両方がダメージを受けます。その結果、
- Area 4の障害による運動麻痺とバビンスキー反射
- Area 6の障害による痙縮と腱反射亢進
これらが合わさって、私たちが臨床で最もよく目にする**「痙性片麻痺」**という症候群が完成するのです。
この知識を理学療法にどう活かすか?
この神経メカニズムを理解すると、日々の臨床がもっと面白くなります。
1. 評価の解像度が上がる
患者さんの麻痺の性質を注意深く観察することで、主たる障害部位の仮説を立てられます。
- 「急性期で弛緩性が目立ち、バビンスキー反射が陽性。これはArea 4(錐体路)のダメージが主体かもしれない」
- 「麻痺は軽度なのに、痙縮が非常に強い。Area 6を含む錐体外路系の障害の影響が大きいのかもしれない」
このように考えることで、評価の視点がより鋭くなります。
2. アプローチの根拠が明確になる
症状の背景にあるメカニズムを理解すれば、アプローチの選択にも自信が持てます。
- 弛緩性が主体の患者さんには、神経筋促通手技や筋の再教育を中心に、運動出力を引き出すアプローチの重要性が高まります。
- 痙縮が主体の患者さんには、筋緊張のコントロールや相反抑制を利用した分離運動の練習など、錐体外路系の過剰な活動を抑えるアプローチの根拠が明確になります。
3. 予後予測の一助となる
回復過程も予測しやすくなります。例えば、急性期に弛緩性麻痺だった患者さんが、徐々に痙縮が出現してくるのは、神経系の再組織化の過程で錐体外路系の影響が顕在化してくる現象として捉えることができます。この変化を予測できれば、ご家族への説明や早期からの対策(ポジショニングやストレッチ指導など)に繋げられます。
まとめ
今回の内容をまとめます。
- 上位運動ニューロン障害の症状は、障害部位(Area 4かArea 6か)によって大きく異なる。
- **純粋な錐体路(Area 4)障害では「弛緩性麻痺」**が起こる。
- 痙縮や腱反射亢進は、主に錐体外路系(Area 6)の障害によって引き起こされる。
- 臨床でよく見る**「痙性片麻痺」は、Area 4とArea 6の両方が障害された混合症状**である。
この知識は、日々の臨床での「なぜ?」を「なるほど!」に変えてくれる強力な武器になります。患者さんの症状をより深く理解し、的確なリハビリテーションを提供するために、ぜひ今回の内容を役立ててみてください。


