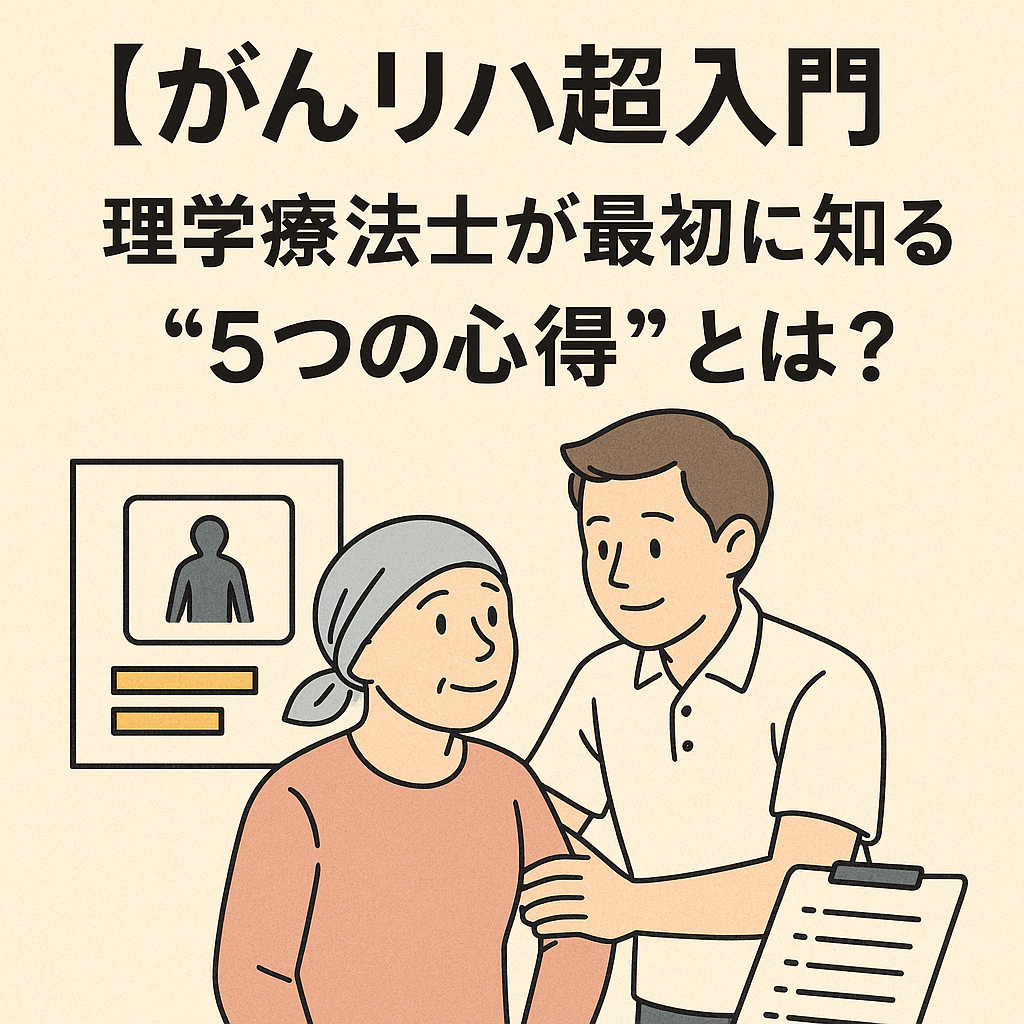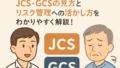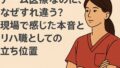はじめに:がんリハビリに“怖さ”を感じていませんか?
理学療法士として働く中で、初めて「がんの患者さん」を担当することになったとき――

動かしても大丈夫なの?

何に気をつければいいの?

何したらいいんだろう
と、不安を感じたことはありませんか?
僕自身、「骨転移があるから、折れたらどうしよう」と手が止まりまったことも少なくありません。
がんリハビリテーションは、高齢化や治療技術の進歩により今後もニーズが高まる分野かと思います。
この記事では、がん患者さんを初めて担当する理学療法士が**「これだけは知っておきたい」**と感じる5つのポイントを解説します。
1. 「がんの病期」と「治療内容」
理解すべきは“いまどのフェーズか”
がん患者さんにリハビリを行う際、最初に確認すべきは「現在の治療フェーズ」です。
がんには手術・化学療法・放射線治療・免疫療法・緩和ケアなど、複数の治療段階があります。それぞれの時期に応じて、身体状態やリスクが大きく変わります。
たとえば、術後直後であれば創部の痛みや臓器機能の変化に配慮しなければなりませんし、化学療法中なら免疫力低下や倦怠感が大きな課題になります。
病期(ステージ)による違いにも注目
がんは「ステージI〜IV」に分類され、進行度によって治療方針も違います。
特にステージIVの患者さんでは、転移・再発・全身状態の悪化などが見られるため、アプローチの目的が「治す」から「支える」方向に変わっていくケースもあります。
2. リスク管理が最優先
がん患者さんのリハビリで何より重要なのが「リスク管理」です。
代表的なリスクと注意点
- 骨転移 → 転移部位によっては荷重禁止、骨折リスク
- 白血球減少 → 感染リスクが高く、マスク・手洗いなどの徹底が必要
- 血小板減少 → 内出血、点状出血、圧迫・転倒に注意
- 貧血 → 疲労感や息切れ、過剰な運動で悪化の恐れあり
これらは血液データからも判断できます。
**Hb(ヘモグロビン)、WBC(白血球)、PLT(血小板)**など、医師・看護師から情報共有を受けながら安全な介入を計画しましょう。
3. がん関連疲労(CRF)を理解しよう
がんリハビリにおいて特に見落とされやすいのが**「がん関連疲労(Cancer-Related Fatigue:CRF)」**です。
これは、治療中・治療後に持続する強い倦怠感や疲労感で、休息を取っても回復しにくいのが特徴です。
CRFへの対応ポイント
- 疲労度のスケール(NRSやBorg)を用いて主観的評価を行う
- 無理のない運動処方を行う(例:短時間の歩行訓練や関節可動域運動)
- 患者の言葉を丁寧に拾う:『疲れやすくて動きたくない』=CRFかも?
CRFの存在を知らないと、「怠けている」「リハビリのやる気がない」と誤解する可能性もあるため、リハビリ職にとって必須の知識です。
4. ACP(アドバンス・ケア・プランニング)とリハビリの関わり
ACPとは、「患者が将来の医療やケアについて前もって考え、希望を共有しておくプロセス」です。
理学療法士が関わる意味
- 患者さんの「こうなりたい」を聞き取る立場として重要
- 病状進行とともに、目標が「歩けるようになりたい」から「自分の部屋で過ごしたい」へと変わることも
- リハビリの“ゴール”が、単なるADL獲得だけでなく、“生活の質(QOL)”の維持へと変化する
ACPを理解していないと、「意味のあるリハビリ」が提供できなくなる可能性があります。
5. 多職種連携が成果を左右する
がんリハビリではチーム医療が基本です。
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、MSW(医療ソーシャルワーカー)など、さまざまな職種と連携して情報を共有することが、より良い介入につながります。
実際の現場で大切にしたいこと
- 「○○の治療が始まったので運動量を調整した方がよさそう」など、医師とこまめに相談
- 看護師からの「最近すごく疲れているようです」という一言が、介入判断の決め手になることも
- MSWや栄養士と連携して、「生活再建」までを見据えた支援を行う
おわりに:がんリハは「怖い」から「寄り添う」へ
がん患者さんを担当するのは、確かに怖いと感じることもあります。
でも、その一歩を踏み出すことで、**「生きている今を支える」**というリハビリの新しい可能性に出会えます。
あなたの声かけや1回の介入が、患者さんにとって「安心」や「希望」になるかもしれません。
【まとめ】
- 治療フェーズと病期の把握が第一歩
- リスク管理を徹底し、安全に配慮した介入を
- がん関連疲労(CRF)を理解して、無理のない支援を
- ACPを通じて、患者の「本音」と「望む生活」を尊重する
- チーム医療の中で、理学療法士としての視点を発揮する
もっと知識を深めたい人は「臨床理学Lab」
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇