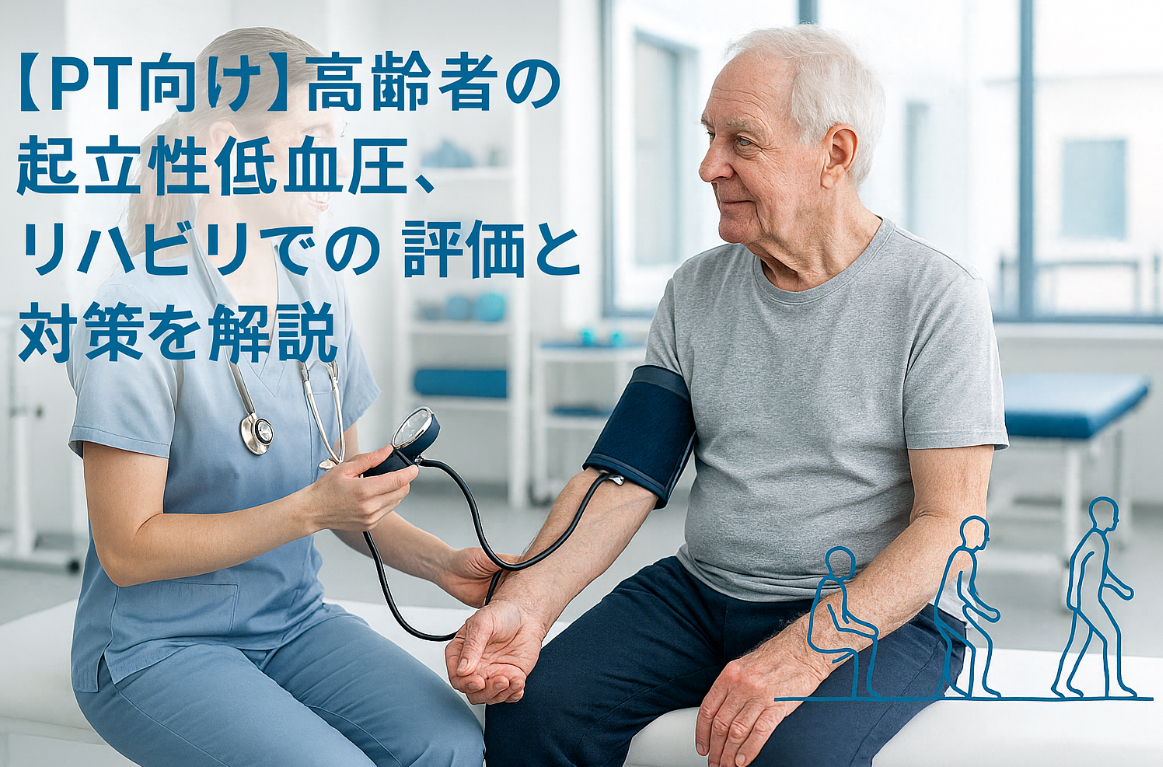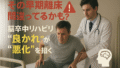はじめに
「リハビリで立位練習をすると、いつも『ふらふらする』と訴える…」
「離床に意欲的でない高齢の患者さん、もしかして起立性低血圧が原因?」
理学療法士として臨床現場に立つ中で、このような場面に遭遇し、対応に悩んだ経験はありませんか?
高齢者の「立ちくらみ」や「ふらつき」の背後には、転倒や廃用症候群のリスクを高める「起立性低血圧」が隠れていることが少なくありません。
この記事では、高齢者のリハビリテーションに関わる理学療法士に向けて、起立性低血圧の基礎知識から、見逃さないための評価方法、そして明日から実践できる具体的なリハビリ介入の工夫まで、網羅的に解説します。
あくまで、一つの選択肢の一つとして活用してみてください。日々の臨床の一助となりますように。
臨床理学Labについてお知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

なぜ? 高齢者の起立性低血圧が転倒・廃用につながる理由
起立性低血圧とは、身体を起こした際に血圧が急激に下がり、脳への血流が不足する状態です。これにより、めまいやふらつき、失神などを引き起こします。
この症状が高齢者にとって特に危険なのは、以下のような負の連鎖を生むからです。
- 転倒リスクの増大: 立ち上がりや歩き始めの一瞬のふらつきが、大腿骨骨折などの重篤な怪我に直結します。
- 活動意欲の低下: 「動くと気持ち悪くなる」という不快な経験が、リハビリや離床への意欲を奪います。
- ADL自立度の低下: トイレや更衣など、立ち上がりを伴うすべての動作が困難になり、介助量が増加します。
- 廃用症候群の進行: 活動量が減ることで、筋力、心肺機能、認知機能が急速に低下してしまいます。
私たち理学療法士は、この連鎖を断ち切るために、起立性低血圧への正しい知識とアプローチが求められます。
起立性低血圧の基礎知識|原因とメカニズム
まずは基本をおさらいしましょう。
【診断基準】
一般的に「起立後3分以内に、収縮期血圧が20mmHg以上、または拡張期血圧が10mmHg以上低下する状態」と定義されています。
【主な原因】
立ち上がった際の血圧維持メカニズム(自律神経の働き)が破綻することで起こります。
- 自律神経障害: 加齢、糖尿病、パーキンソン病など
- 循環血液量の減少: 脱水、利尿薬の使用
- 薬剤の副作用: 降圧薬、向精神薬など
- 長期臥床: 入院などによる活動性低下
【臨床の視点】高齢者特有の背景因子を見逃すな!
教科書的な原因に加え、高齢者の臨床では以下の要因が複雑に絡み合っていることを念頭に置く必要があります。
- 隠れ脱水: 水分摂取量の不足や口渇感の低下により、本人が自覚しないうちに脱水状態にあります。
- ポリファーマシー(多剤併用): 複数の薬を内服していることで、副作用として血圧が下がりやすくなっています。
- サルコペニア・フレイル: 下肢の筋力低下は、血液を心臓に送り返す「筋ポンプ作用」の著しい低下を意味します。
- 心疾患の合併: 心不全など、心臓自体のポンプ機能が低下しているケースも少なくありません。
起立性低血圧の評価方法|血圧測定と動作観察のポイント
「なんとなくふらつく」という訴えを、客観的な評価で裏付けすることが重要です。
STEP1:臥位・立位の血圧測定
これは必須の評価です。以下の手順で正確に測定しましょう。
- 臥位安静: まずは仰向けでリラックスした状態の血圧・脈拍を測定。
- 立位へ移行: 患者さんのペースで立ち上がってもらいます。
- 立位後の測定: 立位直後、1分後、3分後の3点で血圧・脈拍を測定。
- 症状の確認: 各測定時に「めまい」「ふらつき」「目の前が暗くなる感じ」などの自覚症状を必ず聴取します。
STEP2:TUGや立ち上がり動作の質的評価
血圧測定と併せて、動作の中からヒントを探します。
- TUG(Timed Up and Go test): 椅子から立ち上がった直後に、ふらつきや躊躇、歩き出しの遅れがないか観察します。
- 立ち上がり動作分析: 手すりに強く依存したり、極端にゆっくり立ち上がったりする動作は、血圧の急な変動を避けるための代償行動かもしれません。
【明日から使える】リハビリ介入の工夫と実践的アプローチ
評価に基づき、安全かつ効果的なリハビリプログラムを立案します。キーワードは**「段階的」「多角的」**です。
① 体位変換の段階付け|急がず重力に慣らす
いきなり立位を目指すのではなく、徐々に身体を起こしていきます。
- Level 1:ベッドのギャッチアップ (30°→60°→90°)
- Level 2:端座位の保持 (足底をしっかり床につける)
- Level 3:座位での運動 (足踏み、貧乏ゆすりなど)
- Level 4:支持物を利用した立位保持
各レベルで血圧や症状を確認し、クリアできたら次のステップへ進みましょう。
② 筋ポンプ作用を促す運動療法
下肢に溜まった血液を心臓に戻す力を高める運動は非常に効果的です。
- 離床前に必ず!: 臥位での足関節底背屈運動(アンクルポンプ)は、血流を促す準備運動として必須です。
- 座位でできること: 膝伸展運動、足踏み
- 立位で行うこと: その場での足踏み、踵上げ運動(カーフレイズ)
③ 物理的対策と多職種連携
理学療法士だけでは解決できない問題は、チームでアプローチします。
- 弾性ストッキング・腹帯の活用: 下肢への血液のうっ滞を物理的に防ぎます。看護師と相談し、医師の指示のもと導入を検討しましょう。
- 水分・塩分摂取の推奨: リハビリ前にコップ1杯の水を飲んでもらうだけでも効果的な場合があります。医師や看護師、管理栄養士と連携し、摂取管理について相談します。
- 薬剤の調整依頼: 評価結果を医師に正確に報告し、原因となっている可能性のある薬剤の調整を相談することも重要な役割です。
【ケースで学ぶ】離床が進まない高齢者へのアプローチ例
85歳女性、肺炎で入院後、1週間の臥床。離床を試みるも「強いめまい」で端座位も困難。
【PTの対応】
- 評価: 臥位血圧130/70mmHg。端座位をとると収縮期血圧が30mmHg低下し、強い症状が出現。長期臥床による起立性低血圧と判断。
- 介入プラン:
- 初日: 無理に起こさず、臥位でのアンクルポンプと、ギャッチアップ60°での座位保持(5分)から開始。
- 連携: 看護師に評価結果を共有し、日中の水分摂取を促してもらうよう依頼。
- 2日目以降: リハビリ前に水分摂取を習慣化。弾性ストッキングを装着。ギャッチアップ座位の時間を徐々に延長し、座位での足踏み運動を追加。
- 結果: 約1週間後、めまいなく安定して端座位がとれるようになり、平行棒内での立位訓練へとスムーズに移行できた。
まとめ:転倒予防とADL向上の鍵は、起立性低血圧への視点
高齢者のリハビリテーションにおいて、起立性低血圧は決して軽視できない問題です。
私たち理学療法士は、筋力やバランスだけでなく、血圧というバイタルサインを的確に捉え、リハビリ内容を個別最適化する専門家です。
「なぜ、この患者さんは動きたがらないのだろう?」
その問いの答えが、起立性低血圧にあるかもしれません。
この記事で紹介した評価とアプローチを参考に、患者さんの安全を守り、その人らしい生活を取り戻すためのリハビリテーションを実践していきましょう。