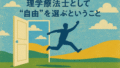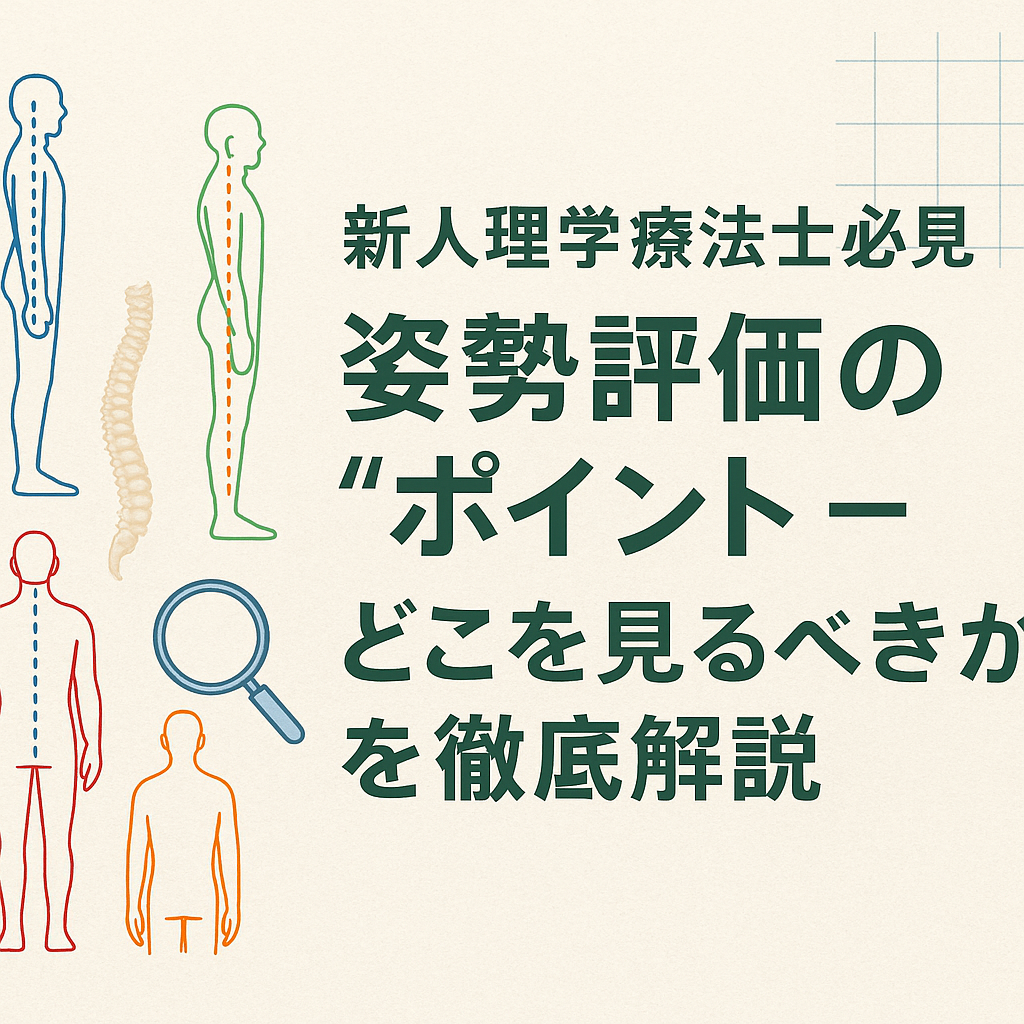はじめに
2025年に改定された心不全診療ガイドラインでは、心不全患者の運動療法の重要性と安全性が一層強調されています。
心不全は慢性的な疾患であり、患者の生活の質(QOL)に大きな影響を与えますが、適切な運動療法を行うことで改善が期待できます。しかし、運動療法を実施する際には、負荷設定の基準や中止基準を守ることが重要です。
本記事では、ガイドライン改定後に求められる運動療法の実践方法とその安全管理について、理学療法士や医療従事者が理解しておくべきポイントを解説します。
\より専門的な記事は臨床理学Labから!/

心不全患者における運動療法の重要性とは?
運動療法の影響と治療効果
心不全は、心臓が十分に血液を送り出せないため、体全体に酸素や栄養を供給することが難しくなります。そのため、運動機能が低下し、日常生活に支障をきたすことが多いです。運動療法は、これを改善するための重要な治療手段となります。心不全患者における運動療法の効果としては、以下の点が挙げられます。
適切な運動は、心臓の拍出量を増加させ、酸素供給能力を向上させます。また、心臓の筋肉の強化を促し、疲れにくい体を作ることができます。
有酸素運動や筋力トレーニングによって、患者の運動耐容能(VO₂max)が向上し、日常生活の動作をこなす能力が改善されます。
適切な運動療法は、心不全の悪化を予防し、再入院のリスクや死亡率を低下させることが多くの研究で示されています。これは心臓への負担を減らすため、重要な治療戦略となります。
長期にわたる心不全の管理には、患者の精神面での支援も必要です。運動はストレス軽減や不安の解消に役立ち、抑うつ状態の予防や改善にも効果があるとされています。
心不全患者のリハビリにおいて運動療法は、身体面だけでなく、精神的・社会的な回復にも寄与する非常に重要な役割を果たします。
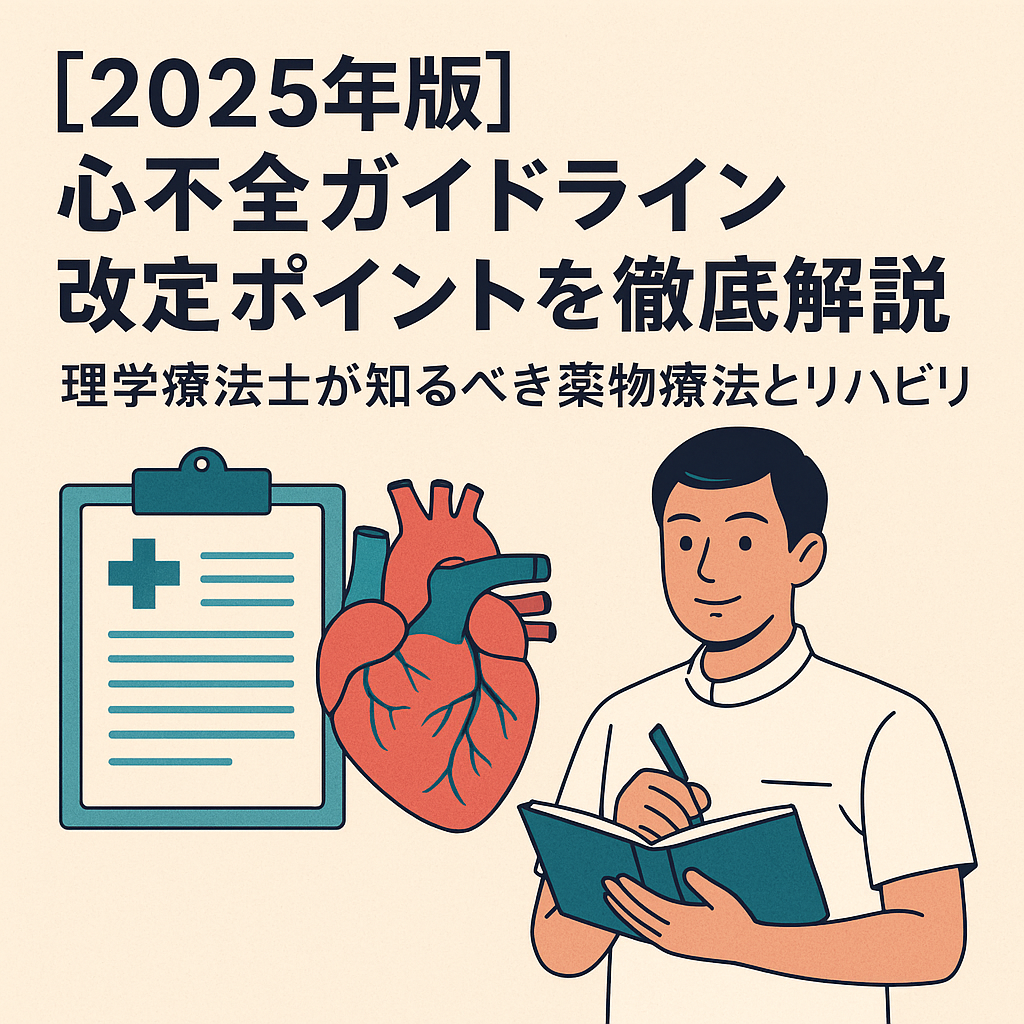
ガイドライン2025:運動療法の目的と位置づけ
心不全管理におけるリハビリの役割
心不全は薬物療法や外科的治療が主流となりますが、運動療法はそれらの治療と併用することでより高い効果を発揮します。運動療法の目的は、心不全の症状を緩和し、**患者の生活の質(QOL)**を向上させることです。具体的には、以下のような役割があります。
心不全患者は運動耐容能が低下しているため、運動療法により耐久性を高め、日常生活での活動レベルを向上させることが重要です。
適切な負荷をかけることで、心臓の運動応答力が高まり、血液の循環が改善されやすくなります。これにより、心不全による症状を軽減が期待できます。
運動によって血圧や体重の管理が改善され、心不全の再発リスクを減少させます。
リハビリ、特に心臓リハビリにおける運動療法の目標は、個別の患者に応じた運動処方を行い、患者が安全に運動を続けられるようにサポートすることです。これには医療従事者との密な連携と患者の状態に応じた負荷の調整が必要となります。
安全な負荷設定の方法【心不全運動療法】
運動負荷試験(CPX)を活用する
運動負荷試験(CPX)は、心不全患者の運動耐容能や心機能を評価するために非常に有効な検査方法です。
CPXを実施することで、患者のVO₂max(最大酸素摂取量)や嫌気性代謝閾値(AT)の同定など、運動強度を把握するための情報を知ることができます。このデータをもとに、安全な運動負荷を設定することが可能になります。
CPXでは、運動を行いながら酸素消費量を測定し、患者の最大酸素摂取量(VO₂max)を求めます。これにより、どの程度の運動耐容能が保たれているか、生命予後や運動療法の効果判定などの情報を得ることができます。
嫌気性代謝閾値(AT)を把握することで、至適運動強度や運動療法の効果判定など、運動処方に必要な情報を知ることができます。
CPXを通じて、運動中の心拍数や血圧の変動を確認し、安全に運動が行える範囲を特定します。
負荷強度の設定基準
2025年改定ガイドラインでは、以下の基準に基づいた運動負荷設定が推奨されています。
- VO₂maxの50〜70%
VO₂maxは運動能力の指標であり、その50〜70%の範囲で運動を行うことが一般的に安全で効果的とされています。 - 心拍数
運動中の心拍数は最大心拍数の50〜85%を目安に設定します。AT時の心拍数が算出できている場合は、THR(TargetHeartRate)はそのAT時点での心拍数を使用。CPXは行えておらず、AT時点での心拍数が不明な場合はカルボーネン法や、安静時心拍数+30bpmで設定し、β遮断薬の内服がある場合は安静時心拍数+20bpmをTHRとする。高齢者や重症患者では、低い強度から始めることが重要です。 - Borgスケール
Borgスケール11〜13(ややきつい)の範囲が推奨されており、これは患者が運動中に感じる息切れや疲労感を基に設定されます。
これらの基準に従うことで、患者に過度の負荷をかけず、段階的に負荷を増やしていくことが可能です。

運動療法の中止基準:具体的な数値と症状
運動療法を行う際は、常に中止基準を意識することが重要です。以下の基準を超えた場合は、運動を中止し、再評価が必要です。
バイタルサインの変化による中止基準
- 心拍数の異常な上昇
運動開始から急激な心拍数の増加が見られる場合、特に最大心拍数の30%以上または心拍数が120/分を超える場合は、運動を中止します。 - 血圧の低下
収縮期血圧が運動前より10mmHg以上低下する場合、血圧が不安定である可能性があるため、運動を中止するべきです。 - 酸素飽和度の低下
SpO₂が90%以下に低下した場合、酸素供給が不十分であるため、運動を中止します。
自覚症状による中止基準
- 強い息切れ
Borgスケールが15以上(非常にきつい)になった場合、運動を中止します。 - 胸痛や不快感
胸痛や圧迫感、締めつけられる感覚が現れた場合、すぐに運動を中止し、医師に報告することが重要です。 - めまいや意識障害
めまいや軽度の失神感を訴える場合も、即座に運動を中止します。
心電図異常・不整脈による中止基準
- 持続的な心室性不整脈
心電図上で心室性不整脈が確認された場合、運動を中止します。 - 虚血性変化の出現
ST下降やT波逆転など、虚血の兆候が見られた場合も中止が必要です。
これらの基準を遵守することで、患者の安全を確保し、治療効果を最大化することができます。
安全管理とリスクマネジメントの実践ポイント
運動前評価でリスクを見逃さない
運動療法を開始する前には、徹底した評価が必要です。以下の項目をチェックリストとして活用しましょう。
- 体重の変化
体重増加(2kg以上)や急激な減少が見られる場合、浮腫の可能性や水分バランスの乱れが考えられます。 - 呼吸状態
呼吸困難や起坐呼吸(横になると息切れが強くなる状態)の有無を確認します。 - 浮腫の有無
下肢の浮腫が見られる場合、循環機能の悪化が考えられ、過度な負荷は避けるべきです。