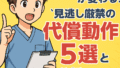その評価、もったいないかも?
「10m歩行テストを再評価したら、タイムはしっかり改善!でも、ふと記録を見ると歩数が前回と全く同じ…。なぜ?」
リハビリテーションの現場で、こんな経験はありませんか?
患者さんの「前より楽に歩けるようになった」という手応えと、データ上の「変わらない」部分。この一見矛盾した結果にこそ、臨床の質をもう一段階引き上げるヒントが隠されています。
この記事では、この現場でよくある“現象”を「臨床推論」の視点から深掘りします。単なる結果の解釈で終わらず、明日からのアセスメントとアプローチに繋げるための思考プロセスを、解説していきます。
\臨床理学Labで臨床推論のトレーニング/

【本題①】基本の再確認:10m歩行テストは「タイム」だけじゃない
10m歩行テストは、歩行能力を評価する上で非常にシンプルかつ有用なツールです。しかし、その手軽さゆえに、私たちは無意識に「タイム」だけを追いかけていないでしょうか。
▶ 歩行能力の「量」と「質」を捉える評価
10m歩行テストの第一の指標は、歩行速度という「量的」な側面です。しかし、同時に「歩数」や「歩容(歩きぶり)」を観察することで、歩行の安定性や効率性といった「質的」な側面も評価できる、非常に奥深い評価バッテリーなのです。
▶ 陥りがちな「タイム至上主義」への警鐘
「タイムが短縮したから改善した」と短絡的に結論づけてしまうのは危険です。なぜなら、そのタイム短縮が、体幹を左右に大きく振るなどの代償動作によって生み出されている可能性や、転倒リスクが増大している可能性を見逃すことにつながるからです。
タイム、歩数、そして歩容。この3つの視点を持つことが、より精度の高い歩行分析の第一歩です。

【本題②】タイムが改善、歩数は横ばい…この結果が意味するもの
ここからが本題です。「タイムは改善したのに、歩数は変わらない」という結果をどう解釈すればよいのでしょうか。
▶ 謎を解くカギは「歩行速度の公式」にあり
まず、歩行の基本となるシンプルな公式を思い出してみましょう。
歩行速度 = 歩幅(ストライド長) × 歩行率(ピッチ/ケイデンス)
- 歩幅(ストライド長): 一歩の大きさ
- 歩行率(ピッチ): 単位時間あたりの歩数(脚を回転させるテンポ)
この公式に、今回の結果を当てはめてみましょう。
- 歩行速度 → タイムが改善したので「向上」
- 歩幅 → 10mの距離を同じ歩数で歩いているので「変化なし」
すると、答えは自ずと見えてきます。
▶ 結論 → 「歩幅は変わらず、ピッチが上がった」
つまり、患者さんの歩行は「一歩の大きさは以前と変わらないけれど、脚を繰り出すテンポが速くなった」と解釈できます。これは紛れもない改善ですが、なぜピッチだけが向上したのでしょうか?
そこには、さらに深い理由が隠されています。
▶ なぜピッチが向上したのか?考えられる3つの理由
- 起始・終止動作の改善
歩き出しの「よっこいしょ」という躊躇や、ゴールで止まる際のふらつきが軽減した可能性があります。これにより、10mを通過する全体的な動作がスムーズになり、結果としてタイムが短縮されます。 - 歩行リズム(テンポ)の向上
麻痺や痛みによって乱れていた歩行リズムが整い、リズミカルに脚を振り出せるようになったのかもしれません。これは、筋出力のタイミングや左右の協調性が改善した証拠です。 - バランス能力の向上による「一歩あたりの不安の軽減」
これが最も重要なポイントかもしれません。一歩一歩の立脚期が安定し、身体のグラつきが減少したことで、「倒れるかもしれない」という潜在的な不安が軽減します。その結果、自信を持って次の一歩を素早く踏み出せるようになり、ピッチが向上したのです。

【臨床応用】その解釈から「次の一手」を考える
この臨床推論を、明日からのリハビリにどう活かせばよいのでしょうか。3つのステップで考えてみましょう。
【Step1】まずはポジティブな変化を認め、共有する
「ピッチが上がった」ことは、素晴らしい改善点です。「以前よりもテンポ良く、スムーズに歩けるようになりましたね!」と、まずは患者さんと成果を共有し、リハビリへのモチベーションを高めましょう。このポジティブなフィードバックが、次のステップへの意欲を引き出します。
【Step2】「なぜ歩幅は伸びないのか?」新たな課題をアセスメントする
次に、歩数が変わらなかった=**「歩幅が伸び悩んでいる」**という新たな課題に目を向けます。なぜ、患者さんは大きな一歩を踏み出せないのでしょうか?考えられる原因をアセスメントします。
- 【身体機能の要因】
- 股関節の伸展可動域制限
- 推進力となる足関節の底屈筋力低下
- 立脚期の安定に不可欠な体幹機能の低下
- 振り出し脚のクリアランスを保つための足関節背屈制限
- 【心理的な要因】
- 大きく足を踏み出すことへの転倒恐怖心
- 過去の転倒経験による過剰な防衛反応
【Step3】「歩幅の拡大」を目指したアプローチへ繋げる
アセスメントで導き出した仮説に基づき、リハビリプログラムを具体化します。
- 目標の再設定:
「次は、もう少し大股で歩いて、もっと楽に前に進めるようになりましょう」と、患者さんと共に具体的で分かりやすい目標を設定します。 - 介入プログラムの例:
- 可動域改善: 股関節伸展や足関節背屈のストレッチ、モビライゼーション
- 筋力強化: ヒールレイズによる下腿三頭筋の強化、ブリッジによる殿筋群・体幹の強化
- バランス・歩行練習: 床に引いた線をまたぐ、目標物に向かって歩くなど、視覚的フィードバックを利用して歩幅の拡大を促す練習
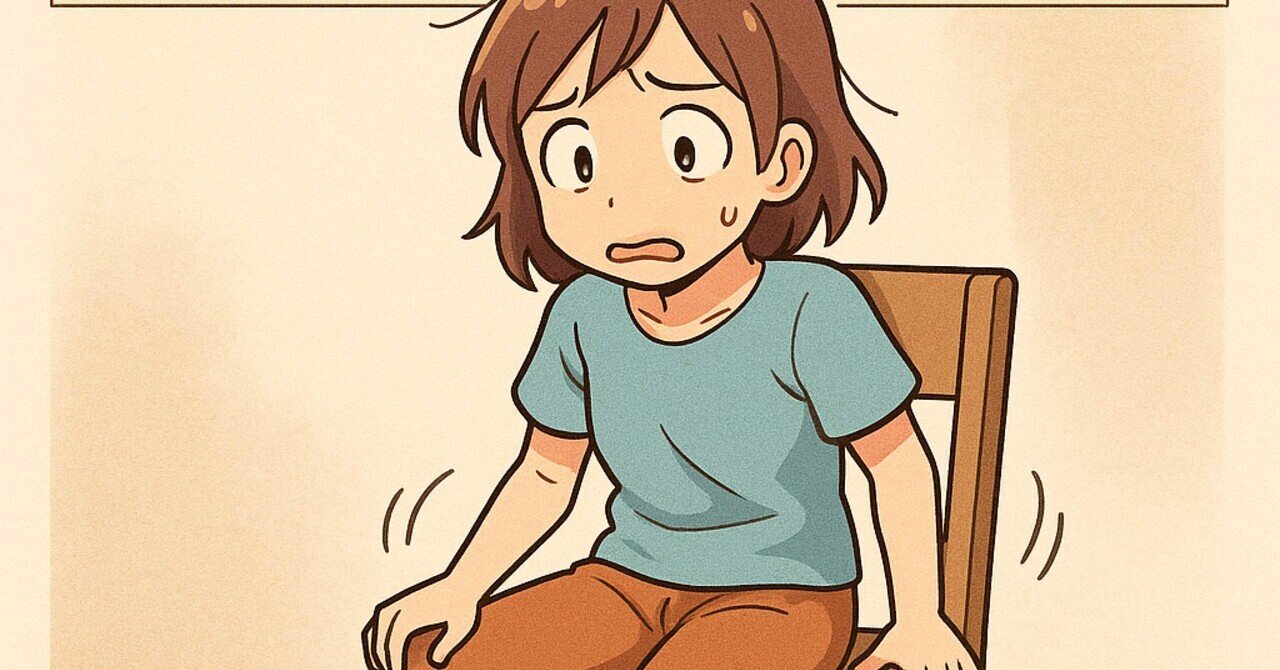
【まとめ】数字の裏側を読む力が、臨床の質を高める
10m歩行テストは、「タイム」と「歩数」という、たった2つの数字から多くの情報を引き出せるパワフルな評価です。
**「タイム改善、歩数不変」**という結果は、**ピッチ向上という「成果」**と、**歩幅停滞という「課題」**の両方を示唆してくれる貴重なサインです。
この「なぜ?」を考え、仮説を立て、検証していく臨床推論のプロセスこそが、マニュアル通りではない、患者さん一人ひとりに最適化されたリハビリテーションを提供するカギとなります。
明日からの臨床で、ぜひタイムと歩数の両方に注目し、その裏側にある物語を読み解いてみてください。あなたの評価の質が、きっと変わるはずです。