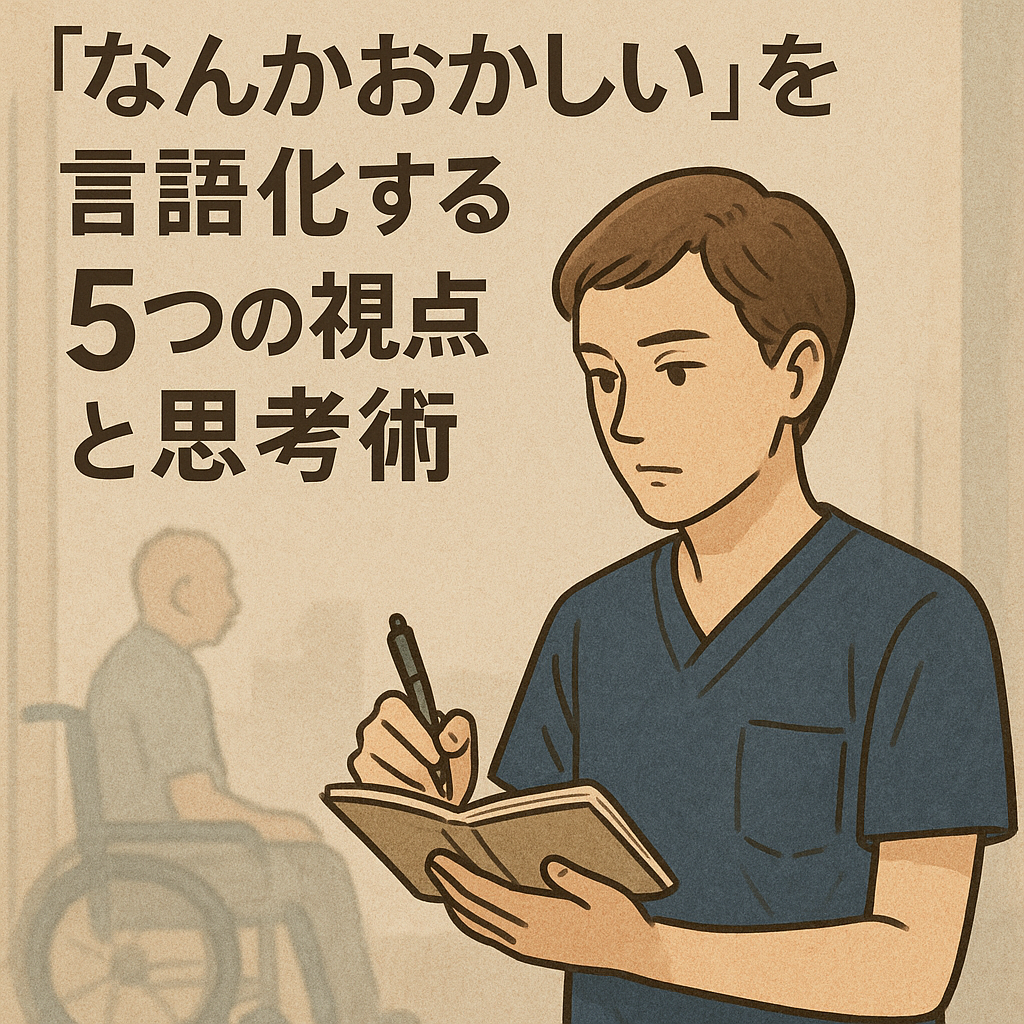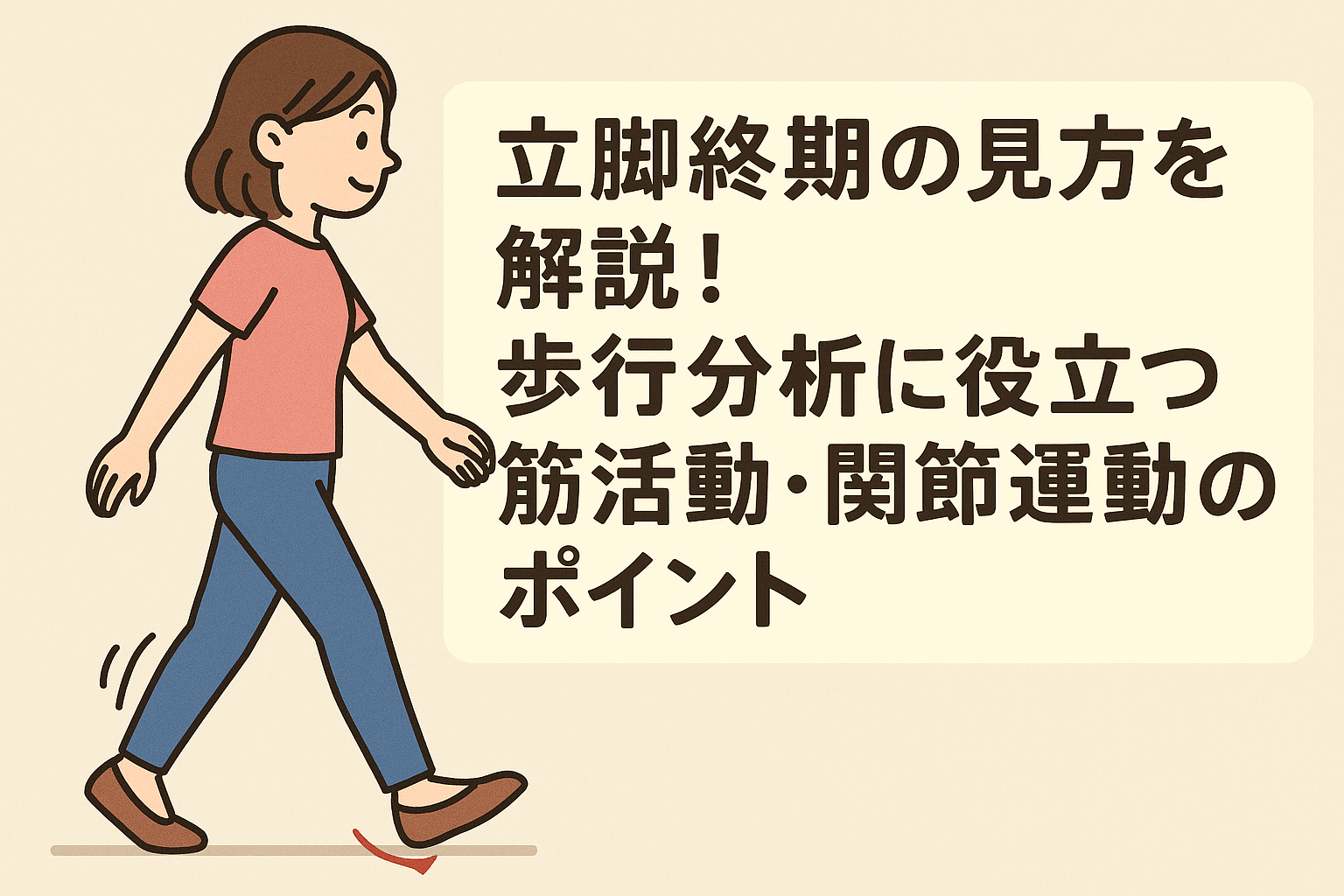はじめに ― 「なんかおかしい」で終わっていませんか?
理学療法士として患者さんを担当していると、ふとした瞬間に「なんか今日は違うな」「この人、いつもと様子が違うかも」と感じる場面がありますよね。
その“なんかおかしい”という感覚は、臨床現場での重要な気づきです。
しかし多くの人が、

違和感はあったけど、記録にはどう書けばいいのかわからなかった。

うまく言葉にできず、気のせいだったかもと思ってスルーしてしまった。
という経験をしています。
この“違和感”はただの主観ではなく、臨床における非常に価値のある兆候です。言語化し、記録に落とし込み、共有する力があれば、あなたの臨床力は確実に高まります。
この記事では、そのための「臨床メモ術」を5つの視点で丁寧に解説します。
\より専門的な記事はこちら/

“なんかおかしい”は、すでに立派な気づき
多くの中でも若手療法士や学生は、「確信がないから書かない」「エビデンスがなければ書くのは怖い」と感じてしまうことも少なくありません。
ですが、ここで大切なのは「その感覚はすでに重要な臨床的観察のひとつである」ということです。
臨床に慣れた先輩ほど、この“違和感”に敏感です。そしてそれを丁寧に拾い上げ、記録やチームカンファレンスで共有しています。たとえば、以下のような例です。
- 「ベッドから起き上がるときのスピードが明らかに遅い」
- 「立ち上がるときの膝の揺れが大きい」
- 「目線が下がっていて、反応が鈍い」
これらは、倦怠感やバランス機能の低下、精神的な不安定さなどを表している可能性があるサインです。
このような「ちょっとした変化」を“感じる力”があるなら、あとはそれを言語化してアウトプットする力を身につけるだけです。
言語化できない理由は「観察の軸」がないから
違和感を言語化できない最大の理由は、「何をどう見たらいいのか」という観察の軸が曖昧であることです。
たとえば、「今日は足取りが重そうだった」と感じたとき、以下のような視点を持てているでしょうか?
- 歩行の速度は?(普段と比べてどうか)
- 歩幅の変化は?
- 上肢や体幹の動きはいつも通りか?
- 足の挙がり方や接地音に違和感はないか?
- 本人の表情・訴えと関連があるか?
このように、1つの主観的な印象を構成要素に分解する力=観察のフレームワークがあると、記録に書ける情報が格段に増えていきます。
違和感を放置するのではなく、「それって何がどう違うの?」と一度立ち止まるクセをつけることが、言語化力の第一歩です。
臨床メモ術【実践編】“違和感”を言語化する5つの視点
① バイタルの変化:数値×タイミングを記録する
“様子がおかしい”と思ったら、まずはバイタルを確認する習慣を持ちましょう。
血圧・心拍・SpO₂・呼吸数などは、動作中にどう変化したかが重要です。
例)
「起立直後に収縮期血圧が20mmHg低下、脈拍数が12増加」
「歩行10m後、SpO₂ 97%→93%へ低下、本人より息切れ訴えあり」
→ 数値+動作+本人の訴えで記録するのが基本です。
② 姿勢・動作の質:何が、どのように変わったか?
「立位が不安定」「動作が鈍い」では伝わりません。
代償動作・左右差・動作の“質”に着目しましょう。
例)
「立ち上がり時、体幹前傾角が増加し、両手を大腿部に強く押しつける」
「立位保持中、左体幹側屈が出現し、5秒以内にバランス崩す場面あり」
→ 曖昧な動作表現を、観察できる事実に変換することがポイントです。
③ 表情・反応・声のトーン:主観的だけど、立派なデータ
表情や声、返答速度は、身体的変化だけでなく、精神・認知機能の変化を見抜く重要な材料になります。
例)
「発語は小声で語尾不明瞭。呼名反応はあるがアイコンタクトなし」
「普段より笑顔や頷きが減少。話しかけても反応が一呼吸遅れる」
→ 数値化できない情報も、比較対象をもとに客観的に書き残せます。
④ 本人の訴え:繰り返される表現・ニュアンスに注目
「今日はなんかしんどい」「体が重たい」など、曖昧な表現でも重要なヒントになります。
言葉のままではなく、その表現の裏にある訴えや変化に注目しましょう。
例)
「“なんか体が重たい”と繰り返し訴え。実際に起き上がりに要する時間が前回比+10秒」
→ 主観+客観を合わせて記録することが信頼性を生みます。
⑤ 環境・時間帯・直前の出来事:コンディションの背景を記す
違和感の正体が「環境要因」や「心理的影響」によることも多々あります。
例)
「昼食直後で眠気あり、反応鈍い傾向」
「家族と面会後、沈黙が増え、会話を避ける傾向強まる」
→ 訓練中だけでなく、“前後の文脈”まで拾うことで、臨床的な深みが出ます。
5. 書き方のコツ ― メモは「未来の自分への説明書」
臨床メモとは「今の気づきを、未来の判断や介入に活かすための説明書」です。
それを書けるかどうかで、ただの記録者か、臨床家かが分かれます。
おすすめの書き方は、以下の3ステップ:
ステップ① 感覚を残す
「今日は元気がない」「いつもより反応が遅い」など、まずは感じたことを素直に書いてみる。
ステップ② 客観的事実で補足
「座位保持に揺れあり」「歩行速度が低下」「SpO₂低下を認めた」など、感覚を裏づける“事実”を添える。
ステップ③ 仮説を立ててみる
「脱水傾向?」「疲労の蓄積?」「睡眠不足の可能性」など、今後の評価や介入に繋がる視点を記す。
6. 記録例で学ぶ「悪い例」と「良い例」
【悪い例】
「立位ふらつきあり。様子見。」
→ 抽象的・情報不足・臨床推論なし
【良い例】
「立位保持中、右下肢荷重時にふらつき出現。足部接地が不安定。本人より『立ってるのが疲れる』との訴えあり。午後・昼食後の場面。」
→ 状況、観察事実、本人の訴え、時間帯、推論すべてを含んだ良質な記録
7. おわりに ― 言葉にできる人が、臨床を変える
臨床での“違和感”は、すべてを数値化できるわけではありません。
ですが、そこには患者の変化やリスクの兆候、心理状態など、多くの“臨床情報”が含まれています。
大事なのは、その「感覚」に気づいたあなた自身の感性を信じ、それを他者に伝えられる「言葉」に変えること。
臨床メモは、未来のあなた自身への大切なメッセージであり、チーム医療における信頼の土台です。
明日から、“なんかおかしい”を言葉にする練習を、始めてみませんか?